
スヌーヌーの不思議な旅 vol.2 20240426 レポート/夜の旅
スヌーヌーの笠木泉です。
「スヌーヌーの不思議な旅」第二回目が4月27日、横浜市南区にあるスペース若葉町ウォーフで開催されました!若葉町ウォーフは劇作家・演出家である佐藤信さんが創作の拠点とされているアートセンターです。劇場・稽古場・宿泊施設も備わっていて、クリエイションを支え生み出すエネルギーが詰まった場所。今後この勉強会は若葉町ウォーフさんを起点にして開催していく予定です。横浜、黄金町。わたしの大好きなエリア。街に溶け込み羽ばたくこのアートスペースで学びを作っていくことに大きな希望を見出しています。いつか皆で横浜の下町を歩いたり、「ジャックアンドベティ」で映画を見たり、イセサキモールでご飯を食べたりもしたいですねなんて考えつつ。
X アカウント 若葉町ウォーフ
まずは第二回、そのレポートをここにアーカイブします。

夜の旅も始まりました〜まずは映画の話から
夜の旅 2024年4月26日 17時から20時
参加者 16名
笠木泉、律子さん、二田絢乃さん、小出和彦さん、富士たくやさん、キムライヅミさん、南風盛もえさん、冨田萌衣さん、田中大介さん、稲川悟史さん、安田明由さん、田島冴香さん、能島瑞穂さん、羽根井信英さん、踊り子ありさん、加藤じゅんこさん
夜の旅は、昼の旅(14時から17時)のあとすぐ開催されます。
雑談テーマは昼と同じで「映画、この一本」。好きな映画、嫌いな映画、思い入れのある映画、ちょっとよくわからない映画、なんでも結構ですとお願いしました。
年齢性別関係なく、全て関係なく、どの時代どのジャンル、そこにあるただひとつの感情をこめて、みなさんが「この映画」の話をしてくださいました。全ての方のお話が面白いのは、ご自身の記憶とリンクしているからでしょうか。ものすごく静かに、全員が興奮していたように思います。「踊る大捜査線」はお母様が見ていた映画だそうです。その記憶の断片の切り取り方がとても面白いなあと思いました。「太陽を盗んだ男」の話からかつて確かに我々の映像文化に存在していたレーザーディスクの話に飛んだり、昔はなかなか簡単に見ることができなかった映画も今は配信で見ることができるねえとか、さまざまな話になりました。公開時に何度も何度も映画館に通って見た「風立ちぬ」の話も、記憶。夜の旅が終わった後に皆で情報交換していたのも、なんだかとても嬉しい時間でした。
夜の旅で紹介された映画一覧です。
「太陽を盗んだ男」長谷川和彦
「Sunny 永遠の仲間たち」カン・チョンヒル
「チーズとうじ虫」加藤治代
「二十日鼠と人間」ゲイリー・シニーズ
「風立ちぬ」宮崎駿
「ショート・バス」ジョン・キャメロン・ミッチェル
「PERFECTDAYS」ヴィム・ヴェンダース
「アタラント号」ジョン・ヴィゴ
「OLD JOY」ケリー・ライカート
「ショコラ」クレール・ドニ
「不安は魂を食いつくす」ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー
「風の谷のナウシカ」宮崎駿
わたしは昼の旅夜の旅で紹介していただいた全ての映画を時間をかけて見てみるつもりです。
そして我々は山に登る準備をする 戯曲「小町風伝」
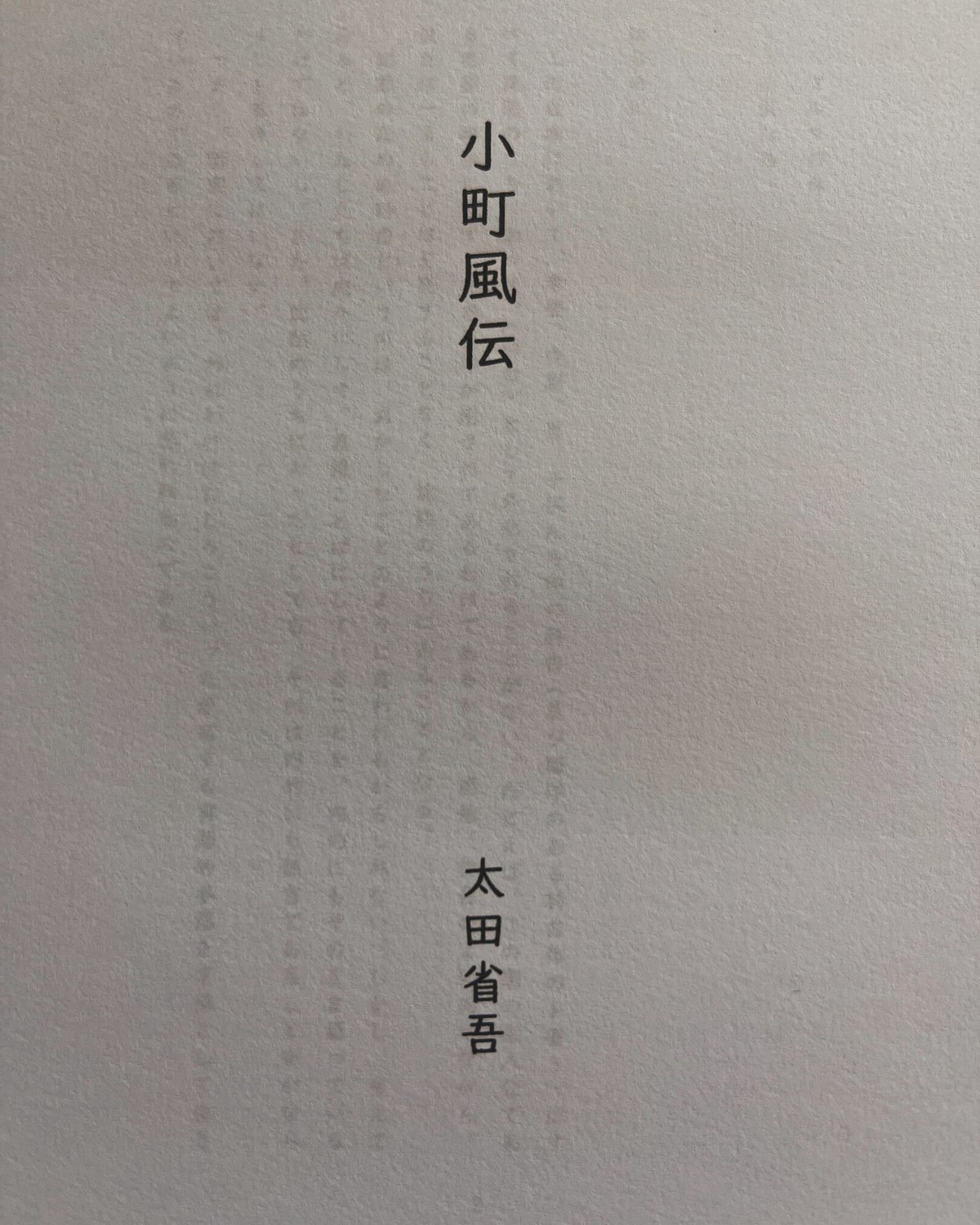
休憩ののち、いよいよ夜の旅の課題戯曲である太田省吾「小町風伝」の輪読を始めます。
戯曲は日本劇作家協会の日本戯曲デジタルアーカイブに掲載されております。そこからダウンロードして読書会のテキストとさせていただきました。
太田省吾さんはみなさんご存知かと思いますが、70年代に「転形劇場」を主宰し、劇作家・演出家として数々の(今となっては)伝説の舞台を創られた方です。代表作は「水の駅」「更地」「砂の駅」「ヤジルシー誘われて」等々。今回取り上げた「小町風伝」は第22回岸田國士戯曲賞を受賞した戯曲となります。太田さんは国内のみならず欧米やアジアなど世界的な活動を展開され、また京都造形芸術大学等で教鞭を取られていました。残念ながら2007年に67歳で逝去されましたが、多くのテキスト(戯曲や演劇論)は今我々の元に、我々の手の中に、劇場にあります。
なぜ今回この戯曲を取り上げたかというと、「太田省吾さんを知りたい」、これに尽きます。太田さんの作ったもの、太田さんご本人に興味があります。「沈黙劇」という新しい演劇を作り上げ、実践し、表現を追求された方が、果たしてどれほど言葉を尽くしてきたか、知りたい。今リアルに太田さんの演劇を見ることは叶わないけれど、戯曲に向き合えばその表現の意味や本質がほんの少し、一瞬でも感じることができるはずだ。この時間をメンバーと共に味わいたい。そんな理由です。
それにしても、大きな山です。
私たちは太田省吾という山の麓で待ち合わせして、今集合した。
そんな気持ち。
読み進められない

まずこちらも「オイディプス王」同様、私が調べてきたことなどを皆さんにシェアします。
「小町風伝」にはまずもって私たち読者が(特にこの舞台を立体化しようと思って本を開いたものにとっては)越えなければならないいくつかのあるいはいくつもの試練があります。
はじめに
この台本において、老婆、少尉、男、子供たち印の科白(及び■印のある科白体のト書き)はすべて沈黙のうちにあって、〈科白〉として外化されることがない。たとえば、この劇の主人公である老婆の科白にはすべて老婆印が附されてあるわけであるから、終始、舞台の上にありながら、 彼女は一言もことばを発することなく、沈黙のうちにあることとなる。 沈黙のための科白というのは、おかしなことのように思われるかもしれない。しかし、考えて みると、わたしたちは応々にして、直接ことばにしていることを、内的にもそのまま語っている わけではないし、また、沈黙のうちにあったとしても、それは内的にも無言であることをかならずしも意味してはいない。 つまり、現実においては、われわれはむしろこういった矛盾する言語的事態を常態として生きているのであるといってよいように思われるのである。
〈科白〉として外化されることがないーーーこの言葉にまず驚きます。すべて、すべての言葉は決して音として発することはないとあらかじめ述べられているわけです。その理由は、この太田さんの文章を読めばなんとなく理解できます(理解した気になれます)。矛盾する言語的事態、これも理解できる。むしろよくわかる。うなづける。そしてその表現方法がとてもエキサイティングでチャレンジングであることも。しかし、それが実際に演じられる時、俳優はどのようにこの内的言葉を外的表現として「そこ」に出現させたのか。
そして、■/科白体のト書きという名称の不穏さよ…
最近、品川徹さんから聞いたのですが、「小町風伝」初演に向け赤坂の工房で稽古中のある時、稽古を早めに切り上げ、全員で矢来能楽堂へ下見に行ったことがあったそうですが、工房に戻ると太田は突然、主役の老婆はじめ数名の台詞と台詞体のト書きは、「すべて沈黙のうちにあって<台詞>として、外化されることはない」と、封印してしまったそうです。
太田は、渾身の台詞が「能舞台からカーンと蹴飛ばされ、600年の伝統に比べ、たかだか100年の現代劇の台詞は、はじき飛ばされ、拒否されたように感じた」と後に書いていますが、この下見の時に、太田の頭の中でカーンと蹴飛ばされたことを初めて知りました。
すでに大量の台詞を覚え稽古に臨んでいた役者さん達は、台詞として外化されることのない台詞をもとに、どう演じればよいか大変苦労したと聞いています。
この太田の厳しい要求に、主役を演じる当時20代の若き女優佐藤和代さんは、なんと、足の指先の動きだけで舞台を移動するという、驚異的な身体表現で応答し、これら長く苦しい模索の稽古を続けるなか、回転を遅らせた緩やかな音楽、それに呼応するゆっくりと滑るような登場人物の動き、照明による時空の変換など、今まで観たことがないような表現が能舞台上に創造されていきました。
ーーSPAC 記事 2015年4月30日
【小町風伝】夫、太田省吾、そして、「小町風伝」のことなど(太田美津子)より引用
これは太田さんの奥様である太田美津子さんの文章です。つまりこれを読むと、「膨大な量の科白を覚えていたが、それは全て言葉として発しない」という段階があったということです。私は太田美津子さんの文章を何度も読みました。そして、自分がその場所にもしいたとしたらどうしていただろうと想像しました。その途方も無い、時間と模索。
夜の旅に参加してくださっている方は比較的演劇に関わっている方が多いように思ったので、この文章と共に私の現在の永遠にも似た、砂漠の入り口に立ったような、山の麓で呆然としている、その気持ちを、正直なる思いを告白しました。
そこでみんなで話したのは、この外化しないという表現に至るまでの「内化」の部分の豊かさに触れることの喜びです。
それが演劇の、舞台上に存在する「身体」なのではないかと、私は思います。
みんなで稽古場の様子をあれこれ想像して話をしました。当時の俳優のみなさん、どんな心持ちだったかしらと。いろいろ話していくうちにだんだん「覚えた科白を言わなくなったとしても、それは結果としてではなく過程として絶対的に心の中に存在がある、充実と深みがあるであろう」というような流れになり、私は感銘を受けました。そうですよねえ、大切なのはきっと過程です。この勉強会も、過程です。ですから、みんなで過程を信じて戯曲としての太田省吾さんの言葉を全力で掴み取りにいこうと改めて感じました。当時稽古場にいらっしゃった転形劇場の俳優のみなさんもきっと言葉を掴み取り、手放し、また内に戻る、その繰り返しという過程の中で、自分の表現を苦しみつつも獲得していったのではないでしょうか。
わからなくてもいい。でもみんなで進んでいこう。
そのほか様々な「転形劇場」のエピソードや、「私が体験した太田さんの舞台作品」(私は「ヤジルシ」を劇場で見ました、私は太田さんの生徒でした!などなど)など話が弾みまくって、戯曲を読み進めるまでなかなかいきません。それでいいですよね。ゆっくりいきましょう。
ちょっとだけ読んでみた

ここでもう残り時間が少なくなっていたことには薄々気がついておりましたので、さてとにかくまずは読んでみようとなりました。
1
襤褸の十二単衣に身をつつんだ老婆が、ひとり風のありかを訪ねるように、あるいはゆるい風に身をまかせるようにしてあらわれる。 立ちどまった老婆は、躯をなでる風を衣にふくんでゆれている。 衣は、時の漂白を受けて白い。
上記の引用部分が、まずは冒頭の冒頭です。ト書きが始まり、三行の中に埋まる時間。眩暈がする。まず「襤褸」が読めない! (あらかじめ一応調べておきました。正解はぼろ/らんるです)そして私たちはこのたった三行のト書きの美しさに、ただ感嘆しました。
「衣は、時の漂白を受けて白い」
ーーーこんなト書きをかつて読んだことがない。私は正直、そう思いました。そしてみなさんにもそのように告白しました。ある方は「これで日本酒が飲める」と。…なんというわかりみ!
そしてこの戯曲の中心にいる「老婆」、ほとんどのシーンにおいて彼女の物語は最も重要であるのは、この戯曲が能の「卒塔婆小町」を下書きにして描かれていることからもわかります。
まず、観阿弥作/能「卒塔婆小町」のあらすじは、このようなものです。旅に出るお坊さんが卒塔婆に腰掛けている汚らしい老婆に出会いますが、その聡明な問答から「あなたは本当は誰なのか」と問いただすと「小野小町(おののこまち)の成れの果てだ」と真相を明かします。小町は、自分を恋した深草少将の恨みによって若かりし頃の美貌を失い、あるいは落ちぶれた老婆となってしまったと告白します。百夜通いの伝説(百日間私の元へ通えば、あなたの思いを受け入れてあげよう叶えてあげようと提案するものの少将は九十九日目に死んでしまう)によって狂ってしまった老婆を、お坊さんが成仏させる…という話で、この話をさらに三島由紀夫が「近代能楽集」において夜の公園で出会う老婆と若者の物語に蘇らせています。三島版の老女も「私は小野小町だ」と宣言し、その悲しい恋の末路を憑依したかのように演じます。
老婆の悲しき恋の話、そう思えば普遍を感じます。太田さんの描いた「老婆」も、そこに、言葉の中にある意思と共に存在しています。
私たちは一年間をかけてこの「老婆」が語る言葉を噛み締めていくことになるのだ、と、みんなで輪読しながら、たぶんあの場所にいた全員が思ったでしょう。それぐらいの重量でした。ディスカッション、感想、多め。転形劇場のことを話した時間、多め。俳優だったらこの「老婆」役をやりたいか? など、そんな話にもなったりして。「やりたい」とおっしゃったのは一人だけでした(立候補、かっこよかったなあ!)。
戯曲は数ページ、ほんの少しだけ読んで、これはまた来月はじめから読もうではないかと。ここで時間です。楽しかったなあ。
次回はもう少し読み進めます。でも読み進められないかもしれません。ト書きで何日でもディスカッションできそうですから。

参加メンバー佐藤桃子さんのレポート
まるく並んだ椅子、昼の旅と夜の旅が交差する時間があり、おもしろく、旅のレポートを書く人が発表されると、視野がすこしひらけて、らくになり、椅子に座っている意識が軽くなった気がしました。
まずは、「映画、私のこの一本」というテーマで、ひとりずつ、お話しして、前回の自己紹介の時間もすごくたのしかったので、お話しを聞くこととてもたのしみにしていました。
観たことのない映画、知らない映画について、そのひとのことばをきいていて、みていないけどこういうかんじなのかなって想像してみる映像や、お話しているひとの様子が、どこかでむすびついて、その映画をみたときもしかしたら思い出されるのかもしれないと、映画は体験で、という話しをそのとききいて、いま、考えていました。もっともっと聞いていたいです。好きだとおもう映画のタイトルが出てきたときのわくわくは、あれはなんだったのだろう、、こころのなかで、大興奮というかんじでした。また、「この一本」にした理由も、みなさんが、それぞれに、あって、枝がどんどん伸びていくかんじがして、ひろくなりました。途中、地震があって、しばらく揺れていて、窓をあけて、地震のときは窓をあけるのだと、笠木さんが話されて、ここは横浜のちかくで、わたしの住んでいるところからはここは遠いところだとおもって、うちは母が扉をあけている音を地震のとき聞く、みなさんの家がある地域のことを考えました。
夜の旅は、太田省吾「小町風伝」を、1年間かけて、読んでいくことになります。
今回は、はじめに と、一章を、段落ごと順番に声に出して読みました。まるくなって聞こえてくるひとりひとりの声の老婆のことばは、すごくおもしろかったです。それで、この声は はじめに によると外には出てこないから、聞こえない声となっていくのかとおもうと、もうその過程のなかにわたしもいるのだ、という気がしてきました。
わたしは文字で書かれたことばを声に出してよむことが苦手で、それは息を吸って吐くタイミングがわからなくなってしまうからなのですが、息をどこで吸ったらいいか、話しながらどのくらいの量の息を吐いているのか、「、」「。」では息をどうしているか、みなさんはいったいどうしているのか、いっしょに読むことができる時間で、すこしずつ考えていきたいとおもいました。
はじめに について、そのあとは考えて、どうおもったか、太田省吾とこの作品の上演について、科白封印の経緯について、じっくり、おしゃべりする時間。いちど覚えた科白を、沈黙する、というのは俳優にとって、どうだろうか、「頭で考えること 身体で考えること」、「それが重なったとき」、「やったことないことをやってみたい」その話がとっても印象にのこっています。
はじめに には「沈黙のための科白」、ということばがありました。沈黙のために科白があるなんて、外に出てくることば、内にあることば、ほんとうにどういうことなんだろうか、なにが起こるのか、まだまだなにもわからず、でも身体は沈黙することが、きっとないのではないか、といまはおもって、いて、その身体を想像するのはむずかしそうで、とてもたのしそうです。
今回の旅から、若葉町ウォーフが拠点となり、これから1年間、通う街があること、とてもうれしいです。すぐ近くに映画館があって、台湾料理屋には行列ができていて、古本屋があって、すこし歩くと野毛があって、動物園もある、みんなで行けたりしたら、いいなあと想像していました。これから、どうぞよろしくお願いします。
ーー佐藤さん、素敵なレポートをありがとうございます! 参加していただき、一緒に知らないこと思いもつかないこと今まで触れることがなかったものを探しに行けることの喜びを感じます。また次回、ゼロから読んでいきましょう!(と言っていると一年かかっても読み終わらないかも、まあ、それも楽しい)
近日中に稲川さんのレポートも掲載予定です!
次回の夜の旅は5月25日。
またみんなで太田さんの言葉に触れることができる幸福。
とにかくがむしゃらに闇雲にのんびり読んでいくつもりです!
次回もよろしくお願いします。
(文章:笠木泉)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
