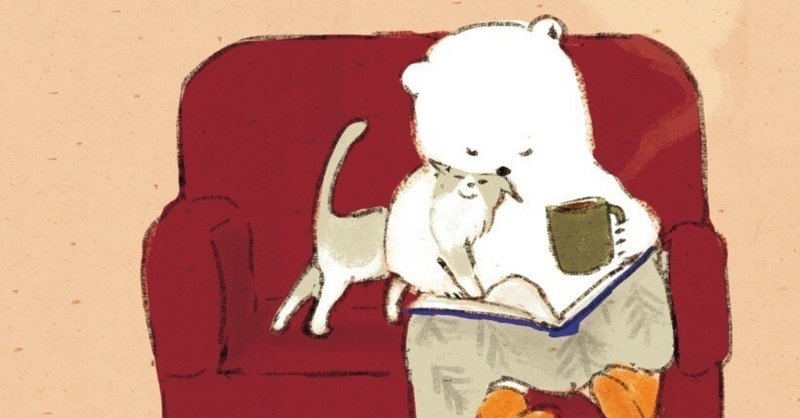
私が子供の頃に「浴びた」もの、の話。
このノートを偶然見つけて読みまして、それで考えた事を書いてみます。
幼少期になにを浴びたか?英才教育について考えた。
(桜林直子)
https://note.com/sac_ring/n/n5e7f6f9a0619
noteの記事に表示されるおすすめをどんどんたどって行くと、思いもよらない記事や数年前に書かれた記事を見つける事があるのですが、これがまた面白いんですよね。
これは!と思ったものには「スキ」を押したり、マガジンに追加したりしています。
三つ子の魂百まで、はあり得るかも知れない
これは、母から聞いた私が幼い頃の話です。
両親共に英才教育という代物に興味がなかったため、初めての子供である私が生まれた時も絵本や知的玩具はほとんど用意せずに育てていたそうです。
しかしそのうち、私は母が読んでいた雑誌に興味を示すようになりました。まだ文字は読めませんでしたが、広告や写真を見て「とまとー!」などと喋る私に、母は「この子には読む物が必要なんだ」と悟り絵本などを買ったのだとか。
幼い私は何度となく読み聞かせを要求し、ついには気に入った物語を丸暗記するに至りました。やはりまだ文字は読めなかったのですが、絵と文章を結びつけて憶え、まるで読めているかのようにページをめくりながら朗読(?)したりしていたそうです。
恐らく妹が生まれる前なので、1歳から2歳くらいの出来事だと思います(妹とは学年で2つ違いです)。
やがて文字を憶えて自分で本を読めるようになった私は種類を問わない読書好きに成長し、親から「あんたは本屋さんに連れて行くと機嫌が直るねー」と言われるまでになりました。そして小学校では図書室で世界の名作から漫画(『はだしのゲン』が置いてありました)まで読みまくる日々を送り、今に至ります。
「三つ子の魂百まで」「雀百まで踊り忘れず」という諺がありますが、それは間違っていないのかも知れません。
発達障害の特性も活かされていた?
以前私の持つ発達障害について書いた記事で、知能検査をしたら言語性IQが高めだった事について触れました。読書と物書きが好きなのはこれも関わっているのかな?とは思います。
知能検査の結果は、IQの数字こそその時のコンディションによって変わる可能性があるものの、能力の凸凹加減は生まれつきの要素が大きいそうです。だから「特性」という言葉が使われるのだと思いますが。
発達障害でない方(定形発達)の場合、能力がバランス良く年齢相応に発達しています。それが凸凹していて突出している部分と劣っている部分の差が大きいと、発達障害の傾向ありとなるわけです。
話が逸れましたね。
つまり私は言語能力が高めのタイプだったため、本に興味を示すようになったのかも知れません。
幸運だったのは両親共に本好きで、本だけは好きなだけ買ってくれるような環境で育てられた事です。もしも親が楽器演奏やスポーツの英才教育をさせたい人間だったら、早い段階で潰れていたでしょう(動作性IQが低くて不器用な上に運動音痴なので)。
環境や能力だけではないけれど
当然ながら、環境に恵まれなくても才能を発揮している方は存在していますし、生まれつきの能力はすぐにわかるものではありません。
最近は発達障害などが早めにわかるようになったとは言え、知能検査で高かった項目を活かせる習い事を始めさせようとしても、お子さん自身が興味を示すとは限らないでしょう。発達障害の人には特別な能力がある!と巷では言われているらしいですが、それもごく一部の「世の中に受け入れられやすい才能」を持つ方々が目立っているだけなので。
本当の英才教育は親御さん自身が好きな事を楽しみ、その姿をお子さんに見せ、興味を持っているようなら「あなたもやってみる?」と誘う事から始まるんじゃないかな、と私は自分の経験から思うのです。
※画像は「みんなのフォトギャラリー」からお借りいたしました。ありがとうございました。
ちょこっとでも気紛れにでも、サポートしてくだされば励みになります。頂いたお気持ちは今のところ、首里城復元への募金に役立てたいと思います。
