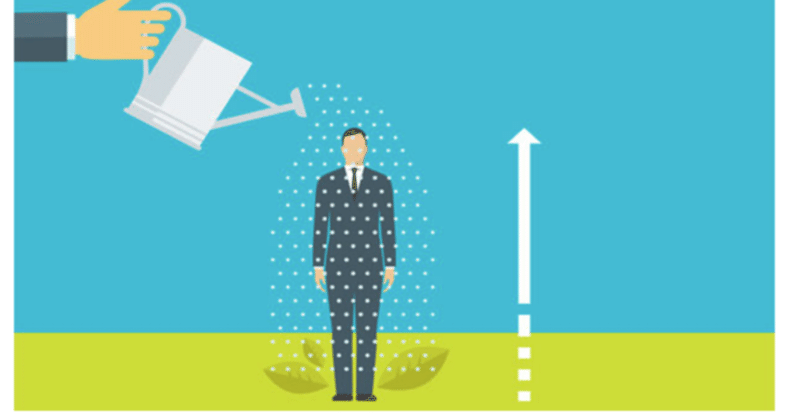
マクロ経済、流動性の罠。
今回、マクロ経済でベーシックのIS-LMモデルで”流動性の罠”の事をやっているので紹介します。IS-LMとはInvestment-Saving(投資&貯蓄)とLiquidityPreference-MoneySupply(流動性のあるマネーサプライ)の頭文字。例えば、なんらかの理由(例えばコロナ)で市場の需要と供給バランスが壊れ、企業や人々の所得(Y)が減っているとします。グラフで言うIS0とLM0の交差点Y0。そこで政府が財政政策の追加を行うとIS0が右方向のIS1にシフトします。日銀も金融緩和を行いマネーサプライを増やすとLM0が右方向LM1にシフトします。そして人々の生活水準と経済活動を守ろうとします。早い対応が経済ダメージを最低限に押さえ、より早く景気の回復に向かいます。

しかし先進国、特に既に財政赤字の多い国、日本、ベルギー、イタリアなどは利子率の弾力性が衰えています。弾力性が衰えるとは金融緩和で利子率を低くしたり、マネーサプライを増やしても企業の投資(企業は固定資産や取引可能な物への投資が多く、人間への投資は低い)や一般の消費は増えません。下のグラフで言うとLM0線が既にゼロ付近なので金融緩和をしてもあまり効果ありません。日銀のレポートから2020年6月時点は-0.1%のマイナス金利になってます。そこで財政政策に期待して政府が支援を行い回復を目指します。若い世代は将来稼ぐ力があるので消費する傾向が高いですが、高齢化のすすむ日本全体でみると消費のインパクトは少なく成長回復には時間がかかります。この緩和効果が低い状態を”流動性の罠”と言われています。

最近の経済学の一つ、リアルビジネスサイクル理論は生産技術の向上と財政政策によって景気が左右されると言っています。企業や個人が適切な投資をし、国民が将来の回復に期待を持っているか?先ほどの日銀のレポートに書かれている”物価安定の目標2%”との言い方は世界各国で目標とされている健全な物価上昇の事で経済が円滑になっている状態。2020年5月、統計局データの消費者物価指数0.1%の原因は賃金収入の低下と成長の期待値が低いからとの見方が強いです。後、もう一つEconomistの記事によると、2019年後期の消費税増税が6.3%のGDP降下に影響しているとも。賃金の低下に関して興味を持ったのでワールドバンクのwebサイトで国々のデータ比較をしてみました。以下はアメリカ、ドイツ、日本、韓国、中国、インドの1990年から現在までのグラフです。日本は2005年位からドイツと大きく差が開き始め、現在は韓国と同じ位になっています。

私が思うに、企業や個人が適切な投資(賃金向上含む)をし、創造的&効率的に価値のあるアウトプットを出せる環境を作る事。それが将来への期待を高める第一歩かと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
