まほら大和3
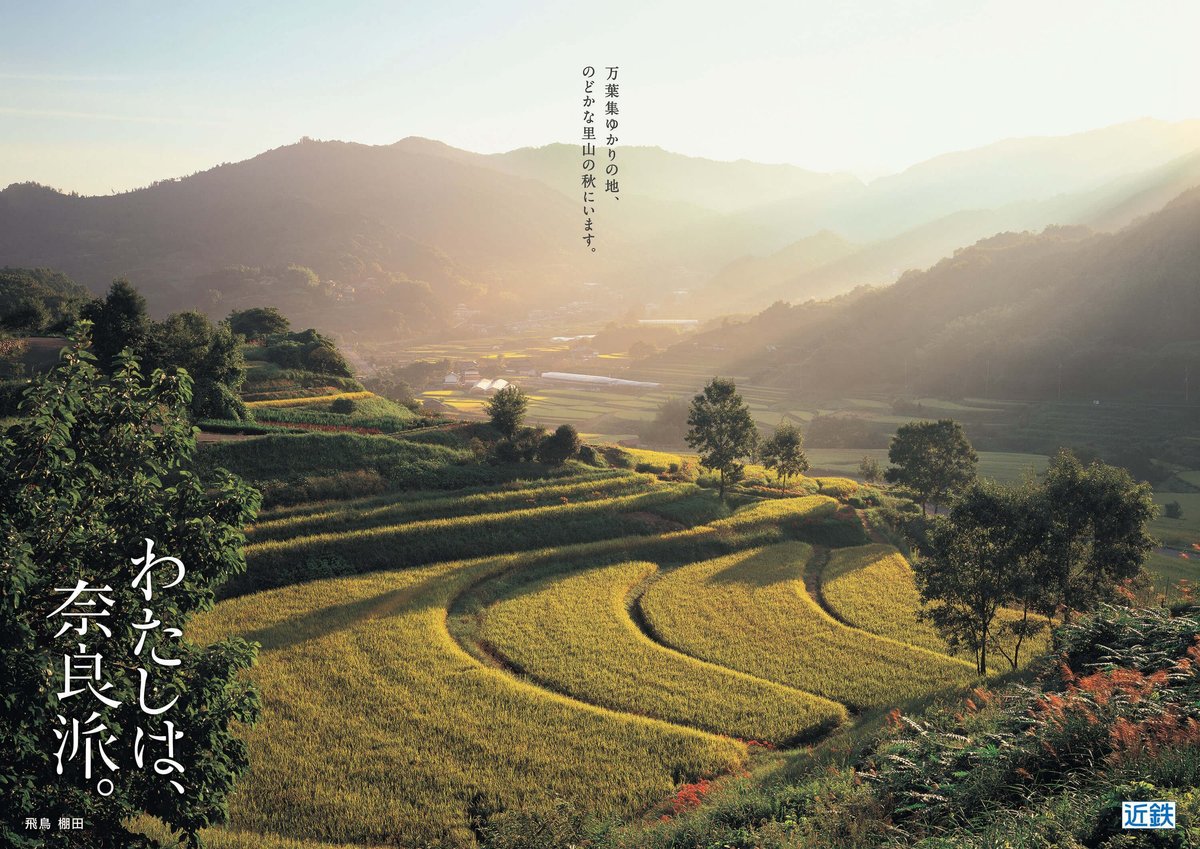
唐招提寺から尼ヶ辻駅へ向かう。
少し先にこんもりした森が見える。

森に向かう途中にこんなものをいくつも見掛ける。



田道間守(たじまもり)とは人名。
菓祖と称され、お菓子の神様としても祀られる。
いったいどんな人物なのか。
記憶の範囲では、但馬国の人。
新羅の王子で日本に渡来した天日槍(あめのひぼこ)の子孫。
そして天皇の命を受け、非時香菓(トキジクノカクノコノミ)を求めて常世国へ向かった人。

手にするのが常世国から持ち帰った
非時香菓
時は第11代垂仁天皇の御代、田道間守は天皇の勅命により「非時香菓」を探し求めるために常世の国へ旅立つこととなる。
そもそも非時香菓って何か。
非時香菓とは橘のことだと言われている。
これは日本書紀の垂仁紀九十年二月の条に、「九十年の春二月の庚子の朔に、天皇、田道間守に命せて、常世国に遣して、非時香菓を求めしむ。香菓。此には箇倶能未と云ふ。今、橘と謂ふは是なり。」。とあるからだ。
橘は、ミカン科ミカン属の常緑小高木で柑橘類の一種。 別名はヤマトタチバナ、ニッポンタチバナ。
非時香菓=橘説には異論も出ている。
バナナだ!と言う人もいる。
橘は柑橘の総称で、必ずしも大和橘を限定して指すわけではないとする意見もある。
僕はどれでもいいかな(笑)
そもそも橘は日本固有の柑橘類だからわざわざ常世の国まで取りにいかなくてもよいだろうという見解がある。
つまんないなー、こーゆーの。
常世の国はどこかいうことに対しても様々な意見がある。
中国、インド、南米なんてのもある。
これを追究することも無粋だ。
常世の国は不老不死の国であり、理想郷。そしてもうひとつ、死後の世界でもある。
非時香菓はその常世の国にある
常世の国へ向かった者は何人かいる。
少彦名神、御毛沼命。この二人は二度と還ってこない。
常世の国へ向かい、戻ってきた者もいる。
浦島子(浦島太郎)は玉手箱を開けた後に息絶える。
田道間守は常世国に渡り10年後、非時香菓を手に帰還する。
しかし垂仁天皇は前年に崩御。そこでタジマモ持ち帰った木の実の半分を皇后の比婆須比売命に献上、残りを天皇の御陵に供えると、その場で慟哭しながら死んだ。
人間が一旦常世の国に足を踏み入れれば、仮に現世に戻ってこれたとしても命はない。
これが8世紀の世界観であり他界観である。

ほんの少し歩けば、さっきのこんもりした森の全貌がわかる。
宝来山古墳。
第11代垂仁天皇陵とされ、全長227mの大きな前方後円墳である。
よく見ると写真の手前に円墳のような小さな島が。

田道間守の墓と伝え呼ばれている。
この円墳、慶応3年(1867年)の『文久山陵図』には描かれていない。
明治期の天皇陵整備に伴い周濠も工事された。その際に撤去された堤のの残存とも言われるらしいが、人々の心の中で陪塚として生きている。
1500年間語り継がれてきた物語が、様々な形で今も生きていることが素晴らしいと感動しながら宿に向かった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
