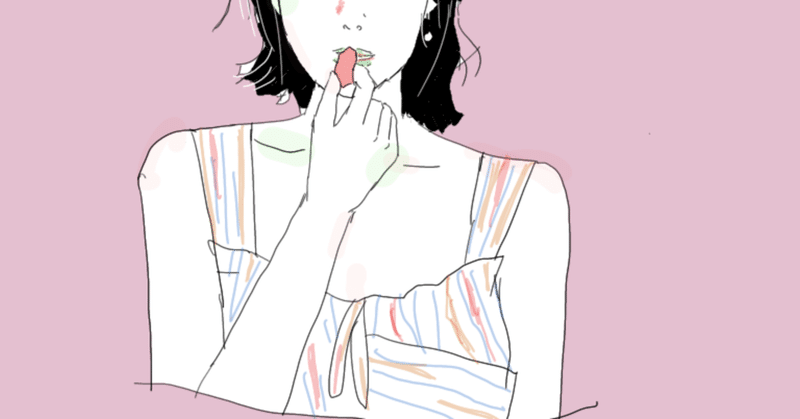
thin
祖母が退院した。
朝、ベッドから落ちて首を痛めた祖母を病院に連れて行くと首の骨が折れていたことがわかり、そのまま彼女は3ヶ月入院になった。3ヶ月の間にいろんな器具を取り付けられたり、手術があったり、大きな出来事も多かったけれど、たまに着替えを持って病院に行くと、コロナで面会こそ叶わなかったものの看護師さんからは「いつも笑顔で、発話も問題ないですよ」と言われ安心していた。そうして秋から冬になり、雪も降り、もうすぐ新しい年を迎えようとするこの12月に、ようやく祖母は退院した。
退院の日、午後休暇を取って早めに帰宅した。3ヶ月の間誰もおらず、物もなく、静寂に包まれていた祖母の和室に入るとそこは病院帰りの荷物にあふれていて、祖母は、テーブルに座っておにぎりを頬張っていた。ばあちゃん、おかえりと声をかけると、彼女は振り向いて、ああちいちゃんと、心から感動したような声を上げた。
かたや私は、祖母に向けた笑顔がひきつるのを果たして抑えられたかどうか分からない。私に声をかけられて、振り返って、立ち上がった祖母は、3ヶ月前を経て見る影がないほどに痩せてしまっていたからだった。
もともとふっくらした人だっただけに、痩せた姿を見るのは私の人生で初めてだったかもしれない。けれど3ヶ月の病院生活が彼女の体型を否応にも変えた。痩せた祖母は一回りも二回りも小さくなっていた。私は顔にぎこちない笑顔を張り付けたまま、どうして思い至らなかったのだろうと考えていた。どうして、3ヶ月を経て祖母が1ミリも変わらない姿で帰ってくるものと無邪気に信じていられたのだろう。
祖母の部屋を出たあと、今度は祖父のことを思い出していた。7年前に死んだ祖父。嚥下障害を起こし、晩年は骨と皮、という表現がまさにぴったりの、ぺらぺらで、しわしわで、やせ衰えた姿だった。痩せてしまった、ということは母から聞いていたものの、まだ大阪に住んでいた私はあまりぴんと来ていなかった。痩せたといっても、限度があるだろうと。けれどそうして次に帰省して祖父に会いに行ったとき、限度というものは存在しなかったのだと、私の想像をはるかに超えてくるものなのだと思い知った。まごうことなき骨と皮になってしまった祖父もまた、大阪から帰ってきた私を快く迎え入れた。私は、私を迎え入れる余裕があるなら何か食べて、としか、思うことができなかった。祖父の姿はあまりに衝撃的で、私もしばらく食べ物が喉を通らなかった。それから間もなく祖父は力尽きたように入院し、その2ヶ月後に死んだ。最後にお見舞いに行って、大阪に帰ってきた夜、電車の中で食べようと思って忘れていたおにぎりを部屋でひとり頬張りながら、涙が止まらなかった。
そんなことを思い出していた。
人が痩せた姿は、死を想起させる。老いた人ならなおさらだ。老いた人に痩せられると、理由のない無力感に苛まれる。この人は一歩も、二歩も死に近づいたのだと感じる。痩せた人は小さくなる。痩せた人は土気色の肌をしていて、血の気配がない。痩せた人に刻まれた皺は、もう二度と元には戻らない、その肌に永遠に刻まれてしまったもののような気がする。
痩せた人からは小石が小石とぶつかるような、そんな硬くて静かな音がする。痩せた人が笑うとき、命がむやみに燃えていると思う。痩せた人が歩くとき、その命は削れていると思う。
痩せた人は、常に死とともにあるのだと思う。
私もまた痩せている。以前はもっと痩せていた。
進学を機に実家を出て一人暮らしを始めたけれど、一人暮らしを始めてみて、自分はそもそも食べることにそこまで興味がないのだということに初めて気づいた。食材のためにお金が減っていくことの方が恐ろしくて食べる量が大幅に減ったり、大学の混んだ食堂が嫌でしばしば食事をスキップした。演劇部に入って体力勝負な毎日を過ごした。そうしたら1年と待たずに糸がほどけるように痩せていった。料理も嫌いだったから、食べずにいるのは楽だった。それに体重計の数字が減っていくことには達成感があった。痩せていくのは楽しかった。体が軽くなって、嬉しかった。羽が生えたような気分だった。痩せたせいでしょっちゅう体調を崩し、周囲に迷惑をかけていたけれど、それでも痩せていることは楽しくて嬉しかった。
働き始めてからは、私が私でいるために、痩せていることにこだわるようになった。都会にいて、私という個体を維持するために、痩せておくことを選んだ。仕事ができなくても自信がなくても痩せていれば、それくらいは頑張っているのだから、じゃあ生きていていいよと、言われるような気がした。生きていていいと思える実感が欲しかった。自分が頑張っている実感が欲しかった。実際、私は太りにくくて痩せやすい体質だったから、痩せている状態を維持することはそこまで難しいことでもなかった。バウムクーヘンばかりを食べて過ごした。甘いしカロリーもあるし、これで十分だと思っていた。全然十分じゃなかったから、痩せていたのだけど。
だけどここまで書いてみて、本当にそこまで切実なものだっただろうか? と、うすうす感じている。私が痩せていたのはただ痩せやすい体質だったのと食べることに興味がなかったからで、全然、痩せるために頑張ってなどいなかったんじゃないだろうか。頑張っている実感が欲しいとか、生きていていいと言ってほしいとか、もちろん、その側面は確かにあったかもしれないけれど、本当のところはただ面倒だったから、それだけのことだったんじゃないだろうか?
紐解いていくのが難しい。
むやみに痩せていたころの私を見て、両親や親戚はきっと心配していただろう。
私は一人で勝手に痩せているつもりだった。私が痩せていることは、誰にも何にも関係がないことで、誰に何を言われる筋合いもないと思っていた。けれど他人が痩せた姿に自分だってここまで動揺するのに、それならむやみに痩せていた私を見て周囲が動揺する可能性になぜ思い至らなかったのだろうか。私がむやみに痩せていて、周囲は動揺したかもしれない。もしかしたら悲しんだかもしれない。私がいつか本当に、近いうちに死んでしまうのではないかと恐れたかもしれない。その、人の感情の機微に、私はとても鈍感だった。もともと大した理想もなく食べずにいて、痩せて、その程度だったのだから、早いところ思い直してもっと食べていたらよかったんだ。私は何も考えていない。いつもぼーっとして、その場の雰囲気と自分の気分に流されて、流れゆくままに、染まりゆくままに生きて、ここまで来ているだけだ。それならもっと他者を思って生きたらよかった。
けれど他者の感情は関係なしに私は今でもできれば痩せていたい。単純に、痩せている自分の体型の方が好きだからだ。それに近いうちに死んでしまってはいけないことは分かっているけれどそれでも死にたい気持ちを消し切ることはできない。生きているのはしんどくて、つらい。この自分でこの世界に存在していることがしんどくて、つらい。もうこの自分で人間としての生を続けることは限界だと、常に思っている。そして多分、太っているとその死にたい気持ちがもっともっと強くなっていただろうから、だから、もしかしたら生き続けるために痩せていたいのかもしれない。痩せることと死ぬことと生きることは私の中で常にとても近い場所にあって、その3地点を私はぐるぐるとめぐっているのかもしれない。けれどそれも今はわからない。食べることに興味はない、食べずに済むなら食べずにいたい、けれど食べないことにそこまでの信念もないし、母の作った食事をはねつけられるほど強情でもない。
かと言って、やせ衰えた祖母や祖父のことを思って、ああなってはいけないから食べなくてはならないとすぐに納得することもできない。
なんて中途半端な意思だろう。
実家暮らしに戻ってから、痩せていたいという強い気持ちは少しずつ消えていっている。今はただ、体重は減りもしないし増えもしない、そんな状態がいい。むやみに痩せることもせず、かと言って積極的に太りにもいかず、ただ、今の状態が永遠に続けばいい。両親を心配させない程度に。両親を失望させない程度に。両親を悲しませない程度に。ここにも私の意思は薄く、地に足をつけることもせずただ日々の海にぷかぷかと浮いている。流れる方へ行く。思うことがあるとすれば、祖母には元気になってほしい、ふっくらしていた頃に戻ってほしい、死んだ祖父だって、どうせ死ぬならあんなに痩せなくてもよかったのに。他人に対してはそんなふうに思う。結局私は何を願っているのだろうと考えて、つまるところ、痩せようが太ろうが誰も傷つかない世界であれということなのかもしれなかった。それも、第一に「私が」傷つかない世界であれという、とても自分勝手な願い事なのだけれど。
読んでくださってありがとうございます。いただいたお気持ちは生きるための材料に充てて大事に使います。
