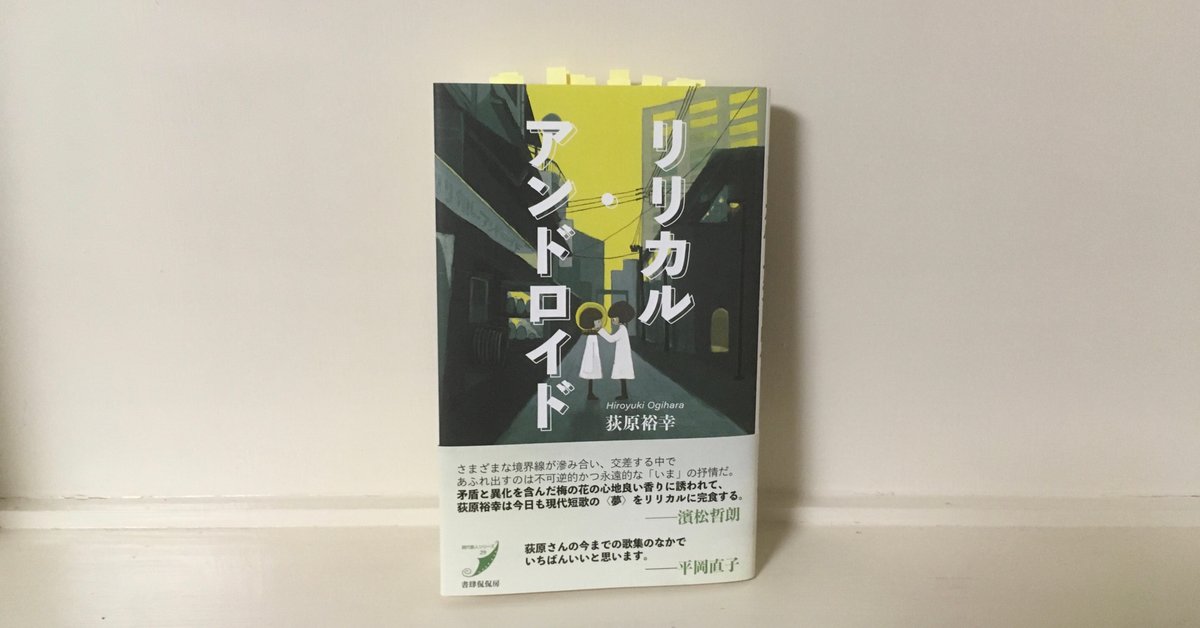
おくすり飲めたね 荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』は幻をたぐりよせる
『リリカル・アンドロイド』という楽しい短歌の本
荻原裕幸の短歌集『リリカル・アンドロイド』は、いまのところ私がこれまでに読んだうちでもっとも楽しんだ短歌集である。荻原裕幸の本の内で、ではなく、読んだすべての短歌集のうちでである。
実は、荻原裕幸の短歌集を単独で読むのは初めてだったのだが、『リリカル・アンドロイド』には強く刺激された。読みながら自分も短歌をどんどん思いついた。その勢いを殺したくなかったので、あえて書評を書いていなかった。私自身の創作が一段落したので、この楽しい短歌集を紹介したい。
特に、幻のような不思議な題材を扱うものを取り上げる。幻を読者に共有させるために、荻原はどのような技を使っているだろうか。
つゆ晴れのひかり
いまのいままで妻のゐた空間につゆ晴れのひかりが揺れてゐる
妻がいることは変ではない。空間があるのも当然だ。ならば、「妻のゐた空間」もある……だろうか?
空間とはただのスペースである。妻がいるとき、妻がいる空間である。それはわかる。
だが、たとえば妻の残り香があるというのでもない、ただ単にさっきまで妻がいた場所は、特別な性質を持たないただの空間だ。
偽装する短歌
あとの部分は「つゆ晴れのひかりが揺れてゐる」である。実感のある言い方ではあるが、普通だ。新しい着想はない。
新しい着想はないが、妻のゐた空間はただの空間だから、ここに本当にあるのは「つゆ晴れのひかり」のほうだ。読者もまた、それを見る。
この短歌が言いたいのは「つゆ晴れのひかりが揺れてゐる」であって、前半部分はその場所説明にすぎない……かのように、書く。
すると、読者は「いまのいままで妻のゐた空間」を「平凡な前提」として飲み込むよう誘導される。
おかしいではないか。つゆ晴れのひかりが揺れるほうがよほど平凡なことで、ただの空間を「いまのいままで妻のゐた空間」などと名付けるほうが妙なはずだ。
ところが、平凡なひかりの方が強く言いたかったことであると偽装することで、妙な認識を共有させてくるのだ。
おくすり飲めたね
株式会社龍角散から、「おくすり飲めたね」という商品が出ている。苦い薬を嫌う子供に、薬をすんなり飲んでもらうための商品だ。チョコレート味などがついていて、薬といっしょに飲む。
この一首は、薬を混ぜた「おくすり飲めたね」ではないか。つゆ晴れのひかりが揺れているという飲みやすいものを飲んだら、いつのまにか「妻のゐた空間」なる面妖なものも飲まされて、そっちが効いてくる。
痛みのなかに梅が咲く
父に頬を打たれるやうな懐かしい痛みのなかに咲いてゐる梅
梅は、風の中に咲いている。梅の枝に咲いている。そして梅の木そのものは土の上に生えている。梅が痛みの中に咲いたりはしない。
それを短歌で実感として表現したところに面白みがある。だが、この短歌にはどこかおふざけの感じがある。語り手はまじめくさった顔をしているが、本当にやっていることは真剣か。
もう少し分析してみよう。「父に頬を打たれるような懐かしい痛み」。
ここには、平凡な感じ方を、少し詳しくして面白くした形跡がある。
父→懐かしい
父に頬を打たれた→懐かしい
父に頬を打たれた痛み→懐かしい
このように見ると、「父に頬を打たれるような懐かしい痛み」とは、ほとんど決り文句のような平凡なノスタルジーである。
ただし、「父が懐かしい」に比べると具体性を持ってはいる。
取り巻く幻の痛み
さて、平凡なノスタルジーで始まったこの短歌は、「咲いてゐる梅」で急展開する。咲く梅は現実のものであろう。だが、梅が痛みのなかに咲くわけはない。
ここに来て、「父に頬を打たれるような懐かしい痛み」は、梅の花を取り巻く幻の痛みになる。
ノスタルジーの共感性が、急に幻の側に追いやられる。だが、読者はすでに共感してしまっているから、梅を取り巻く痛みの空間を感じ取ってしまうのだ。
共感性を持つ表現を利用して、梅が痛みのなかに咲くことを受け入れさせる。ここでも荻原の短歌は「おくすり飲めたね」である。
飲んでしまうおくすり
『リリカル・アンドロイド』には、他にもおくすりを飲ませてくる短歌が頻出する。
咲きさかる花火のあとの暗がりに残つて祖母の霊の手をひく
壁のなかにときどき誰かの気配あれど逢ふこともなく六月終る
海中で冬のひざしを見るやうなまなざしを卓のむかうに気づく
祖母の霊の手をひくなどということはオカルトだ。壁のなかには誰もいるはずがない。海中で冬のひざしを見るやうなまなざしを、作者だって見たことはないだろう。
これらの幻を現実の側にたぐりよせるため、一首の残りの部分が使われる。だが、そこで「たぐりよせたな」と読者に思われては、幻は幻のままに終わる。だから、荻原裕幸は残りの部分を「おくすり飲めたね」にするのである。
「咲きさかる」「逢ふこともなく六月終る」「卓のむかうに気づく」。ここには、少しばかり現実を真面目に見た感触がある。「咲きさかる」の「さかる」の適切さ。「六月」や「卓のむかう」という具体性。こういったものが読者にわかりやすく「本当さ」を伝える一方で、祖母の霊、誰かの気配、見たこともない眼差しを、するりと喉に通してしまう。
(短歌はすべて、荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』より)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
