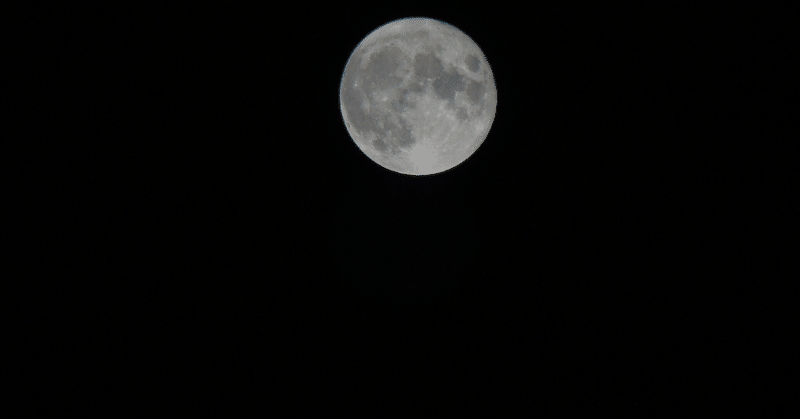
映画「流浪の月」を観てきた
年齢を重ねて、「小さな感動」に対する感度が極端に低下してしまった気がする。
それは、「色々な刺激に慣れてきた」ということなのかもしれないし、「自分が分かる形の何かにラベリングする」ということが、多少得意になったからかもしれない。
…でも、どこかでそういう自分を残念にも思っているわけで。言語化することで、少しばかりでも自分の中に、「小さな感動」を刻む作業をできれば と思って、今、これを書いている。
今回、書き残そうと思ったのは、映画「流浪の月」の感想。ゴリゴリにネタバレなので、観ようと思っている人は、避けた方が良いかもしれない。
この映画は、凪良ゆうさんの同名小説の映画化だ。内容が面白そうだったのと、「パラサイト」の監督だということで、興味を持ち、映画館へ。
以下、あらすじ。
〈女児誘拐事件〉ふたりしか知らない、
あの夏の〈真実〉。
帰れない事情を抱えた少女・更紗(さらさ)と、彼女を家に招き入れた孤独な大学生・文(ふみ)。
居場所を見つけた幸せを噛みしめたその夏の終わり、文は「誘拐犯」、更紗は「被害女児」となった。
15年後。偶然の再会を遂げたふたり。それぞれの隣には現在の恋人、亮と谷がいた。
『悪人』で善悪の境界を朧にし、『怒り』で信じることの困難を世に問うた監督・李相日。人間存在を極限まで掘り下げ、観る者の心にそれまで感じたことのない感情を呼び覚ます濃密な映画体験を提供し続けてきた李が、待望の新作として選んだのは、2020年本屋大賞受賞の凪良ゆうのガラスのように繊細な物語。
(公式HPより)
内容としては、「解れない物語」だった。
というか、「解かる」なんて軽い言葉で、物語をまとめてはいけない気がした。ただひとつ言えるとしたら、観て良かったということだ。
最近のコンテンツは、「共感」にふっているものが多い。それは時代の流れで、もちろん悪くないのだけれど、「解らないを理解する」ということを定期的にしていかないと、どんどん視野が狭まっていっちゃうなと改めて思った。
視聴後、ズドーンと重くのしかかってきて、答えの見えない問いをグルグルと考えている。この物語を観て、傷が抉られる人も居るだろうし、共感する人もいると思う。ただ、やっぱり、私は登場人物の感覚が分かるけど、解らなくて、それはとても幸せなことであると同時に、「考える」ことはしなきゃなと思ったわけである。
以下、備忘録のような、メモのような私の記録を残しておく。
父親が死に、母親は恋人を作り、伯母に育てられている10歳の少女・更紗。更紗は中学生の伯母の息子に、日夜性的虐待を受け、その日常から逃れたいと考えていた。
そんななか、文に「うち、くる?」と誘われ、それに合意。そこで、初めて「自由」を手に入れたわけである。
伯母の家では食べられなかった夕食後のアイスがその象徴として描かれていたけれど、アイスを一緒に食べるシーンは「共犯」としての2人を、分かりやすく表現していた。
「アイスを食べる」という行為を「正しくないことをする」という文脈で使っているのに、感激もした。
15年後の更紗を演じる広瀬すずさんがあまりにも、「イノセント」な存在として浮かび上がっていて、演技云々というよりも彼女の俳優としての華を感じた。重い物語だけれど重くなりすぎす、希望を感じさせる存在として、適任だった。
一方の文は、誘拐時19歳。ロリータ・コンプレックスを隠し、規範のなかで、寡黙で朴訥と生きてきたわけである。
そんななか、10歳の更紗と出会う。更紗と過ごしたその時間だけ、自由を感じ、その純粋な美しさに、自然な笑顔が生じていた。
観ていくなかで、管理的な「正しい」母親のもとで育った反動として、無垢な少女を愛するようになったんだろうなと「解った気」になったりもしたのだが、そういう「解った気」になっている自分もちょっと怖いなと観ながら思った。
文が、「誘拐」時から読んでいた 「ポー詩集」。物語の中でも随所で詩が引用され、それが文の心情描写となっていた。ポーは、13歳の少女に求愛した少女愛者。マイノリティーとしての文を際立たせる道具として、効果的に機能していた。また、更紗の読んでいた本は「赤毛のアン」。それぞれの境遇を反映したような本を交換し、読書をするシーンは、シンプルながら心の交流を効果的に描いていたと思う。
終盤、文は更紗に自身の身体的コンプレックスを吐露する。文が何の病気かは無知な私には分からなかったが(勃起不全?)、身体的コンプレックスを抱いて生きている文の生きづらさが出てくるシーンは、「静かな狂気 」「悲痛な叫び」といった感じで、松坂桃李凄い……となりましたね、ええ。
誘拐から15年後のそれぞれの恋人も興味深かかった。
更紗の恋人・亮は、田舎の地主の息子で大企業の正社員。顔も良く、まさに理想的な彼氏…ではない。
暴力で恋人を支配し、服従させようとしている。その根底に母親が蒸発した過去と、自分もまた将来を規定され、自由の利かない立場にあるように描かれていた。
亮が複雑な家庭環境の恋人を選ぶのは、自分から離れていかないためだ。また、亮はしばしば愛していることの証明として、肉体関係を結ぼうをしている。精神的なつながりが描かれる文と対比した存在としての亮が、イキイキと描かれていて、よかった。最後、自ら肉体性を排除し、しがらみを断ち切ったのは良かったな。亮にも、幸せになって欲しいと思わせる最後だった。
また、文の恋人・あゆみも、リアルだった。彼女は、「正しい人」として描かれる。自立した、自己の考えをしっかりもった積極的で聡明な女性。物語としては描かれていないけれど、「母親」と似た存在として、どこかで惹かれていたし、惹かれようとした気がした。文の過去を言えなかったのも、やはり、あゆみはとても「正しい人」だからで、だからこそ、好きになろうとしたのではないかなと思う。あゆみにそれを詰められた際、1ミリの愛も肯定しなかったのは、文なりの「誠意」で、「愛」にも感じた。
そして、趣里さん演じるバイトの同僚・安西さんも罪深い。安西さんはシングルマザーで生活にも苦労している。そんな中で、金持ちとの恋(不倫)に夢中になり、娘を蔑ろにする。(結果次の"事件"に繋がっていくのだが)。
恋人を作り、逃げていった更紗の母とリンクしてくるわけである。共感しているような顔をして、利用してくるタイプが1番タチ悪いわけで、そういう人間の嫌らしさとか性みたいなものが上手く乗っかっていたなと思った。
15年後に再会した2人は、一緒になって、流浪することを選ぶ。誘拐女児と誘拐犯の「共犯」的な生き方が正解なのかどうか、やっぱり解らなかったし、そこに正解を求める時点で、やっぱり解っていないのだと思う。
ただ、希望とも絶望ともとれる、寓話的でもリアルでもあるその終わり方に、余韻を感じ、しばらくそのことを考えていた。
150分という、今の映画としては比較的長いものではあったけれど、長さを感じさせない魅力に、暴力的な引力を感じたのだった。愛って何だろうね、そんなことも映画は提示してきた。小説家の朝井リョウが「(私にとって)良いコンテンツは答えではなく、問いをくれるもの」みたいなことをどこかで語っていたけれど、まさしくそれで、沢山の問いをこの映画は私にくれた。その答えが出るのは、もう少しあとかもしれないし、それは永遠に解かれないかもしれない。それでいい、それがいい。
「更紗は更紗だけのものだよ」、文は言った。私もまた、私だけの感性や意志を大切に、今日を生きるのみである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
