
おもいとのぞみ
この物語は一部実際の地名や歴史上の人物名を使用しておりますが、ほとんどの人名地名は架空のものです。
登場人物
上棚田想 (かみたなだそう)
草水望 (くさみずのぞみ)
加瀬川巌 (かせがわいわお)
1
昭和50年、日本は行動成長期の夜明け間近。当時は三木武夫内閣で、それまでの戦後経済から脱却しようとしていた。世間は穏やかな景気の中で、テレビを中心としたエンタメで家族団欒を行うことが中流階級の姿となっていた頃。上棚田想は地元の映画館「カシオペア座」に入ろうとしていた。
想は予備校生で浪人一年目。隈川予備校に通っている。東京の関東綜合人材大学は落ち、公立も落ちた結果だった。当然関東綜合人材大学に行くものと考えていたため、落胆ぶりは激しかった。優秀な方だっただけに、想は妙なプレッシャーに苦しんでいた。ゲーセンで遊ぶ気にもならず、彼女を作る気にもなっていなくて、たまたま入った劇場で観た「タワーリング・インフェルノ」の面白さにハマってしまっていた。
この作品はジョン・ギラーミン監督のパニック作品でポール・ニューマンやスティーブ・マックイーンら超豪華俳優陣が目玉の作品だった。それから想は、勉強の合間に映画を観るようになっていた。
映画は、日常のストレスから解放してくれて、自分が自分でいられる夢のような空間だった。想は行ける範囲の映画館はほとんど回り、この「カシオペア座」で最後だった。想はいつものように近くのスーパーでラムネ玉とオレンジジュースを買い、カバンに隠してチケット売り場でチケットを買った。12月なので、待っている間の風がやたら冷たかった。
この日は南アフリカとイギリスの合作映画「マイウェイ」が目当てだった。同時上映作品は「続・青い体験」で、こちらも思春期ボーイには楽しみだった。劇場に入場する際、この当時は途中から入ったりするのは当たり前だったので、想が扉を開けた時には「続・青い体験」の終盤だった。平日だったので、人気は全くなかった。映写室から落ちてくる暖気とかすかな映写機の音だけが聞こえていた。この雰囲気も大好きだった。
想は暗闇に目が慣れるまで入り口近くに立ち、空いた席を探したのだが、やはりほぼ空席だった。右奥に一人だけいたようだが、想は左側の通路側に席を確保した。膝にカバンを抱え、すぐに飲み物を取り出せるようにしていた。
当時の人気女優ラウラ・アントネッリは美しかった。共演のオッタビオ・ジェンマとのラブシーンがあり、そしてエンディングとなった。場内の照明がつけられ、俺は劇場内を見た。
(あれ、女の人だったのか。)
右端に座っていたのは若い女性のようだった。さほど広くない地方の劇場なので、結構な確率で知り合いがいるものだが、さすがに知らなかった。一度気になるとどうしようもなくなり、ブザーが鳴って「マイウェイ」の上映が始まっても集中できずにいた。
だが映画青年になっていた想は、南アフリカという未知の国の映像と社会を見ながら、徐々に引き寄せられていった。裸一貫で自分の会社を立ち上げて大成功したウィル・マドリックスと家族の葛藤、そして人生の価値観を見出したウィルがマラソンに出て走るシーンでは、もう涙が止まらなかった。だが鼻をすするのも恥ずかしかったので、想は何とかこらえていた。
そしてフィニッシュシーン。家族との愛情を取り戻したウィルと家族の愛情が全面に出てきて、さすがに嗚咽する寸前までなったときだった。
「え・・・えく・・・。」
右端にいた女性から嗚咽の声が聞こえてきた。想はこみ上げてきた感情が一気になくなってしまい、女性から目が離せなくなってしまった。女性は暗闇でもわかるくらいに頭が揺れていた。相当に感動したのだろう。そして映画は終わった。
照明がつき、想はもう「続・青い体験」を見る気がなくなり、ロビーに出てオレンジジュースの瓶を収納箱に入れようとした。するとこれ以上ないタイミングで、別方向から空き瓶が出てきた。想は瓶の主を見ようとしたが、見るまでもなかった。あの女性だった。
「あ、ごめんなさい。」
「あ、いえ。」
想は女性の顔を見た。補正は髪を束ねて髪留めをしていて、大人しい感じで派手さはなかったが、ものすごくかわいかった。そしていい匂いがした。女っ気がまるでない想はちょっとした衝撃で、次の言葉が出てこなくなった。
女性は軽く会釈をすると、ハンカチで目を拭きながら劇場を出ていった。想が女性の後を目で追っていると、売店の女性が声をかけてきた。
「お客さん、ここ初めて?」
「え・・・ああ、そうです。」
受付の女性は先ほどの女性客が出ていった入り口を指さした。
「あの人ね、たぶん『ポルト』にいますよ。」
「ポルト?」
「そこを出てすぐ右にある喫茶店。行ってみたら?」
「・・・なんで俺が行くんですか?」
受付の女性は笑って色々仕事を始めていた。想も特に話をするつもりもなかったので、「カシオペア座」を出た。人間とは面白いもので、そう言われると見てしまう。劇場を出て右を見ると、確かに小さな看板が出されていて「喫茶ポルト」と書かれていた。さらに人間の性として、中を覗いてみたくなった。
想はポルトの前まで移動した。中を覗こうにも、でかい木製の扉があって窓はなく、見ることはできなかった。一瞬迷ったが、想は扉を開けて中に入った。
「いらっしゃい。」

気持ちのいい男性の声がした。中は間接照明のみで少し暗く、カウンターだけがあるさほど広くない店だった。席は5つほどのようだ。声の主はカウンターの中からで、白い髪をきれいにバックに整えて、髭を生やした長身の男性だった。そして一番奥の席に、先ほどの女性の姿があった。
「どうぞ、お座りください。」
想は言われるがまま、入り口近くの席に座った。何の木かはわからなかったが頑丈な板で作られていて、椅子は据え付けになっていた。壁には「ローマの休日」と「シュルプールの雨傘」のポスターが飾られていた。そして「チャールトン・ヘストン」「ロバート・レッドフォード」「スティーブ・マックイーン」らのポートレートも飾ってあった。
そして件の女性は何やら本を読みながらコーヒーを飲んでいた。薄いピンク色のコートを着ていたと思ったが、コートは壁に掛けられていた。白いセーターとダークブラウンのスカートを履いていて、ロングブーツが見えた。髪は下ろされていて、ウェーブがかった髪で表情は見えなかった。
「はい、メニュー。今日のおススメは、このホットケーキセットですね。コーヒーはキリマンのブレンドです。
「え?・・・あ、はい。」
想は彼女ばかり目が行っていて、マスターが差し出したメニューに驚いた。メニューは小さな写真アルバムに収められていて、非常に見やすくて好感持てるものだった。想はとりあえずホットケーキセット350円を注文した。
出されたホットケーキは直径15センチくらいのものが2枚重ねられていて、バターが乗っていた。横にはハチミツが添えられていて、ハムと目玉焼きが乗ったサラダ、そしてコーヒーというもの。かなりボリュームがあり、これでこの値段なら良心的だ。想は食べながら、やはり彼女が気になってチラチラ見ていた。
「お客さん、いかがです?」
「え・・・あ、おいしいです。」
「学生さん?」
「いえ、あ、まあそうです。浪人です。」
「ああそう。来年受かるといいね。どこ志望なの?」
「一応関東綜合人材です。」
「へえ!そりゃすごい。しっかり食べてってね。」
マスターと会話していながらも、想の視界は広くしていたので、彼女がこちらを向いたのがわかった。何にどう反応したのかわからなかったが、ここのマスターはかなり話好きなようで、次々に話題を振ってきた。
「どうしてうちに来たの?」
「あ・・・そこの映画館出たらあったんで・・・。」
マスターはニヤリと笑った。
「ははあ、ここに行ったらいいよって言われたんでしょ。」
「は?なんでわかったんですか?」
「いえね、あそこの受付、私の姉なんですよ。お客さん一人だったんでしょ?そうと見るとすぐに勧めるんですよね。すみませんねえ。ああ・・・そちらもそうでしたっけ?」
マスターは彼女に話を振った。
「最初はそうでしたね。なんで私が行くのって思いました。それからはこの流れになっちゃいましたけど。」
「まあ、ありがたいことなんですけどね。癒着の度が過ぎるからもういいよって言ってるんですけどねえ。昔から世話好きな姉だったんですよ・・・あ・・・ひょっとしてご一緒でした?」
マスターは想と彼女を交互に見た。
「違います!」
想と彼女は同時に答えた。そして目が合って、なんかおかしくなって二人とも笑い出した。
「あら、もう気が合っちゃってるよ。よかったらお隣でどうです?」
「え?いえ、いいですよ。」
「まあそう仰らずに。袖触れ合う縁も何とやらってね。さあ、どうぞ。」
言いながらマスターは、想のコーヒーをさっさと彼女の隣に移動させた。彼女を見たがさほど嫌がっているようでもなかったので、想は移動して彼女の隣に座った。
「ごゆっくりどうぞ。」
自分も世話好きだろと思いながら、想は内心ドキドキしていた。彼女のいい香りが鼻をついた。彼女が読んでいた本は、タイトルはわからなかった。ただ、すごく大切に扱っていることはわかった。
「あ、ども。」
「ええ、はじめまして。」
「あの、俺・・・僕は上棚田想って言います。」
「私は草水望です。」
マスターは微笑んで二人を見ていた。
2
「へえ、じゃあ上棚田さんって浪人生なの?」
「そうなんですよ。本当なら関東綜合人材大学文学部に行ってたはずなんですけどね。」
「あら・・・。」
「どうかした?」
「あ・・・あの、そう、わたし・・・関東綜合人材の文学部なの。」
「え?・・・そうなの?」
「そう・・・ワンダーフォーゲル。」
「そうかあ・・・本来なら、俺たち同級生だったんだ。はああ・・・。」
想は持ち上げたコーヒーカップを落としそうになった。望は慌てて手をカップの舌に添えた。
「あ・・・す、すみません。まだショックあるのかなあ。」
「なんか・・・ごめんね。」
「いや、だからあ。謝られると余計みじめになっちゃうじゃん。」
「じゃあ、どうしてればいいの?」
「どうって・・・まああの、その・・・。」
絶妙なタイミングで、マスターがグラスをコーヒースプーンでカンと叩いた。狭い店内なのでやたら響いて聞こえた。
「はーい、第一ラウンド終了ね。」
そう言われると、想はすっごく恥ずかしくなってきた。望も真っ赤になっていた。
「いやその、どうも。よし、来年こそ通ってやる!」
「いいねえ、その意気。よし、お二人に私からの奢りだ。これ、食べて。」
マスターが出してくれたのは、500円玉サイズのクッキーだった。白くてプレーンっぽかった。
「私が焼いたんだよ。美味しいと思うよ。」
想と望は、クッキーを口にした。
「美味しい!すっごく美味しい!」
「うめえな、これ。バターの香りがすごい。」
「あれ・・・これ、紅茶入ってます?」
「あ、そう言われれば確かに紅茶の香りもする。」
マスターはニコニコしながら頷いた。
「お見事。これはね、国産の無縁バターに和三盆と練乳を入れてね、紅茶の葉を砕いて焼いたの。私はクッキーが好きでね。お口に召したかな。」
「いやあうまかったです。どうもありがとうございます。そろそろ、僕帰ります。お会計を・・・。」
「えー、姉の紹介なので、今回はお代いりません。」
「え、それじゃ悪い・・・。」
「いいの。それが私たちのルールなんだからさ。」
「ひょっとして、好意受けないと呪われちゃうとか?」
「望ちゃん、バカなこと言わないの!人聞き悪いじゃない。良かったらまた来てね。」
「あ、はい。どうも御馳走様でした。」
帰り際に、想は望を見た。望は手を振ってくれた。その笑顔は最高に素敵だった。その笑顔を見ていると、どうしてもこのまま帰ることはできなくなった。
「あ、あの。」
「あれ、なにか忘れ物?」
「いえ・・・あの、草水さん。」
「え、わたし?なにか?」
「あの・・・良かったら、電話番号の交換を・・・お、お願いしたいなって。」
「えー・・・いや、それはちょっと・・・。」
「あ、い、いいです!ごめんなさい!」
想は全身の汗腺が一気に開いたくらいに汗をかいていた。冬なのに、セーターが邪魔になるくらいだった。そこにマスターが口を挟んできた。
「そりゃあちょっとねえ・・・でもね、いい方法があるよ。」
「え?」
「ここに電話すりゃいい。お互いにいついるかって知ってればいいじゃない。もしいなかったら、私が伝えてあげるよ。それならどう?」
想は望をチラ見した。猛烈に反対されるかと思っていたら、反応は意外だった。
「マスター、いいんですか?それならわたしもいいですよ。」
「え・・・いいの?」
「うん、そうね。でもマスターが間に入ってくれるならそれでいい。そして・・・いや、それでいいわ、マスター。」
「何か無理してない?」
「ううん、全然。わたしも君と仲良くなりたいもん。
想は別の意味で汗をかいていた。衝動的に言ったものの、もし完全シャットアウトになったら取り返しがつかないところだった。だが内心、嬉しくてしょうがなかった。
「じゃあそういうことでいいね。そうだなあ・・・望さん、明日の夕方は何時くらいに来れる?」
「そう・・・ですね。明日はご飯終わってからの、6時ならいいかな。」
「じゃあ想さん、明日はどうなの?」
「ええと、予備校終わってだと・・・電話は大丈夫です。」
「よし、では明日電話してみてね。ああ、番号はこれね。」
マスターはカウンターを指さした。そこには店の紹介カードが置いてあった。マスターの名前は「加瀬川巌」とあった。想はカードを取り、財布におさめた。
「ええと・・・あの、草水さん、いきなりでごめんなさい。」
「ううん、嬉しい。素敵な出会いかも。ね、マスター。」
「そういうこと。じゃあ気を付けてお帰りください。」
「はい。じゃあまた。」
想は望に軽く会釈して店を出た。今度はもう振り返らなかった。なぜなら、とにかく無性に飛び跳ねたかったからだ。別に恋愛ではないのだが、展開に興奮していたのだろう。
雨は降っていなかったが、想は近くの街頭につかまって「雨に歌えば」のシーンを踊りながら帰宅の途についた。
3
それからというもの、想は毎日のように喫茶ポルトに電話をした。望がいるときもいないときもあったが、どのみちマスターが伝言してくれていたので、会話しても違和感なかった。たまにポルトで会うと、とにかく楽しかった。望の笑顔を見ていられるからだ。そして望の笑顔は最高だった。望も本当に楽しそうにしていた。毎日が楽しくなり、勉強もはかどってきていた。
会話は主に映画の話だった。望が古い時代の映画が好みだったので、まだファンになりたての想は感心することばかりだった。
「望ちゃんってさ、どこでそんな古い映画観るの?」
「ん~まず、ちゃんはやめて。」
「え?」
「望でいいよ。わたしも想って呼びたいから。」

「そう?だったら、ええと・・・望は、どこでそんな古い映画を観てるの?」
「ギンマクとか文明文化座とかかなあ。」
「なにそれ。」
「そっか。想はまだ映画ファンになりたてだもんね。名画座って言ってね、古い映画を安く観れることろがあるの。」
サブスクもレンタルビデオもなかった時代である。映画ファンは公開された映画ばかりでなく、店主の好みで上映される名画を観るために、よく名画座に通っていた。なにせ300円で下手すると3本観れたりすることもあったのだ。だが想はまだ知らなかった。
「そんなとこがあるんだ。よし、そのうち行ってみる。」
そこで、マスターがすかさず入ってきた。
「想ちゃんさあ、まさか一人で行くなんて思ってないよね?」
巌マスターの一言はまさにズバリだった。想は思いっきりカウンターパンチを食らったような気になった。
「え?え?え?」
「だから想ちゃんは・・・望ちゃん、この子を連れてってくれる?」
「わたしが?」
「そりゃそうでしょ。だってそもそも映画館で初めて会ったんでしょ。」
そういえばそうだった。まだそのことについて尋ねてもいなかった。
「ああ・・・そうだったよね。『マイウェイ』観ながら泣いてたじゃん、望って。」
「・・・聞こえてたの?」
「だって、二人しかいなかったし。」
「嫌だ、恥ずかしい!」
望は真っ赤になって下を向いた。
「別に恥ずかしいことじゃない。あれはいい映画だよ。想ちゃんもそう思うでしょ。」
「うん。いい映画だった。」
望は首を振って顔を上げた。
「わたしね、人前で泣くことってしちゃダメだって思ってきたのね。だから・・・はあ。」
そして望はスケジュール帳を取り出してページをめくった。
「想は、今度の土曜日のお昼12時には空いてる?」
「予備校だからそりゃいつでもいいけど。」
「この日にね、前から行ってみたかった名画座があるんだ。『チネマテアトロ6』ってとこ。場所は・・・ええと、ここね。」
望が示した場所は、幸いにも予備校から電車一駅くらいのところだった。
「うん、すぐ行ける・・・え、一緒に行くってこと?」
「想ちゃんさあ、あんたもうちょっと成長しなよ。女の子から言わせるんじゃないよ。」
残念なことに、想は全く女性と付き合った経験もなく、どうしていいかわからなかった。またこの時代においては、まだまだ古い時代の感覚が残っていた。
「え・・・ど、ど・・・。」
「ちゃんとしろよ!想から誘うんだよ!」
想はもう鼓動が激しくなっていた。まさかこんなことになるなんて。だが確かに巌マスターの言う通りだ。想は覚悟を決めた。
「ええと・・・今週土曜日に・・・お、お、俺と、映画に行ってきゃ・・・行こ・・・行きませんか!」
「うん、行こう。」
望はあっさりと答え、想はまたまたどうしていいかわからなくなった。想はマスターを見たが、マスターは知らん顔でカップを拭いていた。
「ええ・・・と・・・ああ、はい。」
「想って。」
望が想に顔を近づけてきた。それだけで想は気を失いそうになっていた。
「珍しいくらいに純情。でも、嫌いじゃない。」
「そ、そう?望もそう・・・。」
「違うと思うけど。」
そう言って、望は軽くため息をついた。そしてコーヒーを飲み干し、バッグを抱えて立ち上がった。
「マスター、わたし、そろそろ帰るわ。はい、コーヒー代。ここに置いておくわね。」
「おや、もう帰るの?気を付けてね。」
「うん、ご馳走様。じゃあ想、土曜日の12時にチネマテアトロ6ね。バイバイ。」
望は店を出ていった。なんとなく、後ろ姿がいつもと違って見えた。
「マスター、望、どうしたんだろ。」
マスターはカップ拭きをやめて、想をじっと見た。
「想はさ、まだ未成年じゃん。だからまだわからないこともたくさんある。だからね、これはよく覚えておいて。わからないことは、黙っておくこと。黙って知識を得て、自分の中で消化してから口にすること。望ちゃん・・・なにかあるんだろう。」
そこまで言ってマスターは黙った。想は居心地が悪くなって、帰ろうとした。
「もう帰るの?ああそうだ。また姉貴の劇場にも行ってあげてね。」
「うん、わかった。またね。」
想は店を出て地下鉄の降り口まで歩いていった。と、そこで想は見た。
(あれ・・・望じゃ?)
公衆電話ボックスの中で話していたのは、間違いなく望だった。だが、その望は想が知らない姿だった。泣きわめき、壁を叩きながら喚いていた。激しい感情を全面に出していた。想は立ち止まり、しばらく見ていたがやがて地下に降りていった。

(なに叫んでたんだろ・・・。)
見てはいけないものを見たような気がしていた。
4
想は約束通りに「チネマテアトロ6」の前に来ていた。まだ望は来ていなかったので、初めての名画座を覗いてみたり、受付にあるチラシを見たりしていた。
(へえ・・・イタリア語なんだ。)
チネマはシネマのことで、テアトロはシアターのイタリア読みらしい。イタリア映画はまだよく観ていなかったので、この地で映画が盛んであることも想は知らなかった。
(で、なんで6なんだ・・・『プリズナーNО6』から引用?これを館長が好きだったからって?そもそもこれ知らない。)
『プリズナーNО6』は1967年のアメリカのSFテレビシリーズだ。かなりマニアックな館長のようだが、そのことすら想は知らなかった。すると望の声がした。
「ごめん、待った?」
「ううん、ついさっき来たとこ。」
「ええと・・・上映まであと10分か。入ってようか。」
「うん。」
想と望は劇場内に入った。その時初めて想は本日上映作品を知った。
「今日は・・・『明日に向かって撃て!』と『サウンド・オブ・ミュージック』・・・どっちも観たことないな。」
「どっちも名作よ。『明日に向かって撃て!』はロバート・レッドフォードとポール・ニューマン主演で、『サウンド・オブ・ミュージック』はジュリー・アンドリュース主演で・・・ほら『ドレミの歌』知ってるでしょ。あれよ。」
だがそう言われても想はまだ観ていないのでわからなかった。代金400円を支払い、想と望は中に入った。もう半分ほど席が埋まっていた。名作である証拠だろう。ということは観客も映画ファンなのだろうか。そしてブザーが鳴った。
最初は『サウンド・オブ・ミュージック』だった。オーストリアのマリアが、ナチスとの間で揺れる物語だ。確かに名曲が数多くあった。そして次は『明日に向かって撃て!』で、伝説のアウトローで実在の銀行強盗ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドの逃避行を題材にした西部劇だ。想にとっては、これは面白かった。大体において、男子はこういうアクションものが好きなのだが、途中から変化してきていた。3人の関係性が主体になり、徐々に追い詰められていく。途中、大ヒットした名曲『雨にぬれても』が出てきて、想が知らなかっただけで、世の中にはかなり映画音楽がヒットしているのだと思い知らされた。
そしてラストのシーン。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードがボリビア警察に囲まれて、「次はオーストラリアに行こうぜ」と言って飛び出したところでストップし、「撃て!」という声で雨のように銃弾音が聞こえた時だった。想の手を、隣にいた望が握ってきたのだ。
想は驚いて望を見たが、望はハンカチを目に当てていた。俺の手を握る力は強く、かすかに震えていた。
エンディングとなり、エンドロールの間ずっと、想と望はそのままだった。そして照明がつけられ、観客が帰っていく間もずっと同じだった。想はどうしていいのかわからないままだった、意を決して望の手に自分の手を置いた。望はそれでも震えていたので、想はその手を望の肩に置いた。まだ震えていたのだが、少しずつおさまってきた。
「・・・ありがとう。」
望の声が聞こえ、やっと顔を上げた。涙でぐしゃぐしゃだった。
「どうしたの?大丈夫・・・。」
「もういい。出よう。」
2人は席を立って劇場を出た。もう夕方になっていた。長い間座っていたので、妙に尻が痛かったが、想はどうしていいのかまるでわからなかった。そして気がついた。あれからずっと、2人は手を繋いでいたままだった。
「あ、悪い。」
想は手を離そうとしたのだが、望は離さなかった。
「望・・・?」
「お願い、このままでいて。もうちょっとでいいから!」
想は言う通りにするしかなかった。だがもう夕方だ。そろそろ帰らなければならない。
「望、もう帰ろうか?どっちに行く?」
望はほんのちょっと頷いて、指さした。
「こっちね。歩くよ。」
2人は手を繋いだまま歩き出した。どこに行こうとしているのかわからなかったが、歩くしかなかった。できるだけゆっくり歩いたのだが、いつまでたっても望の歩みは止まらなかった。
「ねえ、どこまで?」
我慢できずに想が訊ねると、望はようやく手を離した。もうすっかり暗くなっていた。風も冷たく、望はマフラーを少し顔まで上げた。
「ありがとう。もう・・・いい。」
「え、ここ?でもここ・・・地下鉄もバスもないよ。どこまで行くの?」
「こっちじゃないんだ。」
「え?」
「ごめんね、手を離すと大泣きしそうだったから。わたしの家、ちょっと離れてる。タクシーで帰るよ。想はどうするの?」
「え、どうするって・・・ここから戻って・・・。」
望はにっこり笑って頭を下げた。
「ごめんね、変な付き合いさせちゃって。また今度、ポルトで会おうね。」
「あ、ああ。そうだね。」
「じゃあ、お勉強頑張ってね。わたしの後輩になるんだよ!じゃあね!」
望は手を振りながら去っていった。想も手を振ったのだが、とんでもないことに気がついた。
「あー!電車代!」
望に借りようと思っていたところだったのだ。財布の中には20円しか残っていなかった。しょうがなく、想は近くのタバコ屋に行った。映画に行ったなんて伝えていなかったので家にも電話できず、どうしようと思っていると、ふと思いついた。想はポルトに電話してみた。
『おや想ちゃん、どうしたの?今日は映画じゃなかった?』
「うっかりして・・・。」
望とのことは黙って、電車賃がなくなったことを告げると、マスターは大笑いした。
『あっははは、若い時にはよくあるやつだ。今どこ?』
想はあたりを見て、大まかな住所を伝えた。
『ああ、そこか。だったらうちからなら30分で着く。迎えに行くからさ、そのあたりに喫茶店ボルドーってあるはず。その前にいてよ・・・いや、寒いね。私が電話しておくから、中に入らせてもらいなさい。』
「ごめんなさい!」
想は電話を切って、喫茶ボルドーを探して店内で待った。間もなくしてマスターが来てくれて、おまけに家まで送ってくれた。
「マスター、すみません。今度お金できたら・・・。」
「馬鹿言ってんじゃないよ。予備校生にお金なんざ期待しちゃいないよ!これでもね、私は結構硬派なんだからね。ましてやうちの大切なお客さんだ。言いっこなしだ。いいね!」
想は黙るしかなかった。そして家のすぐ近くで下ろしてくれた。
「すみません、マスター。また今度お店に行きます。」
「望と一緒にね。じゃあね。」
去っていくマスターの車を見ながら、想はどうやって恩返ししようかと考え、そして望の奇妙な行動を思い出した。
(望・・・どうしたんだろ。)
5
望との映画デートの後、想はしばらく勉強に専念した。なんとなくやる気が起こらなかったのが、望という存在と出会い、無性に大学に行かなくてはという気になったのだ。望と同じキャンバスに行きたいという思いが強く、当然文学部志望となった。歴史や英語は得意だったので、全く問題はなかった。人間のモチベーションってどこから来るのかわからないものだ。
数日ポルトに連絡しない日が続いたある日、予備校から帰宅していた途中のことだった。バスを降りて歩いていると、公衆電話ボックスが開いた。
「あ・・・望!」
淡いピンク色のロングコートに身を包んだ望だった。タータンチェックのマフラーをしていて、肩までの髪の毛が風になびいていた。望も想を見て、笑顔が浮かんだ。そして手を振って近づいてきた。
「想!久しぶり!聞いたわよ。マスターに送ってもらったって?」
「もう聴いたの?そうなんだ。全く俺ってさあ・・・。」
「予備校生じゃしょうがないよ。なんかあったらわたしに言ってね。」
「冗談じゃないよ。女子にお金出させるなんてできないじゃん。」
「あら・・・想って結構古いタイプ?もうそんな時代じゃないよ。」
「そうかなあ。でも俺は自分でなんとかしたいんだ、うん。」
望は少し間を開けて笑い出した。
「ふふふ、いいわね、想。わたし、そういう引っ張っていってくれるタイプ好きよ。」
「え・・・い、いや、そんなつもりじゃ・・・。」
「じゃあ甘えちゃおうかな。お金じゃなくてね。」
「なに?」
「えとね、『ドリームパレス』のチケット貰ったんだ。連れてってくれる?」
「『ドリームパレス』?いいよ。あー・・・でもアトラクションは俺が払うからね!」
「うん!じゃあ、今週の土曜日は?」
「ええと・・・あー、模試がある。日曜ならいいけど。」
「オッケー。じゃあ日曜日ね。」
「うん・・・ねえ、どこか入る?寒いじゃん。」
「そうね、ポルトはちょっと遠いから、わたしが知ってる喫茶店でいいかな。すぐ近くなんだ。」
「うん、いいよ。行こうか。」
想と望は歩いていった。途中、望が思い出したように語りかけてきた。
「あ、この間はごめんね。わたしが悪かったからね。遠くまで行っちゃって。」
「あ、ああ。どうしたの?」
想は先日の望が、映画で感動しただけとは思えない狼狽ぶりだったことを思い出した。ずっと手を繋いで歩いてきて、それで足代が足りなくなったのだ。
「あの時ね・・・ちょっと色々あったんだ。でも想で助かったよ。」
「あのさ。」
「なに?」
「訊いていい?」
「なにを?」
「彼氏・・・いるの?」
望は下を向いた。想は、しまったと思ったが、望はすぐに顔をあげた。
「いないよ。」
「過去形じゃないよね?」
「いないって。」
「あ・・・そうなんだ。」
想は先日、電話ボックスで激しく叫びながら電話している望を見ていた。ひょっとしたらあれが、彼氏だったのかもと思っていたのだ。
「なんで訊くの?」
「え?・・・まあその、なんとなく。」
「なんとなく、か。まあいっか。」
「え、どういうこと?まあいっかって。」
「想はねえ、純粋なんだよね。」
「意味がわかんねえよ!」
「そっか・・・。」
望は軽く笑みを浮かべて続けた。
「あのさ、想こそ彼女いるの?」
「・・・残念ながら、ゼロ。」
「付き合ったことは?」
「片想いばっか。俺、剣道やってたから、練習と勉強ばっかで。」
「そか・・・じゃあひとつ教えよう。」
「なになになに?」
「あははは、気になる?」
「あ、当たり前じゃん!」
「あのさ・・・女の子ってね、基本は男性に引っ張ってもらいたいんだよ。」
「引っ張る?」
「そう。色んなパターンはあるけど、基本はそう。」
「ん~・・・イマイチわからん。なんで今それ?」
「ほーら、わかってなーい!」
望は呆れたように肩をすくめ、想の顔を見た。
「あのさ、想って本当にダメだよね。」
「そう言われても・・・なにが?」
「はあ・・・まあいっか。」
望は肩を下ろし、そして思いついたように想の手を握ってきた。
「え?また何か?」
「いいから、黙ってて!」
望はかなり強めに言って、想はまたまたどうしていいかわからなくなった。ただ、やたら心臓が激しく動いてはいた。想はチラチラと望を見たが、望はもう口を開かなかった。となるとただ歩くしかない。2人はしばらく手を繋いで歩いた。
「あ、ここ。」
望が急に立ち止まったので、想は危うくつまずくところだった。そして望が指さした先を見た。
「喫茶REⅯ・・・ここが知ってるとこ?」
「うん。でもちょっと変かも。」
「え、高いとこ?」
「ううん、そうじゃないけど・・・入ろうか。」
望は手を繋いだまま、想と一緒に扉に手をかけた。その時、急ブレーキの音がした。
「わー!」
一台の原付バイクが突っ込んできた。寒さで道路が凍結していたようだ。
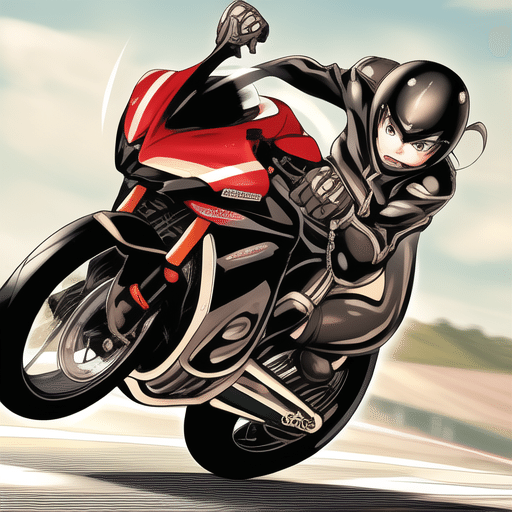
「危ない!」
想は望を店内に押し込んで、自分は反対側に逃げた。間一髪で衝突を避け、バイクは壁にぶつかって去っていった。想は起き上がろうとして肘に痛みを感じた。
「痛え・・・。」
「想!大丈夫?」
想は痛い箇所を見てみた。転げて凍結した道路にこすったのだろう。ダッフルコートに穴が開いていた。少し血も滲んでいた。
「大丈夫だけど、ちょっと痛いかな。」
「どうする?帰る?」
「そうね・・・ハンカチ持ってる?」
望はハンカチを取り出して、想に差し出した。青い縁取りで鳥の絵がプリントされていたハンカチだった。
「後で洗って返すね。今度の日曜日に持ってくるけど、それでいい?」
「うん、いいよ。」
ここからバス停まではすぐだったので、想はコートを脱いでハンカチで傷口を押さえた。寒風がやはら寒かったので、すぐにまた着た。そして喫茶REmの看板を見上げてつぶやいた。
「これが変ってこと?」
「そうね・・・そうかも。じゃあ日曜日にね。」
望はずっと玄関で想を見送った。想は肘の痛みやこの店が気になったが、それよりも見送ってくれた望がすごくきれいに見えた。
6
望と偶然会った日からしばらく、想は望を会うことはなかった。REMにも来ていないそうで、巌マスターも少し心配していた。
「本当に、何があったんだろうね。特に何も言ってなかったからねえ。」
「そうですか・・・。」
2人は少し無言になった。口を開いたのは巌マスターだった。
「あのさ、訊いていい?」
「なに?改まっちゃって。」
「想さ、望ちゃんが好きでしょ。」
想は飲みかけのホットココアを吹き出しそうになった。
「じょ・・・冗談はやめてよ!何言い出すの?」
「あははは、悪い悪い。でも、本当のところそうじゃないの?」
想は自分でもはっきりとはわかっていなかった。確かに望はきれいだし、彼氏も絶対いたはずだし、モテないはすがない。だが想はごく普通の予備校生だ。不釣り合いだとわかっていた・・・痛いほどに。
だがその一方では何かしらで連絡取れないと、どうしようもないもどかしさがこみ上げてくるのも事実だ。
「あのさ、マスター、俺にもわかんないんだよ。望はきれいだし、話は合うけど。でもさ、ついこの前まで彼氏いた・・・と俺は思ってるんだ。」
「それ、想の妄想でしょ。」
「絶対いたはずだって!」
想は、電話ボックスで狂ったように壁を叩き、喚いていた望のことを思い出していた。よほど嫌な別れ方をしたんだろうとしか思えない姿だった。だがそれを巌マスターには言わなかったし、言いたくもなかった。
「そうなの?まあそりゃあねえ、望ちゃんはモテると思うよ。タレントになってもおかしくない別嬪さんだしね。でもさ、想。よく聴きな。恋愛にはそんなの関係ないんだよ。」
「・・・なんかえらく重いね。そんな経験あるの?」
「私にあるわけないでしょ。でもさ、長く生きてるとそういうのをよく見ちゃうわけ。たくさんいたよ。すごい美人さんが、ごつくて全然イケメンじゃない旦那だってパターン。要はここってこと。」
マスターは自分の胸を親指で指した。
「つまりハートってことか・・・それも自信ないけど。」
「ほーら、やっぱり。」
「何が?」
「自信がないってことは、告白するだけの気持ちはあるってことじゃん。」
想は言葉を失った。伊達に年齢を重ねてはいないマスターの言葉は、想の心の奥底まで響いた。
「すげえよ、マスター。そうなんだろうね、きっと。そうかあ・・・。」
「ひとつはっきりしたんで、それは置いておこう。望ちゃん、どうしたのかねえ。」
「マスターは電話番号知らないの?」
「うん、知らない。かかってくるだけなんで。」
まだまだアナログの時代である。番号履歴などあるはずもなかった。
「そうか・・・じゃあしょうがないな。そろそろ俺、帰るよ。」
「そう。また模試?」
「浪人生だしね。」
想はコーヒー代を払ってポルトを出た。もうすぐ師走だ。風の冷たさが身に染みてくる。マフラーを少し上げて、風の冷たさを軽減しようとした。
「うん?」
誰かが想を呼んだような気がした。想はあたりを見回したが、何人かの通行人はいたが誰も知り合いはいなかった。
(気のせいかな)
想は肩をすくめて歩き出した。もうすぐたて続けに模試がある。今さら慌ててもどうしようもないのだが、とにかくやるだけやるしかない。家への距離はさほどでもないのだが、寒風があるだけ辛い。するとまた、あの妙な感覚がやってきた。
(あれ・・・)
まただった。想は止まって見渡したが、今度は誰も歩いていない。だんだん気味が悪くなってきた。それは耳で聞こえるのではなく。心に直に突き刺さるようなメッセージだった。それを形にするのは難しく、ただただ心に響いてくる何か、としか表現できないものだった。
(なんだ、これ・・・)
強制するような感じではなく、探ってくるような、想を知りたがっているような・・・あえて表現すればそんな感じだった。だが決して不愉快になるものでもなかった。むしろ、心強い感じすらするものなので、だから余計奇妙に感じていた。
「変だな・・・勉強疲れなのかな・・・。」
多かれ少なかれ、受験生はこの時期ナイーブにはなるものだ。それはそうだろう。自分の人生がこの時期にかかっているわけなので。だからそれなのだろうと想は考えていた。
それと同時に、絶対に抗えない力も感じていた。母親の胎内にいる赤子のような気分でもあった。
(これが運命の力ってものなのかなあ・・・)
想はこの奇妙な感覚を感じながら、第一志望の関東綜合人材大学受験まで後たった二か月しかないことを思い出していた。どんな運命が待っているのかわからなかったが、かなりモチベーションが下がっていた想を立ち直らせてくれたのが巌マスターであり、望だった。
「クソー!絶対受かってやる!」
望と同じキャンパスにいて、声をかけ、ランチをし、そしていつか告白という流れをぼんやりと考えながら歩いていた。
「ん?なんだ?」
ちょうど周囲にビルも民家もなくなり、家近くの遊歩道を歩いていた時だった。正面から何かが飛んできたのだ。想は避けようとしたのだが、避けきれずにそれは顔にぶつかった。
「うわ、なんだこれ?」
やたら軽いものだった。想はそれを見た。
「え?これ、マイウェイじゃんか。」
それは、以前に見た映画「マイウェイ」のチラシだった。よく見たかったのだが暗かったので、想は街頭まで持っていった。
「あー、やっぱりカシオペア座のだ。誰かが捨てたのかな。」
上映日と場所が記載されていた。想は前方を見たが、誰もいそうになかった。どこからか風で飛ばされてきたようだ。想はどうしようかと思ったが、そのままバッグに入れた。どうせただのチラシだ。想には嬉しいものだったが。
歩きながら、想はあの時のことを思い出していた。望と最初の出会いはあそこだった。あそこにたまたま2人だけで劇場を独占していて、しかも弟の店を紹介してくれた店員さんがいたから、ポルトで二人は話せた。マスターとも親しくなれた。そこにもってこのチラシだ。想はさきほど考えていた運命の力をちょっとだけ信じるようになった。
7
それからしばらくの間、巌マスターも想も、望と連絡できなかった。だがマスターは情報を集め、どうやら旧市街あたりに住んでいるようだとわかった。そこはいまだに木造のボロ家が点在する地域で、裕福ではない地域だった。
「あそこ?望が?そうなんだ・・・。」
「まあ、あそこはよく何かしら起こっているところだし、トラブルに逢ったかもしれない。今のところはそっとしておくしかなさそうだね。」
住んでいる地区がわかったところで、どうしようもないことだった。
「でも想は受験があるでしょ。そっちに専念しなくちゃならないし。いい機会と考えたら?」
「まあそりゃそうだけど・・・俺たち、別に付き合ってるわけでもないし。」
「あははは。想は嘘つけないよ。全部顔に出ちゃってるよ。」
「え?どこに?」
「ほら、すぐそうやって顔を触る。好きだって言ってるようなもんじゃん。」
想は真っ赤になった。こういう大人には嘘はつけない。
「参ったな。さすが人生経験豊かだ。」
「いずれ、想もなるって。」
「ねえマスター、大人って、どうなんだろうね。俺、映画好きじゃん。映画の中ではさ、大人の世界に触れている気がしてるんだけど、でも俺は全然大人じゃない。これってどうなんだろ。」
巌マスターはちょっと複雑な表情で、空になった想のカップにコーヒーを注いだ。想のような常連には無料で追加できていた。
「そうだなあ・・・私も経験あることなんだけどさ、映画を観た時にはわからない感覚ってあるでしょ?」
「うん・・・ある。これが大人なんだろうなって思うけど、実感ではわからない。」
「うん、それでいい。たとえば親子の話があるとする。でもさ、想みたいな若い人にはその意味がわからない。結婚して子供ができたら、その時初めてわかる。」
「そうかあ。よくさ、西部劇で酒場の殴り合いなんてあるでしょ。あれもまだわからないんだ。周りにそんなのないし。」
「私は前に何回かアメリカに行ったことあるよ。東部ではないけど、アリゾナとかあたりではそういう酒場がまだあってね。その時初めてわかった。だからさ、今は、この時代にはこういうことがあったんだって思うだけでいいんじゃない?大人になる前の知識って思えばさ。」
「アメリカかあ・・・行ってみたいな。」
「そうね。まだアジア人差別とかはあるんで、ハワイあたりからならいいと思うよ。あそこは日系人が多いから。」
「ハワイって、フラダンスのとこでしょ?何かあるの?」
「まだ知らないからね。あそこは日系人が発展させたようなものだから、ちゃんと町があるよ。あ、そうそう、アロハシャツってあるでしょ。」
「うん。」
「あれはね、着物を持っていった日本人が、ハワイ向けに着物で作ったシャツなんだよ。」
「えー!そうなの?知らなかった!」
「そうなんだよ。だからね、映画だけじゃなくてね、色々わからないことがあったらすぐに調べてみたらいい。百科事典でもいいし、ほら広辞苑でもある程度わかるんだから。」
「そっか。さすがだマスター。勉強になりました!」
「ついでにさ、想はなんで勉強してるの?」
「そりゃ受験のためで・・・。」
「それはそうだけど、だったら意味がないじゃん。学問は必ず実生活に役立つものばかりなんだよ。だからちゃんと学んでいた人が社会に出て全部忘れちゃうなんて、本当にもったいない。忘れちゃダメだよ。そしてね、そう思ったら楽しくなる。楽しくなったら覚えられるし、忘れない。例えば想は、微分積分習ったでしょ。」
「うん。」
「あれは、たとえば壺を作るときにカーブの具合がどの範囲でどう曲がるかがわかったら立体にできるし、逆もまたありなんだよね。機械や建設にも役に立つ。そういうものなんだ。」
「そっか!そう思えばいいんだ!そうやって受験まで見直すといいってことだね。そうしたら無理に覚えなくても自然に入ってくる。ありがとう、マスター!」
想は急に目の前が明るくなったような気がした。気が重かったのが、めっちゃ楽しくなってきた。
「どういたしまして。」
「ついでにさ・・・。」
「うん?」
「女心って・・・。」
マスターは両肩をすくめた。
「こればっかりは・・・永遠の謎だろうね、男性にとっては。」
「え、マスターでもそうなの?」
「そりゃそうさ。だってさ、まず女性は体力的に弱いし、子供産めるでしょ。生理もある。それに理屈じゃ動かない。感情で動く。単純に1+1=2じゃあない。」
「どういうこと?」
「1+1=2って決めつけるの、好きじゃない・・・っていうところかな。」
「そうなんだ!そりゃあわからねえや。」
「普通は1+1=2なんだけど、君の場合にはもっと上かなって言うと納得したりする。でも褒めすぎちゃいけない。少しだけ余白を作っておくと、あの人たちはそこにロマンを感じるみたいね。推測だけど。それともちろんビジュアルも多少はね。」
「うわー・・・俺には無理だよ、そんなの。」
「いやあ、想はイケメンだよ。剣道やってて男らしいし。だけど経験が少ない。想はね、もっとたくさん失敗することだよ。失敗しながら覚えていくもんだ。これこそ理屈じゃない。それにね、若い時の失敗なんて、大人になったら笑い話になるもんさ。取返しのつかない失敗はしょうがないけど、許される範囲ならば、失敗は成功の元ってこと。ビジュアルも、過ぎたらいけないんだよ。その人なりに好感持てるファッションやヘアスタイルであればいい。当たり前に、女性に対しての思いやりもね。」
想は首を振って、少し冷めたコーヒーを干した。
「でも、今日は色々助かったよ。マスターは恩人です。」
「そう?そうだったらいいけどね。」
「うん、そう。じゃあ、今日は帰ります。またね。」
「はい、またね。」
想はポルトを出て、あまりの寒さにニット帽を被った。そして家へ歩いて行った。電車賃がもったいなかったからだ。
歩きながら、今日のことを思い出していた。勉強は未来のためにやるもので、手段じゃないってことが大きかった。数学が何のためにあるのか、古文漢文がなぜ必要なのかを考えた。数学は、専門職に進むのなら絶対必要だし、進まなくても知識くらいはあったほうがいい。古文漢文は人の感情を理解する材料だ。歴史と地理と公民がなぜトータルで必要なのかは、立体的に社会を見るのに役に立つ。理科もそうだ。
(ありがたいな。そう思って復習すりゃいいんだ。)。
気がつくと、ちらほらと雪も降りだしていた。もう間もなくクリスマスなんだった。近所の店からは、ちょっと早いジングルベルが流れてきていた。想は、今度は違ったものを想像していた。
トラッパーハットを被り、白いコートを着た姿の望の姿を思い描いていた。
(かわいいだろうなあ。でもなあ、彼氏いるよな、絶対。)
まだ勇気が持てない自分に多少嫌気がさしながら。想は家路を急いでいた。
8
「あー、終わった!」
関東綜合人材大学の試験が終わり、想は試験会場前で大きく背伸びした。とりあえず、手ごたえはあった。巌マスターからのアドバイスが功を奏し、社会人になって役に立つのが学問だという概念で復習してみたら、それまでの紋々とした受験勉強が異常に楽しくなってきていた。すると無理に覚えなくても、勝手に脳内に入ってくるのだ。
それまでの模試は苦痛でしかなかったのが、急に確認作業と変わっていった。要は覚えにくい箇所だけ頑張ればそれでいいわけだ。それができてからはぐっすり眠れるようになった。ただひとつのことを除いてだが。
(望・・・今どこにいるのかな)
この大学に所属しているはずなのだが、試験中には学生はここにはいない。体育会系の連中も騒音になるのでいない。それでも想は、大学をできるだけ見て回った。どこかに望を感じられるものがないかどうか見たかったのだ。
関東綜合人材大学は文字通り人材育成を主眼とした教育方針なので、即戦力となるべきカリキュラムと施設が完備されている。工業系は巨大な工場があって、授業と実習が同時に行える。法科は裁判所を模した教室で学び、実践できる。そして想が目指し、望がいるはずの文学部には巨大な図書館と細かく分類された資料があり、すぐに検索とコピーができるようになっていた。想は文学部棟に行ってみた。だが、やはり閉鎖されていた。
「ここか・・・でも・・・見れない、か。」
棟の周囲を見て回ったが、窓は高い位置にあって中をうかがうことはできない。私立なのできちんとお金をかけているようだ。想はしばらく歩き回ったが、間もなく門が閉まるので諦めて外に出た。
となると、行くところはポルトしかない。想は電車に乗ってポルトに向かった。
「マスター!終わっ・・・の・・・望?」
「お久しぶり、想。」
いつもの席に草水望が座っていて、マスターと話していた。
「望!今までどこに何してたんだ!」
「まあまあ想、取り乱さないの。試験終わったんでしょ。じゃあ、コーヒーは私の奢りね。」
「え・・・あ、ありがとう・・・。」
想は受験終了の喜び以上に、望が突然現れたことに驚いていた。
「想、お疲れ様。」
「あ・・・ありがとう・・・で、ちゃんと話せよ!何やってたんだよ。」
巌マスターは静かにカウンターの端に移動して、想と望がサシで話せるようにした。感情をあらわにする想を見て、望はコーヒーを一口飲んで語り始めた。
「えとね・・・たくさんのことがあったんだ。それでね、これはまず言っておく。あたしも、想に会いたかった。そしてここに来たかった。」
想は受験疲れから解放された感覚と同時に、望と再会できた喜び、そして望も想に会いたかったということを知り、安堵というか実に奇妙な感覚に包まれていた。
「そりゃあ、俺も同じだよ。本当に会いたかった。」
「ごめんね。」
「詳しくは言わなくていいけど、何があったの?」
望はコーヒーを飲み、じっと想の顔を見た。長く会っていなかったこともあるのだろうが、想には最高にきれいに見えていた。望は髪留めを外した。肩まで伸びた髪の毛はきれいに処理してあって、サラサラだった。
「嬉しいね、想の気づかい。そういうとこが、わたし、好きだよ。」
「え・・・や、やめろよ。恥ずかしいじゃんか。」
「ううん、素直なわたしの気持ちだから、そのまま受け取って。わたしね・・・難しいことなんだけどさ・・・。」
「だから、全部言わなくていいって。」
「言いたいの!」
望は大声をあげた。普段はクールビューティな望なだけに、たまにこういう姿を見せられると、想はどうしていいか全くわからなかった。
「そう・・・なら言っても・・・。」
「でも・・・ごめん、言えない。だから、難しいの。」
すると巌マスターが何かを思い出したように二人に寄ってきた。
「今気がついたんだけどさ、あそこのモールでちょっと早いけどクリスマスバーゲンやってるんだ。私、明日息子が帰ってくるんだけどケーキ買ってなかった。二人で見つくろってくれない?」
想はマスターの顔を見て言いかけたが、先に望が喋った。
「いいよ。どれくらいのがいいの?」
「普通サイズのイチゴケーキでいい。ホールでお願い。で、これお代金。おつりはいらないからね。」
マスターは封筒を望に手渡した。
「ごめんね、今からちょっと出かけるんだ。2時間くらいいないから、何か食べてきてもいいからね。お願いね。」
「わかった。じゃあ想、行こう。」
「あ、ああ。じゃあマスター、また後で。」
2人はポルトを出ていった。道を挟んですぐ近くに、この辺りでは一番大きいショッピングモールがあり、2人は歩いて行った。その間に、望は少しずつ語り始めた。
「想はね、不思議だなって経験したことある?」
「え?何言い出すんだよ。」
「そっか・・・訊き方が悪かったかな。だってさ、カシオペア座で2人っきりで映画観たことから、ポルトで出会うまでだって不思議じゃない?」
「まあ、そう言われりゃそうだけど、考えたこともなかった。でも、いい出会いだったよね。」
「いい出会い・・・か。そうだよね。」
「なんだよ、その言い方。そうじゃなかったの?」
「ううん、違う。じゃあさ、それが偶然なのか必然なのかってことで考えたら、どう?」
「あれが必然?んなわけないじゃん。」
望は意味深そうな視線を想に投げかけた。そして2人はモールに入っていった。
「あ、ここだ。」
そこはもう人がたくさんいた。あらゆるクリスマスグッズが展示販売され、子供用のサンタ服などもあった。そして一段と人が多かったのがケーキコーナーだった。12番の整理券が手渡され、予め購入品目を記入しておいてから待機となっていた。
「あれは1500円だったよね。いくら入っているんだろ・・・え?」
想は封筒の中を覗いて、驚いて閉じて望に渡した。そして望の耳元でささやいた。
(あのさ・・・2万円も入ってるよ)
(え?そうなの?)
2人は驚いて小声になり、何となく話せなくなって黙って待機していた。
「12番のお客様―!」
「あ、はい!」
2人は同時に立ち上がり、そのタイミングの良さに周囲から注目されてしまった。2人は足早に会計に駆け寄り、支払って立ち去った。そしてモール内のフードコートに落ち着き、顔を見合わせた。
「まだ・・・1時間以上あるよ、時間。どうする?」
「そうね。きっとマスター、わたしたちにゆっくり話せって言いたいんじゃないのかな。」
「でも、なんでそこまでやってくれるの?」
望はまた意味深な笑みを浮かべ、ケーキの箱を見た。クリスマス仕様のテープで結んであった。
「それはまた後で。今はゆっくり話そうよ。」
「まあ、そうだな。」
9
2人はフードコートでホットティーとフライドポテトと焼きプリンを購入して、食べながら話し始めた。つりはいらないとマスターは言ってくれたのだが、そうは言われてもなかなか使い方がわからなかったのだ。
「まあ結局、こういうのが一番いいんだよね。」
「そうね。マスターには何か買っていこうか。」
そんな会話をしながら、想は幸せを感じていた。今まで感じたことがない「ほわっとした感覚」だが、心臓はかなり動いていた。想はその時はっきりと、恋している自分に気がついていた。
受験が事実上終わったからかもしれないのだが、このタイミングで戻ってきてくれたこと自体が奇跡としか思えなかったし、運命すら感じていた。
(本当にそうなんだよな。運命だ。こんなことありえないし。)
想は今のこの感情に陶酔していたようだ。いろいろな幸せなイメージが次から次へと沸き起こってきていた。そしてその陶酔は、望の一言で消えた。
「想!想ったら!」
「え・・・あ、あれ?俺、どうしちゃったんだ。」
「どうしたじゃないわよ。ぼうっとしちゃって。」
想は周囲を見渡し、そして現実に戻った。
「受験・・・終わったからかな。」
「そうだったね。お疲れ様。」
望はホットティーが入ったカップを持ち上げて想の目の前に上げた。想も気がつき、自分のカップを持ち上げて、望のカップを軽く叩いた。
「乾杯、おめでと。」
「ああ、ありがとう。」
想にはもう、望の顔から眼が離せないでいた。ずっと見ていたかった。こんな激しく女性を好きになることなどなかった。すると想の考えを見透かしたように、望が声掛けしてきた。
「ねえ、想・・・何考えてたの?」
「え?何って・・・。」
「想ってさ・・・わたしのこと、好きでしょ。」
想は口に含んだホットティーを吹き出しそうになった。しかも熱い。吹き出すにもできず、想はやっとのことで飲み込んだ。
「ブファア・・・な、何言って・・・。」
「うふふ、ごめんね。でも本当に、そうじゃないの?」
想は何をどう返答すればいいのか全くわからなかった。やっとのことで絞り出したのがこれだった。
「の・・・望はどうなんだよ!」
自分のことがわかっていないので、相手の出方を見るしかなかった。望はにっこり笑ってカップを両手で持ち、目の前に置いて答えた。
「好きよ。大好き。」
想はあまりにもあっけらかんと言われたので、どう感情をコントロールしていいのかわからなくなってしまった。ちゃんと言えなかった自分が情けなくもあった。
「す・・・そ・・・って・・・。」
「でもね。」
望はカップを置いて、下を向き、ちょっと考えてから上目使いに想を見た。
「今のこの思いは・・・幻なのよ。」
「まぼろし・・・?」
「そう、まぼろし・・・現実じゃないもの。だけど、確かなもの。」
「意味が・・・わかんねえ。」
「意味・・・意味は、ある・・・はあ・・・。」
「な、なんでため息つくんだよ。」
望は下を向いたまま、遠くを見る目になった。
「ため息・・・そう、そうするしかないの。」
「だから意味が!」
「わからなくていい!」
望は大声をあげた。想は想わす周囲を見渡したが、フードコート内の人たちは全く何の変化もなかった。それは助かったのだが、想は望が心配になった。そして望に手を伸ばしかけてやめた。
「どうしたんだよ。何があったんだ?ちょっとおかしいよ。」
「そうね。最初っからおかしいからしょうがない。でもね、想が好きってことに変わりはないの。最初っからそうだったんだから!」
「ちょ、ちょっと待てよ。最初っからってどういうこと?出会った頃からってこと?」
「・・・その前・・・。」
想はゆっくりと立ち上がった。望が何を言っているのか、本当にわからなくなったからだ。そして少し怖くもあった。
「望・・・何言ってんだ?出会う前から俺を好きだったって、どういうこと?俺が知らなかっただけで、望は俺のこと知ってたってこと?どうして?」
望は顔を上げた。その眼には涙がにじんでいた。
「想・・・ごめんね。」
「なんで、なんで謝るんだよ!俺、おかしくなりそうだ!」
「想はね・・・想は・・・なんで・・・なんでよ!」
「望!」
想は望の肩に手を置いた。肩は少し動いていた。泣いていたためだ。そして思った以上に細い肩だった。
「しっかりしろよ!」
望は自分の肩に置かれた想の手に、自分の手を重ねてきた。
「・・・あたたかい・・・やっぱり想だ。」
「あのさ・・・寝不足なんじゃない?気持ちが安定してないよ。」
「そう見える?」
「うん。」
「あのね、お願いしていい?」
「なに?」
「このケーキ、マスターに渡して。」
「え、望も一緒に・・・。」
「もう無理なの・・・ごめんね。」
望は立ち上がった。ピンクのコートを羽織り、マフラーを巻いた。そして想に向かい合って手を伸ばした。
「望・・・。」
「握手して。」
「なんで今・・・。」
「お願い。」
想はためらいながらも手を伸ばして握手した。望の手のぬくもりが伝わってきた。
「ああ・・・嬉しい。じゃあ、またね。」
望は手を離し、想に背を向けて歩き出した。
「おい、望!」
想は望を追いかけたが、ちょうど数人の客が食べ物を持って席に移動しようとしていたため、ちょっと遅れた。
「ちょ・・・ちょっとすみません・・・望!」
想は客に文句を言われながらかき分けて走り出した。だがもう望の姿はなかった。フードコートから出てみたが、やはりいなかった。
「望・・・君は一体・・・。」
10
それから想はマスターにケーキを渡し、つりを帰そうとしたのだが、マスターは微笑んで受け取らなかった。そして、なぜ望が一緒ではないのか、訊こうともしなかった。
想はしっくりこないまま、家路についた。電車に乗って色々思った。
(なぜ望はあんな態度なんだ?)
(俺を好きだと言ってくれたけど、あまりにもあっさりしすぎてない?)
(なんでマスターはあんなに俺たちに良くしてくれたんだ?)
まるで整理がつかなかった。受験で頭が一杯だったからかなとも思ったが、これまでそんなに考えたことはなかった。
(望、たくさんのことがあったって言ってたなあ。何があったんだろ。)
そういえば、想は何度も望と会っていたのに、何も知らなかった。望も語ろうとしなかった。それでいいとも思っていなかったが、不思議と気にならなかっただけだった。だが今はそれが気になる。
さらにもっと不思議なことがあった。
(なぜ今なんだ?)
もっと前に気になっていて良かったはずなのだ。そのこと自体が不思議でしょうがなかった。そんな自分自身が不思議だった。なぜか、いきなり夢から現実になったような、そんな感覚に近かった。現実的な夢から起きたらベッドの上だったような、そんな感じがしていた。そしてそれは、さっき望と話してからだった。
(なんだろうな・・・。)
どう考えても疑問符しか出てこなかった。そろそろ降りる頃なので、想は外を見た。
(え?)
電車は走っているはずなのに、確かに動いている感覚はあるはずなのに、外の景色は動いていなかった。
「な・・・こりゃなんだ!」
想は電車の中を抜けて出口まで行った。途中もおかしかった。無謀に人を押して行ったのに、誰も顔色一つ変えずにいた。まるで妙に動いている感覚だけがあるショッピングモールの中にいるようだった。電車の中の人々はマネキンと変わらない。そして出口まで来た。
「開いてる・・・電車、動いてないのか?」
感覚としては確かにある。だが、ノブに手をかけるとスッと開いたのだ。自分は動いている電車の中にいる感覚だし、Gも感じているのに、出口の外は動いていないのだ。この奇妙なギャップで迷ったが、想は思い切って目を閉じて外に飛び出していった。
「・・・ついた。」
想はちゃんと駅のホームに着地していた。後ろを見ると、電車は確かに動いていた。だが移動はしていなかった。妙だが、電車は動きながら静止していた。
「ここも?」
ホームには数名の人たちがいたが、ピクリとも動いていなかった。風が吹いていたが、それは確かに感じることができた。想はどうしていいかわからず、ホームのベンチに座って落ち着こうとした。
(何がどうしちゃったんだよ!)
想は落ち着こうとしたが、なかなかそうもいかなかった。このままでは家に帰れるかどうかもわからなかった。家に帰りさえすればどうにか・・・。
「家・・・俺の家?・・・家族は?・・・いない!なんでだよ!」
想は家族のことを思い描こうとして、全くできなかった。つまり、想の家族はいる。だがいるという事実以外、思い出せないのだ。名前も顔も、何人いるのかさえ思い出せない。というよりも、そもそもいないのだ。だがいると言う知識だけはある。まるで意味がわからなかった。
「俺・・・一体・・・誰だ?なんでこんなことになってるんだ?・・・で、なんで今そう思うんだ?この違和感はどうすりゃいいんだよ!」
まるで大波のように一気に、あらゆる感覚が押し寄せてきたようだった。想はその感覚をコントロールできずにいて、誰一人動かない駅のホームで転げまわった。
苦しみながら、想はとんでもないことに気がついていた。どう考えても納得できないことだったのだが、間違いなかった。
(これ・・・この感覚・・・強い!)
この場合の強いというのは、強烈という以上のものだった。自分のあらゆるものが、グググっと広がっていくようだ。そしてそれを感じている自分でさえ広がっていく、そんな状態だった。視覚的に言えば、巨大化しながら変身するヒーローのようだ。
どれくらいの時間が経過したかわからなかったが、この拡大感覚は急にストップした。想は一気に解放されてゼイゼイと息をした。
「もしもし・・・大丈夫ですか?」
想が目を開けると、駅員が覗き込んでいた。周囲には何人か見知らぬ顔も見えた。
「え・・・あれ・・・俺、どうしちゃったんだ・・・。」
「立てます?」
「は、はい。」
想は立ち上がった。特にふらつきもない。想は軽く頭を振って周囲を見た。数人の男女が取り囲んでいて、目の前には戸惑った表情の駅員がいた。その姿を、想はまじまじと見つめた。
(やっぱり・・・なんか違う。)
「医者を呼びましょうか?」
「あ、いえ。もう大丈夫です。すみませんでした。」
想は歩き出した。歩いていても、これまでとは違っていた。
(なんだか・・・しっかりしてる。)
歩くことなど、生まれてからこれまでずっとやってきたはずなのに、なんか違う。感触が強い。戸惑いながら、やっと駅から出て駅前広場に進み、ベンチに腰かけた。
「生まれてずっと歩いてきた・・・あ・・・まただ。」
想は生まれてからこれまでの記憶に触れたのだが、一切なかった。まるで白紙状態なのだ。想は頭を抱えた。なぜこうなったのか、全くわからない。家の電話番号すら記憶にないのだ。もうすっかり陽は落ちていて、薄暗くなっていた。想はどうしていいのかわからなくなり、涙がこぼれてきた。
(俺、どうなっちゃったんだよ!俺の記憶がなくなってる・・・え・・・)
想は立ち上がった。またとんでもないことに気がついたからだ。
「俺・・・過去があるって・・・家もあるって・・・思い込んでいただけってこと?なんでだ!」
想は感覚の整理ができてきていて、そうすると記憶の質がわかってきた。自分がこうだと思い、そのまま実践して生きてきたこと自体に、まるで現実味がないことに気がついたのだ。誰かにお前はこうだと教えられただけで、自分自身は経験していない・・・そう気がついたのだ。
想はまた周囲を見渡した。知っているはずの駅前風景がそこに広がっていた。確かに知ってはいた。だが、ここに来るのは初めてなのだ。
「どういうことなんだ・・・俺、生まれたての赤ん坊みたいだ。なんで・・・。」
想はふらふらと歩き出した。どこに行こうとしているわけではなく、ただ歩いていた。現実的だが夢の中にいるような、妙な感覚だった。当てもなく歩き、道路を渡って戦前からあるような食堂が並ぶ路地を抜けて、さらに歩いた。もう何も考えられなくなっていた。なぜこの道を歩いているのかさえわからなかった。
想はただ歩いていて気がつかなかったが、周囲の風景は少しずつ変化してきていた。急にメタバースのようなありえない立体感がところどころで発生していた。想が歩いたところからそうなっていた。
やがて想は、なぜか足が止まった。意味などわからなかった。何かに気がついたわけでもなく、気がついたら止まっていた。
「なんだよ・・・また何かあるんか・・・?」
想は周囲を見て、そして止まった。
「ここは・・・なんだ?」
目の前にあったのは、白い木造の建物だった。独特の匂いがしてきた。
「ここは、病院?」
匂いは薬剤のもので、玄関横には「神門内科医院」と書かれていた。想はそこに行きたいわけではなかったが、自然と足が向いていった。玄関を開けると、待合には数名の患者たちが座っていた。想は受付の横にある階段を登っていったが、誰も何も言わなかった。なぜこの階段を登っているのか、想には理解できていなかった。
3階まで来ると、足は止まった。この階は入院用らしく、看護師が行き来していて、体温がどうとか言う会話が聞こえてきた。想は歩いていき、一番奥の部屋の前で止まった。
「なんでここに・・・。」
患者名が扉横に書かれていたが、そこには妙永幸恵とあった。
11
想が病室前に立つと、ごく自然に開いた。そして想も、ものすごい勢いで知識が流入してきていた。なぜ自分がここにいるのかが、いきなりわかった。
「そうか・・・そうだったんだ。」
想はゆっくりと中に入っていった。病室は割に広く、長期入院していることはすぐにわかった。昭和のこの時代には、長期入院も珍しいことではなく、ベッドの横には本棚が置かれていてたくさんの本が置いてあった。種類はわからなかったが、良い香りの花が飾ってあり、大きな鏡も置いてあった。
部屋の中央に大きなベッドが置かれていて、いわゆる病室っぽくはなかった。どうやら裕福な環境にある人のようだった。
想は本棚を見て、軽く触れながら歩いた。変な話だが、そこも懐かしさに溢れていた。見ていると、後ろのベッドから声が聞こえてきた。
「想・・・?そこにいるの?」
それは初めて聞く声だったが、想はすぐに理解した。
「望・・・君か?」
ベッドが少し動き、ゆっくりと傾いた。そしてその中から、初老の女性が顔を出してきた。女性は想の姿は見えていないようだったが、そこにいるということだけはわかっていたようだ。白いパジャマを着ていて、きれいな顔だった。
「そうよ。ああ嬉しい・・・想、ここに来て。」
妙永幸恵は手招きした。想はベッドの横に来て、望を覗いた。
「望・・・やっとわかったよ。」
「いつかわかるかもって思ってた。でも・・・本当に来てくれるなんて。」
「だって・・・俺は君の作品じゃないか。いつでも来れるよ。」
ベッドの横には、一冊のコミックが置かれていた。タイトルは「おもいとのぞみ」で、作者は草水望だった。
「君は・・・自分の作品の中に、俺を作ったんだね。俺は・・・。」
想が本棚に手を伸ばすと、一冊のアルバムが現れた。想はアルバムを開いて、手が止まった。
「上上津役(かみこうじゃく)浩二・・・同じ顔だ。君が好きだった人だ。」
そこには、剣道着を着た若者たちが仲間をじゃれあって笑っている写真があった。その中央に想が映っていた。
「ああ・・・見えてきた。想だわ・・・嬉しい。・・・アルバムの人は高校の同級生でね・・・とっても素敵だった。女子はみんな好きで、わたしなんか話すこともできなかった。でも、大好きだった。わたしは漫画家になりたくて、上京しなくちゃならなかった・・・最後にやっと話せたのは卒業式。目の前にいたのに何にも言えなくてね。おたおたしてたら、『初めて話すんだな。ごめんな、なかなか話せなくて。』って言ってくれたの。もうわたし、嬉しくて!握手してもらって、本当に嬉しかった。だけど・・・彼にはもう素敵な彼女さんがいた。わたしの恋はそれで終わるはずだった・・・。」
想は幸恵の横にある椅子に腰かけた。そして幸恵の頬に流れる涙をぬぐった。
「ありがとう・・・わたしね、関東綜合人材の文学部に在籍していたの。でも交通事故で歩けなくなっちゃった。ワンダーフォーゲル好きだったな。山と映画が大好きでね。でももう二度と登れないし、劇場にも行けない・・・絶望したけど、たまたま書いた小説が編集の目に留まってね。それで小説家になれたの。おかげで本は売れたわ。だけどどれもわたしが書きたかった作品じゃない。編集が望んだものを書いていただけ。そんな中で、わたしの中の浩二さんはどんどん大きくなっていった。いつか浩二さんを描きたいなって思ってたの。でも、描く時間がなくて・・・そして・・・こんな病気になっちゃって。」
何も言わなくても、想にはその病気が悪性腫瘍であることはすぐに伝わってきた。
「わたしにはもう・・・時間がないの!もどかしくてもどかしくて、毎日泣いていた。泣きながら、浩二さんと観たかった映画のワンシーンを書いていたら・・・わたし、その中にいた・・・そしてそこに、あなたがいたの。浩二さんとそっくりなあなたが。」
想は幸恵の手を取った。そして優しく握った。
「ここは、望の世界でしょ。君が望んだ世界。現実的だけど現実じゃない。だから二次元の俺は本来ならここに来ることはできない。だけど・・・そうさせた人がいたからね。」
想はアルバムを取り、ページを開いた。
「この人だったんだ・・・剣道部顧問の小森田之人先生・・・君の世界では加瀬川巌マスターになった人だ。でもなぜ?」
幸恵が話す前に、病室の扉が開いて白衣の初老男性が入ってきた。想はそれを見て立ち上がった。

「巌・・・マスター?」
「ここでは違うんだよ、想。私は幸恵の担当医師小森田之人だ。」
「でもそれ、本名じゃ・・・。」
「想、だからこの人のおかげなの。」
小森田之人は想と反対側に立ち、幸恵の脈を測った。
「64回・・・まあまあだね。」
「マスター、ちゃんと話して!」
小森田之人は幸恵の手を置き、想と向かい合った。
「私は、ジャンクションメンターなんだ。」
「ジャンクション・・・メンター?」
「そう。現実の世界は目に見えるものだが、そうじゃない世界、つまり物質世界ではない世界というものがある。それは想にもわかると思う。なんせ、君はそこで生まれたんだからね。この世界では、交流が実に複雑になっている。無数の交差点があるようなものだ。だがその世界はちゃんとそれぞれで存在しなくてはならない。だから、私のような者がいて、一種の交通整理をしなければならない。そのために、私はどの世界にでも行けるし、どのようにも変わることができる。幸恵が描いた『おもいとのぞみ』では、私はポルトのマスターだ。ちなみに、ポルトというのはフランス語で扉、という意味なんだ。幸恵はフランス映画が好きだったからね。世界がクロスするカオスな場所にある扉ということで、そうなっている。もちろんそれは・・・。」
小森田之人は幸恵の手を握った。
「幸恵が望んだからだ。幸恵の中にある上上津役浩二と幸恵は結ばれなくてはならない。この世界はそのためにできた。だが当然最初からうまくはいかない。君たちは初めて出会い、そしてこの世界でのお互いを知らなくてはならない。幸恵がこの世界に来るにあたり、私は入り口を作った。それは君にもわかるものだ。それが・・・。」
だが、もう想にはわかっていた。
「電話ボックス、か。」
幸恵は少し笑って、話した。
「そうなの。でもわたしだって混乱したわ。自分が作った世界なのに居心地悪くてね。おまけに病気のことが頭にあって、時々やりきれなくて暴れちゃった。それ、想も見てるでしょ。」
「ああ、何だろうなって思ってた。そうだったんだ。」
「あの変な喫茶REⅯもね、わたしがあの世界から離れるとき、レム睡眠になりかけたら出てくるの。そうそう・・・『マイウェイ』のチラシも、わたしが思ったら想にぶつかったみたいね。」
想は幸恵の手を握った。
「やっとわかった。この世界に来るとき、自分が経験したことない感覚があった。あれ、二次元から三次元への中間に来るってことだったんだ。俺自身が積分されたようなものなんだね。そして俺には過去の記憶がなかった。それは、全く存在しなかったからしょうがない。望・・・君が俺の家を描いていなかったからだ。」
「ごめんなさいね。だってわたし、浩二さんの家、知らなかったから。」
「というわけだ。ここでの時間というものは、かなり三次元に近いものがある。だから、急いだ方がいい。」
「急ぐ?」
「つまり・・・。」
「わたしが言うわ。わたしの命、長くないの。描けるうちに描いておきたいのよ。だから・・・。」
想は全てを理解した。そして理解した瞬間から、上棚田想は存在しなくなり、別の人格に変化した。実家もちゃんとある。そして幸恵の姿も変化していた。
「・・・妙永幸恵さん、だね。」
幸恵は黒いジャケット姿になっていた。若々しくなっていて、ベッドは消えていた。

「ちゃんとお話したかった・・・浩二さん。」
「話せなかったからね。でも、俺、君が気になっていたんだよ。言えなくてごめんね。そうこうするうちに彼女できちゃった。」
想はそれまでの姿から、若い上上津役浩二になっていた。二人は目と目を合わせ、幸恵は幸せそうに両手を胸のあたりで組んで握っていた。そんな幸恵を、浩二は抱き寄せ、幸恵は浩二の胸の暖かさを感じることができた。
「わたし・・・幸せ。」
浩二と幸恵はしばらくお互いの存在を確かめ合った。すると小森田之人の声がした。
「それでは、私はここから去らなければならない。だがその前にやることが残っている。幸恵、君の望む世界ならどうなっている?」
そこから二人は、二人だけの世界に入っていった。そこでは幸恵と浩二は、高校卒業してから恋人になり、デートを重ねて結婚までする仲になっていた。初めてのベッドインの時、望は震えていた。二人はウェディングドレスと純白スーツ姿になっていて、シチリア島にある教会前に立っていた。二人は手を取り、中に入っていった。中には多くの親戚友人家族がいて、盛大な拍手で二人を歓迎した。幸恵の横には父親がいて、浩二は正面で待った。
正面には神父がいて、その姿は小森田之人だった。神父の姿をしていて、オルガンがメロディを奏でて讃美歌を全員で歌った。幸恵と父親がバージンロードを歩き、浩二の前に幸恵が立った。神父が二人に問うた。
「病めるときも、健やかなるときも、愛をもって互いに支えあうことを誓いますか?」
「誓います。」
指輪の交換が行われ、キスが行われた。
「ああ・・・幸せ。」
幸恵の口から言葉が漏れた。そして世界はまた変わり、初老となった二人は自宅でアルバムを開いていた。
「母さんもこんな時代があったんだなあ。」
「嫌だわ、あなた。子供の前でも言うのはやめて。恥ずかしいじゃない。」
「ははは。しかし、もう子供も自立して孫もか・・・長かったね。」
「その孫がもうすぐ来ますから、楽しみだわ・・・ほら来た!」
玄関が開き、元気な子供の声が聞こえてきた。
「祖父ちゃん、祖母ちゃん!こーんにちわー!」
「まあまあいらっしゃい!・・・。」
家族は幸せな空間に包まれ、そして白い雲の中に消えていった。
12
出版会社命道社では、この年の当社発表作品選考会が行われていた。すでに予備選考は行われていて、後はグランプリ作品と最優秀新人賞の選考のみとなっていた。別室ではグランプリ選考が行われる予定なのだが、そのためにはここでの最優秀新人賞が決まらなくてはならなかったのだが、難航中だった。
「だからさ、どうして草水望がダメなんだ?」
「だってこの人はもうベテランですよ。このPNでは初めてですけど、妙永幸恵でこれだけやってるならちょっとダメでしょ。」
「それは承知だ!だが読者の声を反映しないとダメだろ!どれだけこの人が読者に影響与えているかわかってるのか?いまだにこんな鮮烈な青春ものは読んだことがないという評価があるじゃないか。ここでやらなきゃ、我が社の信用にかかわるだろ!」
「逆でしょ!規定じゃないことやったら、それこそ・・・。」
このような状態が続いていた。この会社は編集の熱がかなりなことでも知られていた。
「おう、まだかよ。」
「あ、編集長。まだです。」
編集長はゆっくりと席についた。そして資料を眺め、葉巻に火をつけた。煙をふきながら、編集長はぼそりとつぶやいた。
「草水望は、実はグランプリ候補でもあるようだぜ。」
「え、そうなんですか?それじゃあ話は早い。それで行けば・・・。」
「だが、ダメだ。」
「なぜです?」
「つい先ほどだが・・・本人が死んだそうだ。」
「えええ!」
編集長によると、文字通り命を削るようにして対象作品『おもいとのぞみ』を書き上げたそうなのだが、その無理がたたり、悪性腫瘍の前に心臓発作で亡くなったとのことだった。規定では、生存者のみにグランプリは与えられる。もちろん他の賞も同様だ。
「じゃあ対象外ってことになりますね。」
「あーあ、この議論も無駄かよ!」
選考委員たちの愚痴が聞こえてきた。編集長は黙って聞いていたが、いきなり机を両手で叩いた。
「うるせえ!」
一声で全員が黙った。
「規定規定って、なんだよ!うちはそんな会社じゃねえだろ!お前たちもついさっきまで激論してたんだろうがよ!ふざけんな!いいか、これまでに合わない規定なら変えちまえばいい。そうだろ!」
「で、でも・・・それじゃあどうすればいいんで?」
「あのな、本ってのは読者が選ぶもんだ。俺たちは手助けしてナンボだろ。だったら、編集全員一致の読者賞って作りゃいいだろうが。」
全員に安堵感が伝わってきた。この編集長はワンマンだが、絶大な信用を勝ち得ている。それは適格な判断ができる人物だからだ。
「ではその旨で行きましょう。おい、グランプリに伝えてくれ。こちらでは次選作が賞だって!編集急げよ!」
全員が大急ぎで飛び回って、会議室を出ていった。一人残された編集長は窓を開け、空を見た。空にはひときわ目立つ盛り上がった雲が発生していた。
「おもいとのぞみ・・・想と望の物語、か・・・。」
編集長は背広を取り、ランチに出かけた。ビルの玄関で、受付に休憩帳にサインしたところで、受付2人が声をかけてきた。
「編集長、失礼ですけど、おいくつになられました?」
「俺かい?たったの60だよ。」
「えー!還暦ですか!絶対そうは見えませんよ、ねえ。」
「本当ですよ。社内で有名ですよ。年齢不詳だって。」
「ははは、誰もカッコいいって言わねえな。」
「あ!いえいえ、そんなことは・・・。」
「いいってことよ。じゃあ飯食ってくらあ。」
「いってらっしゃい。小森田編集長。」
小森田之人は外に出て、よく通う洋食屋ポルトに向かった。その途中に電話ボックスがあり、小森田は中に入って受話器を取り、耳に当てた。
「よう、元気か?編集全員一致の読者賞ってことになったよ・・・ああ、そうだ。ところで想・・・違った、浩二も元気かい?・・・そうか、変わらずか。じゃあまた連絡する。それまで元気でな。」
小森田は電話ボックスを出て、先ほどの雲を見上げた。雲はそのままそこにあって、心なしか少し明るくなったように思えた。そして小森田はつぶやいた。
「この件も片付いたか・・・次はどこだろうな。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
