
こゆり
この物語は完全にフィクションであり、登場人物は全て架空の人物です。
上田山純一 主人公 放送作家
郷畑こゆり アイドルから女優に転向したタレント
素水一二三 山小屋管理人
鷹澤光徳 映画監督 脚本家 放送作家
郷畑満・留子 こゆりの義親
1
冬の山は美しい。美しく、冷たくて危険だ。かなり大きい木の間を、俺は雪を踏みしめながら歩いていた。山のプロが見たら全てアウトにしか見えない恰好で、一人で歩いていた。雪が服の隙間から入り込み、ずっと凍えていた。顎鬚でさえ凍っているようだ。
俺の名は上田山純一。放送作家だ。主にローカルで複数県のメディアのお世話になっている。それなりに数字取れる作家として知られていて、全国放送も結構な回数を書いたことがある。もう40歳も越えていて、独身だ。この業界にいると、それなりに出会いはある。だが俺は業界人や女優たちを異性として見たことはない。あまりにも表の顔と違う素顔を見てきているからだ。考えてみればわかることだが、プロである以上表の顔が全てでいい。俺の方がおかしいのだ。
「・・・まだか。」
俺が目指していたのは、この山の中腹にあるはずの小屋だった。小屋とは言っても、別荘として使えるレベルのものだ。2年前に一度行ったことがあって、その時にはロケ現場に行かなければならなかった。監督とプロデューサーが揉めていて、どういうわけか俺が悪者にされてしまっていたからだ。よくあることではあるのだが。
俺は人嫌いで通っている。実際そうなのだ。人付き合いほど面倒なものはなく、一銭にもならないと思っている。だが作品は、自分で言うのも何だが結構なものだと自負している。一応は売れっ子作家のひとりなので、監督やプロデューサーも黙るしかない。
その時のロケは俺の短編作品で、山小屋で起こる複雑な人間関係をメインに描いたサスペンスものだった。ヒロインの「田原淳子」役は当時アイドルグループから卒業したばかりの22歳の郷畑こゆりで、絶大な人気があった。だが正直、俺のイメージするキャスティングではなかった。数字を稼がねばならないので仕方ないのだが。しかしこゆりは、俺が現場に着くと、いきなり挨拶に飛んできたのだ。
「上田山先生!お世話になります!郷畑こゆりです!よろしくお願いします!」
さすがアイドルだっただけに、抜群のスマイルを見せてくれていた。業界では普通に行われる挨拶なのだが、俺は初めて心臓が強く動いた。
「あ、ああ。こちらこそよろしくね。」
こゆりは深々と頭を下げ、そしてこんな質問をしてきた。
「あの、先生?この田原淳子さんなんですけど、あそこで告白されるじゃないですか。どんな気持ちだとお考えになりますか?」
「ああ、あそこね。あれはいわゆるW不倫がまだわかっていない状態でしょ。それを感じるか感じないかというギリギリの状況だから、少しだけ疑問を内包しながらの応対になると設定している。監督さんは何て?」
「えーと・・・それが・・・もう不倫はわかっているから、相手を責めろって・・・。」
「責めろだって?あいつがそんなこと言ったのかい?」
あの監督は俺も知っていて、あれこれ良くない噂は耳に入ってきていた。何か言ってやろうと前から思っていたところにこれだ。頭に来ていたところにバタバタと音がして、小太りでサングラスをかけ、ファー付きジャケットを着た男が走ってきた。
「こりゃ先生!わざわざすみません。あのね、こゆり・・・俺の指示に従いなって言っただろ?ほら戻って。」
「はい・・・。」
「監督さん。ちょっといい?」
「は、はい?」
俺はこゆりから少し離れて、監督とサシで話した。
「あんたね、俺の作品にケチ付ける気?」
「と、とんでもないですよ!」
「じゃあなんで、俺の考えと違うことをさせようとすんのさ。さっきプロデューサーとも話したんだけどさ、あいつも勘違いしてたけど、あんたの勘違いはひでえよ。話を聴いて本当かよって思って来たけど、主演の子でさえ疑問に思ってるじゃねえか。降りるか?」
「冗談じゃないですよ。わかりました。そのようにいたします!」
「気をつけな。他にも人材は多いんだ。せっかく選ばれたんだ。チャンスを逃がすなよ。」
「は、はい・・・。」
この監督は自分の考えは正しいと思い込むタイプだったので、よくこうしたことは起きる。プロデューサーも困っていたはずだ。ただ、正論には妙に弱い。俺の場合、俺がへそ曲がりってこともあるわけだが、俺は正論しか言わないし、相手次第ではすぐ降りる。俺は別に投資で稼いでもいるので、放送作家という面倒臭い仕事やらなくても食っていける。だからハッキリ言う。そうなるとこの男はどうしようもない。
俺が20歳近い年齢差を考えないほどに、業界人である郷畑こゆりに入れ込んだのはこのロケからだった。最初はこゆりの方からだった。どこからか連絡先を仕入れてきて、俺のメッセに送ってきた。色々相談に乗ってほしいとのことからだったが、程なくして俺たちは男女の関係になった。
若いこゆりと会うタイミングは難しかった。相手は元アイドルだ。当然推すファンも多い。ありとあらゆる手を使って、俺たちは隠した。スマホやPCを使うことはなく、共通の隠語を作ってそれで連絡したりした。だからかもしれないが、俺はのぼせにのぼせた・・・あの日までは。
「先生!えらいことですよ!」
俺のマネージャーでもある、個人会社の相棒坂田が慌てて電話してきた。
「どうしたんだ?血相変えて。」
「ほら、先生の『ロッジコンフィデンシャル』で主演した郷畑こゆりっていたじゃないですか。」
「あ、ああ。あの子ね。それが?」
「死んだんですよ!睡眠薬大量服用で!」
俺は心の中で、嘘だと叫んでいた。昨日も会って一夜を過ごしたばかりなのだ。眠れないなどと聴いたこともない。
「で、警察から事情を聴きたいそうなんですよ。もうすぐ来るはずです・・・先生?どうかしました?」
俺は立っていられなくなり、近くにあったバス停のベンチに腰を降ろした。こゆりのスレンダーなボディと、愛くるしい笑顔、感情のままにあえぐ顔などが浮かんできた。
(なんでだ!こゆり、なんでだよ!)
だが、警察から何か訊かれない限りは男女の関係であったことは黙っていようと思った。清純派で通っているこゆりのイメージを損ないたくなかったからだ。
俺は警察の質問に丁寧に答えた。仕事でのこと、プライベートでの関係などを尋ねられたが、警察も男女関係があったかどうかは尋ねられなかったので助かった。

翌日、俺はこゆりの通夜に出席した。数多く来ている業界人たちや家族に挨拶し、これは棺桶の中のこゆりの顔を覗いた。こゆりの顔は綺麗で、今にも起き上がって抱きついてきそうだった。顔を撫でてやりたかったが、それは不自然だ。家族も見ている。俺は軽く頭を下げ、あの作品の関係者と話して誤魔化した。
俺の心は、その日から一切晴れなくなった。仕事も手につかない。どうしようもなくなり、坂田に当面体調不良で休むと伝えて、気がついたらあの山小屋に向かっていたということだ。実際、登山口に来るまでなぜここに来たのか覚えていないくらいだった。雪に足を取られながら歩き続け、俺はようやくあの山小屋に到着した。もう午後になっていた。
2
「久しぶりだな・・・あれからどうなったんだろ?」
俺は過去の記憶を引っ張り出して、山小屋の管理室に行こうと思った。誰もいない時には、確か管理人がいて清掃など行っていたはずだからだ。正面はガラス張りで、中は暖炉がある暖房も効いた広いリビングがあって、そこから見る雪景色は最高だったことを思い出しながら、俺は裏手に向かった。
「あった、ここだ。」
そこは二人ほどが寝泊まりできる別棟があり、俺は扉横のベルを鳴らした。
(どなたです?)
中から年配と思われる男の声がした。
「こんにちは。私は以前にロケで来たことがある者です。」
「あー・・・ちょっと待ってね。」
少しして扉が開き、50代と思われる男が顔を出してきた。白髪で白いひげを生やし、厚いダウンジャケットを着ていた。

「やっぱりそうだ。インターフォンで顔見て、どこかで見た顔やなあって思ったんだわ。ドラマのロケで来られていた作家の先生でしたかね?」
「ああ、そうです。放送作家の上田山純一です。お久しぶりですね。よく覚えてくださって。」
「上田山・・・さん?そう仰いましたかね?」
「ちょっと変わった名字ですから、わかりにくいですよね。」
「え?まあ、そりゃあなあ・・・あ、気にせんでください。まあ、どうぞ。」
俺は管理人の、ちょっと何かを含んだ言い方が気になったが、芸能関係者だからなのだろうと思った。部屋は割に広く、2DKくらいの広さがあった。奥には作りつけのベッドとキッチンがあり、電話やパソコンが乗ったテーブルが中央付近にあり、手前には薪ストーブとソファがあった。老人は俺を中に入れてくれ、俺はソファに座った。外人用なのではないかと思うくらいにゆったりとしたソファだった。管理人は間もなく熱いコーヒーと地元の煎餅を持ってきてくれた。
「ええと・・・すみませんね、お名前が上・・・なんとかやったねえ。」
「上田山純一です。はい、これ、名刺です。あなたのお名前は?」
「私は、素水・・・素水一二三です。」
「素水さんですか。あのロケはもう2年前でしたね・・・その前からこちらの管理人をされていたんですか?」
「まあねえ。ここはオーナーさんが建てたんだよ、別荘としてさ。もう10年前になるかねえ。私はそのオーナーさんの運転手だったんだ。それでお話があってね。私は独り身で子供もいねえから、天涯孤独なもんで、オーナーが働かないかって声かけてくれたんだよ。それからずっとここで暮らしてる。もう10年以上かな。」
素水は薪ストーブに薪を放り込み、俺の名刺をじっと見た。
「あの、今は山小屋の中に入れるんですか?」
「え?・・・あ、ああ、いいよ。この頃じゃあ、こんなところにまで来て泊る客は少なくてね。もう一月くらい誰も入っちゃいねえ。私も一緒に行った方がいいかい?」
「ああ、いえいえ、私だけで結構ですよ。」
「そりゃ助かる。ここんとこ腰をやっちまってねえ。動くと痛えんだよ。じゃあこれが鍵だ。玄関を開けて入っておくれ。中の暖房はここから操作できる。つけておくよ。どのくらい居なさるんで?」
「そうですね・・・できれば少し仕事もしたいし・・・あ、そうだ。今から宿泊できますか?いきなりですみませんが。」
素水は呆れたように肩をすくめた。
「本当にいきなりだわ。予約もねえし、いいんだがよ。ちょっと待っててな。」
素水は受話器を取って、誰かに電話した。
「あーもしもし、社長?ええ、素水です。急に宿泊したいってお客さんがいらして・・・ああお一人様です・・・そうなんですよ、お一人で・・・そうですよね・・・はい、わかりました。では・・・え?そりゃ嬉しいですよ。あそこで食事・・・はははは・・・はい、では失礼します。」
素水は受話器を置き、テーブルの引き出しから書類を出してきた。それを俺の前に置いて、色々記入してくれと言ってきた。そしてチェック用紙や説明同意書にサインし、前金として3万円支払うようにと。
「で、残りは明日の部屋の様子次第で金額が変わりますけど、何もないようでしたら3万円の残金です。」
戸建てでかなり広い山荘なので、これは破格値だと言って良かった。一人だから高くなるが、俺一人なのだから仕方ない。いきなりだったし。俺は前金を支払い、残りはネット決済で良いか確認してから山荘に向かった。
この山小屋は一応ログハウス風になってはいるのだが、実は当時としては結構な最新式家屋で、外壁には材木を張り付けているが、一歩玄関から入るとまるで豪華ホテルだ。来客用にリニューアルしたと思われるでかい玄関には、これもでかい何か碑文が書かれた岩が置かれていて、あちこちに金色が使われていた。ロケで来た時にはゆっくり見る時間がなかったのだが、改めてすごいなと思った。先ほどの社長って、どんな仕事なんだろう。
俺は玄関からドアを開いてリビングに入った。まず、やたら広かった。おそらくは30畳くらいはあるリビングがあり、キッチンダイニングが奥に見えた。手前にはコの字に豪華なソファが暖炉の前にあり、二階にあがる階段もあった。ここの暖炉は直火ではなく、いわゆる電気ストーブ方式だ。確か二階は寝室やクローゼットなどがあったはずだ。俺はロケ現場を思い出した。ここがあのドラマのメインステージになる場所だった。
「ここに、座ってたんだよな・・・。」

こゆりにとっては女優として初めてのテレビロケで、田原淳子という女性を演じていた。田原淳子は大学を卒業したばかりの女性で、ここに友人たちと旅行に来ていたという設定だった。この山小屋で殺人事件があり、各々の事情を描きながら連続殺人が行われていくという群像劇だ。こゆりはその中で次第に疑いをかけられていき、最後に大逆転が起こるというものだった。2時間ドラマにしてはいい出来だったと話題にもなった。作家冥利につきる。
俺はまずリビングのカーテンを開けた。広いところなので、カーテンもスイッチで開閉する。ゆっくりとカーテンが開き、目の前には見事な雪景色が広がった。
「相変わらず、見事だな・・・。」
俺はキッチンからグラスを二つ持ってきて、持参してきた自衛隊仕様の水稲からメーカーズマークを注ぎ、ひとつを俺の横に置いてグラスを鳴らした。
「こゆり・・・乾杯。」
こゆりは全く酒が飲めなかったのだが、俺に付き合って飲んでいるうちに好きになっていった。中でもこのメーカーズマークは好きだった。高級バーボンではあるのだが、俺もこれが好きだ。口に持ってくるとまず芳香が鼻を衝く。そして口に含むと、芳醇な香りと甘さ、程よい刺激が口いっぱいに広がる。俺は一気に干して、深く息を吐いた。
「こゆり・・・なんでだよお・・・。」
たった半年ほどの付き合いだったのだが、本当に幸せだった。世知辛い業界にもまれているうちに、自然と俺の周りには敵か味方かという色分けでしか見られない人間関係だけになっていた。そこにこゆりの存在は、まるでオアシスだった。年齢差を感じない恋だった。生まれて初めて、結婚という文字が脳内に見え始めたばかりだった。
この広いリビングから景色を見ながら酒を飲んでいると、あの幸せだった日々が蘇ってきた。俺は溢れてくる涙を拭い、グラスを置いて二階に上がった。二階は一階よりも天井が低い設計になっていて、寝室とクローゼット、バスルームなどの生活エリアになっていた。ここの寝室で、こゆりが相手の男性を追い詰めるシーンが撮影された。俺は寝室に入り、あのシーンの場面の位置に立った。
俺がこゆりの現場に居合わせたのはこの時が最初で最後だった。俺たちが付き合っていることを知られてはならないからだ。今でもあの中で光っていたこゆりの姿が思い出される。こゆりだけが見えている、そんな感じだった。その時から一目惚れしていたのだろうか。
「・・・何考えてんだ、俺・・・。」
もうすでに思い出に浸っている自分が情けなく、改めてこゆりがもうこの世にいないことを実感させられた。俺は手入れされているベッドに潜り込んだ。ここで田原淳子が犯人が誰かという事実に気がつき、これからベッドを共にしていこうとしていた友人を追い詰めていく。俺はそのシナリオを思い出しながら、目を閉じた。ベッドは暖かく、心身ともの疲れで俺はすぐに寝落ちしてしまった。
3
俺はぐっすり寝ていたのだが、光を感じて目が覚めた。やたら眩しい光だった。
(なんだこれは・・・)
ベッドから起きようと思ったのだが。全く体が動かない。いわゆる金縛りにかかったと思った。だがそれにしてはこの光は不自然だ。俺はどうにかして顔を動かそうとした。だがそれでも動かなかった。
俺があがいていると、ふと顔に何かが触れたような気がした。
(・・・これは・・・)
俺にはこの感覚が何かすぐに分かった。一夜を共にした時、俺が疲れて寝ようとすると必ず顔に触ってくる、こゆりの手だ。まだ寝ないでとつぶやきながら。
(こゆり・・・お前なのか?こゆり!)
俺はその時、こゆりがすでにこの世の住人でないことなど全く頭になかった。あの懐かしく愛おしい掌の感触を味わいたかった。小さくて、柔らかい掌を。
顔に感じている感触はしばらく続き、そして消えていった。
(待て!こゆり、待て!)
俺は必死に心で叫んだ。すると今度は目の前に別の景色が広がった。それはどこか高層ビルの一室のようだった。目の前にはソファがあり、だれか座っていた。
(誰だ?)
その人物の顔を見たとき、俺の心は激しく動いた。
(これは・・・鷹澤!)
そいつは俺と同じ放送作家、脚本家でもあり、映画監督でもある鷹澤光徳だった。正直好きなタイプではなく、作家仲間からも敬遠されていた男だ。上には媚びへつらい、役に立たないと見るや簡単に見切る。一旦下と思えばとことん上からモノを言ってくる。噂では反社とズブズブとも言われている。
(なぜこいつが?)
鷹澤はタバコをふかしていて、俺からすると相変わらず下品なサングラスをかけていた。
いつもニヤニヤしながら話しかけてくるのだが、どうにも腹を探ってくるようで嫌いだったが、この時にはその下品なニヤケ顔ではなかった。無表情に近かった。そしてタバコを灰皿に置いて、身を乗り出してきた。俺的には気持ち悪かったのだが、その後はもっと悪かった。
『どうだ、上田山とはうまくいってるか。』
どういうことだ、こいつが何を言っているのだと思った。誰に向かって言っているというのだ・・・と思った瞬間、俺の中にとんでもない思いがスパークした。そして、あの懐かしくて、決して忘れない声が聴こえてきた。
『・・・ええ。』
こゆりの声だった。俺は頭の中がパニックになっていた。全く何も考えられなかった。そして鷹澤は信じられないことを言ってきた。
『お前をあいつに惚れさせるのは簡単だ。見事に引っ掛った、あのアホ。これから少しずつあいつを落としていってやるさ。』
『・・・あの・・・。』
『なんだ?』
『もう・・・嫌。』
『なんだと?』
『もう、嫌なの!』
鷹澤はタバコを持って、深く吸いこんで揉み消した。
『何を言ってるんだ?お前、自分の立場を理解してんのか?』
『だって・・・だって・・・あんなに素敵な人を・・・もう嫌!』
『ふざけんじゃねえ!』
鷹澤は立ち上がって張り手を見舞った。こゆりはソファに倒れ、泣き出した。
『うわああん!』
『てめえの親の借金、俺が肩代わりしてやったんだろうが!文句言うならあの外道両親に言いやがれ!喜んでお前を差し出したんだからな!』
俺はようやく理解した。こいつが俺の腹の中をいつも探ろうとしていたのは、俺に本では敵わないと思っていたからだ。少しでも俺を押しのけたかったということだ。そのためにこゆりを使って俺を腑抜けにしようとしたのだ。俺はまんまと引っ掛かってしまった。こゆりは涙でぐしゃぐしゃになった顔を上げて、鷹澤を見た。この映像は、こゆりが見た像なのだろう。感情も伝わってきた。
『なんでよ!あたし、あの家の子じゃないんだから!』
『ああ、そうだったなあ。お前は元々孤児で、あいつらに引き取られたんだよな。おまけに・・・あの野郎に惚れたってか?けっ、アホらしい。てめえにそんな大層なこたあ似合わねえよ。だが・・・。』
鷹澤は顔をこゆりに近づけてきた。うす汚い面をどアップで見せられるのは苦痛でしかない。

『んなこた、俺には関係ねえ。お前は一生俺に尽くすんだ。』
鷹澤はこゆりに手を伸ばしてきた。
「離れやがれ、このクソ野郎!」
俺の感情が爆発すると同時に声が出て、ベッドから飛び起きた。そして無我夢中で、そこにいるはずのない鷹澤にパンチを連打した。もちろん俺の拳は虚しく空を切っていた。そして俺は知らずに移動していて、激しく壁を打った。
「痛え!」
手から血が噴き出し、俺はティッシュで止血した。そして階段を降りて、一階にあった治療ケースを開けて、ガーゼを当てた。包帯を取り出そうとしたところで、チャイムが数回鳴り、素水が飛び込んできた。
「上田山さん、どうしました?すごい音が・・・え、大丈夫ですか!」
俺は包帯を取り出そうとして、力が入らずに落とした。
「俺がやるよ、そこに座って。」
素水は俺をソファに座らせ、ガーゼを外して消毒液を塗り、改めて包帯巻いてくれた。
「これでいいんだが、救急車呼ぼうか?」
「いや、大丈夫だ。ありがとう。」
素水はキッチンの引き出しからチョコや飴を持ってきて、俺に勧めた。
「こんな時には甘えもんがいい。ほら食いな。」
俺は勧められるままチョコを口にした。こんな時だが、確かに少し気分が回復した。
「どうなさった?この辺はコウモリが飛んでくる。それで驚いたかと・・・。」
「違うよ・・・何でもねえ。夢でも見たんだろ。」
「夢?」
素水は眉を顰めた。
「どんな夢だい?」
「何でもねえって!」
激高した俺の肩に手を置いて、素水は話しかけてきた。
「まあ落ち着きなさい。あんた、夢を見たって言ったね。」
「ああ、言ったよ。悪夢だったけどな。」
「ひょっとしてそれ、かわいいお嬢さんの悪い夢じゃなかったかい?」
俺は驚いた。まさかこの男からそんなことを言われるとは思ってもみなかったからだ。
「管理人さん、どうして・・・。」
「やっぱりなあ。こんなこともあるんやなあ。」
「だから何だって!」
「落ち着けって!」
素水は半分怒鳴りながら俺の肩を押さえた。
「ほれ、俺がよ、あんたの名前聴いた時、ちょっと変だっただろ?」
俺は最初に合った時のことを思い出した。俺の名前を言った時、確かに素水は聞き返した。
「それが・・・どうかしたのかい?」
素水は俺のタバコの吸い殻を捨てに行き、そしてきれいな灰皿を持ってきた。
「俺もよ、変な夢見るんだよ。」
「え?」
「夢ん中にな、かわいいお嬢さんが出てきて言うんだよ。上田山先生にあれを渡してって、お願いしてくるんだ。」
「俺に?」
素水は懐に手を入れて、何かを取り出した。
「これがな、あのロケに出てたお嬢さんが忘れていったんだ。俺はあのロケの誰かに渡そうと思ってたんだがよ、忘れちまってよ。しばらくしてニュースであのお嬢ちゃんが自死したって聞いて驚いてさ。そのままにしちまったんだ。あんたに渡してくれってお願いされたのは、これじゃねえのかなって思って持ってたんだ。その相手の名前のあんたがこうだろ。ここに来る時に持ってきたんだ。ほれ、あんたに渡すよ。これ、鍵ねえから開けられねえんだがよ。」
素水はそれを俺に手渡した。それは鍵つきの、日記のようなものだった。
4
俺はこゆりの本を手に持って呆然としていた。裏にイニシャルでG・Kと書いてあったし、間違いなくこゆりの字だった。
俺は自分の中に沸き起こってくる感情を整理できていなかった。愛しいという想いもあり、あの鷹澤の女だったかもしれないという想いもあり、板挟みで苦しんだだろうという想いもあり。もう何がなんだかわからなかった。 おまけに間違いなく日記と思われるこの本には鍵がかかっている。本来ならご家族に渡すべきなのだろうが、夢の中で鷹澤が言っていたような両親だったらそうはいかない。俺はソファに座ったまま、何時間も呆然としていた。
ようやく何とか考えるようになったのは、もう夜明けだった。間もなく素水にこの山小屋の鍵を渡さなければならない。俺は困り、じっと鍵穴を見た。
「うん?・・・待てよ・・・この形・・・どこかで・・・。」
鍵穴の形が、ちょっと普通とは違っていたのだ。直系2ミリ程度の穴が開いているだけだったのだが、この丸い形が妙に俺の心に留まった。それにバンドもブックカバーとは違っていた。おそらくこゆりが自分で直して使っていたのだろう。だからなおさらだった。
俺はこゆりとの記憶を遡って考えた。俺に渡してくれと言ってきたのなら、俺自身がヒントを知っているはずだ。普通なら馬鹿馬鹿しいことなのだが、あの夢を見た跡では真剣にならざるを得ない。俺はどんな小さなことでも逃すまいと真剣に思い出そうとした。そして、記憶が止まった。
「あれ・・・あれじゃないか・・・そうだ、あれだ!」
俺はクローゼットに駆け上がり、ワイシャツを取った。そしてシャツに引っ掛けてあるタイピンを手に取った。これは、こゆりから誕生日祝いにと貰ったものだ。このタイピンにアンテナのように飛び出した突起があり、その先端が2ミリくらいの円形だったのだ。なんだか安っぽいなとは思っていたのだが、こゆりからのプレゼントなので大切に使っていたものだ。
俺は一階に下り、そしてタイピンの先端を日記の鍵穴に差し込んだ。ブックバンドがカチッと音を立てて外れた。
「開いた・・・。」
俺はゆっくりとバンドを外した。おそらく、文房具屋あたりで売っていそうな、安っぽいものだ。女子学生たちが秘密にしている日記として使うものなのだろう。日記帳自体もよく見るキャラクターがデザインしてあり、どう見ても光求そうには見えないしろものだった。俺は日記を開いた。
「こゆり・・・。」
そこには2年前からの日記が書かれていた。最初のページにはこれからこれを始めるにあたって、と書かれていた。読んでみると、芸能界に入る前日からの日記だった。こゆりは字に特徴があって、少し斜めっていて丸みがある。それで期待と不安の気持ちが書かれていた。同時に、義理の親に対する感謝と憎しみと両方の感情も書かれていた。
読み進めていくと、徐々に知った名前が出てくる。業界人たちの名前だった。誰それが厳しいとか、あのADさんイケメンだとか書かれていた。女の子らしい感性の文章が続く。そして、見たくない名前が登場してきた。
「鷹澤・・・。」
こいつが何を言ってきたか、そしてこゆりの義親とどうかけあっていたのかが、生々しく記載されている。怒りを込めて書く時、こゆりはかなり機械的に書いていた。そうしなければ書けなかったのだろう。中でも、鷹澤に弄ばれたあたりは本当に切なく、俺自身もあいつに対しての怒りが沸騰してくる。
だが、あのロケの後から文章が変化してきていた。ところどころに俺の名前が出てきて、そして途中から「純一さん」に変わっている。もちろん、俺たちが付き合い始めた頃だ。こゆりに何て呼べばいいのって言われて、好きに呼べよって返したらこう呼んでくれていた。思い出の場所は、こっそり日帰り旅行した台湾でのことだ。台湾の食事を食べながら、こゆりが言ってきた。

「ねえ純一さん。」
「なんだ?」
「おいしいね、これ。」
「ああ、うまいな。」
「ねえ・・・あたし、思うんだ。」
「何を?」
「ええとね・・・うーん・・・ええと。」
「なんだよ、いったい。」
「あの・・・幸せだなあって。」
「あはは・・・俺もだよ、こゆり。」
「あたし、純一さんが・・・好き。」
こゆりがちゃんと告白してくれたのは、これが最初で最後だった。当然この日のことも日記に書いてあった。書き終わった後の一文が、俺の心を打った。
『ずーっと すき 純ちゃん。』
俺は目をこすった。危うく涙を日記に落とすところだったからだ。思わず俺もつぶやいた。
「馬鹿・・・純一さん、だろ。」
辛い過去を背負い、なおかつ現在も辛かったはずだ。このわずかな自由な時間、何もかもから解放された貴重な時間を心から楽しんだのだろう。どれだけ救われたのかは、これまでの日記と比べたらすぐにわかるほどに、女の子の文章だった。
だが、それからは辛い日記が続いていた。鷹澤の名前が出てきて、明らかに憎しみの日記になっていた。ところどころで俺と会った日のことが書かれていたのだが、以前のように女の子の文章ではなかった。嬉しいのだが、それ以上の辛さが溢れていた。鷹澤から弄ばれていたのだろう。時おり字が見えにくくなっていた。涙が落ちたのだろう。俺の中にも、鷹澤に対する憎しみが沸いていた。
そして日記は唐突に終わった。ロケが終わり、帰ったからだろう。それから一週間後に、こゆりは自らの命を天に返した。俺は白紙のページを意味なくめくった。こゆりのそれからの心情が伝わってくるようだった。
俺はひたすら白紙のページをめくりながら、溢れる涙をこらえることができなくなっていた。俺はハンカチで目を拭き、一旦日記をテーブルに置いた。すると、紙ではない音がした。ドン、という音だ。
「・・・うん?」
俺はハンカチをしまい、日記をもう一度手に取った。
「え?」
日記帳の背の中から、何かが落ちてきた。それは黒いハンコ入れのようなもので、日記帳のロックが外れないと落ちてこないようになっていたようだ。俺はそれを手に取り、開けてみた。簡単に開いて、その中に入っていたものは32GBのメモリーカードだった。
「これは・・・なんだ。」
俺はカバンを取り出し、いつも持ち歩いているノートPCのスイッチを入れてメモリーカードを差し込み、起動させた。メモリーカードが自動的に開き、そこには幾つかのファイルがあった。それぞれに番号が入っていて、俺は最初から開いてみた。
最初は動画のようだった。幾つかあるファイルの左上にあるファイルとクリックし、日付が書いてある一番古いものから開いてみた。
仰天するしかない映像と画像が、そこに残されていた。俺は観ながら、必死に吐き気を堪えていた。悔しさと怒りが激しく沸き起こってきた。
「・・・これは・・・こゆり・・・お前、これを伝えたかったのか?」
俺はノートPCを閉じ、こゆりのことを想った。
5
俺は小劇場「キーノ」にいた。ここはインディーズ映画の聖地として知られている場所であり、ここで低予算映画を上映することがよく行われていた。「キーノ」とはドイツ語で映画館という意味だ。俳優劇団たちが作り上げるマニアックな世界に見せられて通う常連たちで継続されている。完成したのが昭和なので、席も古いタイプのままだ。俺も自作の劇をここで観たりしていたものだ。だが俺は、客席にいるわけではなかった。
無人の劇場にまず入ってきたのは、二人の初老男女だった。女の方はケバケバしいメイクをしていて、派手な服を着ていて太っていた。見るからに分不相応だ。男の方は無表情で痩せていて、冴えない安っぽい服を着ていた。明らかに男女間で格差がありそうだ。
「なによ、ここ。間違いなくここなんでしょ?」
「あ、ああ。ここで間違いないよ、ほら。」
「ハワイ旅行券引き渡し会場・・・間違いないわねえ。でもさ、ここ映画館じゃないの。それっぽい人、誰もいないじゃない。騙されたんじゃないの?」
ハワイ旅行券を受け取りに来た二人だった。二人は手近な席に腰掛けた。二人はスマホをいじくっていたが、間もなくしてもう一人がやってきた。
「あれ!郷畑さん。どうしたの?ここは新作上映会場だよ。」
「あら、鷹澤さんじゃないの。違うわよ、あたしたち、ハワイ旅行が当たったのよ。ここが引き渡し会場だって。ほら。」
「・・・本当だ。でもさ、俺の方にもこんなメッセが来てるんだよ。上映会のはずなんだが。」
「あら、ここになってるじゃない。あんた間違えてんじゃないの?」
男女は郷畑こゆりの里親たちで、もう一人は鷹澤光徳だった。
「どうなってんのよ!あんた、訊いてきなさいよ。」
「ええ、どこで?」
「事務所に決まってんでしょ!・・・あら?」
急に照明が落ち、真っ暗になった。
「ほら、上映会じゃん。でも他の連中は・・・いねえじゃねえか。」
鷹澤も異常さに気がついたのだが、目が慣れるまではと判断して席に座った。同時に音楽が鳴り、スクリーンが明るくなった。そして音声が流れた。俺が声優に頼んで入れてもらったのだ。
『ようこそリアル上映会へ。ご列席の皆様、お好きな席でご覧くださいませ。』
「あたしたちが間違ってんじゃん!あんた、帰るよ!」
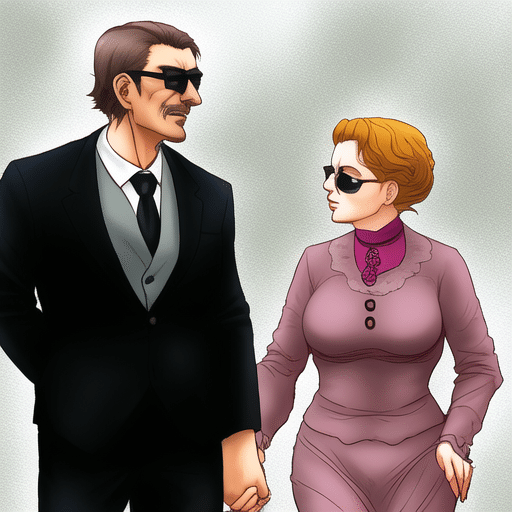
郷畑夫婦は立ち上がって入口に向かい取手に手を当てた。
「・・・あれ?開かない。なんで?あんた、訊いてきなさいよ!」
「どこにだよ。」
「事務所!」
「でもここ出れないなら・・・。」
「あー使えない!」
「ちょ・・・ちょっと黙って!」
鷹澤が叫んでスクリーンを指差した。郷畑夫妻もスクリーンを見た。
「え?・・・なにこれ・・・。」
スクリーンに映し出されていたのは、ドアの隙間から撮影されたと思われる映像だった。そしてそこにいたのは、この劇場にいる3人だった。鷹澤と郷畑夫妻は向かい合って座っていて、目の前には何か書類のようなものがあった。同時に声も流れてきた。
『じゃあこれで、あんたらの借金は俺が肩代わりする。その代わりに、こゆりは俺が預かる。もうあんたらと会うこともねえ。いいな。』
『いやあ助かったよ。里親になってみたけどさ、子供もなんて好きでもなかったしねえ。あんたが好きにできる年齢まで預かるってことだったんでね。どうせあたしたちの子じゃないんだし。好きにしてよ。』
3人はスクリーンから目が離せなくなっていた。もちろん現実であったことだからだし、これが誰にも知られるはずのないことだったはずだからだ。
『ところでさ、あの子をどうするつもりなの?どうでもいいけどさ。』
『へへ。まず俺の好みなんでね。たっぷり教育してやるさ。それからどうするかねえ。とりあえず女優にするか。』
『まあ、あたしが言うのも何だけどさ、可愛い顔してるしさ。ちゃんと教育すりゃいい人形になるよ。』
『だからこその肩代わりだ。じゃあ、これでもうあんたたちと俺は関係ねえ。もう連れてっていいか?』
『まだ寝てるよ。睡眠剤飲ませてるから起きないかもよ。』
『じゃあお姫様抱っこからだな、へへ。』
そして鷹澤たちが近づいてきて、そこで映像は終わった。次に流れてきたのは、夢で見たあの映像だった。
「なんなんだこれえ!」
鷹澤が怒鳴った。誰にも知られるはずのない映像だ。慌てるのも無理はない。
「だ、誰が撮ったんだ!」
「あんた、馬鹿だね。こゆりに決まってんじゃないさ。」
郷畑妻がタバコに火をつけながらつぶやいた。誰もいないとは言え、ここは禁煙だ。常識がない。
「このアングルでさ、こゆりの声がしてんじゃん。誰だってわかるわ。」
「じゃあ、その前のは誰なんだ!お前たちか?そうなんだな!」
「馬鹿言ってんじゃねえよ!」
郷畑妻は立ち上がって鷹澤を睨みつけた。
「こんなの撮影して、あたしたちに何の得があるってんだよ。これもたぶん、こゆりさ。」
「なんだと?」
「あの子はさ、あたしたちが言う資格もないけどさ、頭は良かったよ。後で気がついたんだけどさ、あの子の部屋から安物のデジカメが見つかったんだ。それで撮影してたんだろうね。」
「じゃあこれは?」
郷畑妻はタバコの煙を大きく吐き出しながら、タバコを床に投げて足で揉み消した。
「隠しカメラか何かじゃないの?あんたが脱がせた服についてなかったのかい?それも気がつかねえほど熱中してたってわけかい?結構なこった。こゆりは、あたしたちに面と向かって反抗はしなかったけどさ、きっとこんなの撮影してたと思うよ。はあ、大したもんだ。」
「感心してる場合かよ!おい!誰だ!こんなの流してるのは!出てこい!」
鷹澤はまた怒鳴った。映画監督もやっているだけに声はでかい。
「うるさいねえ。」
「冗談じゃねえ!今これを流してる奴、俺たちを脅迫する気だ!黙ってられるか!」
「あたしたち?馬鹿抜かしてんじゃねえよ!あんたがあの子を連れてきたんじゃねえか!ロリコンのくせに孤児じゃ手を出せないからって、借金あるあたしたちに目つけてさ。否応なく押し付けてったくせに。」
「なんだと?お前たちがどれだけこゆりを虐待してきたか、俺が知らんとでも思ってるのか。あいつが極端にタバコ恐怖だったんで問い詰めたら、お前たちが何かあるとタバコを押し付けたらしいじゃねえか。押し入れで生活させてよ。なーにが部屋だ。ふざけんな。」
「よく言うよ、バーカ。」
「なに!じゃあカネ返せ!」
「何の証拠もねえわ。誰が返すか、馬鹿。」
彼らの言い争いが続いていたが、急に照明がついた。
「なんだ!」
動揺する3人の前に、スクリーン横の通路から男たちが飛び出してきた。警官だった。彼らは警棒を持って3人を取り囲んだ。
「な、なんだ?俺たちが一体・・・。」
彼らの中から、スタジャン姿の男が出てきた。
「鷹澤光徳、郷畑満と留子。人身売買容疑及び児童虐待容疑で逮捕する。証拠は・・・今観た上に、お前たち自身が証明してくれたらな。」
3人は固まり、何がどうなったのか全く理解できないようだった。手錠をかけられ、劇場から出てきたところで、先ほどからそこに立っていた俺と目が合った。俺の冷蔵庫のように冷たい目線と、鷹澤の驚き怯えている目線がぶつかった。
「上田山・・・お前が・・・。」
鷹澤は一言だけ話し、連行されていった。郷畑満と留子も、留子がけたたましくわめきながら連行された。俺は彼らをじっと見ていた。様々な思いがこみ上げてきていた。
「ご協力感謝します。」
刑事が声をかけてきた。中堅どころの猛者という雰囲気だった。
「元々あの男には児童性暴力の疑いがあったところに、あなたからのタレこ・・・失礼、訴えがあったものですからね。しかし郷畑の証言が欲しかった。少々手荒なやり方でしたが、助かりました。」
「刑事さん・・・。」
「なんでしょう?」
「何かを失うって・・・辛いことですよね。」
刑事は軽くため息をついて俺を見た。
「あのタレントのことですか?かわいそうに・・・。あなたは・・・。」
「俺はもういいですか?」
「え?・・・ええ、諸注意はもうお伝えしていますし、証拠は警察で保管。他に何かあれば、何かしら通達があると思いますが、今日のところはもうよろしいです。」
「わかりました。お疲れ様です。」
俺は刑事にあれこれ訊かれるのも辛かった。確かにこゆりの無念を晴らすことはできた。こゆりも安心してくれるだろう。あの山小屋で見た夢も、こゆりが俺に訴えてきたものだと思っている。だが、もうこゆりとは会えないのだ。
俺はタクシーを飛ばして、こゆりがいる納骨堂に向かった。あの義親は、墓さえ作ってやっていなかった。俺がやるべきことは、こゆりの墓を作り、いずれそこに俺も入ることだと思っている。幸いなことに、俺の親も他界しているし、墓の面倒は兄貴が見てくれている。それでいい。
6
鷹澤たちは人身売買容疑及び児童虐待容疑に加えて、こゆりが死亡した際には生命保険受け取り画策及び内臓転売まで画策していた容疑まで加わり、おそらくはすぐに実刑が確定するだろうということだった。とことん非道としか言いようがない連中だった。俺はその後の芸能界にも愛想が尽きて、放送作家をやめて小説家としてデビューすることにした。
それから俺はこゆりの墓を作り、婚約していたとして夫として契約することができた。おかげで俺の財産はかなり消えてしまい、それまで使っていた賃貸マンションを引き払って、兄貴のコネで戸建てを格安で借りることができた。築40年のボロ屋だったのだが、俺は満足だった。なぜなら、あの山小屋まですぐの場所だったからだ。俺は何度もあの山小屋に通い、こゆりとの思い出に浸ることができた。しかしあの夢はもう見ることはなかった。
ある日、俺はこゆりの墓掃除をしていた。毎日通い、掃除しながら何があったかどうかを話して帰るのが日課になっていたのだ。掃除しながら話しかけると、これの中ではこゆりのあの可愛い声がいつも聞こえてきていた。こゆりの墓は小さいもので、生来は俺もここに入る。一応兄貴や甥たちにもその後のお願いはしていたし、それなりの金額も渡していた。
こゆりの墓は、小高い丘にある霊園の一角にある。こゆりの戒名は『明郷小百合大姉』とした。知り合いの住職にお願いしてつけてもらったのだ。俺の中ではあの華奢で明るいイメージのこゆりしかいなかったから。誰もいなかったので、俺は声を出して、こゆりに話しかけた。
「こゆり、今日やっと本の契約ができたよ。もう紙媒体は無理かもな。でもなあ、俺には電子書籍化する気は・・・ねえんだよ。」
俺の中には、あの日記の重さが残っていたのだろう。紙出版にこだわってしまった。すぐに収益は得られないのだ。まあおいおい考えるとしよう。
掃除も終わり、手を合わせて帰ろうと思っていると、スマホが鳴った。兄貴からだった。
「おお、どうした?」
『あのさ、さっき知り合いから連絡あってよ。轟来学苑という児童養護施設に勤めている人なんだ。俺と仲いいんで色々話してたんだわ、お前の奥さんのことでな。』
「こゆりの?」
『ああ。その人はベテランさんなんだがよ。どうやら、こゆりさんの面倒見てた人らしいんだ。』
「え、そうなの?」
『お前と話したいそうだ。田木川さんって人だ。一度会ってみないか?』
「ああ、いいよ。」
俺は早速兄貴を通じて、轟来学苑に向かった。アポを取っていたので、すぐに田木川さんに会うことができた。
「まあまあ、わざわざお越しいただいて恐縮です。田木川巴と申します。」
「上田山純一です。あの、私の妻のことで・・・。」
田木川さんは分厚いアルバムを持ってきていて、俺の前に置いた。
「あの子が芸能界で活躍していたので安心していたんですが・・・まさかあんなことになるとはねえ。そのことをたまたまお兄さんとお話していて、あなたのことをお聴きしたのですよ。」
話しながら、田木川さんはアルバムを開いて俺に見せた。
「この子が、こゆりちゃんです。本名は素水こゆりと言います。」
その名を聴いた時、俺の頭の中が大回転していた。
「まさか・・・まさか!」
「やはり・・・先日警察の方がいらして調査されていったんですけどね、その中であの事件の中で同じ名前の方がいらっしゃるとわかって・・・。」
「それ、警察には?」
「いいえ、申しませんでした。尋ねられたらお答えしようと思っていたのですけど。ですからこうしてあなたにお伝えしているわけです。」
俺は学苑を後にして、すぐにあの山小屋に向かった。もう暖かくなっていたので、花がたくさん咲いている道を飛ばしていった。
「着いた・・・。」
ここのところ忙しかったので、ちょっと久しぶりではあった。俺は早速管理人室に向かった。ドアをノックして待った。少しして、ドアが開いた。
「あんたか・・・もう来る頃だと思っていたよ。」
「一二三さん・・・あんた、ひょっとして・・・。」
素水は微笑んで、俺を中に入れた。そしてあの夜と同じように、俺たちは向かい合って座った。
「まず・・・俺はあんたに感謝しなくちゃなんねえ。」
「感謝?」
「俺の娘の・・・旦那になってくれたんでな。」
「やはりな。じゃあどうして名乗らないんだ。なんでこゆりを孤児にしちまったんだよ!」
素水は薪ストーブの上にあるヤカンを取り、コーヒーを入れてテーブルに置いた。
「俺は元々、霞っていう名字だったんだ。」
「霞・・・。」
「ああ。若い頃はヤンチャでな。当時いた組の、カシラの女に手をつけちまった。知らなかったとは言え、ヤクザの世界では通用しねえ。女は・・・こゆりの母親はこっそりと産んで、俺は擁護施設に預けちまった。家の前に捨てられていたと言ってな。ほれ、こんなもんがあるんでよ、すぐに察してくれたよ。」
素水は腕をまくった。見事な彫物が見えた。
「これは背中一面にある。こんな極道もんならすぐわかってくれるわ。俺は、知り合いの名前を思い出してな、この子の名前は素水こゆりだってことにしておいた。」
素水はコーヒーを飲んで続けた。
「俺はもちろん破門になったし、狙われる立場だ。海外に行って逃げたよ。フィリピン、インドネシア、スリランカ・・・転々としたもんさ。それで、組が解散したって聞いて戻ってきたんだ。娘が芸能人になっていたことは知っていた。今の社長が、同じ組を出た建築屋だったんでな、そのツテでさ。俺は名前を素水に変えて、ここで働いていた。名前変えたのはさ、いつか会えるかと思っていたからでよ。そしたら、まさかここでロケがあるとはな。そして・・・。」
素水の目から涙がこぼれた。
「あんなことになってよ・・・俺は自分を責めたよ。毎晩夢を見てよ・・・。娘がよ、夢の中で言うんだ。あんたに会いたいってな。そして娘からあんたの名前も聴いていた。馬鹿なことだと思っていたら、まさかあんたがやってきてくれた。俺はあんたに日記を渡してやることしかできなかった。その後で、色んな人から聴いたよ。あんた、娘のために墓を作ってくれたんだろ?ありがとうな。」
素水は箪笥の上にある写真を取って、俺に見せた。それは、素水とこゆりが笑って写っていた写真だった。
「ロケの時にな、監督さんにお願いしてファンだからって撮ってもらったんだ。俺にとっては、これ以上ない幸せな時間だったし、これがあるから俺は生きていられる。娘は当たり前に俺が誰かはわからなかったはずだが、魂の世界では何でもお見通しってことなんだろうなあ。俺は、そう思うしかねえ。」
俺はしばらく写真を見て、そして素水に返した。
「わかりましたよ。あんたも大変だったんだな。まさかこんな形で結婚するとは思わなかったし、ましてやこうやって出会うとも思っていなかった。だからこう言わなくちゃな。お義父さん・・・娘さんを、俺にください。」
「う・・・うおお・・・うおおおおおおお!」
素水は顔を伏せて号泣した。嗚咽しながらしばらく泣き続けた。
「もちろんだよ・・・ああ、そうさ!全部俺が悪いんだ。娘にも辛い思いをさせちまった。だけど、あんたに救われたよ、俺も娘も。」
俺は懐から、スマホを取り出して画像を選んだ。
「これがこゆりの戒名だ。書いておくといいよ。」
元水がメモするのを待って、俺は立ち上がった。
「お義父さん・・・もう会うことはないと思う。その方がいい。お互いにこゆりを想って生きていくしかないし・・・それじゃあな。」
「・・・ありがとうよ。」
俺は管理人室を出て、山小屋を見た。ここから全てが始まった。ここでこゆりが、鷹澤の命令とは言え、俺に声をかけてきたことからだ。こゆりとの短い生活は、俺にとっては永遠でもある。もうあれ以上の恋などできない。俺の中では、あの時期こそが新婚生活だったとなっている。そしてこれからは、夫としてこゆりと暮らしていく。
俺はクルマに戻ろうとすると、横が暖かく感じた。
「こゆり・・・そこにいるのか?」
俺は思わずつぶやき、横を見た。かすかな風が吹いてきて、花が舞う形が、こゆりのシルエットに見えた。こゆりは横にいてくれている。そうだ、こゆりが好きで飼いたいと言っていたポメラニアンを見に行こう。
きっとその子が、俺らの子供になるはずだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
