
シリコンバレーで”根回し”はないのか?
日本では、会議の前にメジャーな出席者の同意を取り付けておいて、会議そのものはシャンシャン、と終わって、会議が形式的なものになる傾向があるというような事が一般的には言われたりします。では、シリコンバレーではどうなのでしょうか。
結論からいうと、ありまくりです。どういう風に行われるのかをみていきましょう。
思い込んでいたけど、実際には俗に言われていることと現実が違うってことは結構ありますよね。例えば、「アメリカは、日本と逆で、大学に入るのは簡単だけど、卒業するのは大変。」
これってまったくウソです。特にトップスクールに入ろうと思うと、日本以上の受験対策で徹夜する高校生もいます。シリコンバレー/ベイエリアでは特に、高校生にとっても大変Competitiveな地域であり、精神的に追い詰められて自ら命を絶つなんて事さえも起きてしまっており、問題になっています。
話はそれましたが、この記事を読むことで、ステレオタイプの思い込みを捨て、正しい認識を持つことができるようになります。また、英語は結構フレキシブルな事が分かります。
アメリカでも通用するようになってきた”Nemawashi”
アメリカでも、いくつかの日本語は英語として通用するようになってきます。
ちょっと古いのですが、ものを片付けるのを、コンマリする、という言い方が流行ったことがあります(笑)。
“I need to Konmari my office” これはあの有名な片付けコンサルタントの近藤麻理恵さんが、Netflixの番組で一躍アメリカでも知られるようになったからなのですが、まだまだ知ってる人と知らない人がいます。5人にきいたら3人くらいは知ってるという感じですかね。感覚的には。
こういう記事も見たことがあります。
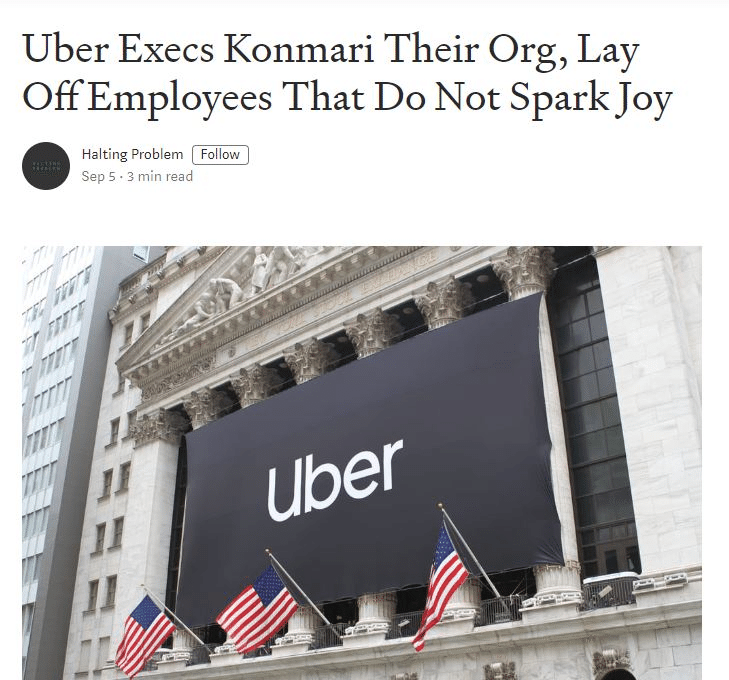
もとの記事へのリンクはここにありますので、ご興味ある方は読んでみてください。
読むと、コンマリさんの影響をつよく受けたUberのCEOを、従業員が会社のマネジメントにとって「ときめくかどうか」で一人ずつ仕分けし “Does this employee spark joy in your lives?” 、そうでない場合はこれまでの勤務に感謝して捨てるという恐ろしい記事なのですが、ここで “Konmari their orgs” (Orgsというのはorganization、つまり部署とか組織のことですね)と書いてあります。組織を整理するという意味で使われています。
他にどういう言葉があるのかというと、
Karoshi(過労死)- これを知ってるのは知識人ですね。
Omakase(おまかせ)‐ これはよくレストランのメニューで見ます
Kaizen (改善)‐ 友人は Kaizan(改竄)と発音するので注意してます(笑)
とかなんですが、Nemawashi も立派に通じます。(少なくともシリコンバレー/ベイエリアのインテリは知っていたりします)
根回しってアメリカでもやるのか?
で、本題。
これについてはこれまで何人もの シリコンバレーのアメリカ人に聞いてきて、答えはいつもYES!です。日本でしかやらないのかと思っていたら、大間違い。当然こちらでもやる、こういう事をやらないのはレベルが低く、Simple mindedな人たちだ、という人さえいます。
「へえー、日本の会社だけかと思っていたけどね」というと、
「そんなことはない、何故なら、We do not want to give him/her a surprise」とのこと。アメリカ人でもそんな話は聞いてない、Surpriseだ、と怒る人はいますので、そのサプライズを与えたくない、というのが良く聞く理由です。人によっては、StakeholderのPerspectivesを得るため、と言ってみたり、先に説明することでBuy-inを得るため(正式な承認ではないが、サポートを得るというような意味でBuy in は使われます)。
日本のトラディショナルな会社では、稟議書みたいなものを回して、根回しというプロセスを正式化しているところもあるようですが(幸いもりやんが昔入社した日本の会社には無かったですが)、そこまでではありません。
ただ、影響力のある人や、聞いてないと怒りそうな人に事前に話しておく、そして理解を得る、またはそこでfeed backを受けてディレクションを修正する、というようなプロセスです。
これを英語にすると、どう表現できるかというと、
I have to have a “nemawashi” meeting with Greg.
I have to “nemawashi” Jennifer. (動詞として使ってます)
We have to do some “nemawashi” in advance.
Let’s give a heads-up toMichelle.
Let’s socialize Daniel before the committee meeting.
最後のsocializeって、よく聞くのに辞書を引いてもあんまり載ってません。綴りはこれのはずなんですけど。
米国と日本が違うのは、実際にこの後ミーティングが行われて、そこでちゃんと物事がトップダウンで決まる、という事でしょうか。
日米のビジネス文化は、エリンメイヤーさんによると、ともに世界でも稀なのだそうです。ここら辺は別途エントリーをもうけて解説していきます。米国で働くうえで、とても参考になった本で、私はこの本を15冊買って、グローバルプロジェクトのチームに配りました。私が読んだのは英語版の方ですが、日本語翻訳版も出ています。

おまけ
言葉というのはフレキシブルで、その時代に応じてどんどん進化していくので、例えば、米国のビザの申請がうまくいかなかったり、入国審査で追加で尋問されたりした人が、I got Trumped! と言えます。トランプされた、つまり、移民政策に厳しいトランプ大統領の影響を実際に受けてしまったよ、という感じです。
これは、誰でもよくて、例えば、以前の会社で、超絶お金に細かいCFOでSamという人がいたのですが、会議にかけた投資案件がSamのせいで却下されてしまった後、その却下されたマネージャーが私に、I got Samed!といっていたのを思い出します。この場合、動詞として使われる人物像に共通の認識があるのが特徴です。
では今日はこれで。
最後までお読み頂きまして有難うございました。引き続き現地からの最新情報や、違う角度からの情報を多く発信していきたいと思いますので、サポート頂けると嬉しいです!
