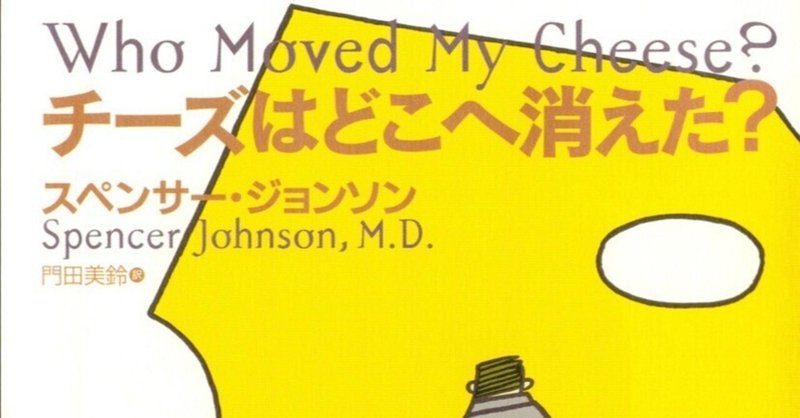
#003 逆に思う。チーズはどこにあったのだろうか?
『チーズはどこへ消えた? 』 スペンサー・ジョンソン(著)
この本を読むことになったのは、やはり自分が参加し始めたマグさんの読書コミュニティ・Lectioでの読書会の課題図書になったからでした。
Amazonの情報によると、2000年11月30日に発売とありますので、もう20年以上経過したビジネス本ということになります。
自分は今回初めて読むことになったのですが、それでも本のタイトルは聞いたことがありましたので、ビジネス本の話題作だったようです。
結論から感想を言ってしまいますが、この本は確実に「良書」だと思います。
ビジネス本としても、人生観を成長させる教養本としてもある種の普遍性を持っていると思います。
分かりやすい寓話の形をとっていますので、普段読書に慣れていない人でもすんなりと読むことができると思います。
優れた本がいつもそうであるように、読み手の人生経験に応じた意味の表われ方をしてくれますので、どんな年齢の方が読んでも、おそらく時を経て読み返しても自分の成長と変化を感じられるような、そんな味わい深い本だと思いました。
いつも思います。読書会のメリットの大きな一つなのですが、自分が意図しない紹介された本を読むことで、自分の想像の延長線上ではない、目から鱗的な体験が得られるということがあります。
これが本当にすごおく、楽しいことなんです。
自分の頭の中の空気を入れ替えるような感じの心地よさがあります。
「本当の出来事」はいつも「晴天の霹靂」だ。
ある迷路の中で苦労をしてやっとチーズを見つけた2匹のネズミと2人の小人がいます。しかしある日突然大事なチーズが消えてしまう。
いち早く別のチーズを探すべく姿を消したネズミに対して、2人の小人はその場を動かず戸惑うばかり。
小人のホーはそれでも勇気を振り絞ってチーズを探しに行動します。
一方で小人のヘムは最後まで動こうとしません。
…この寓話は「あなたならどんなふうに行動しますか」と問いかけてくるようです。
同じ日、ヘムとホーはのんびりとチーズ・ステーションCにやってきた。二人は、毎日小さな変化が起きていることに注意を払わなかったから、いつもどおりチーズがあるものと思っていた。
二人には晴天の霹靂だった。
「なんてことだ!チーズがないじゃないか」ヘムは叫んだ。「チーズがないじゃないか。チーズがないぞ」そう言えばチーズが戻ってくるとでも思っているのか、大声でわめいた。
「チーズはどこへ消えた?」彼は声を上げた。
やがて、腰に手をあてると、顔を紅潮させ、声を張り上げて叫んだ。「こんなことがあっていいわけはない!」
チーズとは物語の中では幸福の象徴です。
まさにそのチーズが消えてしまった日のシーンがこの引用部分です。
自分はこの描写が大好きです。試しに繰り返し読んでみてください。
可笑しくもあり、そして哀しくもあります。
とてもリアリティがある、と感じています。
大袈裟に言えば、人がそれぞれの人生の中で「自分の身にあんな出来事が起きちゃったんだ!」と思うようないわば「本当の出来事」ってやつは、いつもこういうふうに起こるのではないでしょうか。
昨日までは、想像もしなかった出来事が起きるのです。
それが起きる前と、起きた後では決定的に全てが違ってしまうのです。
「晴天の霹靂」
雲一つないような青空において突如として落雷が生じることを意味します。
昔、学生の頃に読んだ『魔の山』(トーマス・マンの小説)で初めて知った言葉です。それ以来、自分の頭の中で鮮やかに残る言葉になりました。
自分は「本当の出来事」を想像します。
それは一夜にして災害で住む場所を失うことかもしれない。会社が倒産することかもしれない。家族を失うことかもしれない。健康を失うことかもしれない。あるいは戦争のようなものが始まってしまうことかもしれません。…皆さんは何を想像しますか。
チーズはどこにあったのだろうか?
本を読む時、できるだけ自分に引きつけてじっくり考えたいと思っています。
そして、その本の魅力をより深く感じるように読もうとします。
そうすることで自分の考えを自分自身が掘り下げて、何かを発見することにつながります。本を読むことは自己内対話をすることです。
例えばこういうふうに自問してみます。
「現実のチーズが変化して消えているっていうのに気づかないとすれば、逆に、昨日までありありと見ていたチーズという存在は一体どこにあったのだろうか?」
二人は、ひどいめにあわされたと、しきりにわめき散らした。そのうちホーは憂鬱になってきた。あしたもチーズがなかったら、どうなるだろう?あのチーズをもとにして将来設計をしていたのに。
物語の中で「チーズ」とは幸福の象徴と考えられます。
二人の小人ヘムとホーも、毎日チーズを食べに通い、いつもの道を迷わず通ってチーズを得ていました。
そしてチーズがまさに消えてしまったこの期に及んでもなお、引用部分のように「あしたもチーズがなかったら、どうなるだろう」などと考えています。
自分はこれこそ「チーズ」があった場所だ!…と思いました。
チーズは「あした」の時間の中にいつもありましたし、それをもとに「将来設計」までしていたのです。
これを小人たちの世界から、自分の世界に置き換えてみます。
「自分は明日も明後日も収入を得ているはずだ。10年後も20年後も老後だって何とか食べていけるはずだ。明日も明後日も将来も多分そこそこ健康でいるはずだし、親しい家族や友人たちと一緒にいて幸せに暮らしているはずだ」
改めて書き出してみると、自分がこういうことをすごく当たり前のように思っているのだと気づきます。
明日も明後日も将来も自分はそれなりに幸福でいるだろうし、そうでありたい。
そのための計画も立てているし、多少の努力もしている。
だから、明日も自分は幸せでいるだろう。(そうであるべきだ!)
しかしそれは残念ながら現実そのものではなく、「あしたの計画」として素朴にいつも願っている欲望であって、その正体は止まった「思考」に過ぎないのだと思います。
そこまでじっくり考えて、自分は思いました。
「ああ、チーズは止まった時間と思考の中にずっと有ったんだな」と。
これがチーズがあった場所ではないでしょうか。
止まった時間と思考とは、自分がそうあるべきと信じる価値観とパラダイムに基づいて計画的であろうとする態度です。それってダメなことでしょうか。むしろ「理性」的な生き方として望ましいことのようにも思えます。
しかし本当の理性とは自分のパラダイムを疑ることを忘れない態度なのだと思いました。
それでも楽天的に行こう
2人の小人のうち、ヘムはその場に残り続ける。
ホーはネズミたちを見習って、新しいチーズを求めて行動をしていく。
新しいチーズは見つかるかもしれないし、見つけられないかもしれない。
こういう時試されているのは、意志であったり勇気と呼ぶべき能力だと思います。
作中に素敵なフレーズがありますので引用いたします。
彼は再び新しいチーズをみつけ、味わっているところを思い描いた。それから新しい地域へ進んでいき、まもなくあちこちで小さなチーズのかけらをみつけ、気力と自信を取り戻した。
この「新しいチーズをみつけ、味わっているところを思い描いた」という部分が大好きです。
まだチーズは見つかっていません。でもいつか見つかった時のことを想像することは自由です。
素朴ですが勇気が出ます。
ここで発揮されているのは「楽天的な態度」です。
軽さ、楽天性、行動の素早さ、変化を恐れない。
考えすぎない。分析しすぎない。
「〜であるべき」より、楽しもうとすること!
きっと読んでいただければ分かると思います。
本当の勇気とは、自分がこの軽やかさを選べることなのだということに。
では!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
