
北京で会った音楽教師
その人の名は書けない。北京で会った元音楽教師の男性としか言えない。その理由を追って書き記す。
戒厳令は準戦争状態
「まことに言いにくいのですが、戒厳令下、つまり準戦争状態の所に行かれる訳ですから、保険の対象にはなりません」
目の前に積まれた百万円の現金と香港に向かう航空券。夜になって雑誌編集部に呼び出された会社の系列旅行会社の男性は事務的に説明を続けている。雑誌記者のぼくは明日の朝には成田からとりあえず香港に出発することになっているが、まだ現実感がない。最終目的地は、戒厳令下の北京だ。
アサヒグラフ記者のぼくが、緊急の編集長命令により、戒厳令下の北京に入ったのは、1989年6月8日。天安門事件が起きた6月4日から4日間が経過していた。都内で別の取材をしていた4日、急遽呼び出され、北京特派が決まった。翌朝、成田空港から香港に入り、すぐに中国本土の観光ヴィザをとり、8日、北京入りした。まず向かったのは、空港に比較的近いホテルだ。大使館員や報道各関係者がまとまって逗留していた。ほとんどの在留邦人はぼくと入れ替わりに日本へ帰国していた。
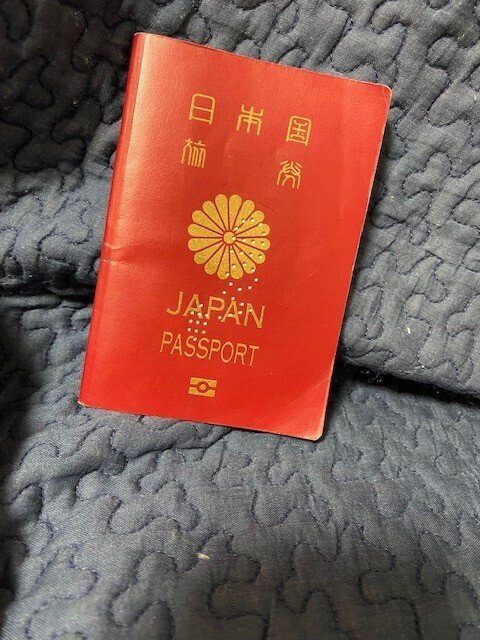
目が合って声をかけられる
「すぐ近くに私の家がありますから、来ませんか。きたないところですが」
たどたどしいが丁寧な言葉遣いの日本語で、男性から声をかけられた。一瞬、返答に詰まった。が、すぐに伺う旨を告げた。扉が開かれたのだから入らないわけにはいかない。誰が味方で誰が敵かわからない状況で、相手も声をかけたのだろうから。
北京市内。故宮の北にある什刹海(シーシャ―ハイ)公園の池で泳いで、水から上がってきた男性と目が合ったので、「ニーハオ」とあいさつすると、「あなたは日本のかたですか」と日本語で声をかけられたのだ。簡潔に、北京に滞在している理由を告げた。戒厳令下で暮らす、ごく普通の市民の様子を日本の雑誌に書くのが自分の仕事である、と。互いに身の危険を及ぼす可能性がある。お互いの身の上を名乗ったうえで家に来い、という誘いだった。日焼けした顔を心持ち上気させながら自転車を引いて歩く、60歳代半ばの元音楽教師の後に従った。数年前まで音楽教師をしていたが定年退職したという。つかず離れずの距離をあけながら、ぼくらは歩いた。
人民の海が砂漠へ変わった
滞在三日目、郊外にある空港近くのホテルから、北京の中心部のホテルに居を移してからは、連日、市内を歩いた。足を棒にして歩き回った。
中国語はできない。時節柄、通訳を紹介できないと旧知の北京特派員から伝えられ、徒手空拳で歩き回るしかなかったのだ。
北京の銀座通りともいうべき王府井大街。夏の日差しを受けて、槐(エンジュ)の並木が緑陰を作り出している。蝉の声も響きわたる。アイスキャンディーをほおばりながら、買い物客の人ごみを歩いていると、定期的に10人ほどが縦列行進でやってくる武装した人民解放軍兵士と出くわした。道行く市民は道をあける。示威行進、そう、明らかに示威を狙っている。
街中には、市民に「暴徒」の存在の密告を促す「通告」のビラがそこかしこに貼ってある。さらに日が経つと、赤い腕章を巻いた自警団とおぼしき人たちが目立つようになった。5月半ばから、北京の様子を見続けてきた先輩記者が教えてくれた。
「6月4日以前は、自分たちが軍や警察に囲まれると、『報道の自由』と叫んでくれる人民の海があった。今はそれが通報する立場に変わった」
海が砂漠へ転じた、という。いつ、どこで、誰が、何をするか判別できない。そんな「威嚇」に囲まれた中では、北京市民は固く口を閉ざすしかすべはない。ぼくはそう思い込んでいた。そんな状況での出会いだった。
水餃子と漢詩
危険を顧みず、初対面の異邦人を、ごく自然に自宅に誘った男性の部屋は、中層アパートの最上階にあった。さすがに部屋に入るまで、ぼくは身構えていた。どうなるだろうか、と。
頭の中でスケッチする。居間はコンクリートが剝き出しで、8畳ほどの広さだろうか。中央にテーブル、隅に整理ダンス、冷蔵庫、テレビ、扇風機、奥にベッドがあった。
扇風機をかけ、ジュースを出してくれた。写真アルバムを開き、日本語のテレビ用教材を取り出して説明する。会話が途切れない。歓待してくれているのが分かる。
彼の身の上の記憶はおぼろげなものだ。60歳代半ば。中国東北部(旧満州)出身で、1949年の中華人民共和国建国の年に北京へ来た。子どもたちに音楽を教えていたと言ったが、詳しくは聞き出せていない。旧満州という出身地のこともあり、日本語に興味があった。日本語の勉強を10年前から始め、学習をほとんど欠かしたことがないと言い切り、嬉しそうな顔をした。日本語にはよどみがない。
本来なら、家族構成や戦争時代のこと、音楽教師のことなど聞き出そうとするのが記者の業だが、不完全だった。ぼくの側に余裕がなかった。気が急いていたのだろう。記事に使えそうな直接的な話題ばかり尋ねていたからだろう。
「私の考えは、ごく一般的で、平凡な北京市民のそれです」と強調した。
好きな政治家は、民主化運動に一定の理解を示していた胡耀邦。彼が死去してからの民主化運動については、言葉を選び、時には筆談を交えて話した。
「運動の内容は複雑で、その後の是非は簡単に言えません。正義のある学生もいたでしょうし、不純な悪い人もいたでしょう。学生は生活経験が少ないので、性急なところがあったかもしれません。でも学生は、これからの中国にとって大切な人たちだから、今後、希望が叶わなくなるのは可哀そうだ。
人民解放軍の北京入りは、北京市民は軍隊を見慣れていないので突然だったので驚いた。99パーセントの北京市民は良い人だから、『暴乱』ではありません」
どこまで記事にしてよいのか、ぼくは尋ねた。名前を出さなければ何を書いてもかまいません。あなたが見て、聴いて、感じたことをそのまま書いていいですよ、と言われ、言葉と胸が詰まった。すると元音楽教師は、「大きなよろこび」という意味の漢詩を書いて渡してくれた。
「他 郷 遇 故 知」
異国で初めて出会って、昔からの友人のように親しくなることと理解した。後ろを向いて、わからないように涙を拭った。食べていけという水餃子の夕食を辞した。送ろうとする彼の申し出を断った。
今考えると申し訳ないことをしたと思う。しかし一刻も早くホテルに戻りたかった。メモを一切とっていないから、見たこと、聞いた事を忘れないうちに原稿にしたかったのだ。締切も迫っていて、余裕がなかった。当時のぼくは35歳。経験も少ない記者に振りかかった幸運に心の底から感謝しながらも、気が急いていた。
階段から降りて、足早に歩いたが、後ろを振りかえらなかった。きっと、彼はぼくの背中が見えなくなるまで見送っていた、と確信している。
