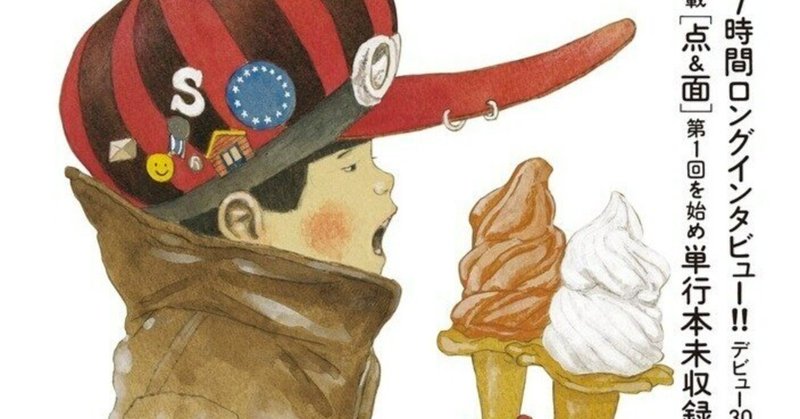
東京ヒゴロ
知ってるかスマイル
・・・ 血って鉄みたいな味するんだぜ。
――――ペコ『ピンポン』より
▼▼▼東京ヒゴロ▼▼▼
『東京ヒゴロ』という漫画を読んだ。
何を勘違いしたのか、2巻で完結すると思ってたら、
今も連載中で、今年以降に3巻も読めると知り嬉しくなった。
松本大洋の漫画が好きだ。
とはいえ僕が松本大洋に出会ったのは結構遅い。
それでも20年も前のことだけど、
まず宮藤官九郎の映画版『ピンポン』に出会い、
そのあと原作漫画を読み、
友達に『鉄コン筋クリート』も面白いよ、
とか『青い春』っていう映画もあってね、
とか教えてもらっては読んだり観たり。
そんな順番で知っていった。
最近だと『サニー』がもうすごくて、
全巻Amazonで購入し所有している。
今は教会の友人に貸している。
『サニー』はちなみに児童養護施設の話で、
松本大洋さん自身が児童養護施設出身者なので、
それはもう、涙なしには読めない漫画だ。
あの独特の「版画みたいな画風」が、
とっつきにくくて読んだことない、
っていう人も多いかとは思う。
特に女性には多いかもしれない。
でも、あの版画みたいな絵のタッチを、
たとえばテニスの王子様みたいな、
現代風の作画にしたら、
もっと大衆にウケ、
全員がその面白さを知ることができてハッピーかというと、
それは全然違うのである。
あの「版画みたいな作画」であることに必然がある。
「世界に入り込む障壁が高ければ高いほど、
その世界に入り込んだときの、
没入の度合いが深くなる」からだ。
逆に言えば、
何の引っかかりもなく、
するすると読み進められる漫画は、
読んだ翌日にはその内容を忘れていたりする。
一番よく覚えている小説は、
文体に癖があり、読みこなすのが困難だった小説だ、
みたいな話って多くの人にあると思うけど、
それとよく似ている。
小中学生のころ、
ご多分に漏れずに月曜日は週刊少年ジャンプを楽しみにしていた。
僕が読み、弟が読み、
『スラムダンク』が始まってからは、
母も読んでいた。
『スラムダンク』の他にも、
『ドラゴンボール』とか『キャプテン翼』とか、
『幽遊白書』とか『魁!男塾』とか、
『ジョジョの奇妙な冒険(特に第3部)』とか、
それはもうきら星のような、
今考えると「神々の共演」ともいえる、
ジャンプ黄金期に少年だった直撃世代なのだ。
さて。
それはそうなのだけど、
いまだに脳内にこびりついている作品が僕にはあって、
それが漫☆画太郎先生の、
『珍遊記』だ。
もう、あれが始まったから、
お母さんがジャンプを買ってくれなくなった、
という家庭も全国には少なからずあったのではないかと類推されるほど、
下品かつ役に立たず、
「何かしら子どもにとって禍々しきものを見せられている」
と、全国の教育ママたちを戦慄させただろうその作品は、
2ページに4回はチンコの絵が出て来たし、
ウンコを描くそのGペンの描き込みの精緻さは、
狂気の領域に達していた。
内容?
覚えているわけがない。
だって、ないんだから、内容なんて。
でも、僕の中の一部は、
いまだに『珍遊記』の世界に閉じ込められている。
そして、「作品の世界に閉じ込められ出てこられなくなる」
という、すべての芸術における至高の体験を教えてくれたのは、
キン肉マンでも北斗の拳でもキャプテン翼でもなく、
『珍遊記』なのだ。
マジで読まないでください。
あれは危険な漫画ですから。
▼▼▼松本大洋の世界▼▼▼
何が言いたいかというと、
松本大洋の作画の「クセのスゴさ」は、
必然があるということだ。
松本大洋の漫画には、
世界が広がっている。
『サニー』を読むと、
たしか三重県の児童養護施設が舞台だが、
「一方その頃、江ノ電ではペコがスマイルに、
カルビーと湖池屋のお菓子作りの哲学の違いについて、
一方的にしゃべり続けてるんだろうな」
とか思うのだ。
『東京ヒゴロ』を読むと、
「今踏切の向こうで自転車に乗っていたのは、
三重県の児童養護施設から、
東京の生みの親に引き取られたあの子かな」
とか思うのだ。
そこには世界があって、
「そこに世界がある」と、
読者に信じさせることができる。
そして読者の一部をそこに閉じ込めることができる。
これはあらゆる「作家」と言われる人種が、
それが漫画家だろうと小説家だろうと映画監督だろうと、
ゲームクリエイターだろうと、
喉から手が出るほど欲しくてもなかなか手に入らない能力なのだ。
その特殊能力を、
松本大洋という天才は、
なぜか授かって産まれた。
▼▼▼書くという「業」▼▼▼
さて。
『東京ヒゴロ』である。
東京ヒゴロは編集者の話だ。
そんな「才能を授かっちゃった人々=ギフテッド」と、
気まぐれな大衆に橋を架ける存在が編集者だ。
「助産師」とも良く喩えられる。
ギフテッドはギフテッドであるゆえに、
性格にクセがある人が多い。
映画版『スパイダーマン』にあるように、
「大きいなる力には、
大いなる責任が伴う」。
「過剰な才能」を、
どうやって殺さず、暴発させず、
世間のサイズに収めてパッケージングするか、
というのが編集者の職能なのだが、
これを主題化した漫画、
というのはとても珍しいと思う。
小説家を主人公にした小説、
みたいな感じで、
構造上「メタフィクション」になるのだが、
これが松本大洋さんの作風と抜群に合っている。
メルマガのシーズン4をはじめたのは去年の秋で、
書き方を変えたりもした。
書けない苦しみも、
書けた喜びも、
書くということの困難も知っている。
それに生活や人生がかかっているプロの作家とは、
また一枚重みが違うのだが、
それでも多分、多くの人よりも、
僕はたくさん書いている。
書くということを習慣にしている。
書くというのは「業」のようなもので、
その業を背負ってしまった人間は、
書かないと生きている気がしないし、
書けないと地獄の苦しみを味わう。
その苦しみから逃れるために書くのだが、
たまーに執筆の女神が微笑んでくれたとき、
「まずまず満足に書けた」という瞬間が訪れる。
ごくたまーに、だけれど。
そのときの脳内物質の出方が、
たぶんパチスロ依存症の人の、
確変が出たときの出方と似ていて、
かくして業を背負った哀れな書き手たちは、
書くという業に閉じ込められていく。
この「閉じ込められ」を松本大洋は『東京ヒゴロ』で描いた。
クライアント中心療法のカール・ロジャーズは、
「最も個人的なことは、
もっとも普遍的だ」と言ったが、
松本大洋のこの「漫画家という人種の業」についての漫画は、
実は普遍性を持つ。
会社員にも医師にも教師にも瓦職人にも、
おそらくこの漫画は響くと思う。
そういう普遍性を描ける作家は少ない。
僕は松本大洋のいる世界に生まれたことを、
神に感謝している。
終わり。
*********
参考文献および資料
*********
・『東京ヒゴロ』松本大洋
・『Sunny』松本大洋
・『ピンポン』松本大洋
・『カール・ロジャーズ クライエント中心療法』佐治守夫・飯長喜一郎編
・映画『スパイダーマン』サム・ライミ監督
+++++++++++++++++++++
『とある氷河期世代・フリーランスの絶望日記』は、
以下の無料メルマガを購読していただきますと、
毎週コーナーとして届きます。
よろしければご登録ください!
NGOの活動と私塾「陣内義塾」の二足のわらじで生計を立てています。サポートは創作や情報発信の力になります。少額でも感謝です。よろしければサポートくださいましたら感謝です。
