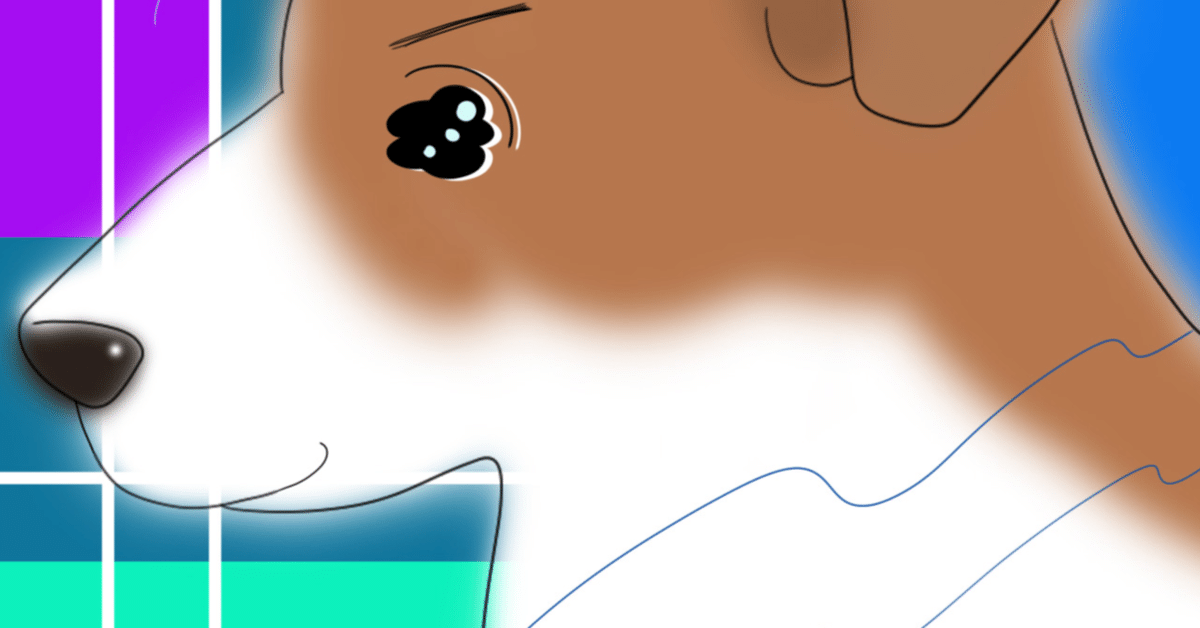
とも動物病院の日常と加納円の非日常
あいつ 1
世の中には色々様々な人間がいる。
当人がどう思っているか分からない。
ただそこに居るだけで吸い寄せられるように人目を惹く。
そうして刻み込むか。
焼き付けるか。
普通ではない強烈な印象で他者の記憶に残る奴がいる。
例えば脇役なのに、主役より圧倒的な存在感でスクリーンに君臨した山崎努みたいな俳優がいる。
薄ぼんやりとした集合写真の中にだって、ビカッと光り輝く三年三組のオードリーが居たりする。
そんな感じのアレだ。
良い意味でも悪い意味でも集団の中に埋没することがない。
嫌も応も無く目立ってしまうペルソナが、世間様には確かに存在するのだ。
あいつとの付き合いは、偶然でも必然でもない。
何とも妙なめぐり合わせから始まった。。
あいつは一度出会ったならばとても忘れる事の叶わない存在。
悪目立ちの権化のようなお猫様だった。
「先生、うちの子猫がドラエモンみたいになってしまったのです」
沿岸低気圧の気紛れ次第では、午後から東京でも大雪が降ろうかと言う朝の事だった。
つい最近ご近所にお洒落なカフェが開店した。
カフェの名前はロイジーナ。
僕が高校生の頃から足繁く通っている国立のロージナとはなんの関係もない。
どちらもロシア語で祖国とか故郷という意味らしい。
発音的にはロージナよりもロイジーナの方が本来の発音に近いらしい。
そのカフェには素敵な笑顔を振りまいておいでになる看板娘様がいらっしゃる。
その看板娘様が大きなバスケットを抱えて僕の前で泣きべそをかいている。
彼女はつい今し方。
ここ、とも動物病院に飛び込んで来たのだった。
数日前、お父上であろうか。
児玉清ばりのスマートで物静かなマスターと一緒に、栗最中の詰め合わせを持って挨拶に見えた。
それですぐに、泣きべそをかいている女性は誰あろう看板娘様である。
そのことが分かった。
彼女は小柄な愛くるしい娘さんで。
おまけにスタイルもなかなかで。
ともさんともども僕も大喜びで。
お近付きの機会を伺っていたところだったのだ。
「あっ。
おはようございます」
噂の娘さんがいきなり目の前に現れて、僕は我知らず舞い上がってしまった。
かと言うとそんなことはない。
妙齢のご婦人が殆ど初対面の僕の前で泣きべそをかいている。
これは何だか萌えのシチュだった。
可愛い女の子の前にして胸がドキドキ。
それとは一味違った意味で、ちょっと顔を熱くして声まで上ずったことだった。
だがしかし、泣きべその理由を心配する前に萌えを感じたなんて、我ながらキモかった。
僕は心の中で陰腹を切り了見を仕切り直した。
「ドラエモンがどうかしましたか」
「そうじゃないのです。
大変なのです。
ドラエモンみたいになってしまったのです」
形の良い唇を震わせて大きな目に涙が溢れている。
性懲りも無く再び胸がキュンとした。
本当は、ここで颯爽と診療に取りかかれば僕も格好が良かったのだろう。
『可愛い女の子の泣きべそは風情があるのぅ』
そのとき僕は陰腹の痛みもものかは。
彼女のいじらしい泣き顔をば。
数秒の間ぼんやり鑑賞してしまったのだった。
この大失態は後々痛い失点となって効いてくる。
「先生!」
「えっ。
あーっ。
それでは猫を診察台の上に載せて下さい」
彼女の名前は、るいさんと言った。
泣いてる娘さんの名前が“るい”とは、シチュエーション的にちょっと出来すぎのようだけれどもね。
不覚にもその涙に魅せられた時。
もちろん僕は彼女の名前をまだ知らなかった。
るいさんは、診察台の上にバスケットをそっと乗せると蓋を開けた。
するとそこには、まるでやくざ映画にでもでてきそうな人相。
いや、にゃんそうの悪い茶虎の猫がバスケットいっぱいに詰まっていた。
そいつは眼光鋭くこちらをねめつけていた。
不良の人ならそんな無礼な振舞いを、ガンを飛ばすとか。
メンチを切るとか。
恐ろしい言葉で表現するのかも知れなかった。
それが、あいつ、だった。
「この猫がドラエモンですか?」
あいつは、普通の猫の倍はあろうかという大きな顔で僕に蔑みの眼差しを向けた。
僕に一瞥を投げつけると『ニャア』の一言。
これっぽっちの会釈も無しに僕のことを見下して来た。
あいつは額の縦縞のせいで、両目の間にしわが寄っているように見えるのが凄みだった。
どう贔屓目に見てもドラエモンと言うよりは、前科十犯の凶状持ちという面差しだった。
あいつは、指名手配ともなれば瞬時に身バレすること請け合いの、強烈なオーラを放っていた。
「そうではなくて、この子なのです」
涙さんは、やくざ猫の胸元から血塗れの小さな黒猫を引っぱり出した。
黒猫は、弱々しく鳴くと頭を振った。
「あっ、耳がない」
子猫には耳がなかった。
どう対処すべきか手順に迷い、一瞬僕の身体は固まった。
猫は何処か隙間さえあれば、取り敢えずは潜り込んでみようと志す生き物だ。
まして気温の低い季節とあらば、自動車のエンジンルームは格好の寝場所となる。
どうやらドラエモン猫は、お店の駐車場に止めた車のエンジンルームに潜り込んだらしい。
車はロイジーナのパートさん車だと言う。
出勤時の走行で適度に暖まったエンジンルームは“暗いよ狭いよ温いよ”ってことだったろう。
おまけに寒風も凌げるのだ。
身寄りのない子猫的に、すこぶる居心地が良かったであろうことは想像に難くない。
エンジンが完全に冷え切り、件の子猫が腹でも空かして這いだしてきたならば良かった。
純情可憐なるいさんが可愛い泣き顔を僕に晒すことも無かったろう。
いつもだったら夕方まで止め置かれたままの車だった。
その車が急用で使われたことで悲劇は起きた。
パートさんが車に乗り込み、エンジンスターターを始動したときのこと。
なにやらギャッと言う叫びが聞こえる。
あわてて車をおりると、血だらけの子猫が車の下からまろび出てくる。
驚いて物陰に隠れた子猫を抱き上げる。
すると頭が血だらけであるべきところに耳がない。
おそらく子猫はエンジンスターターのベルトに巻き込まれてしまった。
それで耳を失ったのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
