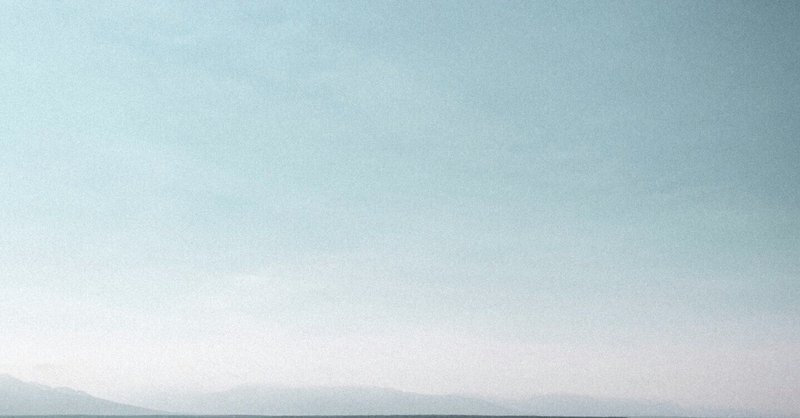
自分からの自由
言語化をするということが、どうやら苦手らしい。するすると言葉が流れ出てくることもあるが、錆びついた歯車のように、脳の回転がうまく噛み合わない時がある。人の前で話す機会が増えたからか、こうした悩みに敏感になっていた。
もう半年以上も文章を書いていない。毎日のように心の言葉を取り出すことをしなかったせいか、どうやって文章を書いていたのかを思い出せないでいる。いまもこうして文章を書き始めたはいいものの、以前までのような快活なリズムを持って書き出すことは難しい。取り留めのない文章だったとしても、練習としてまずは書いてみようと思った次第だ。
ここ半年間は文章も書かずに何をしていたのかというと、仕事ばかりしていた。とても忙しい毎日を送っていた。そのおかげもあって、たくさんの収入を得られるようになった。ただその一方で、今までの僕というアイデンティティは部屋の隅に追いやったままに、余暇を享受するということを一切行わない日々が続いたのだった。
豊かな暮らしを求める以上に、個人の能力主義的な成果を求める日々が続いた。資本主義に則り、個人の生産性ばかり高めてきた。だからこそ、これまで大切にしてきた非効率の中に潜む豊かさは少しずつ削ぎ落とされていく。そうして自分を顧みることなく、あっという間に半年が過ぎたのだった。
4月に差し掛かって、ようやく息継ぎをするかのように水面へ顔をあげてみた。今まで息継ぎもせず、よく泳いで来れたものだと思うが、久しぶりに吸う空気はとても新鮮である。何にも追われない、何もしなくてもいい日々がやってきたのだ。
忙しさに感けていたせいか、立ち止まって考えるというごく当たり前のことを放棄していたようにも思う。忙しさを理由にして、これから先のことについて思考することを後回しにしていたようにも思う。だからこそ今一度立ち止まって、改めてどういった方向に進んでいくのかを検討してみたい。そう思ったので今日は筆を取り始めたのだった。
*
4月から自由な時間を手に入れ、一番に行ったことは本を読むことだった。読書を愛してやまない人間だったが、この半年間はろくに本も読まず、文章も書くことのない日々を送っていた。その反動もあってか、今は過去の自分を取り戻すかのように本を読みあさっている。内田樹の『寝ながら学べる構造主義』、池内紀の『なじみの店』、庄野潤三の『野鴨』。どれも面白い本ばかりであるが、とりわけ熱中して読んだのが福田恆存の著書、『人間の生き方、ものの考え方』であった。
この本は著者が行った国民文化研究会主催の講義の内容と、学生との対話が文字に起こして記されている。いつか古本屋を巡ったときに手にした一冊であったが、所々に赤い鉛筆で線が引かれているのがとても気に入っている。以前にこの本を手に取った方は、きっと細部まで読み込んでいたのだという歴史が見える。黒い鉛筆や赤いペンのときもあるので、おそらく読み進めるうちに環境の異なる場所で読んでいたり、日に分けて少しずつ読み進めていたことがわかる。そして国語の読解問題のように、「しかし」などの逆説には三角の印を付けているのがとても好印象だ。読み継がれて、さまざまな人の手に渡って今僕の手元にあるという巡り合わせに、この一冊の重みを感じるのだった。
特にこの本にある、人生の目的という章に深く膝を打った。人間というものは、居なくたっていいのははっきりとしている。ただ僕たちは生きたいのであると。根本的には存在よりも先に本質がある。たとえば鉛筆であれば鉛筆というものの目的、用途、効用など、そういったものが先にあってその後に鉛筆が存在するのである。ところが人間においては、本質が後で存在の方が先にあるのだ。すなわち人間というものは本来目的がないのだからこそ、なくなったって一向に構わないのである。しかしただ、まず存在した。そして存在し続けようという欲求がある。その前提のもとに、みんなものを考えたり生きていたりするのだと。
なくなったって一向に構わない生命が、存在したのだ。だからこそ、僕たちは生きている目的を求めるのである。そしてその目的、やりたいことについては、この本では『自分からの自由』という定義をして考えているのが面白い。
消極的な自由ではなく、積極的な自由を求めて、人は工夫して『やりたいこと』という壁を乗り越えようと努力するのである。つまり、壁のないことが自由なのではなく、真の自由とは自分という壁を乗り越えられるかどうか、自分という人間を本当に理解し、その目的が、他人やその時代の風潮に流されいるものではないことを掴んでいるかどうかが必要なのであるという。
日々の読書体験は言葉や思考を整理し、いつも新しい気づきを与えてくれる。つまりは成功するにしろ失敗にしろ、やりたいことに挑戦し続ける姿勢こそが充実であり、自分からの自由なのである。
現状の僕は、やりたいことが無数にある状態であるにも関わらず、金銭的な自由や時間的な自由など、消極的な自由を求めていたのかもしれない。立ち止まったからこそ見えた新しい壁がいくつかあるので、今年は自分という壁をよじ登ってみようと思う。
*
仕事に感けているうちに、年も明けて冬も過ぎ去っていた。庭の桜も少しずつ開花し、春らしい陽気が感じられるようになった。夜、窓を開けると澄んだ空気が流れてくる。凛とした冷たい空気でありながら、甘やかで、笑顔が溢れるような空気が肺を満たす感覚は嬉しいものだ。
どこかに懐かしさと寂しさを含みながら、ほのかな期待感が感じられるあの匂いを嗅いだとき、僕はいつも春を思い出すのだった。世の中の春という行事にあまり関心がないので、春になったからといって何も変わらないけれど、その匂いは僕に春という季節を思い出させてくれる。
ちょうど昨年のこの季節に、とあるエッセイを書いていたのだった。思い返すと本当に月日は早いもので、もう1年も半分が終わったことにとても驚いている。昨年書いたエッセイは、無事に昨年の11月下旬に発売となった。手に取ってくれた方がいらっしゃれば、本当にありがたい限りである。
人生で初めて、自分の書いた文章が本になるという経験をした。手元に本が届いた時は、なんとも言えない高揚感に満ちていたことをよく覚えている。普段からよく目にしている、敬愛する作家の方々と同じ並びに僕の名前があるというのは、とても不思議なものだ。
短いエッセーであるので、普段のように冗長な文章を書く訳にはいかない。けれど、短い中でも起承転結を盛り込んだエピソードにしようと思って、当時の僕にとって一番いい文章を書いたようなつもりでいた。本が届いてからも、気恥ずかしさがあって自分の文章はずっと見返せなかった。どんな文章を書いたかすら忘れていたが、いい文章を書いたような記憶はあった。
そうして先日意を決して僕の文章を読んでみると、確かにこんな文章だったなと思いつつ、もっといい文章を書けたのではないかという落胆と、この作品はこれ以上手の加えようのないものだなと、完成された塑像のような確かさを感じたのであった。僕は作品を書いた側の人間であるので、他の人はどんな文章を書いたのだろうと気になって読んでみる。なるほど、そういった角度から描くのかという発見や、短い中でも作者らしい表現が詰まった文章に感銘を受けた。そして純粋な読者としての楽しさもあって、今まで以上に読書をするという体験が面白く感じたのだった。
鬱というのは、非常に厄介なものである。僕自身が長らく躁鬱に悩まされて生きてきた人間であり、深い悲しみや孤独と一緒に生きてきた人間であるからこそ、逃れることのできない苦しさを知っている。でも、だからと言って悲劇のヒロインを演じようとは全く思わない。苦しい過去や経験も含めて、それらを背負ってただ生きていくのだ。そして、その生き様が、さまざまな著者の視点からエッセーとしてこの本には記されてあるのだ。そうした他者の生き方や考え方に触れるとき、少しでも気持ちが楽になるといいなと思う。
短い文章だからこそ、少し憂鬱な時にでも手に取って貰えると嬉しい。多くの人に届いて欲しい一冊です。もしよかったら、ぜひお手に取ってみてください。
ここまで読んでくださってありがとうございます。 楽しんでいただけたなら、とても嬉しいです。
