
伊邪那岐命と伊邪那美命
国土の修理固成
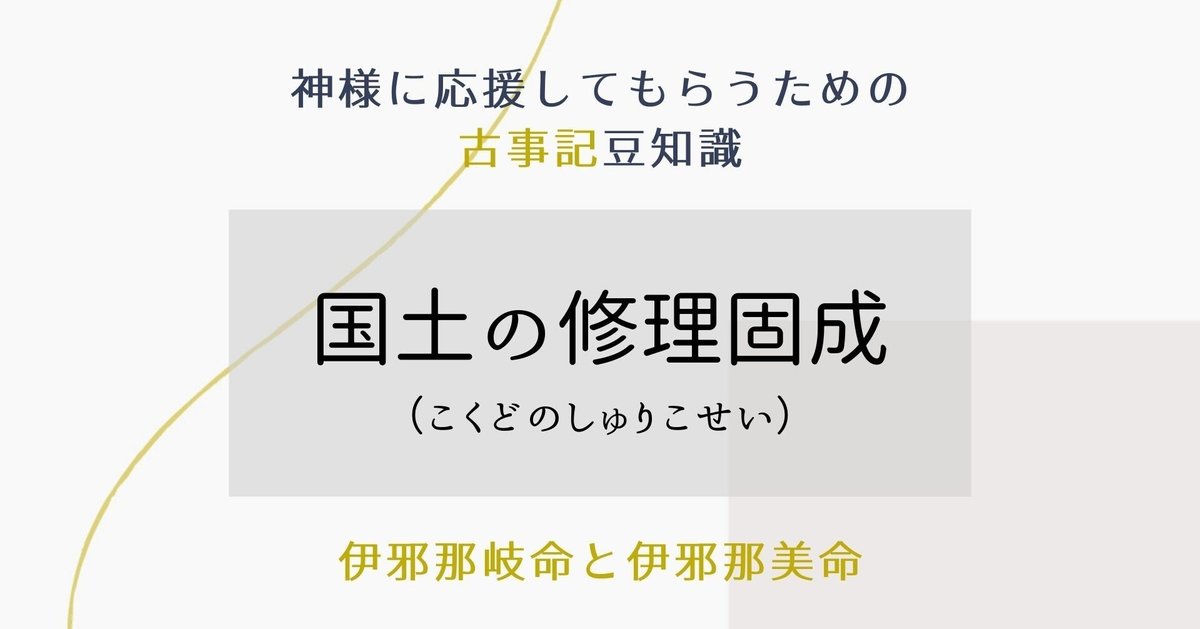
さて古事記では、いよいよここからイザナギ・イザナミの神話が始まります。ここで、伊邪那岐命(イザナギノミコト)と伊邪那美命(イザナミノミコト)の名前が変わったことにお気づきでしょうか。
伊邪那岐神・伊邪那美神
伊邪那岐命・伊邪那美命
神→命 となりました。
古事記では
「神」は宗教的
「命」は人格的
意義で使われています。

まずは国土の修理固成(しゅりこせい)、つまり「国生み」です。五柱の別天つ神のお言葉で、伊邪那岐命と伊邪那美命の二柱の神に、「この混沌とした国を秩序ある国へ修め理り固め成せ」と詔(みことのり)をされます。そして玉で飾った尊い矛(ほこ)を授けました。
ここで重要なのは「天つ神諸(もろもろ)の 命(みこと)もちて」の部分です。つまり「天つ神のお言葉で」国生みを行うのです。みことはいのち。天つ神の御心と一つになることです。
そして、イザナギ・イザナミの二柱は、天空に浮かぶ「天の浮橋(あめのうきはし)」に立って、天つ神から賜った「天の沼矛(あめのぬまぼこ)」を下ろしてぐるぐるとかきまわします。そして海水をコロコロとかき鳴らして、矛を引き上げたとき、矛先からしたたり落ちた海水が固まって島ができます。
これが日本最初の国土、オノゴロ島です。
オノゴロ島は、イザナギ・イザナミが生んだのではなく、「自ずから凝り固まった島」と理解されています。これが実在の島かどうかは議論が分かれるところですが、候補地としては、淡路島の南の沼島、紀淡海峡の友ヶ島、淡路市の絵島などがあります。私としては淡路島の沼島なのではないかと思っています。
二神の結婚

イザナギ・イザナミの二柱は、オノゴロ島に降り立ち「天之御柱(あめのみはしら)」と「八尋殿(やひろどの)」を建てます。天御柱は天地をつなぐ高い御柱、神霊の依り代です。八尋殿は広い神殿です。
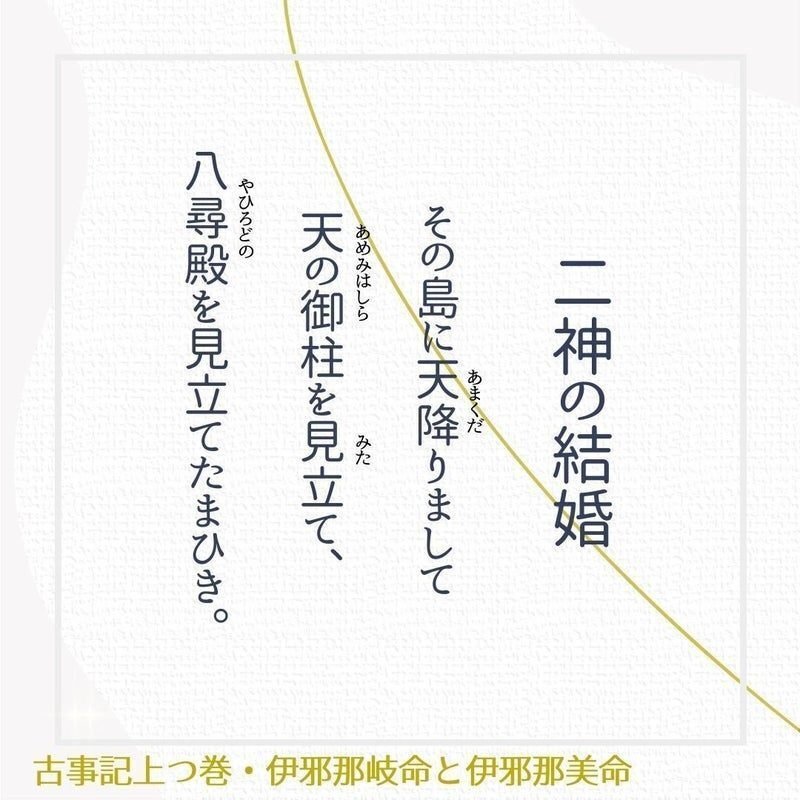
イザナギはイザナミに「あなたの身体はどんな風ですか」と尋ねると、「私の身体はどんなに成長しても合わないところが1つあります」と答えられます。そこでイザナギは「私の身体は成長しても体の外に余っているところが1つあります。あなたの合わないところを、私の余っているところに合わせて国土を生もうと思うがどうだろうか」と言われ、イザナミは同意します。
ここで身体のこととして書かれているのは比喩で、本当の意味は宇宙における陰陽のことだと、小野善一郎先生は「古事記のこころ」の中で指摘されています。
そして、天御柱の周りを回ってお見合いをします。契の儀式として、イザナギは左から、イザナミは右から天御柱をまわり、出会ったところでイザナミが先に声をかけます。女神が先にいうのはよくないと気づいたものの、そのまま夫婦の交わりをしてしまいます。
最初に産まれた水蛭子(ヒルコ)は形を成さない神だったので、葦の船に入れて海に流しました。次に生まれた御子も泡のような淡島でしたので、御子の数には入れられませんでした。
★水蛭子(ヒルコ)
古事記では、この神様を「良い子ではなかった」とのみ書かれているので、具体的にどのようだったかはわからない。そして、「この子は葦船に入れて、流しやってしまった」ということです。
水蛭子は、蛭のように手足の萎えた子、手足のない子、骨のない子などとする説もあります。
その後、このヒルコが流れ着いたという伝説は日本各地に残っていて、ヒルコを祭神とする神社は多く、和田神社(神戸市)、西宮神社(兵庫県西宮市)などで祀られています。
★淡島
水蛭子と同じく、子の数に入れないと注記されています。また、「仁徳記」の国見歌にもこの島の名が見えます。島々を生む際の胎盤のことであるとか、水面上に散在する岩の群れではないかと論じる説もあります。
大八島国の生成

国生みがうまくいかなかったイザナギ・イザナミの二柱の神は相談し、「今、私たちが生んだ御子はよくない。いちど天つ神のところに行って申し上げなければならない」と言って、一緒に高天原の神のご意見を求めました。

そこで天つ神は、占いをして「それは女神の方が先に言ったことがよくなかった。もう一度改めてやり直しなさい」と言われました。
ということで、二柱の神は帰って、天の御柱を以前のように周り、今度はイザナギが先に声をかけ、次にイザナミが声をかけます。すると立派な土地を次々とお生みになります。
ここで注目したいのは、神であるイザナギ・イザナミが天つ神に相談に行き、その天つ神は自分で判断せず「占い」をして教えたということです。つまり天つ神の御心に立ち返って国生みを行うことが、大変重要だということなのです。
イザナギ・イザナミはこのように言い終わって、結婚してお生みになったのは、まず大八島(おおやしま)国と6つの島々。大八島とは日本のことです。

●淡道(あはぢ)の穂の狭別島(さわけのしま)
●伊予(いよ)の二名島(ふたなのしま)
*体が1つで顔は4つ。顔ごとに名前があります
伊予国(いよのくに):愛比売(エヒメ)
讃岐国(さぬきのくに):飯依比古(イイヨリヒコ)
粟国(あわのくに):大宜都比売(オオゲツヒメ)
土佐国(とさのくに):建依別(タケヨリワケ)
●隠伎(おき)の三子島(みつごのしま):天之忍許呂別(アメノオシコロワケ)
●筑紫島(つくしのしま)
*体が1つで顔は4つ。顔ごとに名前があります
筑紫国(つくしのくに):白日別(シラヒワケ)
豊国(とよのくに):豊日別(トヨヒワケ)
肥国(ひのくに):建日向日豊久士比泥別(タケヒムカヒトヨクジヒネワケ)
熊曾国(くまそのくに):建日別(タケヒワケ)
●伊岐島(いきのしま):天比登都柱(アメヒトツバシラ)
●津島(つしま):天之狭手依比売(アメノサデヨリヒメ)
●佐渡島(さどのしま)
●大倭豊秋津島(おおやまととよあきづしま):天御虚空豊秋津根別アマツミソラトヨアキヅネワケ)
つまり
・淡路島
・四国(愛媛・香川・徳島・高知)
・九州(筑前、筑後・豊前、豊後・肥前、肥後・宮崎、鹿児島)
・壱岐
・対馬
・佐渡島
・本州
ということになります。

さらに「おのごろ島」に帰る途中で6つの島を生みます。
●吉備児島(きびのこじま):建日方別(タケヒカタワケ)
●小豆島(あづきじま):大野手比売(オオノデヒメ)
●大島(おおしま):大多麻流別(オオタマルワケ)
●女島(ひめじま):天一根(アメヒトツネ)
●知訶島(ちかのしま):天之忍男(アメノオシオ)
●両児島(ふたごのしま):天両屋(アメフタヤ)
つまり
・岡山県の児島半島
・瀬戸内海の小豆島
・山口県の屋代島
・大分県の姫島
・長崎県の五島列島
・長崎県の男女列島
ということになります。
それぞれの国土には神名がつけられています。つまり国土には神々と同じ
命が流れているということです。
神々の生成

国を生み終わったイザナギ・イザナミは、今度は神々を生みます。

■まず家屋にかかわる神様と海、川に関わる神様、合わせて十神をお生みになります。
●大事忍男神(オホコトオシヲノカミ)
以下の神々を生む大事業の偉大さの象徴としての神
●石土毘古神(イハツチビコノカミ)
土石の神格化の神
●石巣比売神(イハスヒメノカミ)
石や砂の神
●大戸日別神(オホトヒワケノカミ)
住居の出入り口の神
●天之吹男神(アメノフキヲノカミ)
天井を葺く神
●大屋毘古神(オオヤビコノカミ)
家屋の神
●風木津別之忍男神(カザモツワケノオシヲノカミ)
風の神
●大綿津見神(オホワタツミノカミ)
海の神
●水戸の神・速秋津日子神(ハヤアキヅヒコノカミ)
水の出入り口の神
●速秋津比売神(ハヤアキヅヒメノカミ)
水の出入り口の女神
■さらに速秋津日子神と速秋津比売神が、水に関係ある神様八神をお生みになりました。
●沫那芸神(アワナギノカミ)
●沫那美神(アワナミノカミ)
●頬那芸神(ツラナギノカミ)
●頬那美神(ツラナミノカミ)
水面がなぐことと泡立つことを神格化した神
●天之水分神(アメノミクマリノカミ)
●国之水分神(クニノミクマリノカミ)
水の分配を表す神
●天之久比奢母智神(アメノクヒザモノチノカミ)
●国之久比奢母智神(クニノクヒザモチノカミ)
水汲みに関わる神
■続いて、風、木、山、野の神様をお生みになりました。
●風の神・支那都比古神(シナツヒコノカミ)
●木の神・久久能智神(ククノチノカミ)
●山の神・大山津見神(オホヤマツミノカミ)
●野の神・鹿屋野比売神/野椎神(カヤノヒメノカミ/ノヅチノカミ)

■大山津見神と野椎神が、山野にかかわる神様八神をお生みになりました。●天之狭土神(アメノサヅチノカミ)
●国之狭土神(クニノサヅチノカミ)
山地の狭くなったところをつかさどる神
●天之狭霧神(アメノサギリノカミ)
●国之狭霧神(クニノサギリノカミ)
霧をつかさどる神
●天之闇戸神(アメノクラドノカミ)
●国之闇戸神(クニノクラドノカミ)
渓谷をつかさどる神
●大戸或子神(オホトマトヒコノカミ)
●大戸或女神(オホトマトヒメノカミ)
暗くなって惑うことをあらわす神
■続いて船、食物、火の神が生まれます。
●鳥之石楠船神/天鳥船(トリノイハクスブネノカミ/アメノトリフネ)
酉のように天空や海上を通う船
●大冝都比売神(オホゲツヒメノカミ)
食物をつかさどる女神
●火之夜芸速男神/火之炫毘古神/火之迦具土神
(ヒノヤギハヤヲノカミ/ヒノカガビコノカミ/ヒノカグツチノカミ)
物を焼く火力の神
■この火の神を生んだ時に、陰部を焼かれてイザナミは病の床につきます。そして、嘔吐物や大便、小便からも神様が生まれます。船の神から合わせて八神です。
嘔吐物から生まれた神様
●金山毘古神(カナヤマビコノカミ)
●金山毘売神(カナヤマビメノカミ)
鉱山の神
大便から生まれた神様
●波迩夜須毘古神(ハニヤスビコノカミ)
●波迩夜須毘売神(ハニヤスビメノカミ)
粘土の神
小便から生まれた神様
●弥都波能売神(ミツハノメノカミ)
農業用の水の神
●和久産巣日神(ワクムスヒノカミ)
若々しい生産の神
和久産巣日神の子
●豊宇気毘売神(トヨウケビメノカミ)
食物をつかさどる女神
つまり、イザナギ・イザナミは島を14、神を35神お生みになりました。この章では天と地の間に存在するすべてのものに神がいる、ということを示しています。
特に火の神は、イザナミが自分の命と引き換えに生んだということからで
穢れのない状態、浄化の神として神聖視されます。
火神被殺

火神被殺(ひのかみひさつ)のお話です。
イザナギ・イザナミの神生みの際に、最後に生んだ火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)に焼かれ、イザナミはなくなってしまいます。イザナギは「愛しい妻をただひとりの子に引き換えるとは悔しい」といって、イザナミの枕もとに腹ばいになり、足元に腹ばいになって泣き悲しみます。そのときのイザナギの涙から神が生まれます。
●泣澤女神(ナキサワメノカミ)
大和の天香具山(あめのかぐやま)のふもとの丘の上、木の下におられる神です。今でも奈良県橿原市にある「畝尾都多本(うねおつたもと)神社」にご鎮座されています。
亡くなったイザナミは、出雲の国(島根県東部)と伯耆(ほうき)の国(鳥取県西部)の境にある比婆(ひば)の山に葬られます。
ここでイザナギは腰に帯びていた十拳剣(とつかつるぎ)で、カグツチの首を切ってしまいます。するとその剣から八神が誕生します。
長い剣の先についた血が清らかな岩石の群れに飛び散って生まれた神で、岩石を裂くほどの威力があります。
●石析神(イハサクノカミ)
●根析神(ネサクノカミ)
岩石の霊威を表す神
●石箇之男神(イハツツノヲノカミ)
剣のつばについた血が飛び散って生まれた神で、火の根源である太陽をたたえています。
●甕速日神(ミカハヤヒノカミ)
●樋速日神(ヒハヤヒノカミ)
勇猛な雷(いかずち)の男神で、剣の威力をたたえています。
※のちに国譲りの際に重要な働きをします。
●建御雷之男神/建布都神/豊布都神(タケミカヅチノヲノカミ/タケフツノカミ/トヨフツノカミ)
剣の柄(つか)に集まった血が手の指の間から漏れ流れて生まれた神で、渓谷の水をつかさどっています。
●闇淤加美神(クラオカミノカミ)
●闇御津羽神(クラミツハノカミ)
以上の八神は御剣によって生まれた神々で、刀剣製作の順番と解釈されます。
さらに、殺されたカグツチの亡骸からも八神が誕生します。
カグツチの頭から生まれた神
●正鹿山津見神(マサカヤマツミノカミ)
胸から生まれた神
●淤縢山津見神(オドヤマツミノカミ)
腹から生まれた神
●奧山津見神(オクヤマツミノカミ)
陰部(みほと)から生まれた神
●闇山津見神(クラヤマツミノカミ)
左手から生まれた神
●志藝山津見神(シギヤマツミノカミ)
右手から生まれた神
●羽山津見神(ハヤマツミノカミ)
左足から生まれた神
●原山津見神(ハラヤマツミノカミ)
右足から生まれた神
●戸山津見神(トヤマツミノカミ)
このとき、イザナギがカグツチを切った剣の名前は天之尾羽張(あめのおはばり)、またの名を伊都之尾羽張(いつのおはばり)といいます。

この章で、イザナミをなくした悲しみにより、イザナギの中に我が子を憎む気持ちが生まれます。これが異心(ことごころ)です。つまり、天つ神から離れた”自我の心”です。ということは、イザナギが切ったのは、目の前にいるカグツチではなく、自分の心に映っているカグツチであると解釈されているのが小野善一郎先生です。
目の前に起きている出来事は、自分の心が映し出しているもの。だからそれを祓う。祓うことでイザナギの心は天つ神と一体となり、神を生むことができたのです。
ここ疑問が起こります。では切られたカグツチはどうなったのか?この世に火はありますから、火の神がいなくなっというたことはないと思われます。そしてイザナミはそもそも亡くなっているのですから、イザナミと一緒に黄泉の国(死後の世界)に行ったということなのでしょうか?
このあたりのことは古事記には書かれていませんので、とりあえず物語は先に進めたいと思います。
黄泉の国

○黄泉の国(よみのくに/よもつくに)
イザナミが亡くなってしまい悲しみに暮れるイザナギは、イザナミにもう一度会いたいと、黄泉の国へ行きました。黄泉の国は死者の住む国です。
イザナミはすでに黄泉の国の食べ物を食べた後なので、もとの国には戻れない身になっていました。しかし、せっかく来てくれたからと、黄泉の神に相談することにします。
イザナミは「絶対に入るな」と言うのですが、イザナギは待ちきれなくなって約束を破ってしまいます。
そこでイザナギが見たのは、腐敗して蛆がたかった恐ろしいイザナミです。八種類の雷神(いかづちがみ)まで出現していました。
イザナギは急いで黄泉の国から逃げますが、イザナミは「よくも恥をかかせてくれたな」と黄泉の国の醜い女に追いかけさせます。
イザナギが櫛を投げると野ぶどうが別の櫛を投げるとたけのこが生えてきて、醜女たちが食べている間に逃げ延びます。
さらに雷神が兵士を連れて追ってきますが黄泉の国との境界線「黄泉比良平坂(よもつひらさか)」に生っていた桃を投げつけると、兵士たちは去っていきます。
そこでイザナギはその桃の実に
●意冨加牟豆美命(オホカムヅミノミコト)
という神名を与えます。
最後にイザナミが追ってきたので、黄泉と現世の境目を大きな岩でふさぎます。イザナミは捨て台詞で「だったらあなたの国の人を1000人殺してやる」
といいます。イザナギは「じゃあ私は1500人生ませるよ」と答えます。
ここでこの二柱が人の生き死に関わる神様であるということを暗に示しています。
ということで
イザナミには
●黄泉津大神(ヨモツオホカミ)
●道敷大神(チシキノオホカミ)
という名前もあります。
また、黄泉の坂をふさいだ岩は
●道反之大神(チガエシノオホカミ)
●黄泉戸大神(ヨミドノオホカミ)
といいます。
イザナミのお墓は2か所あり
1つは三重県熊野市の花の窟神社
もう1つは出雲の佐太神社です。
見てはダメと言われて見てしまうのは、世界共通、人間のサガなのでしょうか。さすがの神様も死んでしまったものは、もう元には戻せないのですね。
禊祓と神々の化生

〇禊祓と神々の化生(みそぎはらえとかみがみのかせい)
イザナギは、黄泉の国での穢れ(けがれ)を日向の阿波岐原(あわぎはら)で、水で清め祓います。
ちなみに「禊(みそぎ)」とは身体を洗いすすぐことで、身についた凶事や罪穢れを除去して清めること。
「祓(はらえ)」とは心身についた罪を禊などの儀礼や唱え言葉によって、取り払い清浄にすること。禊祓の際に神々が生まれます。
まず身に着けた物を脱ぐときに生まれた神々
●衝立船戸神
(ツキタツフナドノカミ)
●道之長乳歯神
(ミチノナガチハノカミ)
●時量師神
(トキハカシノカミ)
●和豆良比能宇斯能
(ワヅラヒノウシノカミ)
●道俣神
(チマタノカミ)
●飽咋之宇斯能神
(アキグヒノウシノカミ)
●奥疎神
(オキザカルノカミ)
●奥津那芸佐毘古神
(オキツナギサビコノカミ)
●奥津甲斐弁羅神
(オキツカヒベラノカミ)
●辺疎神
(ヘザカルノカミ)
●辺津那藝佐毘古神
(ヘツナギサビコノカミ)
●辺津甲斐弁羅神
(ヘツカヒベラノカミ)
中つ瀬で御身をすすぐときに生まれた神々
●八十禍津日神
(ヤソマガツヒノカミ)
●大禍津日神
(オホマガツヒノカミ)
●神直毘神
(カムナホビノカミ)
●大直毘神
(オホナホビノカミ)
●伊豆能売神
(イヅノメノカミ)
●底津綿津見神
(ソコツワタツミノカミ)
●底箇之男命
(ソコツツノヲノカミ)
●中津綿津見神
(ナカツワタツミノカミ)
●中箇之男命
(ナカツツノヲノカミ)
●上津綿津見神
(ウハツワタツミノカミ)
●上箇之男命
(ウハツツノヲノカミ)
そして最後に
左の目から
●天照大御神
(アマテラスオホミカミ)
右の目から
●月読命
(ツクヨミノミコト)
鼻から
●建速須佐之男命
(タケハヤスサノヲノミコト)
の三貴子がお生まれになります。
この中で
底津綿津見神
中津綿津見神
上津綿津見神
の綿津見神三神は、海人族の阿雲連(アヅミノムラジ)の祖先神であり、
底箇之男命
中箇之男命
上箇之男命
の住吉三神は、住吉大社のご祭神です。

三貴子の分治
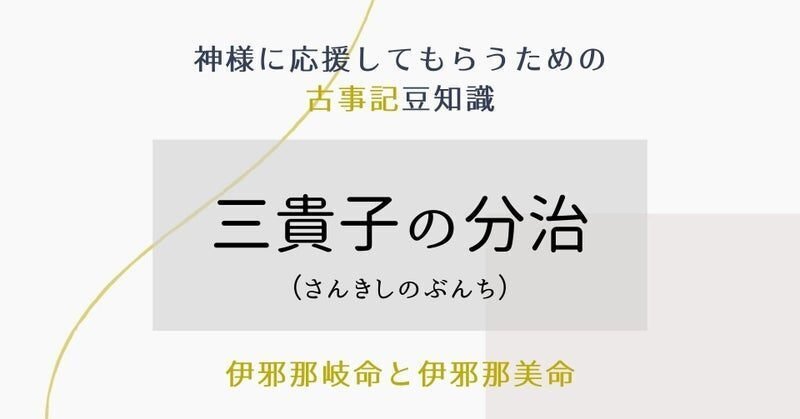
〇三貴子の分治(さんきしのぶんち)
禊祓(みそぎはらえ)で
天照大御神
(アマテラスオホミカミ)
月読命
(ツクヨミノミコト)
建速須佐之男命
(タケハヤスサノヲノミコト)
の三貴子をお生みになり、イザナギは大変喜びました。
そして、アマテラスに自分の首飾りをお授けになり
「あなたは高天原を治めなさい」
とおっしゃいます。
この首飾りの玉は
御倉板拳之神
(ミクラタナノカミ)
といいます。
イザナギの依り代となります。
つづいてツキヨミに
「あなたは夜の世界を治めなさい」
スサノオには
「あなたは海原を治めなさい」
とおっしゃいました。
祓うことで尊い神様が生まれたということは、禊祓がいかに大切かを語っているのです。
須佐之男命の涕泣

〇須佐之男命の涕泣(すさのおのみことのていきゅう)
三貴子はそれぞれ委任された国を治めていましたが、スサノオだけは委任された国(海原)を治めず、長いあごひげが胸元に届くようになるまで激しく泣いていました。
そのありさまは、青々とした山が枯れ木の山のようになるまで泣き枯らし、川や海はすっかり泣き乾されてしまいました。
そのためにあらゆる禍が一斉に起こりました。
そこでイザナギはスサノオに尋ねます
「どうして泣いているのか」と。
スサノオは答えます。
「私は母がいる黄泉の国に行きたい」と。
そこでイザナギは大変怒って、「だったらこの国に住んではならない」と言われ、ただちにスサノオを追放されました。
その後、イザナギは近江の多賀大社に御鎮座されます。
というお話ですがスサノオまさかのマザコン!
天つ神の命令に背くとはなかなかのやんちゃっぷりを見せてくれます。
そしてこの後このスサノオの成長物語が描かれることになります。
イザナギ・イザナミの物語はここでおしまいとなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
