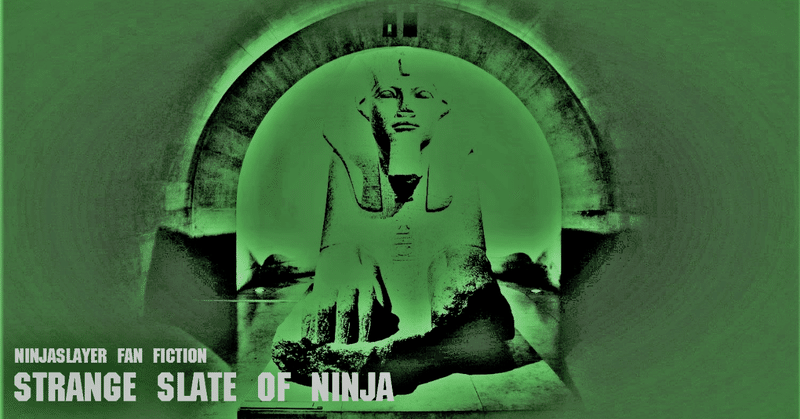
【ストレンジ・スレイト・オブ・ニンジャ】
少し壊れた、奇妙な黒曜石の石板。その表面には「現実には存在しなかったが、あったかもしれない可能性としての過去」がライブカメラめいて映し出されている。貴方は石板の前に立つ。今、そこに映っている光景は……。
【ゴビ砂漠】
砂漠の夜は凍てつくような寒さだ。「ドーモ。サッカーです」「ドーモ。ベンガルタイガーです」両者は挨拶を終えると、即座にカラテを構えた。冷たい風が二人の間を吹き抜けていく。篝火の炎がバチバチと音をたて、砂漠の丘に二人の姿を影絵めいて照らし出していた。「あああ……ベンガルタイガー=サン……!」トヤは瞳を閉じ、ペンダントをぎゅっと握りしめた。祈るように強く握りしめたそれは、母の形見だ。少女は震えていた。(神さま……どうか……どうかベンガルタイガー=サンに勝利を……そしてあぁ……どうか……あの略奪者から村をお救いください……)空気は張り詰めている。ベンガルタイガー、そしてサッカー。二人は対峙したままぴくりとも動かない。いや、動けないのだ。二人の実力はまさに伯仲している。即ち、少しでも隙を見せた者……それが敗者である! 「神さま……母さん……!」トヤは緊張からか、無意識のうちにペンダントを天にかざすように持ち上げていた。その掲げられたペンダントが篝火を反射して煌めいたのは、ほんの、一瞬の出来事だった。「……」サッカーの眉根がわずかに動く。刹那! 「イヤーッ!」ベンガルタイガーは瞬時に距離を詰め、その獰猛なる拳はサッカーの胸を貫いていた! 「バ、バカな……ワシは……」ベンガルタイガーは吠えた。「フンっ! 一瞬。一瞬だけでも俺には充分よ!」「くっ……ふはは! 見事……なり……!」その胸の拳が引き抜かれた直後。「サヨナラ!」サッカーは爆発四散して果てた。「ふん」ベンガルタイガーは己の拳を開き、閉じ、そして握りしめた。ドラゴン・ニンジャとの決闘を思い出す。「結果は違えど、あの時と同じ……ほんの僅差、か」「ベンガルタイガー=サン!」駆け寄るトヤ、そして村人たち。少女の瞳には涙が溢れていた。ベンガルタイガーは、それを無視して身支度を整えていく。「俺の用件はすんだ。ここに、もう用はない」「そんな! せめて……せめて年越しの祭りが終わるまでは、一緒に……」ベンガルタイガーは少女の涙を見た。「むぅ……」と呻く。そして突然、何かを思い出したように「ははっ!」と吠えるように笑い出した。「そうか。ちょうど日本では……新年を迎えた頃ではないかっ!」何かを誤魔化すように、東の方角を見つめる。
【ネオサイタマ、裏カジノ「テッカバ」】
キモノの肩をはだけたヤクザ女が、威勢よく声をあげている。「さぁ、チョウかハンか、チョウかハンか! ハッタ、ハッタ!」「「チョウ!」」「「ハン!」」男たちのギラギラとした眼差しがそれを見つめている。チョウハン賭博。日本では古事記の昔より続くとされる、伝統的なギャンブルである。それはカップの中で振られた二つのサイコロの目が、奇数か偶数かで勝敗を決める。極めて単純なものだ。「はい、チョウハン、コマが揃いました……これは良き新年を迎えるための最後の大勝負。皆さま、ヨゴザンスネ?」ごくり、と唾を飲み込む音。「勝負!」伏せられていたカップが持ち上げられる。サイコロの目は……一と六! 「……イチロクのハン!」溜息と歓声が同時に漏れた。これが、今年最後の勝敗だ。女の眼前にどっかと座った男は、しかし、静かに言い放った。「イカサマだな」「えっ……」賭場は水を打ったように静まり返る。その男は異様な風体だった。エド・スタイルのチョンマゲ。着流し。その顎から下はフル・サイバネティクス。女がドスを利かせて男に凄む。「テメッコラ……何を根拠に……」チンッ。音ともに何かが閃いた。遅れて、女の髪が風圧でふわっとなびく。「「あっ!?」」賭場の客たちが騒ぎ出した。女は我に返る。その手元のサイコロが切断され、中の鉛仕掛けが露出している。「あ……」女は男の何かに気づき、ガタガタと震えだしていた。「くだらんな」男は──シガーカッターは修羅場と化した賭場の喧噪を後にして、外へ。吹き荒ぶ夜風が冷たかった。「……あぁ、そうか。そうだったな」シガーカッターはそう呟くと、何かを思い出したように夜空を見上げた。その顔を、閃光のような瞬きが照らし出す。
【ネオサイタマ、某所】
キタノ・スクエアビル地下街4階9号。椅子に深くもたれたハーフガイジンが、見上げるようにスケベピンナップを眺めている。テーブルに投げ出された足。その足先は落ち着きなく揺れ続けている。傍らではオレンジ髪の女が──いや、自我を持ったオイランドロイド、ウキヨが、所在なげにうろうろとしていた。「アー……」ハーフガイジン──タキは呻き、頭を掻きむしる。そして放るようにスケベピンナップをテーブルの上に置いた。それと同時。「わたし、ちょっと買い出しに行ってきますね!」「おいコトブキ、お前……」「すぐ戻ります!」「おい……」頭を掻く。「どいつもこいつも……ハッ」と笑いとも溜息ともつかぬ声。タキは呟いていた。そこにはいない、誰かに向けて。「ッタクよぉ。もうすぐ年越しだってのに。心配ばかりかけさせやがってよぉ……」地上。「エジャナイザ! エジャナイザ! エジャナイザ!」「エジャナイザ! エジャナイザ! エジャナイザ!」「エジャナイザ! エジャナイザ! エジャナイザ!」エジャナイザ踊りの集団が、通りを練り歩いている。今はまだ年越し前。エジャナイザは本来であれば新年を迎えてから踊る風習だ。新年を待ちきれない若者たちが、ドープ・エジャナイザをキメているのだ。コトブキは人ごみに押し出されるように、人気の少ない裏通りに立っていた。コトブキには何か予感めいたものがあった。「ニンジャスレイヤー=サン……」果たして、その予感は的中する。通りの向こうから、肩を押え、足を引きずるようにしてこちらに向かってくる若者の姿が見えた。「ニンジャスレイヤー=サン!」駆け寄る。「大丈夫ですか」「……何も問題はない」「一緒に、ピザタキに戻りましょうよ」その二人の顔を、何かがぱっと明るく照らし出した。「うわぁ、素敵です」それは、夜空に輝く「アケマシテオメデト」の文字。新年の開始を告げるアケマシテオメデト花火だ。「ニンジャスレイヤー=サン」コトブキはニンジャスレイヤーの目を見つめ、微笑んだ。「アケマシテオメデト、です」「……」「コトヨロですね!」「……あぁ」「わたし、肩貸しますよ!」「……」ニンジャスレイヤー、マスラダ・カイは怪訝そうにその表情を見つめた。いつもとなにか、少しだけ様子が違う。照れ隠しのような、はにかんだ笑顔。「さ、早く戻りましょう。ピザ・オーゾニ、温かいですよ!」コトブキにとって、それは本当の意味での初めて迎えた新年だった。もう、一人ではない。夜空を色とりどりの花火が染め上げていく。「スシはないのか」そう言いかけて、マスラダはその言葉を飲み込んだ。二人は、肩を寄せ合うようにしてピザタキへと帰っていく。
【ストレンジ・スレイト・オブ・ニンジャ】終わり
これは何?
ニンジャソン2019冬に応募した、ニンジャスレイヤー二次創作です!
本家【スレイト・オブ・ニンジャ】はこちら。
きっと励みになります。
