
「明治43年京都」ある商家の若妻の日記
明治43年の京都
読もうと思ってずっと取っておいた本をやっと読む機会がありました。タイトルは「明治43年京都」(著者中野卓)といいます。ある商家の若妻の日記という副題がついています。昭和56年に出版された本で、著者はこの万亀子という20歳の若い嫁のペン書きの日記を活字に起こしたようです。
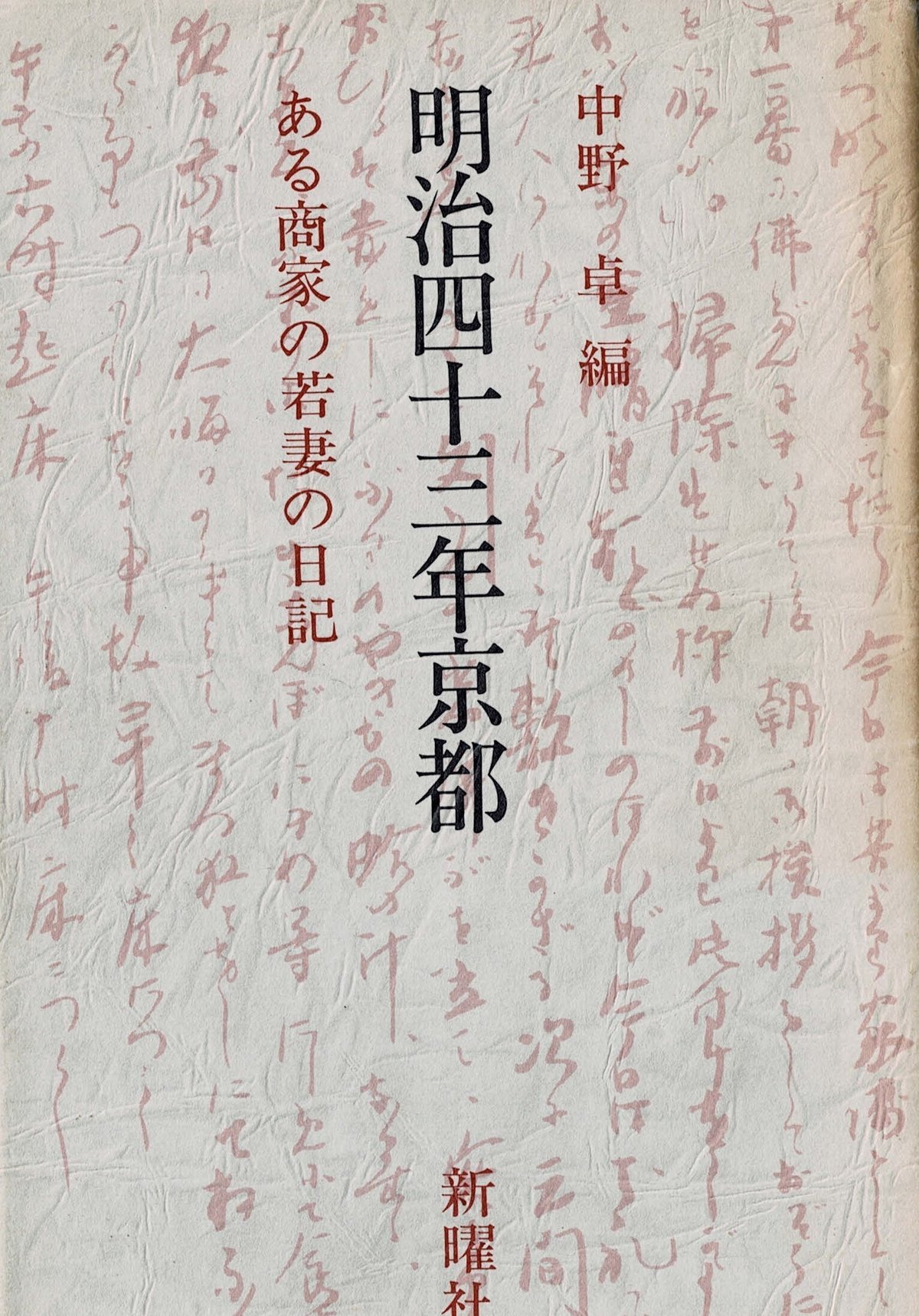
万亀子の嫁ぎ先は薬品商で、同業の実家を継いでいる兄の友人と結婚しています。その気楽さもあるのか、嫁いでで3年目、そろそろ遠慮もなくなって比較的好きなことをしている時期です。時には主人の留守に大番頭に罵られたりと悔しい思いもしますが、西洋料理を習ったり、南座にいったりと楽しい生活のようです。
嫁ぎ先の奉公人は手代が4人、丁稚が6人、上女中1人・下女中1人、一番番頭・二番番頭となる通い別家の番頭がそれぞれ1人ずついます。これだけの人数がいるので家事はしなくてよく、むしろ当時の薬品業界の先端をつとめて、文化人でもあった夫の交際を手助けするのが主な仕事であったようです。「〇〇様がお越しなので早く帰らなければ」などの記述がああります。
筆者が京都で聞き取りをした範囲でも、この構成は大正生まれの女性の商とほぼ同じで、時代が下がって昭和30年代の呉服製造業者でも、丁稚・手代は住み込み、番頭になってやっと別家を許される点は共通しています。「別家」と呼ぶところも同じです。
ある日の日記から
万亀子は女学校にはやってもらえなかったようですが、日記の内容は嫁というより若い娘のようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三月十五日 火曜 晴
今朝、二条から電話がかゝつた。帯のやすぃのがあるので、掛見様が買われたから、一度見にこよとて、午後早くいった。大変お安い事で、四十円ほどもするのが二十八円です。どうか一本お世話下さいと頼んだが、もう一本もないので、また出ましたらとのこと。ほんとにおしい事です。今ばんは、ひょっとすると松井様がいらっしゃるとの事で、すぐ帰った。
今日は何か会があるので来られなんだ。今日森口さん(通い別家)の本復祝いで牛肉が来たので、ビーフ会、夕食に。此頃はいろいろな先生が見える。大島様とかおっしゃる方がいらっして、ちっともかへられないから御飯を出した。夕方から雨降りになった。
三月二十二日 火曜 雨天
今日はまた雨降り。今日お天気ならばお祝もって着物もって〔二条へ〕とおもふて居りましたが、雨ふりなのでよそうと思ふて居りましたら、掛見〔おうた〕様から電話がかとから見にこよとの事で、早速〔二条へ〕ゆくことになった。それにしてもまだ下女が〔「宿下り」から〕帰らない、が、皆さまにお頼みして、いった。〔掛見家に来ていた帯は〕ほんとにどれもくよろしいの計り、一寸拝借して帰った。此日、ついでに〔同じ二条の〕鳥居さま方へもいった。
〔鳥井やす子様は〕今月の二十七日とかに多分ゆかれるそうな。今年はおよめ様でどこもかしこもおめでたい事。
八時頃おびをかゝへて帰った。夏帯一本、シュチン(繻珍)ー本、シュス(繻子)二本とにきまった。向ひの〔東側〕ふさ子様も一本買はれた。ほんとに余りおやすいので、誰にしても、ほしいこと。其中で、それはくよいのがあって、ナデシコのも様。まあ上品でね。どんな人でも、アツと云ふことよ。
三月二十三日 水曜 雨
まだ降りやまない。また昨夜の帯をひろげた。いくら見てもよいものはよろしい。今朝、早速【選びとらなかった分を二条の掛見様へ使いの者をさしむけて】もたせてやった。現金と共に。〔西陣の機屋から直接の品物だから〕ほんとにおやすくて、呉服屋なんぞ、そばへよれないわ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このように日記は文語体ではなく、まるで女学生の手紙のように明るく奔放な記述です。 繻珍や 繻子は昼夜帯の片側に使う目的で購入したのでしょうか。
当時の呉服の値段
更に面白いのは、末尾にあった「金銭出納帳」欄を利用した覚書きで、明治末期の反物の値段が知れます。
「金銭出納帳」欄を利用した覚書き
白羽二重地、一反、羽織地 一三円
白羽二重地、一反、着物地 一一円五〇銭
男物帯地 一〇円五○銭
男物じゅばん袖 三円
羽織裹地 七円五○銭
じゅばんの袖、エーネル
帯の心
羽二重下着地 一円
袷地、一反 七円
袷羽織、一反 一二円
お召し、一反
秩ぶ〔=秩父絹〕裏地、二反 八円五〇銭
明治の30年の物価が現在の3800倍ということらしいので、計算してみました。
白羽二重地、一反、羽織地 一三円 49400円
白羽二重地、一反、着物地 一一円五〇銭 43700円
男物帯地 一〇円五○銭 39900円
男物じゅばん袖 三円 11400円
羽織裹地 七円五○銭 28500円
じゅばんの袖、エーネル
帯の心
羽二重下着地 一円 3800円
袷地、一反 七円 26600円
袷羽織、一反 一二円 45600円
お召し、一反 32300円
秩ぶ〔=秩父絹〕裏地、二反 八円五〇銭 32300円
先に日記にあった帯の値段は152000円のものが106400円ということです。安くなっているとはいえ、10万以上の買い物を相談なしに決められるのはかなり裕福な家庭であると思われます。秩父絹というのは、桐生足利で織られていた絹地のことで、大原の聞き取り調査でも銘仙のことを「秩父絣」と呼んでいました。京都の人にとっては北関東の織物をひとまとめにして「秩父絹」と呼んでいたのではないかと思われます。
明治43年の社会情勢
明治43年とはどんな時代だったのでしょうか?当時の情勢などを「年表 近代日本の身装文化」(高橋晴子著2007年)より拾ってみました。帯について下記のような雑誌からの引用があります。
明治43年11月
沢山の帯。今の人は帯の重いのを嫌う。昔でも300円の帯なぞというと重すぎて困ると云ったものだが、今の人は百円の帯ですら、重くって締められないという人が多く7、80円位のところが大いに売れる。ただし今の人は.本の帯でどこへでも出るというのでなしに、行く場所の変わる度、時の変わる度に帯をとりかえるので、贅沢さは昔に数倍する。
村井弦斎「找国の婦人は斯くまで贅沢になれり」婦人世界11月
・・・・・・・・・・・・・・・・
また、家庭における仕事の役割分担についても参考となる記述があります。
明治44年10月
「衣服を新しく拵えたり、平常置を縫いかえたりする時には、よく仕立屋へ頼むものですが、私の家では必ず家で裁縫します。細物や縮緬物などは女中にさせることはできませんが、ちょっとした平常着や布団などは、皆女中にさせます。これとても、初めからそううまくは行きませんが、段々に教えてやるのです。そして、仕立屋へやって一枚30銭か50銭とられるものならば、その手額位を女中にやって、それを貯金させます。……そればかりでなく、仕立屋ではとかく手を省きたがったり、三丈の絹物をやると縫込をしないで切り捨てて自分の物にしたりします。おくみなどは、東京では鍵形につけますから、今度縫いなおして裏返しすることができません。自分の家ですれば、まるおくみにしておきますから、裏返しするにも便利です。
佐治実然「秋の夜長と女中の戯縫]婦人世界10月
女中という用語は書籍よりそのまま引用しました。教えるためには主婦は自ら和裁ができなければならないので、万亀子もそうした事を経験していると思われます。加えて女中奉公は家庭運営の技術を習うという意味があったのです。万亀子が座布団作りなどを行っていると思われる記録があります。
この年三月に東京日比谷に帝国劇場が開場し、女優の出演が人気を博しました。同年帝国劇場で文芸協会による「人形の家」公演があり、松井須磨子がノラを演じました。従来の伝統芸能に替わる娯楽も出現し始めていたようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
購入してから読み終えるまでに20年もかかった本ですが、その間に聞き取り調査を何度も行ったので、この内容が裏付けになっているのが大変ありがたかったです。著者ももう故人でしょうが、地味な文字起こしの記録がこうして後世の役に立つのですね。感謝の気持ちで読ませていただきました。
加えて、高橋晴子先生の詳細な記録、「年表 近代日本の身装文化」も大変参考にさせていただきました。
参考文献:「明治43年京都」 新曜社 万昭和56年 中野卓
「年表 近代日本の身装文化」 三元社 高橋晴子 2007年
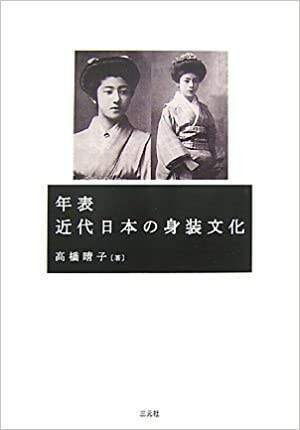
似内惠子(一般社団法人昭和きもの愛好会理事)
一般社団法人昭和きもの愛好会HP
一般社団法人昭和きもの愛好会 youyube チャンネル
昭和きもの愛好会FB
