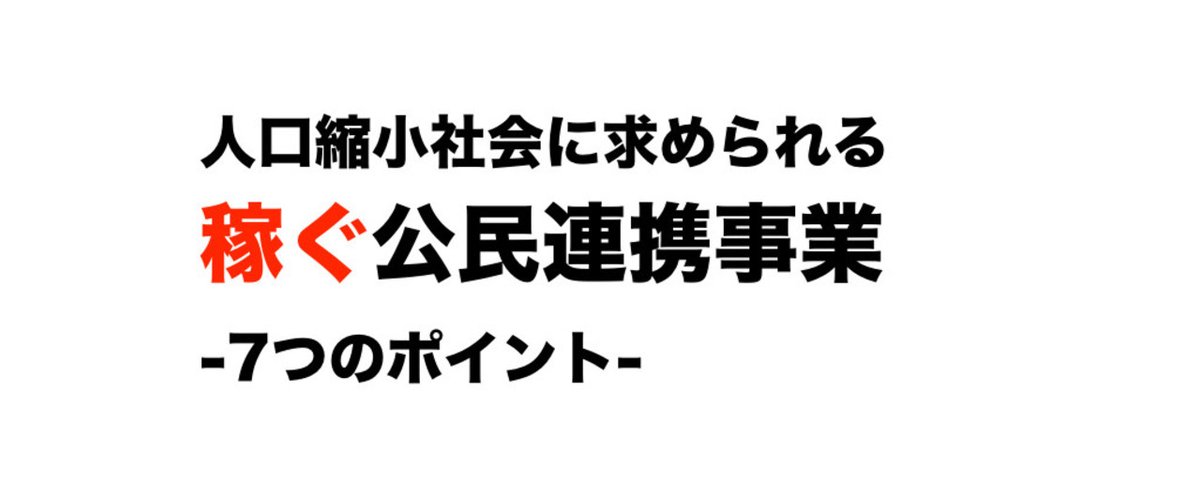
人口縮小社会に求められる「稼ぐ・公民連携事業」-7つのポイント-
本コラムでは、人口縮小、産業衰退にともなう地方自治体における財源の枯渇と、公共インフラ全般の更新問題について取り上げる。現在主流となっている「縮小する財政にコスト削減によって最適化して」という方法論だけでなく、とくに近年見られる「公共インフラの一部を民間で利活用することによって稼ぎを生み出し、その収入で公共サービスを支える」という方法論について検討する。
【目次】全約11,000文字・写真・スライド画像付き
1. 財源の枯渇と公共施設更新のダブルパンチ
2. 減少する収入に合わせるか、稼ぐ策を考えるか。
3. 稼ぐ公共を支える公民連携事業事例
4. ポイント1 : 単独機能だけの公共施設から、複合型公共施設へ
5. ポイント2 : 公共施設だけではなく、公民連携施設へ
6. ポイント3 : 高値の公共発注ではなく、民間開発による開発費の適正化
7. ポイント4 : 先に客付けを行う逆算方式での開発規模の決定
8. ポイント5 : 公民連携施設内だけでなく、外部空間を利用して価値にレバレッジをかけるエリアマネジメント
9. ポイント6 : 地価の上昇による波及効果
10. ポイント7 : 良い点だけでなく、注意点も含めて公民連携事業の正しいスケールアウトが必要
11. おわりに
従来の公共観念からすれば公共資産の一部で稼ぐということはタブー視されてきているが、一方で収入がこれ以上見込めないからすべて削減していくという方法しか考えられない公共のあり方では、財源の枯渇によって「提供すべきサービスも提供できない」という論理しか展開できずにいる。
今後は、従来の公共インフラに対する考え方を再検討し、新たに稼ぐ機能を公共インフラの一部に付随させることによって公共サービスを充実させることが一つの方法論である。実際に、道路の利活用から、学校施設の活用など様々な公共資産が新たな方法で活用され、その収入の一部が公共に還元されている。
1. 財源の枯渇と公共施設更新のダブルパンチ
地方普通会計における道府県の歳入のピークは、1998年の48.9兆円であった(総務省自治財政局財務調査課「地方財政統計年報」)。その後、交付税などで政府によって地方自治体の経営を下支えしているものの、全体として財源が減少していくトレンドは変わっていない。それに対して社会保障費は増加しており、財政は極めて切迫しているのは長らく言われている問題である。
ここから先は
¥ 1,500
サポートいただければ、さらに地域での取り組みを加速させ、各地の情報をアップできるようになります! よろしくお願いいたします。
