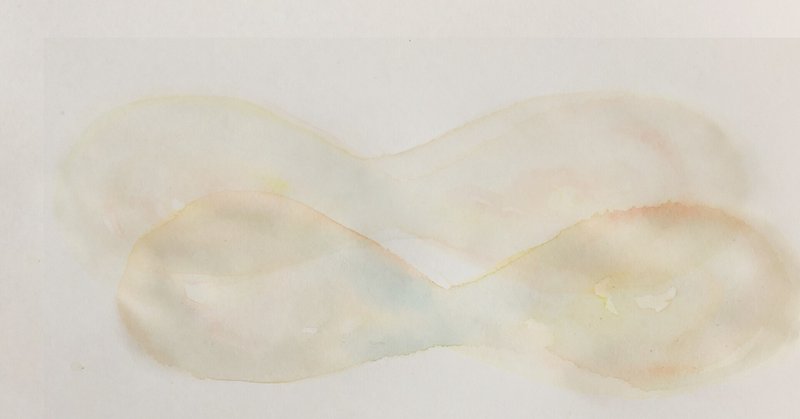
世界を掃除しよう。
大室悦賀(おおむろのぶよし)先生の8時間講義に参加。
大室先生とは「共通の友人」が山のように存在する距離感で、いずれ自然にお会いする機会に恵まれると思っていたのだけど、案外これまで機会がなく、この度、東大の光吉俊二先生がお繋ぎくださったご縁で、ようやくお会いできた。
大室先生のご専門はいわゆるソーシャル・イノベーション領域だけれども、講義の中で「もう、ソーシャル・イノベーションという言葉を使わないかもしれない」と言われていたように、常に境界を移動・拡張しながら探求を続けてきた方だ。
少し振り返りシェアしたい。
大室先生は、「経営にビジョンやミッションは必要ない。むしろ、イノベーションの邪魔になる」という。
僕もその通りだと思う。ビジョンであれミッションであれ、夢であれ目標であれ、それを持つことで、その中に自分を閉じ込めてしまうことになりやすい。夢を持つことで、夢の中に自分を閉じ込めてしまい、その夢に関係のなさそうなものに目をつむり、耳を塞ぐことがおきやすくなる。つまり、認知バイアスを助長する危険性があるということ。
人間を「資源」と捉えるHR(ヒューマン・リソース)的な発想も、危険だ。人間を交換可能な資源と捉える機械論的な経営では、イノベーションは起きてこない。社会課題を対症療法的にではなく根本的に対処していくには、思考習慣を含めたシステムチェンジが必要だ。
哲学とビジネスが関わり始めている。CPO(Chief Philosophy Officer)を置く企業も増えている。「哲学シンキング」問いを重ねていくこと。
そのような中で、縄文的アニミズム、仏教、そして西洋文化の受容という、3要素を持つ日本の役割は大きい。和辻哲郎の『風土』でも描かれているように、アニミズムを違和感なく受け入れられるのは東洋の人間の特質だ。
二元論を越えようとする哲学や人類学の数々の人々。『なぜ世界は存在しないのか』のマルクス・ガブリエルも、西田幾多郎・京都学派の影響を受けている。アクターネットワーク理論。
あいまいさ、「間」「あわい」への注目。
(参考)木岡伸夫先生と大室先生のコラボ講義『あいだの哲学道場』
アートの分野でも。エリー・デューリングのプロトタイプ論。作品を、プロセスとオブジェクトの間にある余剰を含めた連続する完成品と見る。
分けて関係性を問う、ということ。それでいいのか?
相関主義・関係主義グレハム・ハーマンの「二重解体」。
創発とは部分の総和にとどまらない。入不二基義先生に注目。苗字が象徴的。
マルチスピーシーズ人類学が面白い。
More than human
多自然主義and単文化主義。
量子力学の「エンタングルメント(もつれ)」が他分野に影響しつつある。
ネガティブ・ケイパビリティ、もやもやをそのままにする力。
利他的な行為は認知バイアスを軽減する。
『なぜ稲盛和夫の経営哲学は人を動かすのか』(岩崎一郎著)
アダムスミスは『道徳感情論』も書いていた。「経済は道徳や共感がないとちゃんと機能しませんよ」という主張は見過ごされがち。
「ecotone」に注目。汽水域。間。淡い。
イノベーション論はつまらないものも多いけれど、『人類とイノベーション』(マッド・リドリー著)は面白い。
云々
◆
大室先生のお話を聞きながら、二元論を乗り越えていくアプローチと、産業僧について、考えていた。
このところ、僕は「対話」に注目している。
対話とは、カウンセリングやコーチングといった、既存のフレームの中でなされるやりとりではないし、そうあってはいけない。ただの、おしゃべり。それが、どんなきっかけであれ、「ご縁ですね」から始まり、「さようなら」で終わる一期一会がいい。
「何を話すか」は決まっていない。あらかじめ話すことが決まっているのは、対話ではない。
クリストファー・アレグザンダーは「何も起こらないのではないかという恐怖を克服しなければ、自分のイメージを捨て去ることはできない」と言った。
意図は要らない。成功も失敗もない。まっさらな、どこまでも広がるキャンバスの上に、対話そのものが自動的に展開していくのに、ただ任せるのがいいと思う。
客観的な観測者と対象者も存在しない。お互いは干渉し合うし、対話とは干渉そのものだ。観測しようとすると結果が変わるところは、量子的でもあるし、内部観測的でもある。
"Spiritual but not religious"な感覚の人が増えています。Post-religion時代、人と社会と宗教のこれからを一緒に考えてみませんか? 活動へのご賛同、応援、ご参加いただけると、とても嬉しいです!
