
アフリカのきれいな街プラットフォームとは? ~日本のごみ処理技術をアフリカへ~
人が暮らせばごみが出る。急激に人口が増えるアフリカ、特に人口集中が進む都市部では、ごみの量に対して収集・処理能力の整備が追いついていない。
2017年からJICA海外協力隊としてスーダンの首都ハルツームに赴任して、廃棄物収集の改善に取り組んだ隊員は、その現状を目の当たりにした。当時、収集車が各地域の国収コンテナを巡る仕組みはあった。しかし、収集車や人員の不足で収集作業は不定期。コンテナからごみがあふれ、それを家畜 やのら犬があさっていた。ごみの中にあるビニール袋を食べる家畜もいて、海の生物が海に流出したプラスチックごみを誤飲する問題と同様のことが陸でも起きている。ごみが自然発火し、煙を上げている場所もあり、害虫やコレラなどの伝染病、浸出水による地下水の汚染も発生。環境悪化や健康被害だけでなく、気候変動への影響も懸念されていた。
こうした状況はスーダンだけではない。昨今、どの国でも環境への意識が高まってはいるが、インフラ整備などの経済活動が優先されがちで、環境対策、特に廃棄物分野の政策はなかなか進まない。
そこで設立されたのが「アフリカのきれいな街プラットフォーム(ACCP)」。廃棄物管理の好事例や知見を、参加する国や都市で共有している。年1回の全体会合では、各国の取り組みや資金調達の方法などを発表し、それを各国が持ち帰り、自国の状況に応じて実践している。

JICAの活動としては、地域の人々の声を聞き、そのニーズに応えた活動を実施することが求められている。JICAがハルシームで取り組んだのは、市内の他地区で行われていた定時定点収集(決まった場所・時間にごみを廃棄・収集すること)を、新たに3つの地域に導入することだ。JICAの海外協力隊員の強みは、地域の人々の声や要望を直接聞き、対応できること。町内会の方々と会合を開き、定時定点収集の大切さを説明し、何度も話し合ううちに理解者が増え、ごみをポイ捨てしないという意識が広がり、地域全体がきれいになっていく様子を目の当たりにしたという。
さらに学校では環境に関する紙芝居やペットボトルのリサイクル工作、環境絵日記づくりなどを行った。スーダンの子どもたちの絵は、ACCPが主催する日本での環境絵日記展にも出展された。
日本もかつて、高度成長期には急増する廃棄物への対応が追いつかず、ごみ戦争」や公害問題に代表されるような深刻な社会問題となった経験を有する。その解決のために、法制度・基準の整備、収集・運搬・最終処分に至る行政サービスとしての廃棄物管理体制の改善、ごみ減量やリサイクル等に政府、自治体、住民や民間企業が協力しながら取り組んできた経験は、アフリカ各国が地域の衛生・住環境改善を目指す上でも有用である。
JICAでは、横浜市の協力のもとでアフリカ諸国の行政官や実務者を対象にした研修を年2 回 (英語圏、仏語圏対象を各1回) 実施しており、10 数カ国からの参加者が一堂に会し、約1カ月にわたって廃棄物管理に関する行政システム (法体系,組織・財務体制、各種基準・計画等)、要素技術 (収集運搬、中間処理、最終処分)、住民や企業、学校教育を含む地域コミュニティとの連携等、日本の技術や実践の現場を総合的に学んでいる 。
一般に、アフリカ諸国では財政的な制約から廃棄物管 理に対する政府・自治体の政策優先度がさほど高くなく、人員や機材等の不足が多くみられる。また市民の環境意 識が低く、分別、リサイクルの導入はおろか、ポイ捨てや不法投棄を抑制することすら困難な状況にある都市も少なくない。そのため、日本において、住民自らが地域の環境衛生維持に自発的に取り組んでいる様子は驚きや称賛をもって受け入れられている。さらに、高い職業意識や技術専門性をもって日々の業務に取り組む自治体・ 公社等の職員の方々の姿勢は、個人レベルでのロールモデルにもなっている。
さらに、日本の行政・地域が一体となった廃棄物管理体制に触れることで、自国が目指すべき姿としての具体的なイメージをもつだけでなく、日本の現在の状況は、自治体による長年にわたる努力が結実したものであると知り、意欲を新たにする研修員も多い。実際に、これまでの研修参加者からは、「自分の国の現状は、横浜市が1954年に経験してきた状況と同じ。アフリカと同様に多くの問題を抱え、克服してきた経験を学べるのは、非常に有用」、「3R の日本での実践は、自分の人生および 職歴で初めて目にしたものだ。3R の意識啓発に民間セクターや一般市民が関与していることは称賛に値する」などの感想が寄せられている。研修終盤には、各参加者が研修で得た知見を踏まえて帰国後の活動に関するアクションプランを作成・発表し、横浜市も交えて相互に講評を行っており、研修の成果が所属先での具体的な改善活動に活用されることを企図している。研修員同士が、それぞれの国や都市の課題や取組事例を共有し合い、また中央政府、地方自治体、公社等、異なる視点からの意見を傾聴することで、自国の現状を客観的に評価し、現実的に実施可能な改善策の着想を得るなど、改善の方向性が明確になり、アクションプランの実効性が高まる効果も確認されている。立場や国 境を越えて同じ課題に取り組む同志としての存在は大いに刺激となり、長期的なモチベーションの維持につながることも期待される。
日本での研修やアフリカでの会合、スタディ・ツアー 等で得た学びを実際の廃棄物管理の改善につなげるために、ACCP では各国/都市の廃棄物担当者の自立的な取 り組みをサポートするためのツール類の開発を進めている。
2019 年には JICA が中心となり、「アフリカ廃棄物管理基礎理解パンフレット」、「アフリカ廃棄物管理環境教育ガイドブック」 および「アフリカ廃棄物管理データブック 2019」 を、日本語、英語、フランス語で作成した。
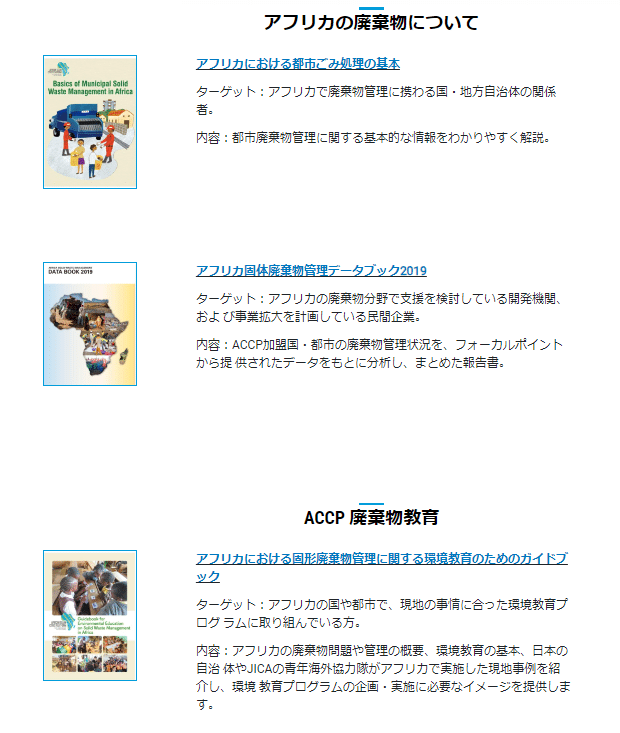
私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。
