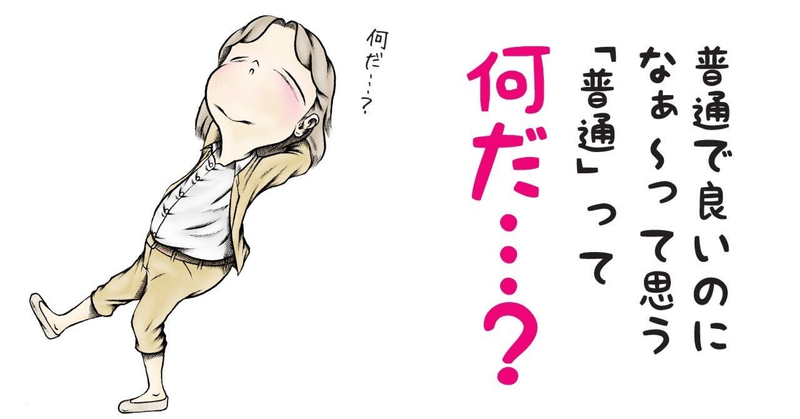
フツウってなんだ?
横山佳という作家の書いた児童文学「二メートル」を読んだ。
高校一年生のハルは、離れたところにある高校に電車で通学している。同じ中学からこの高校に通うのは、もう一人のアイツ=淀川清だけ。通学途中に、余計なことを話しかけられて迷惑だと思うハル。ハルと清の間には、二メートルの距離がある。大家族の中で暮らすハルと、家族に問題がある清。会話をかさねるごとにお互いの理解を深めていく二人・・・。
印象的だったのは、あとがきに著者が記した次のくだりだ。
「わたしのフツウとあなたのフツウ。彼のフツウと彼女のフツウ。となりの席にいるこの人のフツウと、むこうで立ち話をしているあの人のフツウ。フツウはフツウに通じるはずだけど、自分のフツウがフツウにつうじないことがある。」
人と話をしたり、テレビを見たりしていると、「そんなの常識だよ。」とか「フツウは~」という言葉が使われるのを耳にする。しかしながら、「常識」や「フツウ」は個人個人でも差があり、場所や文化、立場によっても変わってくるものだ。
以前、カンボジアの救急病院のICUにて、足を失ったばかりの地雷被害者にインタビューした際、「問題ない。フツウのことだ。」と言われた。この言葉にたいへんなショックを受けた記憶が鮮明に残っていて、頭から離れない。カンボジアでは、家族親戚に一人は被害者がいるのが「フツウ」のことだからだ。しかしながら、日本人の私にとっては「フツウ」ではない。むしろ、そんな「フツウ」はあってはならない。
かつて、かのアルバート・アインシュタインは「常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションのことだ」と言った。ここで言う常識とは、その社会での決まりの最高公約数のようなもの、つまり、みんながこんな感じでいてくれれば秩序が守られるだろうと思われるもの。アインシュタインは科学者として、貴重な発想や感動というのは、常識を超えたところにある、と言いたかったのだと思う。もちろん、秩序は必要なので、まわりを汚したり、嫌な雰囲気・気持ちにさせることは良くない。「常識」を下回ると、自分にとっても他人にとっても迷惑なことだ。アインシュタインのレベルの「常識」を論じる前に、社会秩序を守るための「常識」「フツウ」を下回っている人のなんと多いことか。
「二メートル」の主人公ハルは、アイツとの会話を通して、自分が「フツウ」と思いこんでいた「フツウ」と、アイツの「フツウ」の距離を縮めていく・・・自分のフツウがフツウに通じない苦手な誰かに心を開けば、相手のフツウもいつか自分のフツウになり、世界のフツウになるはず。それがなかなかできないのが人間の面白いところ。
私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。
