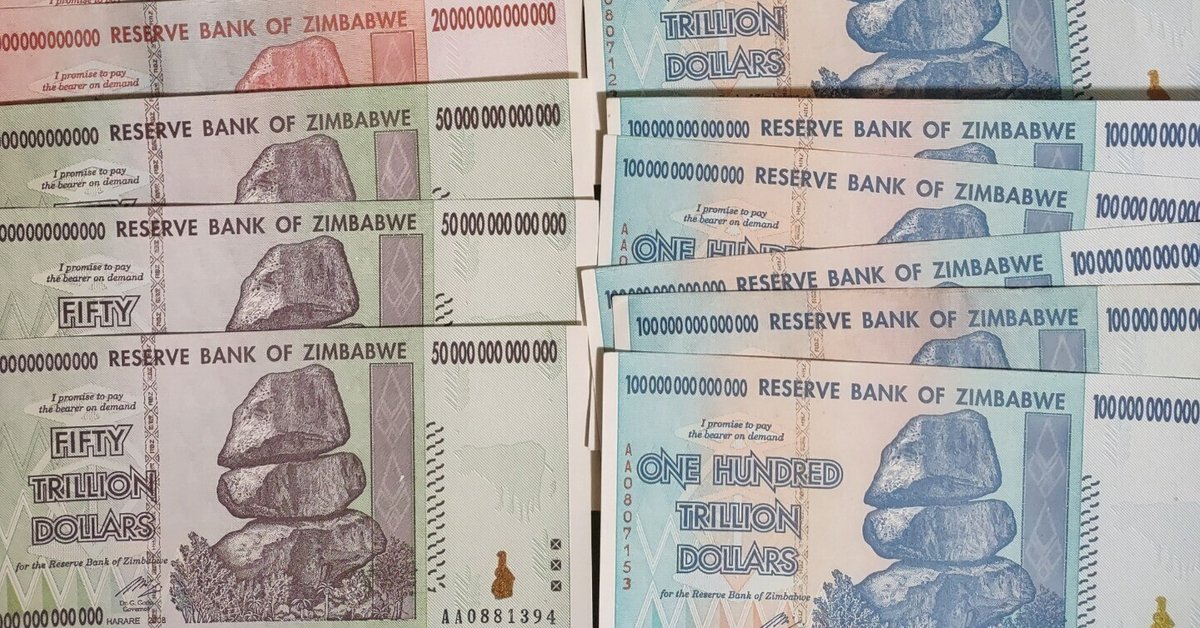
教育ローン返済免除の日本での報道が酷過ぎるので、ニートが解説してやるよ
ミシガン州立大学に博士論文を無事提出して15年ぶりに帰国しました、畠山です。Ph.D. in Education Policyって、日本語だと学術博士(教育政策)でいいんですか?
そんな質問の前に、お前何で帰ってきたんだ?というツッコミもあるかと思いますが、まあ端的に言えば仕事が見つからなかった&土壇場でビザの関係で内定が消えたという事で、どうもニートです。就活もろくすっぽせず毎日隣町のBMDジムに行ってパワーリフティングの練習をしている元気なニートです。
そんなニートが偉そうに言うのも何ですが、最近気になったニュースといえば、なかやまきんに君の日本マスターズの6位入賞です。種目こそ違えど、筋肉という大きな括りではパワーリフティングと遠くないですし、私もマスターズで全日本の表彰台に登りたいと思っているので、気になったニュースはやはりバイデン政権の教育ローン一部返還免除です。
このニュースが気になっている理由は二つあり、一つは政策そのものの芸術度の高さと課題。もう一つは、かなり芸術度の高い政策なのに、日本での報道のされ方がその芸術性を全く伝えられていない&ニュースの読者も我田引水なコメントを連発、という上等な料理にはちみつをぶちまけるがごとき思想を見せつけてくる点です。
ニートとはいえ新型コロナ禍で2年間ほぼ全く勉強していなかったネパールの子供達の支援で忙しいのですが(よかったら活動紹介記事を見ていってください,、もしご支援頂けたらなお有難いです)、見るに堪えない議論が展開されているので、ちょっと解説してみようと思います。
米国の教育ローン問題の3層構造を理解せずに、問題を語るな報道するな
日本の報道が酷いと書きましたが、実は米国の報道もかなり酷いものになっています。それは、教育ローン問題が3層構造をしているにも拘らず、これを理解していないが故に、記者の興味関心のある層にだけ焦点を当てた報道が為されてしまっているからです。パイの実の64層に比べれば3層なんて大した事ないので、簡単に解説しようと思います。
教育ローンの1層目ー営利大学問題
日本ではあまり耳慣れないかもしれませんが、米国の私立大学は非営利と営利に分ける事が出来ます。このため、日本の様に公立対私立の構図で大学を理解するのではなく、州立vs非営利私立vs営利私立の構図で大学を理解していく必要があります。
そしてこの営利大学が非常にヤバい存在で、教育経済学の大家であるハーバード大のデミング先生も論文を書いているほどなので、興味と時間がある人はぜひ目を通してみて下さい(論文)。
論文読むのめんどくさいよーという人のためにデータを出すと(データ元の記事)、営利大学に通う学生はアメリカ全体の学生の1割にも満たないものの、教育ローン破産者の3割は営利大学に通っているという有様です。
何でこんな事になるのかというと、前述の記事によると、営利大学で学生一人当たりに使われている教育予算は、非営利私立や州立大学と比べると1/3-1/4程度に留まっていて、教育の質が低いからです(あと、アカウンタビリティが利いていないとか、なんやかんや)。教育の質が低いと何が起こるかというと・・・退学です。
アメリカの大学の6年以内卒業率は7割未満と低いのですが、実にエグイのが、ハーバードを始めとするアイビーリーグやスタンフォード大などのその他名門校の6年以内卒業率は9割後半と、なんなら東大なんかよりも高いのに対して(確かに学部時代のマージャン仲間で留年しなかったの私だけだったし、退学した奴も・・・)、大学の資金繰りが悪くなる(orランクが下がる)ほど卒業率が下がっていくという点です。そして、全米教育統計センターによると、営利大学の6年以内卒業率は3割を切っています。まあ、ビシエドの打率ぐらいと考えればそんなに悪く・・・ないわけがなく、過半数は数百万の教育ローンを背負ったのに大学の学位が得られず、高卒と大卒の給与差額が得られないわけですから、そりゃ教育ローン破産の主犯となるわけです。
なぜそんなヤバい営利大学が拡大してしまったのかというと、民間企業が強いEdtechの発展と教育の民営化の進展がほぼ同時期に起こってしまい、爆発的な勢いを得てしまったからです。営利大学のピークはオバマ政権前半で、K-12教育でもチャーターやバウチャーといった民営化政策やサイバーチャーターのようなEdtechを推し進めた彼らしい話ではあります。しかし、K-12でも政権末期に反省文を書いたように、オバマ元大統領は政権後半では営利大学の規制を進めていきます。間違いを認めて道を正せるって大事ですね。
しかし、次の大統領であるトランプ前大統領は、K-12教育でもChoiceを掲げて民営化を推進したように、営利大学問題の手綱を緩めてしまいます。このため、今日でも教育ローン破産者の3割は営利大学進学者となってしまっているのですorz
教育ローンの2層目ー中退・短大問題
前述の通り、資金繰りが良くない/ランクの低い大学ほど、学生達が卒業できていないわけですが、営利大学と同程度に学生達が余り卒業できていない高等教育機関があります。それが、Community Collegeです。
日本の短大とアメリカのコミュカレは、UNESCOのISCEDという国際教育段階分類では同じものとして扱われますが、その機能は大きく異なっています。アメリカのコミュカレには、4年制大学編入へのステップアップ、不況で職を失った社会人が地域で求められている知識・スキルの学び直しをする場という特徴も有しています。
しかし、勿論日本人留学生を少なからず集めているような所はそうでもないのですが、コミュカレの資金繰りは一般的に芳しくなく、やはり教育の質は劣悪であると言わざるを得ません。ジル・バイデン大統領夫人はE.D.L.D.という、私が取得したPh.D.よりも実務寄りの博士号を取得して、長らくコミュニティカレッジで教鞭を執っていた(確か現在でも執っている)方で、コミュカレ問題に非常に熱心なので、論文とか読んで問題を追うのはだるいな―という人は、ジル・バイデン博士の動向を追ってみると、この問題の全容が見えたりもします。
話がそれましたが、前述の全米教育統計センターのデータを見ると、コミュカレの卒業率も、営利の4年制大学の卒業率とほぼ同じ3割ちょっとと、調子のよい時のビシエド選手ぐらいになっています。じゃあ(以下略)
とは言え、短大を中退するために(?)借りた教育ローンの額なんてたかが知れているから問題ではない!と思うのが一般的な考えだと思います。私もデータを見るまでそうだと思っていました。しかし、こちらも教育経済学の大家であるハーバード大のダイナスキ―先生の分析によると、教育ローンを借りた額と破産率の間には負の相関が、大事な事なのでもう一度言いますが負の相関があり、借りた額が5000ドル未満という層に至っては、約1/3が破産しています。
なぜコミュカレに少額のローンを借りてきて退学して破産するのか、私も詳しい訳ではないですが、コミュカレの学生の1/4は扶養している子供がいて(データ)、子育て・バイト・学業の3つを上手く回せるわけもなく潰れて破産している、といった事も起こっている様です。Twitterで、米国のコミュカレを再チャレンジの機会ともてはやす日本人の方々も見かけましたが、それを機会と呼ぶにはあまりにも頼りない蜘蛛の糸だと私は思います。
教育ローンの3層目ー大学院(グループ①儲かる大学院出身者、グループ②公的セクターで働く院卒)
教育ローン破産の原因は、主に営利大学・中退者・短大というのは1・2層目で理解してもらえたと思いますが、教育ローンの残高自体が急上昇しているという問題・・・うーん問題なのかな、返せている限りは幾ら借りようと問題ではない気もするのですが、そういう問題も存在しています。教育ローンの破産者が増えているのと、教育ローン貸出総額・一人当たり借入額が上昇しているのは、別の問題だと捉えるべきです、ここテストに出ますよ。
教育ローンの貸出総額は、この20年程で約10倍に膨れ上がっています。これには原因が主に二つあります。一つ目は授業料の高騰です。全米教育統計センターのデータを見ると、州立大学の平均授業料も過去10年で8500ドルから9400ドルと10%以上増加しています。ちょっと現在は円安が驀進しているのであれですが、物価の違いとか考慮すると、高い高いと言われる米国の学費が、州立であれば日本の私大と同程度なのは意外に思うかもしれません(むしろ物価差を考慮すれば安い)。これは、授業料が州外・州内で大きく違ったり、奨学金が豊富にあったりと、額面プライスと実際プライスがかなり異なっている事がそう印象付けているのかもしれません。
いずれにせよ、フロリダなどの州知事を見て分かるように、共和党州を中心に州政府から州立大学への資金カットが進んでいるので、それを授業料で補わざるを得ず、授業料が10%も上昇した訳です。
しかし、データをよく見ると、実は授業料が僅か10年で20%以上も増加したグループが存在している事に気が付くはずです。それは非営利私立大学です。NYTやWashington Postなどの一流紙の記者はそういった名門大学を出ている人が多いので、教育ローン問題で営利大学や短大関係者ではなく、この層に飛びついちゃうんだろうなと私は残念に思っています。
そして、教育ローン貸出総額が爆上がりしたもう一つの犯人が大学院です。連邦政府から教育ローンを借りた大卒者は、平均して3万5千ドル程度を借りています。しかし、修士号を取得した人のそれは7万ドルを超え、博士号に至っては約16万ドルとなっています。そして、大学院修了者が借りた教育ローンの平均額は、オバマ大統領が就任してからの10年で3万ドル以上も増加しています(データソース)。
これもSNSを見ていると、米国の博士課程はフルファンディングが貰えるという意見を目にしますが、それは一部の有名大(非営利私立&州立旗艦校)や一部の分野に限った話に過ぎないというのは看過してはいけないポイントだと思います。私が終えた博士課程はフルファンディングだったので、教育ローンという掠り傷は負わず、離婚・新型コロナで博論変更・ニートと三重で致命傷を負う程度で助かりグハッ・・・
この大学院の授業料高騰も層としては一つの問題ですが、二つの異なるグループがこの中にはいます。1つは、儲かる大学院出身者です。シリコンバレーでは年収1千万でも貧困層みたいな話は日本にも流れていると思いますが、儲かる学位は本当に儲かります。それは有名校のMBAであったり、ロースクール、メディカルスクール、工学部・経済学部といった所です。これらの学位は、修了後にいきなり年収1千万を超えたりするので、授業料が高騰して、教育ローンの額が数千万になろうとも、普通に返済できたりします。唯一の問題は、教育ローンの借入額が増えると、起業が阻害される点でしょうか(研究)。
しかし、ここだけ見れば概ねは教育ローン借入額の爆上がりは経済的に辻褄が合います。前世紀は高卒・大卒程度のスキルを有する人材の需要が広くあり、その層の賃金も上昇しました。確かに高卒・大卒の格差は拡大したものの、高校を中退していなければ何とかはなっていました。しかし、21世紀に入ってからのアメリカはスキル偏重型の経済成長をしています(論文)。これは、
①人口の上位1・2割レベルのスキルを持った労働力への需要はある
②人口の真ん中6割程度のスキルレベルへの需要は減退
③下位2割程度のスキルレベルへの需要は逆に増大
という特徴を有しています。これを学歴別にみると、①が院卒、②が大卒・高卒、③が高校中退以下といった感じになってきます。
これは、①の層は機械化や途上国の労働力を使いこなしてより稼ぐようになる一方で、②の層の雇用は機械や途上国の労働力に置き換えられ、③の層の仕事、例えば新型コロナ禍でエッセンシャルワーカーと呼ばれていたようなもの、は機械や途上国の労働力では置き換えられないので需要が残っていると言った感じです。
この結果、21世紀に入ってから大卒と院卒の所得格差が拡大して行ったので、儲かるのであれば授業料が上がってもペイするだろう、といった感じです。
ただ、はじめに大学院の授業料問題は二つのグループからなると言及しましたが、もう一つのグループは修士号が求められる公的セクターで働く人たちです(学校の先生や社会福祉関係、NPOもそうですが、エントリーレベルを除けば、基本的にはキャリアのどこかで働きながらでも良いので修士号を取得することが求められます)。このグループの人達にとってはスキル偏重型の経済成長の恩恵が行かないので、ただひたすら授業料高騰の暴力を受けるといった感じになっています。
米国政府もバカでは無いので、2007年に公的セクターで働く人達のための教育ローン返済免除プログラムを打ち出しましたが、2020年現在では申請者の98.5%が却下されていて(やっぱり米国政府バカだった、前言撤回)、まともに機能していません。結果、公的セクターで働く人達は、儲かる大学院出身者達と異なり、教育ローン地獄で苦しむ羽目になってしまっています(教育分野で言えば、豊かな学区以外の先生は確かに厳しいですが、教育政策Ph.D.だと、公的セクターでもオファーが1千万円は超えたりするし(政府データを触るので市民権がいる)、実際に私がオファー貰って取り消された某NGOのやつも1千万は優に超えていたので、言う程厳しくはないのかなーという感じもします)。
このように、米国の教育ローン問題は3層からなっていて、これを理解すればバイデン政権の教育ローン返済免除もちゃんと理解できるようになります。
バイデン政権vs教育ローンの3層構造
途中、西バージニアやアリゾナのあれな民主党議員によってバイデン政権は沈没しかけましたが、その危機を乗り越えて、私はとても良くやっていると思っています。そしてそれは教育ローン問題にも現れています。
実は今回の教育ローン一部返還免除が発表される前からバイデン政権は、特定の人達に対してちょこちょこと教育ローン全額返還免除をしていたりしました。今年に入ってからだけでも8月に4千億ドル(ニュース)、6月にも6千億ドルの免除をしています(ニュース)。
なんだそれと思うかもしれませんが、この特定の人達というのが教育ローンの1層目である営利大学へ行った人たちで、誤った情報に基づいて営利大学へ進学してしまった人達向けの連邦政府の教育ローン返還免除がちょこちょこと行われているわけです。営利大学ごとに審査が必要なので、どうしてもちょこちょことしか物事が進んでいかないようです。
そして今回の教育ローン一部返還免除です。折角なので、ホワイトハウスの公式発表を見ておきましょう→ホワイトハウスのサイト。発表によると、
①ペルグラントという奨学金を受け取った事が無い人は1万ドル、受け取った事がある人は2万ドル、教育ローンがチャラになる。
※ペルグラントは、貧しい人向けの奨学金で、要するにペルグラントを受け取った人は貧しい人、受け取っていない人はそこまででもない人です。なので、ペルグラントを受け取ったか否かで免除額に差をつけて、貧しい人はより多くの返還免除となるようにしたのは政策としての芸術度が高いなと思いました(大学授業料の高騰が始まる前はペルグラントだけで大学に行けたという人達も少なからずいました。ペルグラントのインパクトなど詳細が知りたい人はハーバードのデミング先生の論文でも読んでみて下さい。さらにどうでもいい話ですが、ペルグラントがどれだけ貧困層を押し上げたかを分析した論文のタイトルがPropelledってのはセンスいいですよね。私オヤジギャグに走りがちなので、誰かこういったハイセンスな論文のタイトルの付け方を教えて下さい!!!)
②ただし、年収が12万5千ドル、夫婦の場合は合算で25万ドル以上の人は免除にならない(所得の上位5%相当)
③新型コロナ禍で、利息無しで返還期限猶予を続けてきたけど、これは2022年末でお終いにする(※返還免除が揉めに揉めて中々実施されなかったので、一時しのぎ策としてバイデン政権は利息無しの返還期限猶予を繰り返していて、気候変動・インフレ対策資金がそうであったように、揉めに揉めて何もできないバイデン政権の象徴になっていました。西バージニアとアリゾナのあれ問題を解決したのと同時に、返還期限猶予を終了させるのは、何もできないからできるバイデン政権への転換点の一つとなりそう)
上記の①ー③を読むと分かるように、特定層への全額返還免除で教育ローンの1層目に対応して、今回の1万ドルor2万ドルの返済免除は教育ローンの2層目問題に切り込んだものであることが分かります。そしてさらに下記の条項で教育ローンの3層目グループ2にも対応しています。
④申請者の98.5%がリジェクトされるというぶっ壊れっぷりを発揮した公的セクターで働く人達向けの教育ローン返還免除プログラムを、特別に簡単に申請できるようにします(申請は10月いっぱいまでとかなりタイト)→ホワイトハウスのサイト
ここまでの情報できっと理解できたかと思いますが、
①教育ローンは3層の問題から成っている
②バイデン政権は3層ごとに対処策を打ち出し、今回の一部返還免除はその一つに過ぎない
③バイデン政権は1・2層目と3層目のグループ2をこれまで重視してきた
④しかし、日米どちらのメディアも3層目のグループ1に焦点を当て、高騰する授業料・高額の教育ローンを抱える若者を主に報道している
というのが米国の教育ローン問題とその報道の主要なポイントになっています。さすがにちょっとメディアにはガッカリというか呆れるというか、情けなくなるというか、これだけ精密にデザインされた美しい政策を歪曲した罪で④を犯した記者は全員クビでいいんじゃないですかね、と思います。
バイデン政権が教育ローン戦争に敗北しそうな理由
美しくデザインされたバイデン政権の教育ローン施策ですが、残念ながらデザイン通りには機能しない可能性が濃厚です。以下がその理由です。
申請書を書くのは一般的な米国人には難しい
Forbesの記事を読むと、教育ローンの一部返還免除を受け取るためには、所得が12万5千ドルを超えていない事の証明などを添えて11月中旬までに申請することが推奨されているようです。・・・、短大・中退層が一部返還免除になるという情報にアクセスして、いくつかの書類を準備して、申請する・・・。果たして、一体どれだけの人がこの3つのハードルを無事にクリアできるでしょうか?
例えばですが、FAFSAという奨学金制度がアメリカにはあるのですが、これの情報を教えてあげつつ申請書を書く支援をしてあげただけで、大学進学率が8%%も上がったという実験があったりします、なんちゅー実験だという倫理的な批判はさておき。また、先に言及したハーバードのダイナスキ―先生がミシガン大(※私が卒業したのはミシガン州立大。大学ランクはミシガン大の方が上だけど、ミシガン州立は教師教育とアフリカ研究で20年以上全米No.1の大学なので、私のような専門の人には、網走刑務所のような環境に耐えられるのであればおススメ)にいた時に、奨学金が幾らもらえるか生徒に教えてあげるだけで、大学進学率が上がったなんて実験もしています。
裏を返せば、アメリカでは大学に行くか行かないかを迷うmarginalな層ですら、情報を集めて申請書を作成するというのは結構なハードルだったりします。況や、短大進学者や中退者をや・・・。というのを考えると、所得制限をかけて超富裕層が教育ローン一部返済免除の恩恵にあずかれないようにしたが故に、自動的に借入額が減免されるのではなく申請書の提出を必要としてしまったのは、相当な悪手だったんじゃないかなと私は思います。
営利大学問題どうするのよ?
バイデン政権は教育ローンの1層目に対して、連邦教育ローンの全額返済免除を営利大学ごとに審査し実施するという対応策を取っていますが、これはいわば傷口に絆創膏を貼るようなもので、営利大学問題を解決しない事には、やるべきではない2度目の教育ローン徳政令を出さざるを得なくなります。
もちろん、バイデン政権はこの点に対して無策ではなく、野放しにしたトランプ前政権と異なり、かなり厳しいルールを課す予定です。大学収入における助成金とその他収入の比率や、卒業生の教育ローンと収入の比率、助成金そのもののカットなど、オバマ政権のそれを復活させる予定ですが、いくつかきな臭い点も含まれます(ニュース)。
一つ目が、高卒と比べた時の賃金がどうなっているかで規制をかけようというものです。確かに、時間(間接費用)とお金(直接費用)をかけて大学に行ったのに高卒よりも雇用が不安定で賃金も安ければ、そんな大学意味がな・・・アメリカでは学生の人文系離れが進んでいますが、もしこのルールが徹底されると、州立旗艦校はまだしも、それ以下の大学(名前に東西南北がつく州立大学や、州名が入っていない州立大学、一定以下の非営利私立)の人文系は取り潰される所が少なからず出てくるはずですが、バイデン大統領、マジでやるんですか・・・?
二つ目が、営利大学へ行ってしまった学生の救済措置の拡大です。今ちょこちょこと行われている教育ローン全額返済免除は、「誤った情報に基づいて進学してしまった」事が条件となっていて、これの審査があるが故にちょこちょことしか進んでいないのです。
JFK以来の2人目のカトリック信者の大統領だけあって、バイデン大統領はもっとスムーズに多くの被害者を救済しようと考えているようですが、それをやってしまうと、営利大学にエサをやるような事態になりかねないわけで、この辺どうするんだろう?というのは疑問に残ります。
そして何よりもリスクとなるのが、共和党に政権が移った時に、オバマ→トランプでそうなったように、全ての対策が無に帰す事が再び発生しうる点です。それを見越した対策を打てるかどうかがカギとなりますが、この辺りの工夫はまだ見えてきません。持続可能な営利大学対策というのはまだまだ大きな課題であるように私には見えます。
コミュカレ問題どうするのよ?
営利大学以上にマズい方向に行っていると感じるのがコミュカレ問題です。バイデン大統領は、コミュカレの無償化を目玉政策として掲げていましたが、西バージニアのあれのせいでひっこめざるを得ませんでした(ニュース)(自分の配偶者が人生をかけている政策をよく引っ込められたなと、この決断力に私はバイデン大統領を尊敬しましたし、私は政治家にはなれないなと思い、あ、配偶者いなかった。。。)
ただ、どうも無償化以上の手が無いというのが気になっています。昔々あるところに「アフリカから学ぶべき日本の教育無償化のダメな議論」という記事があって、お爺さんは山に・・・、ではなく面倒でなければ記事を読んでみてもらいたいのですが、無償化政策というのは実に難しいものです。
特に、①コミュカレは授業料収入を手放すわけなので、政府から一層の支援が必要になる、②無償化されるので学生が殺到し、教育リソースが逼迫する、という二つを両立させなければならず、単純に無償にするのに必要なリソースを上回る膨大なリソースを投入する必要があります。それが為されなければ、教育の質は低下する一方で、より多くの退学者を生み出します。コミュカレ無償化といえども、無償化されるのは授業料(直接コスト)のみで、間接費用の補填はまずなされないと思います。勿論、学ぶために働けなければ生活費を借り入れざるを得なくなるので、退学者が多く生まれれば、それだけ教育ローン破綻者が生まれる事になります。
なので、そもそもコミュカレ無償化は教育ローンの2層目問題の解となっていない、と私は考えています。しかし、バイデン政権が引っ込めたにもかかわらず、分権的なアメリカ合衆国ですから、多くの民主党知事の州がコミュカレ無償化に乗り出していて(ニュース)、これはむしろ教育ローンの2層目問題が悪化していく恐れがあると私は考えています。
じゃあどうするかと言われれば、やはり資金不足を解消するために多くのリソースを注ぎ込むのが正攻法だと考えますが、無償化すら引っ込めざるを得なかったバイデン政権にそれが出来るのか、民主党知事たちは莫大なリソースをぶっこんでいくのか・・・。
公的セクターで働く人達&大学院問題どうするのよ?
バイデン政権は、今回の教育ローン一部返還免除の中に「公的セクターで働く人達向けの教育ローン返還免除プログラムの手続きの簡素化」を盛り込みましたが、10月末までの申し込みが推奨されているように、一時的な措置に終わる可能性があります。
そもそも社会福祉や教育の様に、利益が個人ではなく社会に波及する分野を大学院までわざわざ行って学んだ人達に対して、むしろ社会的な厚生を悪化させて高給を得ているMBAの人達(・・・という研究が実際にあります、しかも筆者はかの有名なMITのアセモグル教授。。。)と同様に授業料を課すべきなのか、この辺を詰めて行かないと今回の措置が大怪我に絆創膏で終わってしまいます。
そして、バイデン大統領は今回の措置の中に、上記で説明した①から④だけでなく、⑤学部向け教育ローンの月々の返済額をより緩やかなものにする、という施策を入れています。先に説明したように、教育ローン爆上がり問題の主犯は学部というよりは大学院なので、ひょっとすると3層目のグループ②に対する認識がちょっと甘いのではないかとも思わされます(公務員を重視すると言っているのに、公務員から反感を持たれているバイデン政権らしい話かもしれませんが)
インフレ・・・
新型コロナ禍の現金給付や手厚い失業手当が、現在の高いインフレ率の一因となったとも言われていますが、教育ローンの一部返還免除も似たような働きをする恐れがあります。まー、ただ私は経済学者ではないんで、それが具体的にどの程度のインパクトに成り得るのかは、ちょっと何言ってるかよく分からない。
爆上がりする教育ローンと授業料問題
教育ローンを3層に分けて、1層目、2層目、3層目のグループ2について解説してきましたが、自身がエリートであるがゆえにメディアの人達が目を向けてしまう3層目のグループ1はどうでしょうか?
ん-、どうなんでしょうかね。格差社会アメリカだけあって、エンジニアリングや経済学の大学院、ロースクールにメディカルスクールを出れば、初任給でいきなり1千万円を超える事も珍しくありません。そんな人たちに高額の授業料を課して、2千万円ぐらいの教育ローンを背負わせてはいけない理由がイマイチ分かりません。リスク回避的な人達(往々にして貧困層だったりする)が高収入への道を閉ざされる恐れがあるとか、先に出てきた起業が阻害される恐れがあるとか、問題があるのも理解できますが、それって授業料&教育ローンとは別の方法で対処できる気もするし、まあそもそもが自分の勉強不足でよく分かりません。
私が取得したEducation Policyという学位は教育分野全体の政策・経済分析はしますが、K-12やHigher Educationの人達に比べるとドメイン知識が劣るので、やはりHigher Edの人の解説が聞きたいですね。まあ、そもそもニートで帰国してくるような奴に詳細な教育ローン問題の解説が出来ると期待する方がどうかと思いますがね(←!!)
幸いな事に、日本には筑波大学で働いている友達の猛さんがいて、彼は実際に高等教育のコンサルタントをしたり、コミュカレで働いた経験があるだけでなく、何度か記事中でも出てきたダイナスキ―先生、の弟子でコミュカレや高等教育の経済分析分野のスターであるジュディス・スコット・クレイトン先生、の下でコロンビアのTeachers Collegeで教育経済で博士号を取得してきた凄い人なので、遊びに行く機会があったらこの件どうなのかちょっと話を聞いてみようと思います。
おしま・・・、あ、そうだ、気が向いた方はネパールの子供達が新型コロナから立ち上がるための支援にご協力いただければ幸いです(最新の活動紹介・寄付ページ)
おしまい。
サルタック・シクシャは、ネパールの不利な環境にある子供達にエビデンスに基づいた良質な教育を届けるために活動していて、現在は学校閉鎖中の子供達の学びを止めないよう支援を行っています。100円のサポートで1冊の本を子供達に届ける事ができます。どうぞよろしくお願いします。
