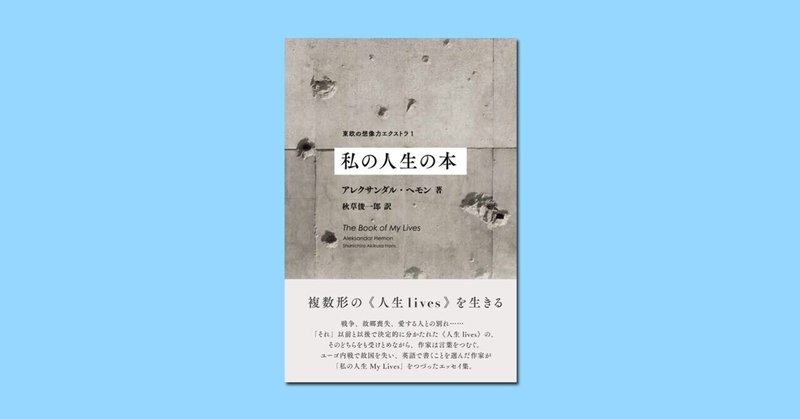
『私の人生の本』訳者あとがき
旧ユーゴ出身の作家アレクサンダル・ヘモンのエッセイ集『私の人生の本』日本語版を刊行いたします。
刊行に先立って、翻訳をしていただいた秋草俊一郎さんによる「訳者あとがき」を公開します。
----------
『私の人生の本』訳者あとがき
1
本書はアレクサンダル・ヘモンによるThe Book of My Lives(二〇一三)の邦訳である。本書は著者はじめてのノンフィクションとして、各媒体に発表してきた散文をまとめたものだ。以下にそれぞれの初出を列挙しておく。
1. 「他者の人生」
“The Lives of Others,” first published as “The Other Questions” in Der Andere Nebenan: The South-East-European Anthology, ed. Richard Swartz, S. Fischer Verlag, Germany, 2007.
2.「サウンド・アンド・ヴィジョン」
“Sound and Vision,” first published as “To Catch a Thief” in The Guardian Weekend, July 10, 2004.
3.「家族の食卓」
“Family Dining,” originally published as two pieces: “Rationed,” The New Yorker, September 3, 2007; and “Borscht,” The New Yorker, November 22, 2010.
4.「カウダース事件」
“The Kauders Case,” McSweeney’s, Issue 8, 2002.
5.「戦時の生活」
“Life During Wartime,” The New Yorker, June 12, 2006.
6.「魔の山」
“The Magic Mountain,” The New Yorker, June 8, 2009.
7.「あり得ざることあるならばあれ」
“Let There Be What Cannot Be,” published as “Genocide’s Epic Hero” in The New York Times, July 27, 2008.
8.「犬の人生」
“Dog Lives,” first published as “War Dogs” in Granta, Issue 118, February 2012.
9.「私の人生の本」
“The Book of My Life,” The New Yorker, December 25, 2000.
10.「フラヌールの生活」
“The Lives of a Flaneur,” first published as “Mapping Home” in The New Yorker, December 5, 2011.
11.「私がなぜシカゴから出ていこうとしないのか、その理由―網羅的ではない、ランダムなリスト」
“Reasons Why I Do Not Wish to Leave Chicago: An Incomplete, Random List,” first published in Chicago in the Year 2000, ed. Teri Boyd, 3 Book Publishing, 2006.
12.「神が存在するのなら、堅忍不抜のミッドフィールダーにちがいない」
“If God Existed, He’d Be a Solid Midfielder,” Granta, Issue 108, September 2009.
13.「グランドマスターの人生」
“The Lives of Grandmasters,” unpublished.
14.「犬小屋生活」
“The Kennel Life,” first published as “In the Doghouse” in Playboy, August 2006.
15.「アクアリウム」
“The Aquarium,” The New Yorker, June 13, 2011.
なお、すべての作品は本書に収録するにあたって、全面的に改稿されている。
長年創作を発表してきた作家にとって、初のエッセイ集というくくりになろうかという本書だが、決して余技的なものではないだろう。
「アクアリウム」は、二〇一二年のナショナル・マガジン・アワードのエッセイ・批評部門の最終候補に選ばれた。また、本書自体も二〇一三年の全米批評家協会賞の自伝部門の最終候補に選ばれている。
また本書は確認できるだけで、オランダ語、イタリア語、韓国語、クロアチア語、スペイン語、スロヴェニア語、セルビア語、ドイツ語、ノルウェー語、ボスニア語、ポーランド語にすでに翻訳されており、ヘモンの全作品のなかでも広く読まれ、読者に愛されている本だと思われる。
なお本書の原書であるハードカバー版では、謎めいた青いエイリアンの挿画がつかわれており、いくつかの国の版でも、同じ絵がつかわれているが、このエイリアンの正体は、本書の最終章である「アクアリウム」を読むと明らかになるしかけになっている。
2
ヘモンそのひとについてはすでに刊行されている訳書の訳者あとがきや、本書自体のなかで詳しくその生い立ちや来歴が語られているが、簡単にまとめておく。
アレクサンダル・ヘモン(愛称サーシャ)は一九六四年九月、いまはなきユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国のボスニア・ヘルツェゴヴィナ社会主義共和国の首都サラエヴォで生まれた。ユーゴスラヴィアは多民族国家だが、ヘモン家もその例にもれず、父親はウクライナ系、母親はセルビア系だった。大学卒業後、ラジオや雑誌の仕事を経験したのち、九二年にアメリカ合衆国広報文化交流局主催の文化交流プログラムで渡米。しかし滞在中にサラエヴォはセルビア人勢力によって包囲され、帰国できなくなった。
ヘモンは滞在先のシカゴに残ることを決断し、グリーンピースの訪問運動などの職をいろいろと経験しながら英語で作品を書くようになる。とはいえ母語話者ではない言語で執筆するのは想像を絶する困難がともない、このときやはり第二言語で執筆したロシア出身の英語作家ウラジーミル・ナボコフの文体に多くを学んだという。九〇年代後半には作品が文芸誌に次々と掲載されるようになり、二〇〇二年には初の長編『ノーホエア・マン』が刊行され、高い評価を得る。二〇〇八年に刊行された長編第二作The Lazarus Projectは全米図書賞ほか数々の文学賞の候補になった。二〇一五年には長編第三作The Making of Zombie Warsを刊行している。
現在はプリンストン大学でクリエイティブ・ライティングを教えながら、精力的に執筆活動をつづけている。近年は小説に限らず、さまざまなジャンルへの進出がめだっている。本書のあと、二〇一九年には本書につづくノンフィクションの第二弾として自分の両親について記したMy Parents: An Introductionを刊行した。小説やエッセイにとどまらず、映画やドラマ・シリーズの脚本の執筆もおこない、今年公開される予定の映画「マトリックス」四作目の脚本をデイヴィッド・ミッチェル、ラナ・ウォシャウスキーと共同で務めることも発表されている。
3
本書自体の内容についてももう少し触れておこう。本書の原題The Book of My Livesでは、単数形のlifeではなく複数形のlivesがつかわれている(実際、「生life/lives」は本書全体をつらぬくキーワードでもあり、各章のタイトルにはlife/livesがはいっているものも多い)。このことについて、作家は二〇一四年、本書の刊行後に来日したさいのインタヴューで次のように述べている。
理由がいくつかあります。まず、私や多くのボスニア人のように、戦争を経験した「戦争前の人生」と「戦争後の人生」という、人生を二つに分断する時点があります。すると、どうやって両方の人生をつなげ、一つの連続した体験として理解するかという問題が現れるのです。
もう一つはアイデンティティの捉え方です。私自身とボスニア人の知り合いのほとんどに当てはまることですが、自分の体験を経て、アイデンティティについて、すなわち何が「私」という人間を構築しているのかについてよく考えました。現時点での結論は、アイデンティティとは一つの「中心」や「本質」ではなくて複数の「人生」の可能性が実践できるような領域だということです。(アレクサンダル・ヘモン、都甲幸治「対談 文学という都市をつくる アレクサンダル・ヘモン+都甲幸治」米田雅早訳『早稲田文学』[第10次]、九号、二〇一四年。)
ボスニア人(内戦前はユーゴスラヴィア人)やアメリカ人という複数のアイデンティティを生きなくてはならないヘモンにとって、人生とは単一のものではなく、「そうだったかもしれない」可能性や分岐が積み重なって層をなしているものだ。また作家とは職業柄、作品の中で無数の登場人物の人生を描くものである。ヘモンがインタヴューなどで述べるように、登場人物は作者そのひとではないが、自分が歩んだかもしれない人生を歩んだ人物ではあるという。本書は通常の意味でのフィクションではないが、ヘモンは実生活real lifeについてもフィクションのような見方を(作家になる前ですら)してしまう(「カウダース事件」)。それはこういった考え方でもある―大きな、見えざる意志が働き、自分や他人を動かしているのではないか。自分は小説の登場人物や、チェスの駒のような存在なのではないか。
それを加速させたのは、ユーゴスラヴィア内戦、サラエヴォ包囲という、自分の想像をはるかに超えた世界史的な出来事である。第二次世界大戦ののちに建国された社会主義国家ユーゴスラヴィア連邦人民共和国は、一般に「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」と呼ばれるほどの多民族国家だった。しかしカリスマ的指導者だったチトーが死に、社会主義が求心力を失って東欧で民主化がすすむと、ユーゴスラヴィアの各共和国でも民族主義者が台頭し、独立をかかげて内戦状態に陥り、おびただしい血が流された(ユーゴスラヴィア成立や解体についての詳しい説明は訳者の手にあまるため、柴宜弘『ユーゴスラヴィア現代史』[岩波新書]など専門家による書籍を参考にしてもらいたい)。ボスニア・ヘルツェゴヴィナも例外ではなく、独立をのぞむボシュニャク人(イスラム系ボスニア人、本書ではムスリム人と記載)、クロアチア人と、連邦残留を主張するセルビア人は激しく争い、殺しあう「民族浄化」に発展した。
サラエヴォをこよなく愛し、ジャーナリストをしていたヘモンは、街が戦火に飲みこまれていく様子をインサイダーの目から克明に描きだしている。それだけでなく、スレブレニツァ虐殺を引きおこし、のちに戦争犯罪人として裁かれることになるセルビア系指導者ラドヴァン・カラジッチのような人物にも焦点があてられる(「あり得ざることあるならばあれ」)。ユーゴスラヴィア内戦は湾岸戦争とならんで私の世代の人間が、はじめてリアルタイムで「目撃」した戦争だった。九〇年代には、サラエヴォ包囲についても『ウェルカム・トゥ・サラエボ』や『パーフェクト・サークル』のような映画を観た方もいただろう。しかし紛争から二〇年が経過して、記憶が薄れつつあることもたしかで、そのなかで本書の内容は「証言」としても貴重なものだろう。
偶然により包囲をまぬがれたヘモンだが、紛争の結果、すべてが以前/以後で区切られ、過去の見え方までもが一変してしまった。また現実の見え方だけでなく、文学の読み方までも一変せざるをえなかった。内戦前、大学で文学の読み方を教えてくれた先生が、セルビア民族主義者として戦争犯罪に加担していたと知ったからだ(「私の人生の本」)。さらに自分の庭のように慣れ親しんだ街がセルビア人勢力によって包囲され、日々破壊されていく様子を海のむこうからテレビニュースで見なければならなかった(「フラヌールの生活」)。こうした痛手から立ち直るためには、新しい街、新しい言語で自分の物語を再生する必要があったのだろう。しかしその一方で、戦争によって人生を損なわれてしまったという怒りは、その後も長くヘモンを苦しめたことも示唆されている(これは著者の最初の結婚の破綻の一因にもなっていることが匂わされているのだが)。
ヘモンの小説はときに実験的で、視点の移動や語りの脱線、断片的な記述などのような(「ポストモダン」的な)しかけも織りこまれ、難解な側面も見せるが、エッセイ集となる本作は(少なくとも表面上は)そのようなこともない。各章の内容はそれぞれ独立してはいるが、収録にあたっておおむね時代順にならべられている。読者は一貫して「私」の視点からヘモンの半生を読むことができるだろう。本書が広く読まれ、評価されているのには、そのような理由もあるだろう。
先にも述べたように、作者の人生のディテールはさまざまなかたちで創作につかわれているため、いままでのヘモンの作品の愛読者なら「元ネタ」がわかってニヤリとするような箇所も多い。ひとつだけあげておくなら、本書の「カウダース事件」は、第一作品集The Question of Bruno(二〇〇〇)に収録されている短編 “The Life and Work of Alphonse Kauders”の成立事情を語ったものになっている。
4
ヘモンと言えば、日本では翻訳家の岩本正恵さんの訳業で読書人にはよく知られている。私自身、『ノーホエア・マン』は岩本さんの翻訳で読み、強い衝撃を受けた(むしろ影響をうけた)ことをよく覚えている。しかし残念ながら、二〇一四年末に岩本さんが亡くなられて以降、ヘモンがまとまったかたちで紹介されることはなくなっていた。今回、(自分の中でも愛着深かった)その組み合わせを壊してしまうことに逡巡がなかったわけではないが、紹介が途絶えてしまうよりはと思い、翻訳の筆をとったという次第である。ご理解いただきたい。といっても、実はヘモンは雑誌やアンソロジーでは、さまざまな訳者の手でこれまでも紹介されてきた。以下に既訳のリストをあげておく(うち正来紀子訳「島々」と柴田元幸訳「島」は同じ短編)。
A・ヘモン「島々」正来紀子訳、エィミ・タン、カタリナ・ケニソン編『アメリカ短編小説傑作選 2001』愛甲悦子ほか訳、DHC、二〇〇一年。
アレクサンダル・ヘモン『ノーホエア・マン』岩本正恵訳、白水社、二〇〇四年。
アレクサンダル・ヘモン「フランス」岩本正恵訳、マット・ウェイランド、ショーン・ウィルシー編『世界の作家32人によるワールドカップ教室』越川芳明・柳下毅一郎監訳、白水社、二〇〇六年。
アレクサンダル・ヘモン「島」柴田元幸訳、柴田元幸編『昨日のように遠い日 少女少年小説選』文藝春秋、二〇〇九年。
アレクサンダル・ヘモン「アコーディオン」柴田元幸訳『モンキービジネス』四号、二〇〇九年。
アレクサンダー・ヘモン「サラエボ 大衆食堂で味わう庶民の誇り」『ニューズウィーク』(訳者不明)二六巻三一号、二〇一一年八月一〇日。
アレクサンダル・ヘモン『愛と障害』岩本正恵訳、白水社、二〇一三年。
アレクサンダル・ヘモン「神の運命」ヴィエト・タン・ウェン編『ザ・ディスプレイスト―難民作家18人の自分と家族の物語』山田文訳、ポプラ社、二〇一九年。
本書の出版を機に、過去の邦訳を手にとってもらえたり、また新たな作品が訳されるきっかけになれば訳者としてはそれ以上のことはない。
本書の翻訳にあたって、作中の旧ユーゴスラヴィア現地語については奥彩子さん、「アクアリウム」の医療用語については乾健彦さんにお知恵を借りた。記して感謝したい。
本書の編集・刊行は、(いつもながら、複数の出版社に断られたあとで)松籟社、木村浩之さんに引き受けてもらえることになった。松籟社・木村さんとは、シギズムンド・クルジジャノフスキイ『未来の回想』で、訳者初めての単独訳を刊行した際にご一緒して以来の仕事になった。木村さんは(十年前と同じように)丁寧に訳文に目を通してくださり、訳を大幅に改善することができた。記してお礼を申しあげる。
アイロニカルなウィットに富み、練りあげられたヘモンの散文を翻訳するのは、私にとって心躍る体験だった。知的な労働意欲は満たされ、充足感を味わうことができる(ただ、「アクアリウム」だけは訳していてどうにもつらくて困ってしまったが)。ノンフィクションでありながら想像力にあふれた本書が(さいわいにして「東欧の想像力エクストラ」のシリーズの一冊目になる)、日本でひとりでも多くの読者に親しまれることを願っている。
二〇二一年五月 訳者
----------
『私の人生の本』について、各オンライン書店さんの販売ページをご案内します(随時更新していきます)。
→hontoネットストア
→楽天ブックス
→セブンネットショッピング
→ブックサービス
→ヨドバシ.com
----------
松籟社の直販サイト「松籟社stores」にて、『私の人生の本』を販売しています。どうぞご利用下さい。
----------
秋草俊一郎さんには、2013年にシギズムンド・クルジジャノフスキイというウクライナ出身の作家によるタイムトラベルSF『未来の回想』を訳していただきました。こちらもよろしければご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
