
哲学の実装、あるものはある。の先。
あるものはある、ないものはない。が50数年生きてきた中で見出した私の哲学だと昨日の記事で書きました。で、それがどうした?とならない様に哲学を持つことの意味や意義を続けてみます。
「あるものはある、ないものはない。」と言う単純な論理に照らすと、物事の判断基準はシンプルにやった方が良いことをやる。やらない方が良いことをやらない。となります。いつもシンプルなものは美しい。
そんなシンプルな考え方をしていると、新しいことに触れるたびにどんどんやることが増えていきます。次のフェーズとして、できるものはできる。できないものはできない。がやってきて、良いことと、できる事は、残念ながら整合しなくなってしまいます。しかし、できないからといってあるものがなくなったりしないし、無いものがあったりはしません。
制限が「ある」
時間や空間、資金等の制限を受けて、本当はやったらいいことと、実際にやっている事の間に齟齬が生まれるのは致し方ないことです。生きていると様々な制約があると言う事実もあるわけで、前提条件が全てなくなる事はあり得ません。
人は、誰しも、このジレンマに突き当たり、そこで初めて何を選択すべき?とプライオリティー(優先順位)を考えるようになります。
本当に大切なのは、そこから先にどのような選択を行うかだと私は思っていて、その選択で人格も人生も事業も人間関係も、何なら全てが作られると言っても過言でないと思っています。
そして、本来、そこに現れてくるのが、自分自身の中にある、価値観や世界観、存在意義、人生の目的、志、そして哲学だと思うのです。
損得中心が判断基準
しかし、残念ながら現在の日本の教育では本来持つべき選択の基準を教えられることがありません。学ぶのは足し算引き算、掛け算割り算と数値に置き換えた時にどうなるか?が中心にあり、損か得か、メリットとデメリットのどちらが多いかの計算になってしまっている様に感じます。古今東西、計算高い人は嫌われるに決まっているのに、です。
そうではなく、自分一人だけの枠組みに囚わることなく、世の中にとって良いか悪いか、美しいか醜いか、喜びと悲しみのどちらの総量が増えるかを考えるべきだと思います。しかし、そんな判断をする人は宗教家かお金持ちの篤志家、若しくはちょっと変わった人で、フツーじゃない。と思われるのが今の世の中になっている様に思えてなりません。これでは世の中はどんどん悪くなるし、格差と分断が広がって争いが絶えない様になってしまいます。教育の場で伝え、導くべきは哲学を探求することの入り口ではないかと思うのです。
蹉跌が価値観を歪ませる
そんな偉そうなことを言っている私も、実は、若かりし頃、欲と色に取り憑かれたようなサイテーの人間でした。当時やってたことを思い出すだけで恥ずかしく、穴があったら入りたい、と思う程です。多くの方に迷惑をお掛けしたし、嫌な思いをさせたと思います。しかし、そんな私でも子供の頃は動物好きの優しい少年で、将来の夢は動物園の飼育係でした。
どこで間違ったのか?と振り返ってみると、どうやら17歳で社会に飛び出し、就職した先でにこき使われ、そこから逃げ出すと働き口も行き場もなく、家賃どころか食べるにも苦労するくらいの超絶貧乏を経験しました。私の判断基準がおかしく歪んだのは貧乏がきっかけの様な気がします。明日の事さえ分からない暮らしをしながら、公務員やサラリーマン等の社会的に守られた人たちのことを羨ましく思うと共に、妬みとライバル心を芽生えさせ、手段を問わず金儲けをしてやる!と心を固めた覚えがあります。
人間は環境の生き物
必死になって金儲けに囚われていた頃の私は、はっきり言って倫理観などカケラも持ち合わせていませんでした。とにかく、人並みの暮らしがしたい。ずっと付き纏う未来への不安から解放されたいとばかり考えて、善悪ではなく損得でしか物事を考えられていなかったように思います。
そんな私も、20代過ぎにはそれなりに収入があるようになり、目先の生きるためのカネと欲以外のことにも目を向ける余裕が出来てきて、自分の人生をどの様に生きるべきなのか?などと考え始めました。衣食足りて礼節を知ると言いますが、まさに人間ってそんなものだと思います。抑圧し、搾り取ってカスカスになった人間は本当にロクなことを考えないし、良からぬことをしてしまうもの。犯罪に手を染めるのはもちろん悪いことですが、実はそれは本人が悪いのではなく、そうなる環境を作った側の責任の方が大きいのではないかと思っています。
悪しきスタンダード
私に限らず、人は喜ばれると嬉しいし、親は子供のためなら自分の身を挺して守ります。経営者になると自分が褒められるよりも社員が称えられる方が幸せを感じます。どんな悪人でも古井戸に落ちかけている子供を見かけると助けます。それを孟子が良知という概念で世に広げましたが、本来、人間は生まれつき良き心を持っているし、知っている。それを覆い尽くして見えなくなるような環境を人が作ってしまうから、悪人が生まれ、悪行が蔓延るのだと思うのです。良知を忘れてしまった人が今の社会を構成してしまうと、損得勘定でしか物事を判断しないのがスタンダードになってしまいます。そして、「そんな悪しき当たり前」の前提に立って子供達への教育が行われる様になります。実際、現在の日本はそんな世知辛い世の中になってしまっているのではないでしょうか?
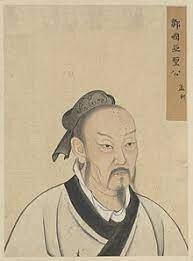
権力者と資本家の理論
映画やドラマ、小説等では勧善懲悪的なストーリーが持て囃されるし、真心が通じて人の心を動かした、この世もまだまだ捨てたもんじゃない。と思われる心温まる事象もネット上でよく取り上げられます。誰もが良き心を持っているし、良きことをしたいと思っている。孟子の提唱した良知は必ず誰の心の中にでも存在していると私は信じています。ちょっとしたきっかけがあれば、この世は随分と良くなる可能性が残されていると思っていて、甘っちょろいかも知れませんが、誰もが助け合う心ある人の共同体を再構築できると思っています。
ただ、資本主義にどっぷりハマった権力者や資本家はそんなことは考えず、ひたすら権力を集中させたり、資本の強化にばかり血道を上げます。大きな影響力を持っている人ほど、現状の延長線で未来を作りたいと思うもの。トマ・ピケティーが発見したr>gの法則が彼らにとって都合がいいからです。当然、既得権益を握っている政府も経済界も変わるわけがありません。そして、これがエスカレートするのに従って格差と分断が加速するのは明らかです。
人口の80人に一人が難民の世界
戦争に紛争、差別と分断、祖国を追われもしくは逃げ出して難民となった人は現在増え続けており、今や世界で1億人を超えて全世界人口の80人に一人が難民となっていると言います。根深く、複雑怪奇で解決不可能とさえ思える社会課題の坩堝と化した世界に対して私たちが出来ることはあまりにも微弱で、何か行動を起こしたとしても山火事に雫を落とすハチドリの様なものだと感じてしまいます。良知を開き一人で何か行動を起こしたところで殆ど意味を感じませんし、やるだけ無駄に思えます。しかし、国を追われた人、貧困に喘ぐ人、未来に絶望した人ばかりになると、私が若き頃に荒れてしまったように、優しい良き心を持った人たちもまともな判断が出来なくなってしまいます。世界はすでに悪循環のスパイラルに陥っているかのように思えてなりません。
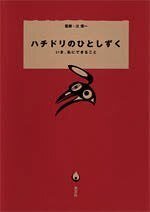
一億のハチドリ
この閉塞感漂う世界に対して私達に出来ることは何か?そんな問いの答えは、やっぱりハチドリの一雫を多くの人と共に落とす事しかないと思います。良いと思うことをやる、当たり前のことを当たり前に行う、良くないと思うことはしない、判断を下す基準は損得勘定ではなく、誰かの苦しみや悲しみ、嘆きを解消出来るかどうか、喜びの総量を増やせるか?頭で損得を考えるのではなく、魂が喜ぶ選択を多くの人が行う様になれば、世の中は必ず変わります。そしてそれは、既得権益を握り、資本の増大を目指す権力者や資本家には絶対に出来ないこと。というか構造的に利益相反の関係です。
世の中を変える可能性があるのは地域に根ざし、人に向き合い、自然との共生を目指す、私たちの様なスモールビジネスに取り組む企業と人しかありません。社会が会社を中心に成り立っているならば、その97%を占める中小企業とその経営者が当たり前の事を当たり前に行う、「理」に叶った選択や判断をする様になれば一億の一雫となってやがて大河になるかも知れません。やったらいいと思えることを素直にやれる。そんな在り方を未来を担う若者達に示したいと思います。
___________________________
天下布理を掲げて職人育成の高校運営に取り組んでいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
