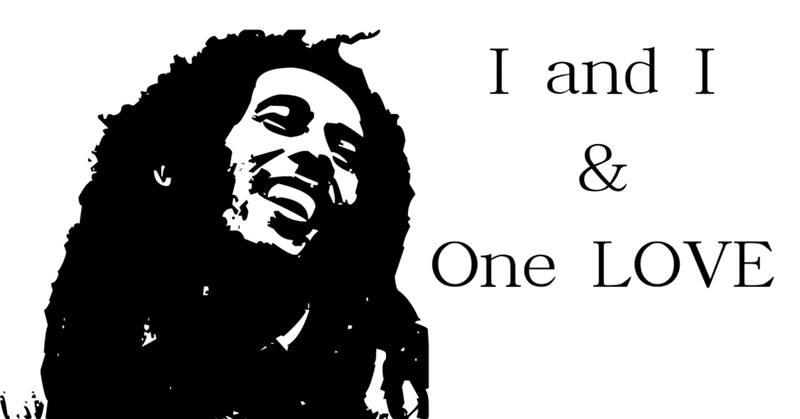
拳を固めろ、そして愛を口ずさめ 〜One LOVE 〜
若かりし頃、横ノリの文化が一世風靡しました。ロックでもR&Bでもない新しいジャンルの音楽としてレゲエは新鮮で、野外フェスに足を運んで、ゆったりとしたリズムに身を任せ、ラム酒をラッパ飲みしながら左右に身体を泳がすのは単に音楽を聴くのとはまた違う楽しみで、それまで知らなかった異文化を感じたのを覚えています。そして、レゲエといえばスーパースター、というより神のボブ・マーリーです。
1981年
1981年、36歳の若さで亡くなったボブ・マーリー。その頃、私はまだ14歳の中学生で、神戸はポートピア81で大盛り上がりしていた頃でした。
当時は彼のこともレゲエもスカも全く知らないし、興味もありませんでした。しかし、中学校を卒業してすぐに社会に飛び出し、世の中の荒波に揉まれる中で、少しずつ自我に目覚め、生きにくく不公平な社会に対して憤りを感じるようになってきました。ラム酒を片手にボブ・マーリーを聴いていたのはその頃です。
ロクに勉強していなかった私に、英語の曲の意味が分かるはずもなかったし、レゲエやラスタをファッションの一つだと認識しており、そのスローで自由な雰囲気に憧れを感じていました。ただ、それだけではなく、ボブ・マーリーの歌詞の端々に垣間見える過激な単語や政治的な要素も同時に感じていました。
社会や政治、未来についてのメッセージを発信しているからこそカッコイイと思っていたのも事実です。

革命と愛
夏になったらレゲエとラムで盛り上がる。そんな程度の薄っぺらい関わり合いで、ボブ・マーリーのファンとも言えない私でしたが、この度、世界で大きな話題になっているボブ・マーリーの映画「One Love」が上映されるのを聞きつけて早速、映画館に足を運んで観てきました。
映画を見てみて、ボブ・マーリーについてもジャマイカについても深く知らなかったことに改めて気づいたと共に、ボブ・マーリーの曲を聴く度にずっと感じていたけど、認識、もしくは言語化することが無かった感覚に気がつきました。ボブの曲は革命と愛をテーマに書かれていたのです。そして、実際に彼の活動によってラスタファリ主義が全世界に広がり、今なお、根強く長年に渡って虐げられてきた黒人のアフリカ回帰の思想として生き続けているという圧倒的な事実に胸を熱くしました。
怒りの向かう先
私は、大工から起業して会社を起こす際に「職人の社会的地位の向上」を志に掲げました。道具のように使われ、要らなくなったらポイ捨て。なんの保証もされずその日暮らしのような生活を自分自身が送ってきた原体験から、このままでは日本の住環境やインフラを守る職人が絶滅してしまうと強い危惧を持ったのが経営者になったスタートでした。
そこにあったのは業界、社会に対する怒りと憤りで、今なおそれは収まる事なく持ち続けており、それが、全国に職人育成の高校を開設すべく飛び回っている私の原動力になっています。業界に革命を起こしたいのです。
もう一つ熱心に取り組んでたのは、職人の地位を上げるには職人自身が自助の精神を持って変わる必要があるのを感じて始めた、職人への教育と研修です。そこで伝えているのは、現場でしか答えを出せないモノづくりの業界だからこそ、職人が圧倒的な信頼を勝ち取ることができる。それが職人の未来を切り拓くとの経営理論と、そのために最も必要なのは「愛」だ。との原理原則に基づいたビジネスの概念です。

One Love
”One Love"を見て、社会への憤りと怒りから繋がる革命への想い、国を愛し、自然を愛し、人を愛し、そして音楽を愛したボブ・マーリーの短く、激しい人生が残した偉大な功績について改めて考えさせられました。彼は武力や暴力ではなく、音楽で世界を変えようとしたし、実際にジャマイカで対立する2大政党の党首に握手を交わさせるまでそれを実装しました。ラスタファリの理念を音楽を通じて現実社会の革命に繋げつつあったのは驚くばかりです。革命はいつも怒りや憤り、不条理が根本にあるようですが、決して暴力的な行為のみがその手段ではなく、根底に皆が敵対、対立するのではなく、1つになろうとの愛があれば、人の痛みや悲しみを伴う事なく、革命を推し進めることが出来るのだと再確認できました。革命を目指す私にとっては非常に大きな勇気をもらえるとても良い作品でした。映画館で観られることを強くお勧めします。そして、一緒にレボリューション起こしませんか?
https://youtu.be/15RLs4vfvxg?si=LggqAOC65cGmXE90
_______________
キャリか教育の高校を全国に開設し、教育革命を推し進めています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

