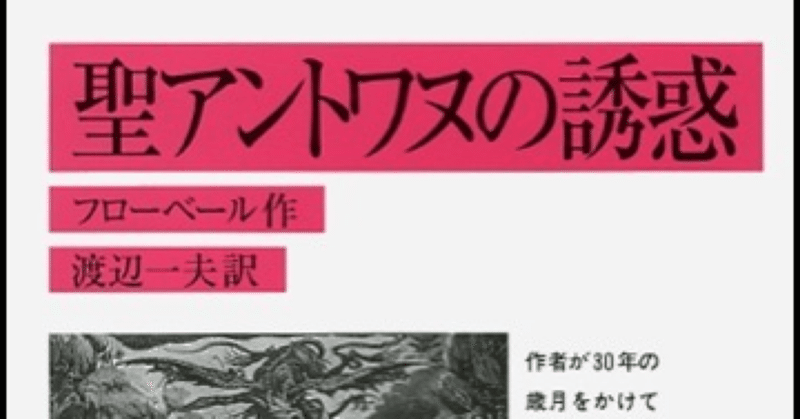
悪魔の誘惑(9/16の日記)
木曜日。
くもり。
昔からの友達と電話。
大学を休学している友人が、家にこもってゲームばかりしているという話。遁世生活を送っているのは僕くらいだろうと思ったら、そうでもない。すこし娑婆から離れているうちに、世の中、コロナウイルスで一変してしまっているのだ。
劇団で知り合ったGさんが、医学部に入るために勉強していると言う話。前に会ったときはデリダだの『万延元年のフットボール』だのを読んでいた、どこか浮世離れした印象のGさんが、どういう経緯で医者を目指すようになったのだろう……と思いを馳せたりする。しかし彼女が白衣を着た姿は、どこかで実際に見たかのようにイメージできる。
フローベール『聖アントワヌの誘惑』(渡辺一夫訳、岩波文庫)。
山奥でひとり修業にはげむ隠者が、さまざまな幻覚=悪魔の誘惑を受けるというお話で、レーゼドラマの形式を取っている。
しかし、実に奇妙な作品だ。
最初は、金、女、権力…みたいな、わかりやすい「誘惑」があらわれ、聖アントワーヌも、あっけないほどコロリとその誘惑に負けてしまう。負けたところで「危ういところだった」と幻覚から覚める。
しかし、やがてその「誘惑」が、異端派や邪教の僧たちの姿を取り始める。神や宇宙の成り立ちについて、キリスト教とは異なる説を唱える人々が登場し、聖アントワーヌが、それに怒って口論したり、危うく説得されかけてしまったりする。
だが、問題は、彼のキリスト教的な信仰が揺らぐところにはない。最初から聖アントワーヌには信仰はない。重要なのは、異教徒たちとの議論が、ついに信仰をめぐるドラマになり得ないことである。弟子の姿をとってあらわれた悪魔は、やがて自ら「知識」と名乗る。あらゆる教義は主人公にとって、知識でしかない。
悪魔「知識」はその後、すべては聖アントワーヌの幻想にすぎないと語るが、それすらも、聖アントワーヌ自身によって、今語られたのは「不可知論」だったと総括される。
不可知論の次には、また別の悪魔たちの幻想が現れ、聖アントワーヌが「生命の誕生」「運動の始源」を見出し得たと叫ぶところで終わる。だが、訳者解説によれば、草稿には削除された結末として、さらに主人公が絶望する場面があるという。
それも当然で、あらゆる感動が「知識」=言葉に落ち込むプロセスには終わりがない。無限に続く悪夢のようなものであって、この作品は戯曲を模して、その堂々巡りを描き出している。
『ボヴァリー夫人』『ブヴァールとぺキュシェ』は、かかる「凡庸さ」を、小説としてそのまま「写実」することによって袋小路を脱している?と言える。
しかしフローベール自身は、すでに『ボヴァリー夫人』を書き上げながら、なぜか本作の方を「生涯をかけた作品」と見做していたという。山田風太郎『人間臨終図巻』に描かれたフローベールの最期は、「エロー…行ってくれ…連れてこい…通りはわかっている」と言って死ぬ姿である。エローとは、その日に彼が知った、ユゴーの住所だった地名。最後まで「知識」だったわけである。
私はむしろフローベールその人に関心がある。
昨晩から、足と肩の激痛に悩まされている。無理やり起き上がって、焼きそばを電子レンジで温めて食べたが、気持ち悪くなった。
(冒頭に病状が表示されると読まれないと気づいたので最後に持ってくることにした)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
