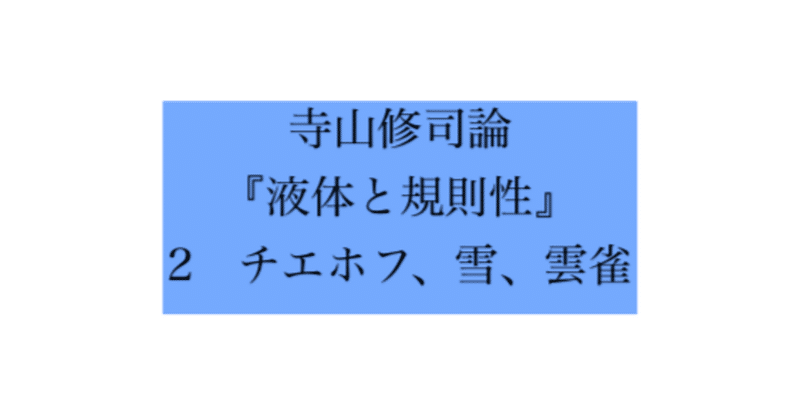
寺山修司論『液体と規則性』
『2 チエホフ、雪、雲雀』
*
寺山はすでに高校生にして
全国の俳句の有志を組織して全国の若き俳句作者たちを率いて
俳壇の乗っ取りを企図し、
大学一年生のときには短歌の新人賞を受賞して世間的な認知を得たが、
その際に他の俳人、歌人の作品からの
盗作や剽窃で作句したという騒動を巻き起こしている。
寺山の本質を早くも露わにしたこの事件を見つめれば、
向日葵の種をさらに一粒蓄えておくこともできるだろう。
「燭の灯を莨火としつつチエホフ祭」(中村草田男)が、
本歌取りの対象となる栄誉を与えられた句である。
この句からは、
明かりを消した部屋に蝋燭をともしながら
チェーホフの戯曲を読んで偲ぼうとする静かな部屋のたたずまいと、
そのなかに浮かび上がる学究の徒の姿が浮かんでくる。
*
ではこれを
万華鏡の中にいれて攪拌するとどうなるか。
「莨火を床に踏み消して立ち上がる
チエホフ祭の若き俳優」(寺山修司)では、
草田男の静謐もほの暗さも鎮魂も
塗り替えられて、
「ところが、ふとやって来た男が、
その娘を見て、退屈まぎれに、娘を破滅させてしまう
—ほら、この鷗のようにね」とつぶやいて
若き女優志望者を愛人へと誘う著名な小説家の役か、
あるいは捨てられて不幸にされてもなお
自分よりはその小説家を愛するという、
かつての恋人の心変わりのなさに絶望して
猟銃自殺してしまう前途有望な小説家の役か、
*
いずれかの華のある役を配されて
『かもめ』へと意気込む青年俳優の出番寸前の一瞬へ、
消された煙草の火が役者の胸の篝火へと燃え移る
瞬間の劇へと書き換えられている。
実は、
寺山修司の作品群そのものが
根源的な動機を欠く空洞の冷気ゆえに
本歌の温風を呼び込んでいるといってもいいだろう。
新人賞応募時の自己紹介で
「埼玉県川口市幸町一ノ三九坂本方、
歌歴皆無なりしも十月『荒野』に参加。
昭和十一年一月青森に生る。
早稲田大学教育学部一年」と書く、
親戚宅に下宿して上京を果たした
*
青森の若き有望俳人は
『父還せ』という
本人の手による稚拙な表題から、
選考者の校閲を経て、
『チエホフ祭』という
デビュー作にふさわしい題名を冠す
新人賞の栄誉に値することとなったのだ。
模倣小僧という誹りを受けた彼は
剽窃が意図的なものであることを弁明しようとして、
現代の連歌、
第三人物の設定などを主張しているが、
そもそも寺山が俳句を始める契機が
文学的でありえるはずがない。
青森には四季などないからだ。
*
彼が育った青森にあるのは、
降り積もった雪を
歩道の端や
中央分離帯に積み重ねる造形の冬、
雪解けを春とよぶ名ばかりの春、
火祭りのある八月を挟んで
朝晩は涼しい夏、
あっという間に冬に浸食されてしまう
瞬間の秋、
そしてまた再びの冬である。
そこには、四季折々の移り変わりに応じて
定期的な循環を反映する
雅びな天然の美などというものもまた
存在しない。
*
青森は俳人を育てる風土としては、
あまりに季節を欠いている。
季節のない街で育った俳句少年は、
高校二年の時の国語の定期テストの
季語を答える問題で、
雲雀を夏に分類してしまったために
満点を逃すという痛恨のミスも犯し、
記念館にその証拠はいまも残されて、
掲示されている。
季節の鳥籠から逃げ出して
それと分からぬまま撃たれた雲雀に哀悼を捧げて、
寺山は次のように歌っている。
「雲雀の血すこしにじみしわがシャツに
時経てもなおさみしき凱歌」(修司)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
