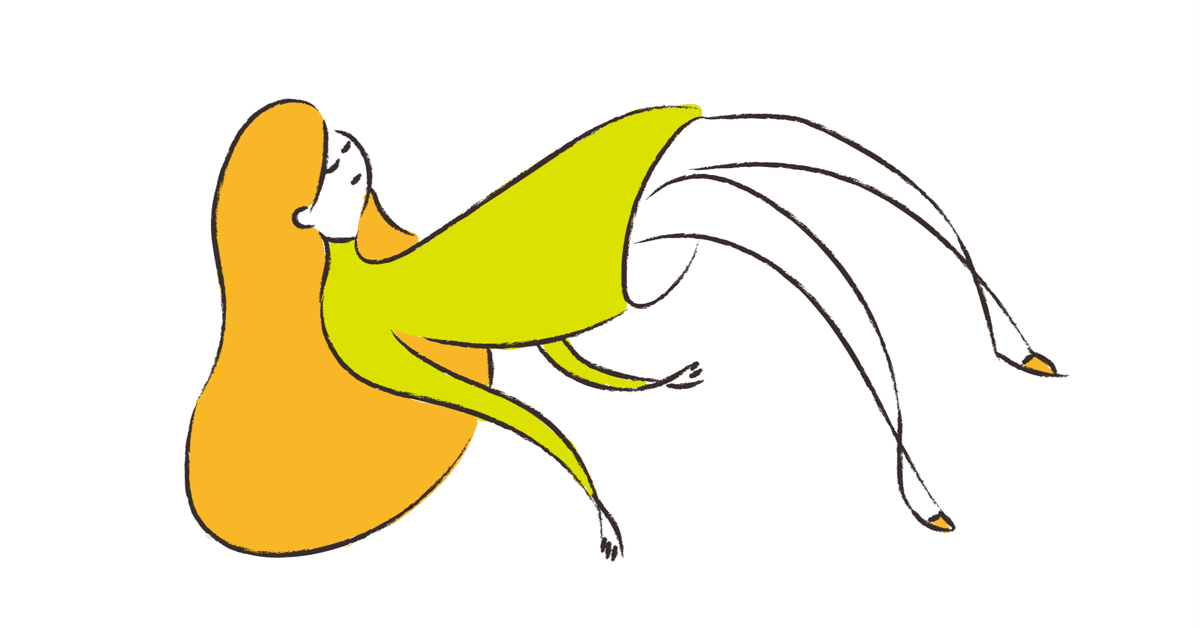
嫉妬にまつわる問い
雛まつり
雛のお節句来たけれど
私はなんにも持たないの
となりの雛はうつくしい、
けれどもあれはひとのもの。
私はちいさなお人形と、
ふたりでお菱をたべましょう。
嫉妬について
冒頭の詩は、わたしが小学生のころに狂ったように読み続けていた金子みすゞの詩である。
彼女の詩には、実に様々なテーマが織り込まれているが、中でもこの詩に織り込まれている「嫉妬」について考えてみたいと思う。
嫉妬はいけないことなのか
嫉妬は、キリスト教の七つの大罪の一つとしても有名である。(参考:
嫉妬、嚙み砕けば「ねたみ」である。大罪として扱われるほど悪いものなのだろうか。
わたしからすればごく身近な感情と言えるものでもある。嫉妬している自分に苦しめられることはよくあるが、それがいけないことであるという認識をもったことは、SNSやメディアや宗教上で言われるほど思ったことはないというのが実情だ。嫉妬がいけないことであると言われるのはいったいなぜなのだろうか?
嫉妬はなぜいけないのか
なぜ嫉妬してはいけないのかという問いを見出した時、真っ先にネットで検索をすることにした。ネットの海には、嫉妬についての記事が大量に存在していた。それだけ悩む人が多いトピックなのだろうということが、検索をしただけでも知ることができた。
まず、東洋経済オンラインの記事では、『「苦しい嫉妬の感情」をスッと消す実に簡単な方法』(参考:
という記事が書かれていることがわかった。
具体的な方法まで提示されて、嫉妬を滅却しようという様は、狂気的ですらあると筆者は感じている。そこまでしてどうして嫉妬をしないように意識する必要があるのだろうか?
そして、はじめの問いに戻れば、嫉妬はなぜいけないのか?この二つの問いについて考えていこう。そして、ここで明示しておく必要があると感じているのが、「嫉妬をしてはいけない理由」という問いと、「嫉妬をしないように意識する必要性がなぜ存在するのか」という問いは、〝相反している〟というところに重要なポイントがあると考えられる。この二つの問いを念頭に置いて読み進めていただきたい。
嫉妬についての検討
エマニュエル・カント
エマニュエル・カントの定言命法の概念を援用(参考:
して、嫉妬という我々に枷のようにがんじがらめになっているしがらみについても説明できそうである。
嫉妬というのは、あくまで人間が作り出した感情的しがらみであって、そこに規範や何らかの決まり・法則などが存在しているわけではないというものである。それについて、メディアが様々なメンタルハックなどを見出してはやし立てているのである。さも、嫉妬することはいけないことであるかのように。そうでなければここまで嫉妬という感情についていたるところでみることはないだろう。
エマニュエル・カントの道徳的な概念を補助線として、それをもとに嫉妬について考える時、メディアが提示する何らかの事柄に従うということ自体がナンセンスというように捉えられるのではないだろうか。そこには、なんの規範や倫理的メッセージはないのだから。嫉妬という感情は、あくまで〝自分の〟感情であり、誰かや何かに決めつけられたり、否定されたりするような類のものでは、そもそもないのである。
嫉妬という私的感情について、外的な価値観を採用することが、そこそこに間違っているとまで言えるとわたしは考えている。強調するが、嫉妬という感情は徹底的に私的なのである。だれかにコントロール可能なものではなく、わたしが折に触れて強調している考え方である、「人は変えることはできない」というのに触れる問題でもあるだろう。それに従って考えるのであれば、社会やメディアが作った〝嫉妬はいけないことである〟という謎の暗黙のルールに縛り付けられる必要はないということだ。このルールは、メディアが我々をコントロールしようとしているに過ぎないとも捉えられるだろう。
まとめると、嫉妬について我々がメディアから学ぶ絶対的な義務などなく、むしろ、メディアが提示する凝り固まった謎のメンタルハックに囚われて己の感情を抑圧する必要はないということである。
ジル・ドゥルーズ
フランスの思想家であるジル・ドゥルーズも、嫉妬について扱っている。
参考:
ジル・ドゥルーズは嫉妬をもシーニュ(記号)
参考:
として捉えている。わたし自身が参考にした頁を読んだ時には、どちらかというと嫉妬を〝感覚的に〟捉えているように感じられてならなかった。
ジル・ドゥルーズは、愛の中に嫉妬を見出したようだった。愛というものも、形がなくとらえることが難しく、また定義もない概念的なものであるという点で嫉妬と共通しているところがある。そして、「愛のシーニュは嫉妬に辿り着く(引用:ジル・ドゥルーズ『プルーストとシーニュー文学機械としての『失われた時を求めて』』)という記述もある。嫉妬は愛の終着点であるとの記述もある。愛についてももう少し深堀りして考察してみたい気もする。何らかの書籍をしっかり読んで考えを深めたい。
しかし、ここで問題となっているのはあくまで嫉妬である。ジル・ドゥルーズから学ぶことはあまりにも情報が少なすぎていまいち掴むことができなかったが、次のトピックではもう少し得ることがありそうだ。
アラン・ロブ=グリエ
アラン・ロブ=グリエは、フランスの小説家であり、映画監督でもある。そんな彼はその著作として『嫉妬』を残している。この作品は、嫉妬について克明に描かれているというよりは、所謂ヌーヴォーロマンといわれるような作品であるようである。この作品の中では、特筆してなにかが起こるわけではないのだが、それでもほんのりと嫉妬の香りが漂っているのである。その嫉妬の描かれ方から、また、ロブ=グリエの描く嫉妬の在り方から、わたし自身の持っている嫉妬観とは別の視点から嫉妬の解釈というものを行っていこうと思う。
嫉妬という感情は炎のように例えられることもあるように、主張が激しいものと捉えることも可能であるが、時には、自分が気付かぬ間に対象に嫉妬の感情をもつ場合もある。
第三者の目線、さながら映画のように、撮影された第三者の目線でなければ気が付かない場合もあるだろう。隠された嫉妬。隠れた嫉妬。そういったものもあるのだ。主張するばかりが能ではない。
結論
本稿のはじめの問いを確認してみよう。「嫉妬をしてはいけない理由」という問いと、「嫉妬をしないように意識する必要性がなぜ存在するのか」という問い。この二つである。これまで、嫉妬についてカント・ドゥルーズ・アラン・ロブ=グリエを検討することによってさまざまな視点を得ることができたが、それによって得られた答えは、この二つの問いは愚問であったということである。
嫉妬というのはコントロールすることのできない、形容不可能で規定不可能な感情であるから、嫉妬をしてはいけないという抑圧的感覚がそもそも間違っており、それに理由など必要がないのだという結論が導き出せる。
二つ目の問いに関しても、抑圧的な感覚がそのまま残った状態で考えられた問いだということがわかるが、コントロール不可能な感情や意識に対する必要性を考えることや、それについて過度に追及すること自体が不毛であるということが、「嫉妬についての検討」で得られたことである。
ある種、本稿での取り組みによってわたし自身の嫉妬観が180度変わったような気がした。
嫉妬について抑圧的になり、コントロールしなければならない・嫉妬はしてはいけないなどと、古く凝り固まった思考をもっていたのは、他でもないわたし自身であったのだ。嫉妬という感情はもう存在している。あるものをどうにかしようという不毛な努力は無駄である。そこにあるものに対して、どのようにみるのか。どこから見るのか。そのような、ある種の自由さが必要なのではないだろうか?
