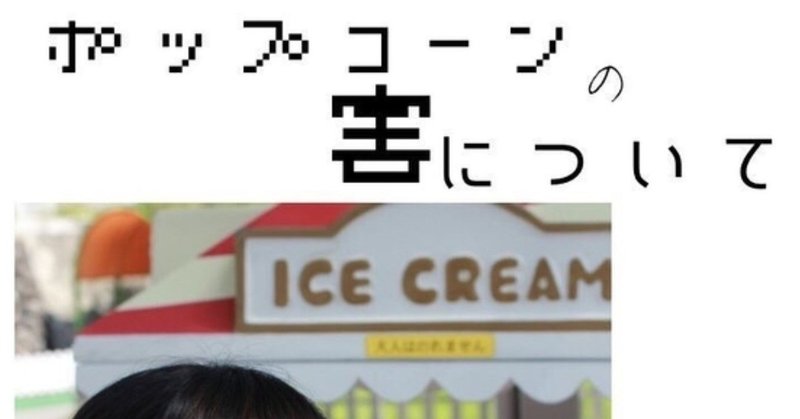
ヴァージン砧 「ポップコーンの害について」
2月2日(日)@上井草(エリア543)
上井草という街は初めて降りたけど、天気の良さもあってか住んでみたくなるような長閑なところ。劇場は一人芝居ということでアクトスペースも小さく、役者はすぐ目の前。
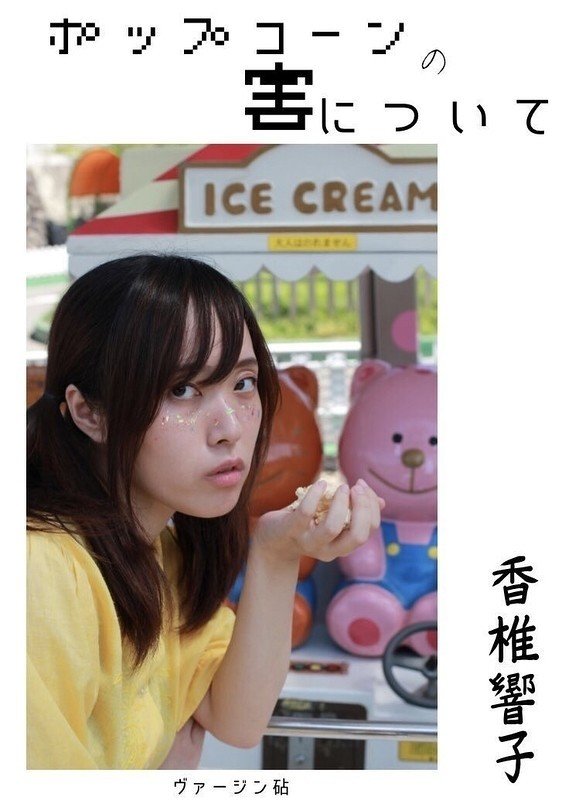
note記事から漂う不穏さ
事前に主宰であり脚本と演出を務めている香椎響子さんの書いたnoteを拝見した。
うん、不穏だ。不穏だけれど、不穏さというのは、演劇な想像力をたくましくする、と思う。
だから一人芝居で、この記事のようなモチベーションがあるとなると、とてもすごいものが、演劇でしか見れないものが見れるのではないかと思った。
○○の害について
ポップコーンの害についてという変わったタイトルは、チェーホフの『タバコの害について』のパロディだ。
『タバコの害について』は、ある男が妻の命令でタバコの有害さについて嫌々講演を行うというもので、講演の話題は妻への不満や自ら不遇さへとどんどん逸れていってしまう。生でみたことはないけれど、日本では、柄本明が一人芝居でやっていたことが有名らしい。
けれど、どちらからというと、チェルフィッチュの岡田利規に『マリファナの害について』という著作があり、これの影響の方があるかもしれない。こちらは主人公が女性で、マリファナを好きな彼氏について話す一人芝居で、『タバコの害について』を現代的に変換したような題材だ。
聞き手の曖昧さ
一人芝居では、「なぜ語るのか」が大事だったりする。舞台上に役者は一人しかいない訳で、通常人間は一人の時に多くを語ることはないので、どう喋らせるかは工夫が必要だ。
『タバコ〜』では、「講演」という設定を用いて、舞台の観客=講演の観客と見立てることで自然と発話をもたらすことができる。
本作では、「講演」というスタイルは採用せず、<パソコンで通話をしているルミという女性>に向けた言葉として、役者に発話を促している。なんだか凄く現代的だ。
面白かったのは、通話相手であるルミという人間の曖昧さ。それが誰なのか、主人公とどういう関係なのか、どこで知り合ったのか、具体的なことは何も語られない。だからルミに対して語りかけているはずの役者の言葉は、どこか宙に浮いたような、モノローグめいた響きが生じていて、その感じがとてもよかった。
それはさながら、SNSという空間に放つ僕たちの言葉みたいだ。Twitterに書き込んだ140文字の向こうには確かに誰かがいる。誰かがいるけど、その輪郭は曖昧な、そういう空気に似ている。
影響を与えること
作中では、社会から隔絶され、孤独感を抱いている少女が、SNSに投稿する言葉を通じて社会や他者に干渉しようと試みる。
少女は自ら望んで一人の状況を作り上げているようにも見えるし、その反作用で他者に枯渇しているようにも見える。(そういう繊細な感情を「あー、彼氏欲しい」の一言で表現しているのが感動的だった)
少女の口からは、メアリー・ベルやエド・ゲインなどの殺人鬼の名前が出てくる。彼らは「他者に影響を与えた人物」として語られる。他者に影響を与えることが「傷つけること」と同義であるあたりに、少女の認知の歪みを汲み取ることができる。
言葉について
冒頭に乗せた作者である香椎さんの文章からは、他者の「言葉」に対する感度の高さが窺える。
ソシュールによれば、人間は言語によって世界を区切っている。「犬」という実体がもともとあるのではなく、「犬」という言葉によって初めて、「犬」(=「四足歩行で尻尾があってワンと吠える人懐っこい生き物」)とそれ以外が区別される。
悪意という曖昧なものは、SNSに投稿される罵詈雑言という言葉によって初めて、他のものと区別され、「うざい」とか「死んで欲しい」みたいな存在感のあるものとして顕在化するんだ。
作中の少女が、悪意ある言葉をSNSに書き込んだ瞬間に歓喜に似た感情を抱いたのは、彼女の想い、が言葉にすることによって世界に認められる次元に浮上したからなんじゃないだろうか。
人間の本性
僕がこの作品を見て、「好きだな」と思ったのは、ヴァージン砧の人たちは、人間は悪い生き物で、本来的に悪があると思っていないところだった。
少女は罵倒の対象であるSNS上の誰かの赤ちゃんに対して、「こんな世界に生まれてくるなんてかわいそう」と言う。(セリフはうろ覚えだけどそう言うニュアンスのことは言っていた)。
この言葉は、人間は本来的には純真なものであると信じていなければ出てこない。「悪意」と言うのは人間の外部似合って、それが人間に影響を与えている、と言う考えが根底にあるんじゃないか。そう思った。
「悪意はどんな小さい種も見逃さない」と言うようなセリフもあった。ここからも、やはり、「悪」は外側からやってくるもので、人間の内側にはない、と言う前提があるような気がして、だから香椎さんと言う方は本当の意味で人間を信じている人なんじゃないかな、と思った。
ファンタスティック・プラネット
後半に怒涛台詞回しがあって、わかるものわからないもの含めたくさんの引用があるのだと思うけど、ファンタスティック・プラネットの話が少し出ていた気がした。
有名なカルトアニメで、ドラーグ族という支配する民族と、オム族(≒人類)という支配される民族が登場する。
本作とも少し重なるような、重ならないような、こういう引用がいちいち好きだった。
ポップコーンの匂いとヴァージン砧
作中で主人公が食べるポップコーンの匂いが劇場に漂っていた。ポップコーンは彼女の脳内の思考と対応しているような言葉もあったが、彼女の脳内が言葉を通じて外部に放たれているように、弾けたポップコーンの香りが劇場内を満たしているのが、比喩的でとても面白かった。
家の近くのコンビニでポップコーンを買おうとしたら売り切れていて、もしかしたらたくさんの人が同じことを思ったのかもしれない、と少し不思議な気持ちになった。
ヴァージン砧のお二人は、なんか本谷有希子の作品に出てくるような感じがして、そう言うことを言われたらあまり嬉しくはないんだろうと言うところ含めて、まるで映画の中の登場人物のような、素敵な魅力があった。
香椎響子さんの作品、次も是非見てみたい!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
