
現実への介入
これは2017年(高専5年)から2018年(社会人1年目)にかけての出来事を2018年末に執筆したものである。
記憶と記録を頼りに、書きとめた。
Medium にて2019年8月に公開した文章の転載となる。

Censor、プロジェクト名である。
このプロジェクトは、僕が 100BANCH というコワーキングスペース(という一言では決して言い表せない)で活動をする中でたどり着いたものだ。
到る経緯は後にし、まずは概要について語ろう。
・・・
2018年にパナソニックが創業100周年を迎えることを機に構想がスタートした 100BANCH は、次の100年につながる新しい価値の創造に取り組むための施設である。未来の実験場である 100BANCH はそういった思想もとに作られた。渋谷という場所や構造、床の素材や照明に至るまで全てが意味を持っている。

この意思は、名前とロゴにも巧妙に組み込まれている。
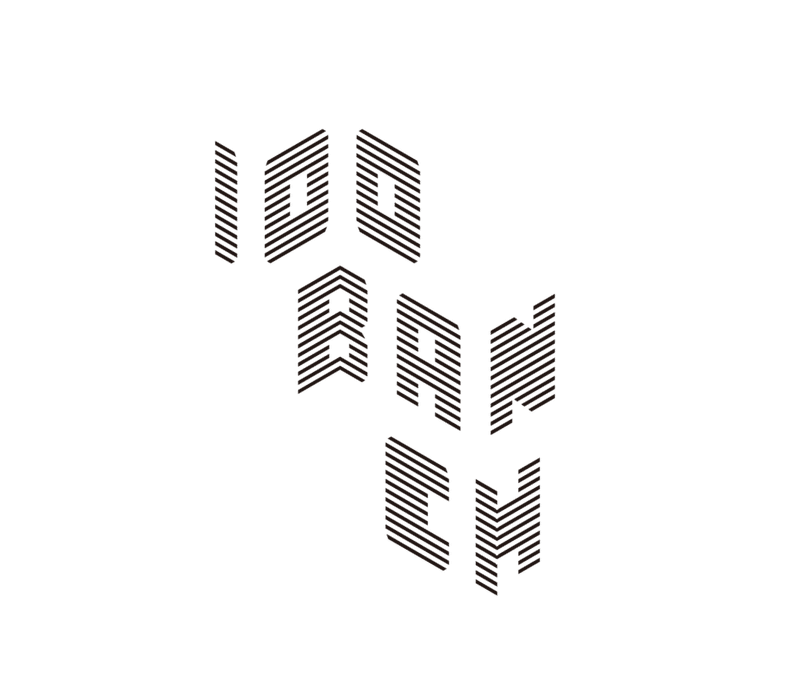
100BANCH という名前は、「まだここにはない、未知の場所」という意味だ。また、エネルギー溢れる人間が集結する「束」を意味する「BUNCH」という英単語に由来している。ロゴを構成する120度に傾いた線は、交差したり束になったりしながら、100BANCH にまつわるさまざまなシーンでサインや装飾として使われている。これからの100年をつくる個性が交差し、渋谷から世界を動かす特異点をつくり出してゆく場所に相応しい名前とロゴになっている。
100BANCH は、そうした意思が束となり交差し新しい価値を想像する。そういったクリエイティブ・コミュニティが活動する実験場なのだ。
コミュニティをリデザインし、
クリエイティビティを演出する
もし、意図的にクリエイティビティを創り出すことができたらどうだろうか。100BANCH では、ジャンル問わず40近いプロジェクトが活動してる。終了したプロジェクトも含めるとその数は200に及ぶ。この束が、交差するにはどうすればいいか、交差する場所には何があるだろうか。
僕は、そこにコミュニケーションがあると考えている。創造的なプロジェクトはそれ自体に価値があり魅力的であるが、もしそれら2つのプロジェクトが交差したらどうなるか。それらは全く異なるジャンルかもしれない。そのとき、誰もが想像しなかった新しい価値が生まれるに違いないだろう。コミュニティとそれらの間に生まれるコミュニケーション、そこにクリエイティブの鍵がある。
15世紀、ヨハネス・グーテンベルグが活版印刷術を発明して以降、コミュニケーションの形は大きく変わり始めた。人は、その多くを視覚に頼るようになっていき、コンピュータやインターネットの発明とともに加速していった。全てのものがインターネットに繋がり、瞬時に大量のデータを送受信する、ポストインターネットといわれる現代ではおそらく当時のコミュニケーションとは大きく異なるはずだ。聴覚から視覚に重点が移りゆく中で失われたものはないのか?同じ場所や空間、時間を共有するコミュニケーションについて改めて考えても良い頃合いであるはずだ。
100BANCH という場所を共有するコミュニケーションでは、温度や湿度、周りの音やその場の匂い、椅子の硬さや机の肌触りまでその全てがコミュニケーションの一部なのではないだろうか。これら全てがコミュニケーションの一部であるならば、そこに介入の、デザインの余地がある。そのためにはコミュニティとそれらの間に生まれるコミュニケーションについて、現状を知らなければならない。
コミュニケーションにおけるそれらの要素がどのように作用し、影響し合い、一部となっているのかを知る必要がある。CENSOR の役割はそこにある。その上で、意図して束が交差するように、結果としてクリエイティビティが、新しい価値が生まれるようにリデザインする。僕は、そうして多種多様な束となり交差し合う場所を、100BANCHという一つの束にしたい。
・・・
経緯に戻ろう。
100BANCH で活動するきっかけは、2017年、僕が高専5年の時に加わったプロジェクトだ。当初は、友人が「教授が在室しているかをインターネットに接続された端末を通してわかるようにする」ということをやっていた。その友人に誘われてプロジェクトに参加した。
僕が参加した2017年初頭、すでにそのプロジェクトは1年ほど経っていた。システムの大枠はできていたが、不在/在室の切り替えが手動だったり、スマートフォンアプリケーションがないなど利便性にいくつか課題を抱えていた。そこからの1年は、それらの課題に注力することになる。高専では、授業は決してモダンと言える内容ではなかったが、多くの人が常に最新技術を追っていた。故に、技術面で苦労することは少なかった。
そんなある日、100BANCH の募集を見つけた。
100BANCH の募集を見つけたのは、偶然だった。Facebook で何気なくタイムラインを眺めていたら1期の募集開始を目にした。僕はすぐにチームに知らせ、応募しようと言った。


当時の応募資料より
次の100年につながる新しい価値の創造に取り組むための施設、には相応しくないプロジェクトだろう。この時は特に外へ向かう力が強かった。僕たちは、採択された。若さもあったかもしれない。運もあったかもしれない。
7月、100BANCH での活動が始まった。
その場所は刺激そのものだった。フロアには、ふんどしを穿く人や着物を着る人、昆虫を食べる人など様々なプロジェクトが活動していた。混沌としていた、それが刺激だった。
チームは、方向性を模索しながらも「教授と生徒」という対象は変えずに開発を進めた。ここではプロジェクト活動期間が3ヶ月と決まっている。8月になるとU22 プログラミングコンテストに申し込んだ。
100BANCHで活動をしていると、時としてそれが社会的に必要とされているものかと考えることが多々あった。ここでは、そのようなことを求めらることがないからだ。
あまりにも限られた、そして具体的な対象を持った僕たちのプロジェクトにとって、それは不安にもつながった。今一度、外の人々の見解を欲していた。
100BANCH での最終報告会は、U22プログラミングコンテストの審査会と同日だったため、生放送を見てもらうことにした。


結果としては、サイボウズ賞、フォーラムエイト賞の受賞。当時の僕たちにとって、それは大きな意味を持った。
もちろん、問題や改善点に関するフィードバックもあった。多かったのは、セキュリティについてだ。部屋にいる/いないは、ただの1と0にすぎない。しかしそれは、あくまで個人情報、プライバシーに関わるものでるということ。BLEビーコン(当時使用していた技術)は特性上、受信すれば簡単に在室状況を操作することができてしまう。
審査会があったのは、2017年の10月。そこからの2018年3月までは主にセキュリティの強化に努めた。
そうした活動を通して、僕の中で徐々に現れてきた考えがあった。
高専を3月に卒業し、すでに8月になっていた。
・・・
まず、頭の中にある瞭然としない考えをどうにか言語化することにした。概要を書くのには苦労した。これだけで伝わるとは思っていない、文章力も含め僕には力不足だった。ただ、それは方向性を迷っても常に原点に戻る役割を担っている。
プロジェクト名は、大切だ。その単語には、多大ない意味を込めることができる。音の響き、文字の形、長さ、その全てが意味を持つ。そして何より、名前を得て初めて他に類のないただ一つのものとして成り得る。
Censor
僕たちは、これを”ケンソル”と呼ぶ。まずは、英和辞書で引いてみよう。
Censor
cen・sor / sénsɚ
名詞: (出版物・映画・信書などの)検閲官.
動詞:出版物や映画などを、検閲する.
現代では、主に出版物に対する検閲として使われる。
統計学の起源の一つにローマ時代という説がある。当時、ローマではCēnsor(ケンソル)と呼ばれる監察官が政務官の職の一つで存在した。彼らは、Cēnsus(ケンスス)という調査を実施し、市民の財産や人口、男女の数などを把握した。これはいわゆる国勢調査のことであり、Census(センサス)として現代でも言葉の由来となっている。今から何千年も前にすでに現実を平面で捉えていたのだ。
この役職の名前がプロジェクト名となっている。そこには確かに監視社会の匂いがあるかもしれない……。
次にデザインを考え始めた。アイデンティティをより視覚的にするためだ。ロゴデザインは、知っている中で僕がもっとも適していると考えたデザイナーの山本文子に依頼した。
Messengerで何度かやり取りをして、僕がやろうとしていこと、ヴィジョンやミッションを伝え、いくつかのプロトタイプを経た。

プロトタイプの一例だ。3番は僕のお気に入りだった。
(僕も含め、多くの人は池田亮司を想起せずにはいられないだろう)

最終的なデザイン
自然を量子化する。
波形を模したシンプルな形で表現したロゴだ。これには、100BANCHにおける活動以外にも、様々な事象を離散的な値に近似し、捉え、そしてまた連続的な値として還元していくことの全てが含まれている。
僕がやろうとしていることは、監視社会なのだろうか。
そこには手続きの存在しない、介入がある。
個々の物理的な現象に注目すれば、運命論に近いのかもしれない。
これからも、考え続ける。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
