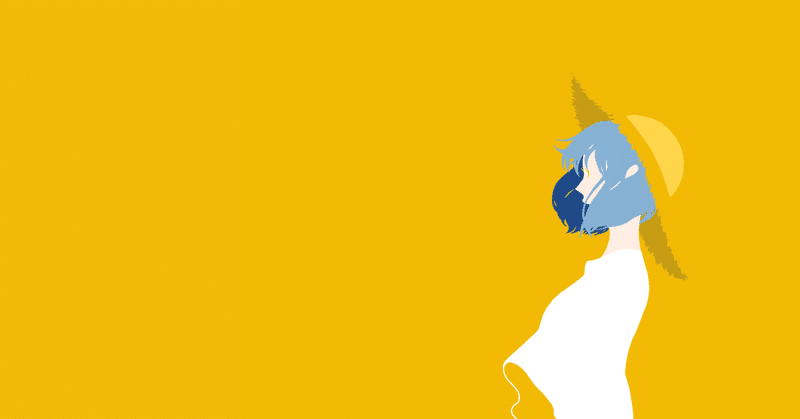
掌編/姉
レースのカーテンが揺れていた。もとは真っ白だったその布は、柔らかく風を纏いゆらゆらと乳白色の陰影を浮かべ、くすんだ色が経た時の長さを感じさせた。
窓を開けたのはいつぶりだろう。閉ざされた扉の向こうに、この部屋はずっとあり続けていた。
◇
姉は美しい人だった。真白なカーテンの脇に立ち、ゆるりと吹き込んだ風がその髪をかきあげ、陽を透かし、ふと彼女が私に気づいて身をかがめると、白い肌に朱の唇が際立っていた。
――ヒロコのほっぺはりんごみたい。
口の端をあげ、ガラス瓶からいくつか飴玉を取り出して私に握らせる。姉の手はいつもあたたかかった。
テーブルには封のあけられた手紙があり、便箋には右上がりのひどい癖字で何か書いてあるようだった。私がのぞき見ようとすると姉は優しくダメよと言い、するりとその紙を隠してしまう。ヒロコはこっちと差し出されるのは裏の白いチラシと色鉛筆で、居間でお絵描きしようと手を引かれた。
ときおり、姉と二人で出かけた。手をつなぎ歩く海沿いの道で、「仲良しねえ」といつも同じ言葉をかける干物屋の小母さんがいた。姉は遠目にその干物屋をうかがい、避けるように足早に海だけ見つめて歩いていた。そうして、その先にある円筒型の古びたポストに手紙を投函するのだった。
幼い私に読めたのは宛名のほんの一部。誰への手紙なのかと問うても「遠くのお友達よ」と、姉がそこにある漢字の読み方を教えてくれることはなかった。
一度だけ「おねえちゃんはあのおばさんが嫌いなの」と聞いたことがある。ポストの前でふたり佇み、ちらと姉が背後を振り返るのにつられて干物屋に目をやると、そこには前掛け姿の小母さんが立っていた。手を振ってくるその人に、姉は会釈を返した。
――そんなことないわ、おばさんはいい人よ。
諭すように私に言った姉はどこか居心地悪そうで、私はふうんとうなずいて、もうこの話はしないことにした。
あの頃の姉はたしかに姉であり、そして一人の大人の女性だった。
◇
ある朝、それは何かの予感のように、私は普段よりずいぶん早く目を覚ました。まだ父も母も布団のなかで、体を起こすと母が「なあに」と眠そうに目をこすり、私はトイレと答えて部屋を出た。
階段を降りると、姉の部屋の扉がわずかに開いており、そろりと中をのぞき込んだ。二日に一度は共に眠る姉のベッドに、私はこの時もぐり込むつもりでいた。
すると、潮の匂いが風とともに頬をなでた。カーテンが風をはらみ、半分ほど開いた窓がカタカタと小さな音を立てた。波と、車の音がかすかに聞こえた。「おねえちゃん」と口にしながら、そこにあのぬくもりがないことは明らかだった。
不意に、姉はいなくなったのだと悟った。残り香をすべて消し去るように風を入れ、朝の冷やりとした空気が、ここには誰も戻ってこないのだとささやいた。
テーブルのうえにはガラス瓶があり、飴玉は目一杯に詰め込まれていた。私はその飴を一日にひとつずつほおばり、それが半分ほどになっても姉が戻ってくることはなかった。
両親が慌てふためいたのは姉がいなくなったその日だけで、父がかけた何本目かの電話のあと姉の部屋に二人でこもり、そうして出てきた時には、「おねえちゃんはしばらくおでかけだから、さみしいかもしれないけどがまんしなさい」と、父は私の頭をなでた。母は口をつぐんだままで、口元に小さく笑みを浮かべていたけれど、その目元は赤く腫れているようだった。
父が出張で家を留守にしたある日、私は母が買い物に出かけている間にこっそり姉の部屋に忍びこみ、あの手紙を探した。けれど、姉が持ち去ってしまったのか、それとも両親が隠してしまったのか、一通たりとも見つけることはできなかった。
◇
姉が姿を消してひと月ほども経った頃だったろうか。母と手をつないで海沿いの道を歩いていると、干物屋の小母さんが「元気?」と声をかけてきた。母はいつかの姉と同じように居心地悪そうな笑みを浮かべ、ちょっと待っててねと私を遠ざけて二人で話しはじめた。
道の端で寄ってきた野良猫と戯れながらチラチラと二人の様子をうかがい、何度か小母さんと目が合った。私はどこか居心地悪く、姉があの小母さんを避けた理由がなんとなく分かるような気がしたのだった。
私が姉からの手紙とも呼べない小さな紙片を見つけたのは、ガラス瓶のなかの飴玉がもう残り少なくなってからのことだ。瓶の底に小さく折りたたまれた紙があり、「ヒロコへ」と青みがかったインクの文字が見えた。
――ごめんねヒロコ。いつか必ず迎えに行くから親子三人で暮らそうね。
走り書きの文字を前に、両親には見せてはいけないものだと思った。
どくどくと心臓が鳴り、頭は真っ白になる。階下から私の名を呼ぶ母の声が聞こえ、我に返ってガラス瓶の底にその紙を戻した。私はその瓶を部屋に持ち帰り、自分で買った飴玉を蓋が閉まらないほどいっぱいに詰め込んで引き出しの奥にしまい込んだ。
――親子三人。
その意味から目を逸らし、私はあの部屋のことを頭の端に追いやった。小学校を出て中学に入り、高校になっても姉からの連絡はなかった。ときおり姉に似た後ろ姿を見つけては逃げるように駆け出し、そっと後ろを振り返ってその人ではないことに胸を撫で下ろした。と同時に言いようのない寂しさが雨のように降りそそぐ。
干物屋の先のポストはいつのまにやら撤去され、そのうち干物屋の暖簾が軒先に掛からなくなり、デイサービスの車がその前に停まるようになった。小母さんと最後に挨拶を交わしたのがいつだったのか、よく覚えていない。
この頃になると、自分が誰のお腹から生まれたのか、その事実から逃れることは考えなくなっていた。懐かしいぬくもりを私の心は変わらず求め、その一方で置き去りにされたという気持ちは拭い去ることができずにいる。
姉――いや、「母親」が突然迎えに来るかもしれない。そんな緊張もいつしか麻痺していた。
◇
高校の卒業式が終わったのは二週間ほど前のことだ。私はまだ、あの日の姉の年齢にはとどかない。そして、今日この家を出る。
レースのカーテンが揺れ、潮の匂いがした。
キィとドアの軋む音とともに、ヒロコと名を呼ばれて振り返る。ドアの脇に立つその人は、どこか淋しげな笑みを浮かべていた。
いつだったか、引き出しの奥にしまっていたガラス瓶の色とりどりの飴玉が、瓶のなかで微妙に色の位置を変えていたことがあった。あの走り書きの紙切れは瓶の底に入れたままで、そのとき私はふと肩の荷が下りたように感じた。
両親から姉の話をしてくることはなかった。もともとこの家の子は私一人だったというように、姉の存在は部屋のなかだけに閉じ込められていた。けれどその部屋はとっくの昔にもぬけの殻だった。私はそのことをようやく今になって知ったのだ。鍵などかけられてはいないのに、頑なにそこに立ち入ることを拒み、目をそらしていた。
いつの間にかタブーになっていた「おねえちゃん」という言葉を耳にしたのは、昨夜の夕飯のあとのことだ。
「ヒロコ、おねえちゃんに会いたいか?」
緊張しているのか父は膝のうえでぎゅっと拳を握りしめ、食べ終わった食器を手に椅子から立ち上がった私を、母は縋るような眼差しで見上げていた。
言葉を失った私に、母はエプロンのポケットから一通の封書を差し出す。宛名は母の名前で、裏を返すとそこには姉の名が、知らない名字の下にくっついていた。その横に右上がりのひどい癖字で男の名が並んでいる。
私はそこにある文字を見つめ、自分が二つに引き千切られるような感覚をおぼえた。裂けたのはその手紙だ。衝動のままに破った封書を手に自室に駆け上がり、引き出しをあけた。とっくの昔に色をなくし、紙片だけがポツンと取り残されたままのガラス瓶。それを両手で掴んで、思い切り床に叩きつけた。手紙もくしゃくしゃにして壁に向かって投げた。その音を聞きつけたのか、私の泣き叫ぶ声が階下まで響いたのか、勢いよくドアを開けて部屋に飛び込んできた両親は、散乱するガラス片を脇に避け私を抱きしめた。
きっと、あの時から私の時間は止まっていたのだ。溜め込んだ十年分の涙は、海の水のようにしょっぱく、そして姉の手のひらのようにあたたかかった。
◇
カーテンが風をはらみ、半分ほど開いた窓がカタカタと小さな音を立てた。波と、車の音がかすかに聞こえる。
「なあに? お母さん」
母はまぶしげに目を細めた。自分の口から出た「お母さん」という声、その言葉にはこれからも違和感が添いつづけるのだろう。母であり、母でない人。その手にはテープで繋ぎ合わせたあの手紙があった。皺をのばした小さな紙片とともにそれを私に握らせ、両手で私の手を包み込む。
あの人は、この手のぬくもりを覚えているのだろうか。私のぬくもりを懐かしむことがあるのだろうか。
まだ読むことのできないその手紙は、けれど確かなぬくもりをもって私の手のなかにあった。それをスーツケースの奥にしまい込み、私は生まれ育った海沿いの家をあとにした。
――end
よろしければサポートお願いいたします。書き続ける力になります!🐧
