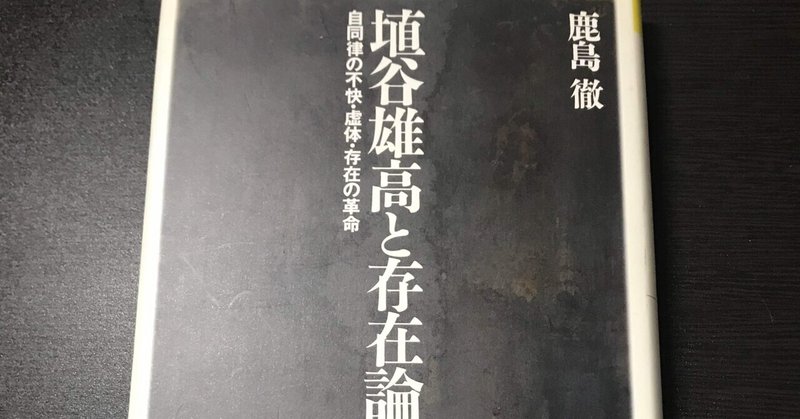
書評:鹿島徹『埴谷雄高と存在論-自同律の不快・虚体・存在の革命-』
埴谷雄高を存在論の見地から読み解く文芸評論
今回ご紹介するのは、鹿島徹『埴谷雄高と存在論-自同律の不快・虚体・存在の革命-』という文芸評論。
『死霊』という文学の斬新性と想像力を高く評価する鹿島であるが、「存在論」という見地から埴谷を見たときに問題視せざるを得ない点が確認されるという指摘を展開する。
まず、『死霊』の出自、執筆開始当初のモチーフを、アフォリズム集『不合理ゆえに吾信ず』から読み解くことから開始する。
そこに読み取られるのは、「存在」という語彙の持つ「繋辞」としての側面、即ち「である」に対する不快感だという。狭義の述定に限らず、所謂同一性言明(埴谷の言葉を用いれば「私は私である」といった「自同律」)すらも、ある種の束縛的規定を伴う。「不快」は、人間が結局その規定形式から脱却し得ないというところに生じる。これが所謂「自同律の不快」である。鹿島はこれを「前-存在論的根本気分」と呼ぶ。
抗い得ぬ繋辞としての「存在」、それに対しせめてもの「平手打ち」を食らわせてみせようという意識から『死霊』の執筆は始まる。その方法は、存在論におけるカント的二律背反をドストエフスキー的ポリフォニー性によって極限化することにあった。
しかしよく指摘されることであるが、『死霊』は前半と後半とでかなりトーンの異なる作品である。具体的には、『死霊』内における「存在」の意味が、「繋辞としての存在」(「である」)から「現事実的存立」(「がある」)へと変遷していく。
これにより、当初のポリフォニー的な性格がモノローグ的なものに変質していくことになったという。具体的には、「存在への平手打ち」を志向することから、積極的な「新たな存在形式の想像」「存在の革命」への志向へと変わっていくこととなった。
何故このような変質が生じたのか。鹿島は執筆期間の断絶や長期化といった安直な解で済ますことなく、精緻に埴谷の文献、インタビューを辿ることでその原因を示していく。
まず前段として、直接の原因ではなくあくまで変遷が生じ得る隙の問題であるが、埴谷自身が「存在」の意味を積極的に明示してこなかったことがあげられる。それ故、埴谷が「存在」という言葉に込めた意味は容易に変遷しうる状態にあったと言える。
その上で、直接の原因として以下の二点があげられている。
一つは、同時代人、殊にサルトルと武田泰淳からの影響である。同時代人のテーゼから受けた衝撃が「存在論」の問題を独自に掘り下げる方向へと向かわしめたのではないかと指摘する。
もう一つは、「死者の贖い」の問題である。生と死を隔てる根本的な壁を突破するには、「存在形式」それ自体を解体することに向かわざるを得ないことになる。
※因みに余談であるが、「死者の贖い」問題は実は『死霊』執筆当初からのモチーフの一つでもあった。つまりモチーフからしてポリフォニー的であったのが『死霊』の特徴の一つでもある。
この「存在」の意味の変質が『死霊』という小説に何をもたらしたか。鹿島は、前述のポリフォニー性の退化に加え、「前-存在論的根本気分」であった「自同律の不快」が結局伝統的形而上学の枠組みの中に取り込まれてしまったと指摘する。
さらに、この変遷によりもたらされた二律背反の緊張感の減退に追い討ちをかけたのが、埴谷自身による物語の「個人史への回収」、つまり作品および思想を個人的な体験へと紐付けるような言明の展開であった。これにより『死霊』は、一個人の感覚の表明に萎縮し、読者を同一気分に巻き込む訴求力を失ってしまうことになったと指摘する。
本著の秀逸な点は、埴谷や『死霊』をはじめとする彼の作品群を一切知らずとも、「存在論」が如何なるものかを概観できる点にある。その意味において、文芸評論という枠に押し込めるにはもったいない著作である。
読了難易度:★★★☆☆
『死霊』の問題点明確度:★★★★☆
「存在論」概観度:★★★☆☆
トータルオススメ度:★★★☆☆
#KING王 #読書#読書感想#読書記録#レビュー#書評#文芸評論#日本文学#鹿島徹#埴谷雄高と存在論#埴谷雄高#存在#存在論#繫辞#現事実的存立#である#がある
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
