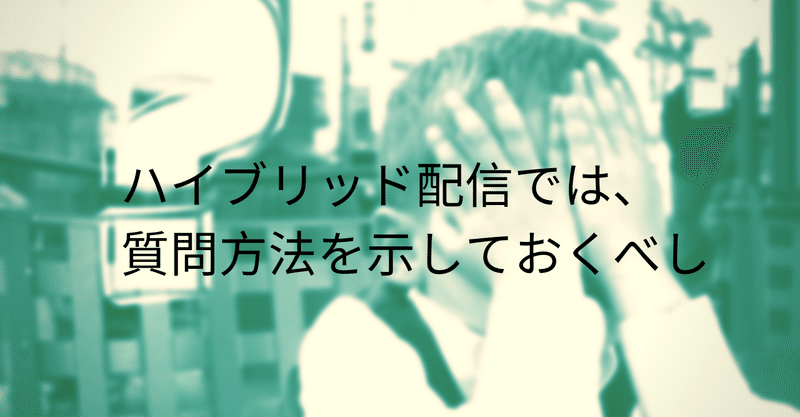
その14:ハイブリッド配信では、特に質問方法を示しておくべし
ハイブリッドは配信では、会場とオンライン上それぞれれに参加者がいます。オンラインだけや、会場だけのイベントより、イベント進行が複雑です。このため、よりスムーズで効果的なイベント運営のために、イベントがどう進行するのか、特にどう質問するのかを参加者に伝えておくことが、一層重要になります。
消極的だったが、やってよかった
今回、私が初めて取り組んだハイブリッド配信では、事務局である私は、質問方法のスライドを1枚共有しながら、1分ほど講演開始前に説明しました。結果として、おおむねスムーズにイベントが進行しました。
最初は、質問方法の説明に消極的でした。しかし、講演者の方から「説明しほしい」と言われて、やることにしたのです。やってよかった…。
さて、どのような方法で参加者に質問方法を周知するのがよいでしょうか?
タイミングは事前告知と講演の直前
一つは、イベント告知する段階でイベントの進行ルールを示すことです。インターネット上で告知するのであれば、その告知ページにそのルールを示すのがよいでしょう。
もう一つは、当日、事務局からの説明として、「講演直前に」質問方法を含む進行ルールを説明することです。数分間、手短にかつ効率よく説明しましょう。今回のイベントで採用したのは、この方法です。
加えて、補足的かもしれませんが、蓋絵に表示してしまうのも一法です。早めにアクセスした参加者は、一読してくれるでしょう。
具体的な周知内容
参加者には具体的などんたことを伝えましょうか?例えば、質問方法に関する次のような内容です。
・「オンラインの方は、質問はQA機能を使って事務局あてに送信してください。講演の開始から質疑応答の終了まで受付いたします。」
・「オンラインの方は、質問はマイクで受け付けますので、挙手ボタンをクリックしてください。挙手ボタンを押すのは、講演直後からにしてください。質問前に必ずマイクをご確認ください。指名され質問が終わったら挙手ボタンを再度クリックして手を下げてください。」
・「会場の参加者の方は、質問がある場合、講演後に挙手ください。座長が指名したら、会場前の法にあるマイクまで進んでご質問ください。」
フィードバックについても注意しておきたい
ちなみに、伝えるべき内容は、質問方法だけとは限りません。配信プラットフォームによっては、フィードバック(「いいね」「笑い」など)を送る機能もあります。それを使っていいのかなどもルール化して説明しておくといいでしょう。イベントの性質にもよるでしょうが、「ぜひフィードバックを講演中にたくさん送ってください!」と伝えて、イベントを盛り上げるのもいいかもしれません。
以上のような内容を丁寧に決めておいて、参加者に伝えるとともに、座長(進行役)の方ときちんと共有しておけば落ちがありません。
質疑応答は参加者との重要な接点
これらを怠ると、質疑応答がうまく運ばないリスクが高まります。また、積極的な参加者ほど、質問をしたいと考えてますし、満足のいく質疑ができないと、何かネット上でネガティブなコメントを発信してしまうこともありえます。質疑応答は、参加者との重要な接点です。慎重に調整しておきましょう。
では、ビーダゼーン!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
