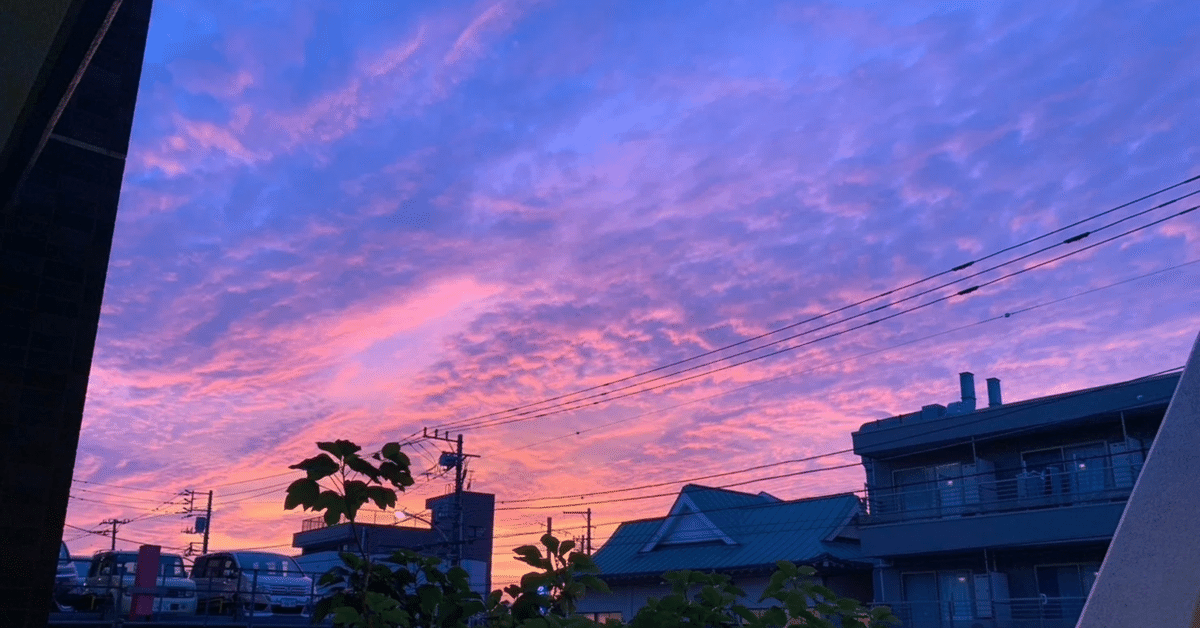
文章と意見とそれにともなう判断について
人のいっていることを正しく、つまりよく判断するのは難しい。私たちは自然と平衡を保とうとするので、極端を嫌うし、突飛な意見も嫌う傾向にある。わかるというのは、さまざまなことを自分の持っている知識と結びつける適切に配置することにほかならない。だから極端だったりすると、結びつけるのが難しくなる。
ところで、私たちはどういう意見を取り入れ、どういう意見をそんなよくないとして排除するのだろうか。証明がされているというのはもはやあまり説得力を持たない。論理が矛盾してないからだろうか。しかし初めの部分というのは前提なので、とりあえず受け入れねばならない。だから私たちは何か別の感覚で、この意見はいいとか悪いとか決めていることになる。好き嫌いだとしても、どういう意見が好まれ、また嫌われるのだろうか。
だから一つ考えられるとすれば、意見というのはいつでも政治的であるということだ。つまり立場を明確にし、自分の立場に合うものであれば取り入れるが、それ以外は排除するという見方だ。確かに意見をいうというのは相手を説得しようとしてのことだし、そこには理性主義的な意図がある。例えば、何々した方がいいという提案的な意見は、それをいえば行動を変えてくれるというのを前提にしている。それは主知主義ともいえる。確かにいってわからない人には何をいっても無駄だろう。
文章を書くというのは以前書いたように伝える形式に則るということだ。そしてそれのためには抽象化が必須になる。つまりその人だけに適応することは削ぎ落とされてしまう。例えば性に関することが下品とかセンシティブとされるのは、その人の普通や体験がそのままは相手に適応されないからだ。それほど実は私たちは異なっている。
だから、必然的に誰にでも当てはまることが正義とされがちだ。確かに個人が大事にされるべきという意見もあるが、結局のところ、その意見はみなに浸透しなければいけないので、意見になった時点で普遍主義だといえる。本当の個人優遇者というのは人の意見など聞かないからだ。
まとめよう
意見を正しく判断するのは難しい。
人は意見をいうとき言葉を使う。
意見はいつでも政治的である。
ということはその時点で普遍主義、理性主義、主知主義の立場を取っていることになる。
問:意見を人はどのように正しく判断しているのか。
解:意見の時点で政治的、普遍主義、理性主義、主知主義であり、説得力があるものがよしとされている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
