
言語の生物学的基盤: CPUとHDD
ヒトの脳をコンピュータに例える議論はあるが、どこが中央処理装置(CPU)で、どこが外部記憶装置(HDD)であるのかを分けて論じている例はない。僕は大脳皮質がHDD、脳室内免疫細胞ネットワークがCPUだと考える。
大きな脳は何も書き込まれていないHDD
ヒトの大きな脳のなかには生まれながらに、生成文法の規則やホモデウスの深淵な知恵が書き込まれているとチョムスキーやハラリは主張する。この考えは正しいのだろうか。
ヒトの脳容量はチンパンジーのおよそ4倍ある。そこに深淵な知恵が詰まっているから、ヒトはチンパンジーより高い知能をもつと常識的に思われている。一方、ヒトより大きな脳をもつ象やクジラがヒトより高い知能をもっているとは思わない。脳容量がすべてではないというのも常識だ。ヒトは自分勝手で、自分に都合のよい常識を振りかざす傾向があり、自分が偉いと思いたがる動物である。
自分自身ふりかえってみると、生まれながらに知っていたことは皆無であり、むしろ生後の教育と学習の結果、知り得たことばかりだ。ヒトの脳は大きいというが、もしかしたらそれは、生まれてからコツコツと学んだ知識を記録していく大容量の白紙のノートブックではないか。
目をキラキラと輝かせて世界と向き合っている赤ちゃんの様子から、ヒトが生まれながらに好奇心をもつことは確かめられる。ヒトは、学ぶ喜び、知る喜びに突き動かされて学習する本能をもつ。たとえ昔話や子守唄を聞かせてくれるおばあちゃんに恵まれない核家族家庭の子どもでも、自然と学びを求めるものである。ヒトは空っぽの大脳皮質に知識を書き込むことを喜びとする「学ぶサル」なのだ。
悪い遊び、間違ったことを丸暗記させる教育、点数だけに重きを置いた受験勉強と親の介入、子どもの自主性を尊重しない教育カリキュラムなどが、子どもたちを勉強嫌いにさせるのだ。
論語にも「子曰く、我れは生まれながらにして之を知る者に非ず。古(いにしえ)を好み敏(びん)にして以て之を求むる者なり」(述而第七)という言葉がある。「私は生まれながらになんでも知っている者ではない。昔のことが好きで、敏感にそのなかから学びを求める者である。」と、生後の学習が大切であることを示す。学ぶべき正しいことを見きわめて、それを自分から求めて学ぶ態度こそ、孔子が推奨した「温故知新」の生き方である。ヒトはそう生きる本能とともに生まれてくる。
大脳皮質が巨大な白紙のノートブックであるならば、それはHDDのようなもので、処理能力はない。ならば、CPUはどこで、言語はどこで処理されているのだろうか。現在、言語は大脳皮質で処理されるというのが通説だが、実は、それについての細胞・分子レベルの仮説は存在していない。言語は本当に大脳皮質で処理されているのだろうか?ほかの可能性はないだろうか?
脳室内のBリンパ球がCPU
僕は2012年から、言語は脳室内で免疫細胞Bリンパ球が処理しているという仮説を提唱している。国内のみならず、世界各地で開催された言語学の国際学会でも発表して、誰からも反論や疑問を呈されていない。
言語を話したり、ものを考えたりする精神機能が脳の一番奥にある4つの脳室(左右の側脳室、第三脳室、第四脳室)に局在することは、ヘレニズム時代に生体解剖したヘロフィロスや、ローマのガレノスがそれを観察した。ガレノスの著作によって、脳室局在論は、18世紀終わりころまで一般に信じられていた。しかし、ガレノスは脳室内のどの細胞がどの分子構造をつかって、意識のネットワークを構築するかまでは解明していない。
脳室は弱アルカリ性の透明な水溶液である脳脊髄液が満たす。(保 2006) これは4つの脳室に隣接する脈絡叢で作られ、側脳室 — モンロー孔 — 第3脳室 — 中脳水道 — 第4脳室 — ルシュカ孔・マジャンディー孔 — 脳槽 — 硬膜静脈洞を流れ、くも膜から静脈に吸収される。
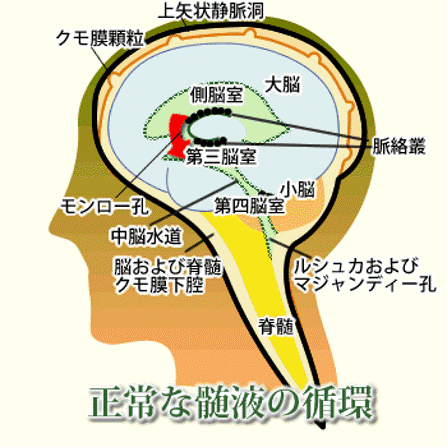
左右の側頭室の脈絡叢は、前頭葉、脳梁、尾状核、 脳弓、頭頂葉、前角、脳梁、透中隔、視床、下角 (海馬)、後頭葉白質、後角、側頭葉と接点をもつ。 第3脳室の脈絡叢は、視床と視床下部、視床間橋、 第4脳室の脈絡叢は小脳と延髄と接点がある。さらに脳脊髄液はクモ膜下で大脳皮質と接する。つまり脳脊髄液は、脳のほとんどの部分と接点をもち、新皮質と辺縁系を結びつける脳内の「情報スーパーハイウェイ」なのだ。
脈絡叢は、キルト地のような構造で、大きな分子が脳脊髄液中に入り込まないよう制御する。おかげで脳脊髄液は、無色透明で澄んでいる。その中にBリンパ球がわずかながら存在することが、最近明らかになった。Bリンパ球はメモリーB細胞とも呼ばれるが、言語処理に必要な能力をすべてもっている。(イェルネ、1984)
以上のことを頭の中にいれ考えているうちに、脳室内免疫細胞ネットワークが脊髄反射と言語処理を司るという仮説が生まれた。
保智巳 他(2006) 脳室の感覚器官:室傍器官ー室傍器官と下垂体との関係 比較生理生化学会誌 23:143-152
イェルネ(1984) Jerne N.K. The Generative Grammar of the Immune System (筆者が試訳したものが読める。P66-71参照)
トップ画像は、脳室系の立体図。脳外科医澤村豊のホームページより
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
