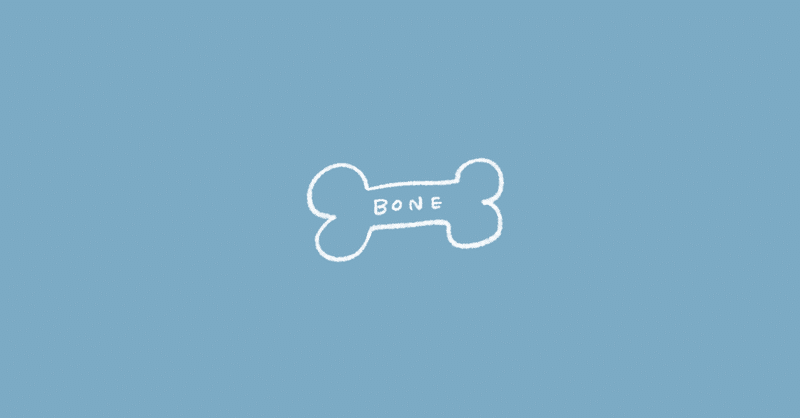
骨格標本の作り方4 骨にする
山で動物の死骸に出会った。
そんな時は,ぜひ骨格標本に。
そのために,いつでもポリ袋を持っていると便利。
メメントモリ。
死。
汚れやけがれ、避けるものとしがちだけど、身近に感じておくことって大切だと思う。
死を身近に感じられる遊び、趣味。
骨格標本
骨格標本づくりのノウハウまとめのnoteです。
今回は、ウジやらろう化、カツオブシムシなど、
一般的に気持ち悪い内容もあるので、向いてない方は、お控えください。
4.骨にする
けものの標本は、毛皮の標本と、頭骨標本を作るのが普通のやり方らしい。
そのため毛皮のはがし方や、保存の仕方には、決まった方法がある。
(1)砂に埋める
地面に穴を掘って、きれいな砂で埋めて何ヶ月かたってから掘り出す。
シカくらいの大きさまでなら、ひと夏こすときれいに骨になる。
いい場所さえあれば、だれにでもできて簡単。
やり方:
1.皮を剥ぐ。内蔵、筋肉もできるだけとる
2.広い穴を掘って、埋める。
3.前足、後足は、胴体から切り離して、埋めた方が掘り出す時、やりやすい。
埋め戻す時は、きれいな砂を入れる
4.犬に掘り返されないように、金網をかぶせる
5.まつ
6.慎重に掘り出す
ポイント:
・穴の広さ
穴の大きさはできるだけ広くするのが良い。
穴が狭く、深く掘った穴の場合、穴の浅い所では骨になっているのに、深い所では、まだ肉がのこっているということになりやすい。
また、狭い穴に骨を重ねておしこむと、掘り出しにくく、小さい骨をなくしてしまう。
・掘り出し方
掘り出す時には、少しずつ砂を掘って、骨の1部分が見えたら、そこをたどって体全体が見えるように掘る。そのあとで、1つ1つの骨の包みを順番にとりあげる。こうすれば、小さな骨もなくさずにすむ。
注意点:
・埋めた場所
正確な地図を作っておかないとどこに埋めたのかわからなくなってしまうので注意。
・色移り
土の色が移る。海岸や川原の砂のようなきれいな砂をもってきて、その中に埋めるのが良い。
・掘り起こされる
犬などの動物に、掘り出されてしまうことがあるので、注意。
埋めていても、人間にはわからない匂いでわかる動物も居る。
(2)ウジに食べさせる→水に漬ける
ハエの幼虫(ウジ)に筋肉や内臓を食べさせる方法。
やり方:
1. 皮を剥いで、内蔵と筋肉をとる
2.蓋付きのポリ容器に、標本を入れる。水を少し入れる。
3.しばらく蓋を開けておく。ハエが飛んできて、卵を産む
4.蓋をする。卵から孵ったウジが残っている肉を食べる
5.何日か経つと、食べ物がなくなって、ウジは死んでしまう。
ハエになっても、フタが脱出防止になる。
6.一度、水で洗ってから、水をいっぱい入れて、脂抜きをする
7.何ヶ月か経ってから、水で洗い、乾かして、出来上がり。
ポイント:
皮をはがず、そのまま始めることが可能。
山で拾った標本は,もうウジがわいていてとても、解剖したり、詳しく調べる気のおこらないものもある。そんな時でも、この方法なら、なんとかなる。
注意点:
・所要時間
時間がかかる。
・腐敗臭
夏には、いくらフタをしておいても、においがするので、できるだけめいわくにならない場所でやる。
・ろう化
気温が低い時にこの方法をとると、筋肉が「ろう化」してしまうことがある。
長い間、水につけるのは、骨の中の脂をぬくため。省略すると、あとで脂がしみ出してきて、ベトベトするし、臭いもする。
大きなポリ容器と、それを置く場所さえあれば、大型動物の場合、いい方法。
ネズミや、モグラのような小型の動物の場合には、骨までかじられたり、頭骨をこわされたりして、よくありません。
ウジに食べさせなくても、皮をはいで、内臓や筋肉をできるだけとってから、水につけて、あとは時間をかけて腐るのを待つ方法もある。
小型の動物でも、この方法なら、こわしたり、小さい骨をなくしたりせずにすむ。
ろう化
深い湖や海に沈んだ死骸。 深い水の底では、水温が低いため死骸の腐敗が進まず、さらに水圧が高いので体の膨張が抑えられ、体は浮き上がることができない。 水に沈んだままの体は、組織が変性して蝋(しろう)化(ろう状あるいはせっけん状になること)し、数年、時には数百年も低酸素の環境でそのまま保存される。
(3)炭酸ナトリウムで煮る
(1)と(2)の方法は、どちらも長い時間が必要。もっと早く、標本を作ってしまいたい時には、この方法がよい。
(2)の方法で、筋肉がなくなった後も、骨から脂ぬきをするのに時間がかかる。
骨だけになったところで、この方法に切りかえるのも良い方法。
やり方:
1.皮を剥いで、内蔵と筋肉もなるべくとる。
2.深い容器(小型ならビーカー、大型なら18L缶など)に、水をはる。炭酸ナトリウムを1%を加える。
3.沸騰しないように、トロ火で気長に煮る。
4.ときどき、ピンセットでつまみ出し、水を流しながら、歯ブラシなどでこする。
残っていた筋肉が全て取れたら終わり。
5.よく水で洗ってから乾かす。
ポイント:
炭酸ナトリウムのかわりに、重炭酸ナトリウム(重ソウ)も使える。
水酸化ナトリウムや、水酸化カリウムは、骨をいためやすいので、やめた方がいい。
注意点:
・煮る温度
炭酸ナトリウムの濃度が高いほど、また煮る温度が高いほど、早く、肉はとける。
が、やりすぎると骨をいためてしまうため、注意。
なので、時々ピンセットでつまみ出して、ハブラシでこすり、肉がはずれるようなら、そこでやめる。ずっと横で見ていられない場合には、40℃くらいで煮るようにした方がうまくいく。
沸騰させないように注意。
(4)カツオブシムシに食べさせる
カツオブシムシ類は乾燥した動物質のごみを食べる甲虫。
動物のひからびた死体に付いていることがある。
名前の通り、かつお節や煮干しを食べる害虫でもある。
博物館では、動物の剥製や昆虫の標本が食べられてしまうことがある。このやっかい者を、逆に利用する。
カツオブシムシは筋肉は食べるが、じん帯は食べない。だから、骨だけがつながった標本ができる。
食べさせる前にうまく姿勢をととのえておけば、いろいろな姿勢の標本が作れる。この場合には、足などをバラバラにはしない。
やり方:
1.皮を剥いで、内蔵と筋肉もなるべくとる。
2.
標本にしようとする死骸を、ふたができる容器に入れ、虫が飛んでくるのを待つ。
3.
虫が付いたのがわかったら、ふたをして、今度は逃げ出さないようにする。
注意点:
・水気
残っている筋肉が湿るとウジが発生するので、湿らないように注意。一度火を通しておくと良い。
・所要時間
この方法は、時間がかかる
・脱脂
骨の中の脂が抜けないため、大型の動物には向かない。
カツオブシムシ
「虫が付いたのがわかったら、ふたをして、今度は逃げ出さないようにする。」と
の部分。
カツオブシムシのフォルムがわからない場合はこちら。

https://kotobank.jp/word/カツオブシムシ-45127
ヒメマルカツオブシ

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/カツオブシムシ
(5)野ざらし
(1)と(2)と(4)を組み合わせたような方法。
森の中などで拾った骨は、実にきれいに骨になっている。
これを、再現してしまおうという方法。
やり方:
1.皮を剥いで、内蔵と筋肉もなるべくとる。
2.寒冷紗で包んだ骨をプラスチックのかごに入れて地面におき、それより大きなかごなどで、日よけをする。
完全にかくしてしまうと、虫が飛んでこないし、雨にも当たらないので、うまくいかない。
また日よけがないと、骨がいたんでしまう。
3.まつ
注意点:
やり方を見てわかるように、この方法の最大の問題点は、適当な場所の確保。
(6)その他
タンパク質分解酵素(パパイン)で筋肉を溶かしてしまうという方法もある。
パイプの詰まりを直す薬品(PPスルーというのがいいらしい)に漬けておく方法が手軽でいいとか。
海岸や、森の中で出会う、骨の白さ。
あの白さめざして、やってみるか、と思った方は是非。
最後まで読んでいただき、感謝です(ペコリ)
#shinmr #SHINBOK #骨格標本 #骨 #作り方
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
