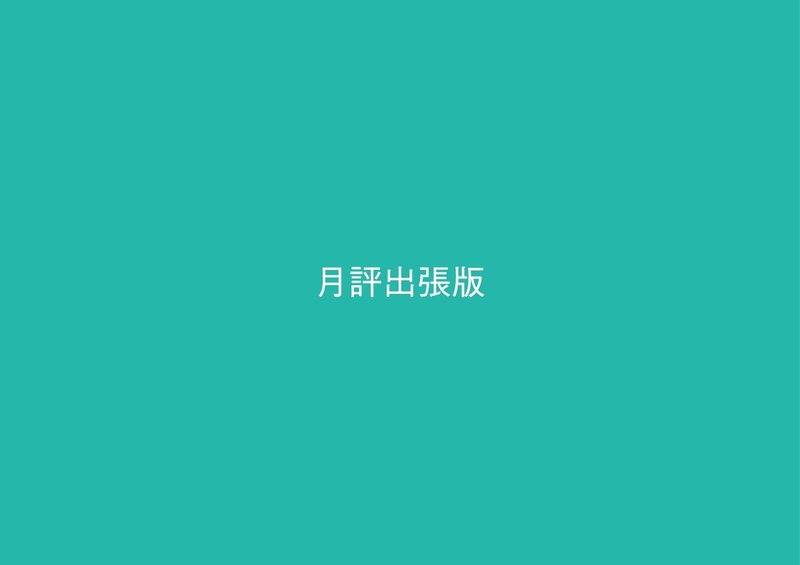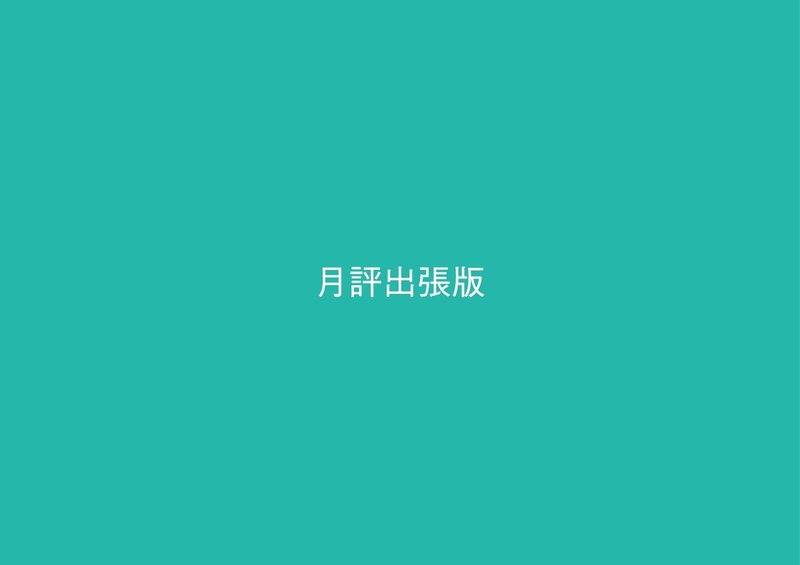ふたつの「通路」─『新建築』2018年11月号月評
「月評」は『新建築』の掲載プロジェクト・論文(時には編集のあり方)をさまざまな評者がさまざまな視点から批評する名物企画です.「月評出張版」では,本誌記事をnoteをご覧の皆様にお届けします!
(本記事の写真は特記なき場合は「新建築社写真部」によるものです)
評者:連勇太朗
「境界」社会にはさまざまな境界があります.
目に見える物理的な境界と,目に見えない不可視の境界.都市空間は,ひとりの生活者の視点では連続的なものとして経験されますが,管理,制度,法規のフィルターから覗き