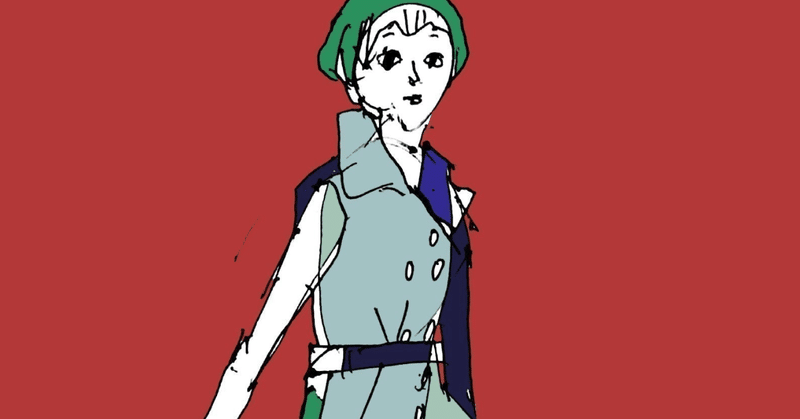
最果タヒを読むのが怖い
IQが10離れると、会話が成立しない。という話がある。その言葉を吐く人には、「自分は10上の側なんだよね」と無言のうちに傲岸不遜ない態度を感じてしまって好きではないのだけれど。それはともかく。
感性も同様だ、と思う。今の日本の教育システムでは、数理的処理能力や言語運用能力については辟易するくらい問われるけれど。こと話が感性に及んだとたん、美術の時間になおざりに触れる程度で義務教育を通過する。だから、感性の偏差値は無いし、自分の美意識を数値化された事も無い。美大を受験していたら、また、別だったかも知れないけれど、少なくとも僕は、感性を数値化する訓練を積む事なく教育課程を終えた。
感性に壁のようなものを感じるのは、詩を読んだ時だ。言葉が文字として、流れ込んでくる。レトリックを理解して「なるほど」と納得する。言葉の領域において、新しい解釈をし直していることに、感嘆する。だが、それだけだ。
本当に感動したものには、前のめりになる、と思う。時間を忘れる。目から涙が滲む。誰もみていないのに頷く。
内田樹『街場の教育論』、吉本隆明『共同幻想論』、滝本竜彦『NHKにようこそ』。どれも読みながら、感動して目から涙が滲んだ。
しかし、詩集で心が揺さぶられても、涙が流れない事がある。いや、むしろほとんどだ。Twitterで感想を見る。「落涙必至」「思わず本を抱きしめた」などと書かれている。
感動するのは、才能だ。
小学校のころは教科書を読むだけで、感動して涙を流す友人がいた。本人は、涙を止めたくて、悩んでいた。クラスメートは涙を流す気持ちが分からなかったから、「あいつ、先生に評価されたくていい顔しやがって」とすれ違い続けた。彼女はいま、作家になっている。
涙が流れない自分は、この素敵な詩集を、味わい尽くせていないのではないか。と怖くなる。まるで高級フレンチを食べているのに、「酸っぱい」「美味しい」くらい粗い感想しか持てていないのではないか、と。
1960年代から1980年代まで、詩や小説には批評家がいた。詩を読む人と同じか、それ以上に、その詩について批評が書かれた時代があった。その背景にあったのは、「この詩がすごいと言われるけれど、何が凄いか分からない」という読み手の呻吟だった。
200年前にニーチェが「神は死んだ」と吐き捨てたように、20世紀末、柄谷行人が「文学は死んだ」と見捨てた。この荒野のような文学の世界で、批評は生き絶えた。
そんな中、僕は詩集を読むのが怖い。最果タヒを読むのが、怖い。穂村弘を読むのが、怖い。
値段で"凄さ"を明示してくれるフランス料理と違って、鋭い感性で抉られた詩集も、鬱憤を晴らすためだけに書かれたような週刊誌も、値段に相違はない。
その詩の感性を、読み取れきれていないのに、「読んだ」気になることが怖い。だから、僕は詩集が好きと言うのが、恥ずかしいのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
