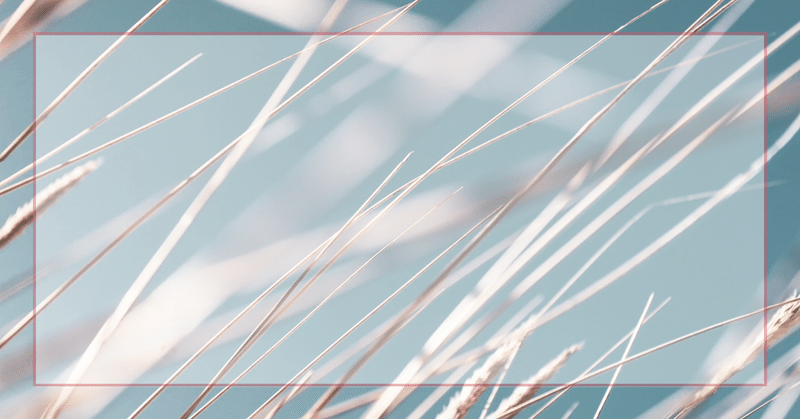
涙も出ないときでも、歌なら歌えることがある|セルフケアの子守唄
悲しみにはまず寄り添いが必要です。
悲しんでいる人の言葉に、ウンウン、と頷きながら、ただただ話を聞くことが必要です。
あと、こういう時に〝歌うこと〟はとても良いと思うのです。
こんなときに歌なんて……と思わなくていい。
人間、悲しくて何にもできなくて、涙も出なくなっちゃう、って時があるけれど、そんな時でも子守唄なら歌えたりしますから。
こんな子守唄、知ってる? あなたはどんな子守唄を聴いて育った? そういった話題で少し心がホッとすることもあるかもしれません。
人の安らぎに必要なのは〝日常〟だといいます。危機対応に追われると忘れがちになりますが、危機の中でも何かしら〝日常〟を思い出せるものがあるとそれを拠り所にできます。お年寄りには懐かしい歌を。また、お子さんは、大人の気持ちを声の調子から感じとっています、ぜひ大人自身が心やすらぐと思う歌をうたってみてください。
子守唄は昔から、子どもをあやす歌であり、歌い手自身の心を癒すものでもありました
『あなたのことを見ているよ』
『あなたのことを想っているよ』
支える側がどんなに相手に共感しようとしても、いっしょにもがき苦しむだけでは、悲しみのなかにいる人を支えきれないことがあります。
そういうときに、歌うことは、連帯を示すひとつの方法になります。
例えば、思わず〝笑っちゃうほどしんどい〟という経験をした事がある人は多いと思いますが、
〝歌っちゃうほどしんどい〟という時も、あると思いませんか? 「歌わなきゃやってられないよ」といった具合に……。
ストレス状況下では体が硬くなりがちなので、歌って声を出すことで体がほぐれる、といった効果もあります。
全ての年代の人に響くのも、子守唄やわらべうたの良いところです。
『子どもの頃、どんな歌をうたった?』
『よかったら歌ってみてよ』
そうしていっしょに歌えば、呼吸を自然と取り戻し、深呼吸ができるようになっていくでしょう。
関東大震災の夜、上野の山に響いたメロディ
西条八十(『かなりや』を作詞した詩人)が、関東大震災で被災した際、ある少年がとうとつにハーモニカを吹きはじめ、その音色に深く癒された……というエピソードがあります。以下、引用します。
八十はそのとき家族と離れて住んでいたため、大混乱のなかを安否をたずねて歩き回り、ついにその夜を上野の山で過ごすことになる。周囲を埋めつくす人びとは、深夜、疲労と不安と飢えで、化石のように押し黙ってしゃがみ、横たわっていた。
::::
すると隣にいた少年がポケットからハーモニカを取り出して吹きはじめた。誰でも知っている平凡なメロディーだったが、吹き方はなかなかのものだった。周囲の反響やいかにとみていると、群衆はジッとそれに耳を傾けはじめ、静かにきいている気配が伝わってきた。
::::
山の群衆はこの一管のハーモニカの音によって、慰められ、心をやわらげられ、くつろぎ、絶望のなかに一点の希望を与えられた。
西条八十はこの少年の演奏に、はげしく胸を打たれました。その後ふたたび辺りはシンとした暗さに包まれたけれど、もうこれまでの暗闇とは違う、と感じたそうです。
そして彼はこれをきっかけに「わたしは大衆のための仕事をする」と決意し、詩人としてのキャリアの後半ではレコード歌(いわゆる歌謡曲)に力を注ぎこみました。
歌謡曲なんてくだらないと今でも悪く言う人はいますが、わらべうたや民謡だって「卑俗、価値がない」とされて長らく不当な扱いを受けていたように、本当はどんな世俗の音楽にも人間にとって何かしらの大事な機能・役割をもっています。
八十が〝大衆のための〟と言ったのは、歌謡によく登場する「物悲しい」ように思える古いメロディーの中に、みんながよく知っている景色、みんなの身に覚えのある懐かしい感情があり、そこに多くの人の心を共鳴させながら癒す力があるのだという理解でしょう。
八十はそれを、上野の山の一件で、体験として理解したのだと思います。
歌になったときに感情は昇華される
歌として表現したとき、その感情は、生の感情のままでなく、歌という姿に〝昇華〟されています。だからこそ誰かの心に寄り添えることがあるように思います。
無理に言葉にしようとすると、なんだか分かったような気になってしまうけど、相手の心は相手だけのもの。
無理やり歪な言葉をひねりだすよりも、歌ったり絵を描いたり、一緒に何かをしたほうが楽になることがある……んじゃないかと思いましたので、今回こんなnote記事を書いてみました。
(言葉が不器用な自分への言い訳、自己満足に近いのかもしれませんが……。)
能登半島地震で被害に遭われた方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。穏やかな日々がはやく訪れることを、願っています。
私自身も、抑うつ傾向で不安定なパーソナリティを持っており、他人との接触や突発的な事態にとても弱いので、
同じように避難生活を難しく感じる人が、能登にも多くいるはずだろうと、とっさにそういった方々の健康状態を案じました。
無力感を覚えつつ、こんな自分にもできることはないかと探す毎日です。
まずは必要な物資、必要な支援がみなさんに届いてほしい。そして不安のなかでも、せめて心休まるひとときが見つけられますように、あたたかい陽が差しますように。
そして、『共感疲労』について。皆さまどうぞご自愛ください。
『共感疲労』という言葉があります。人間のもつ大事な能力としての〝共感〟ですが、そういう能力があるゆえに、直接、ご自身やご家族が被災されたわけでなくても、昨今の情勢やニュースがなんとなく体の不調として響いてくることがあります。
まずは自分を大切にすること、日常を守ることを大切になさってください。
あなたの心が疲れることは、あなたに心があることの証拠です。なんにも悪いことではありません。
軽いストレッチをしたり、あたたかいものを飲んだり、歌をうたったり美しいものを見たり……。
自分を大切にする行動を、ひとつひとつ、できるたびに自分をとびきり褒めましょう! 私もそうします☺️
子守唄をいくつか歌ってみました、今日から何度かに分けてアップしていこうと思います。
よかったら聴いてみてください。いっしょに歌ってもらえたらとても嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
