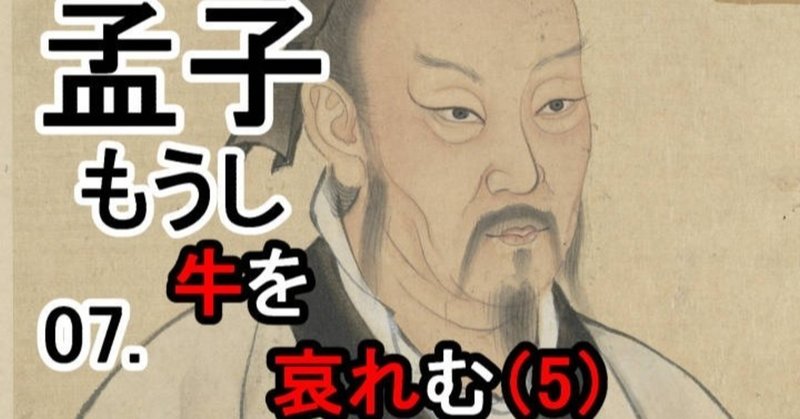
『孟子』07―梁恵王上―孟子と斉の宣王の対話(1)牛を哀れむ〈5〉
◆音声で聴きたい方はこちら↑
宣王は言った。
「もっと詳しくお聞かせください。」
孟子は言った。
「小国の鄒(すう)と大国の楚が戦った場合、王はどちらが勝つと思われますか。」
宣王は言った。
「楚が勝つでしょう。」
孟子は言った。
「そうでしょう。
小さければそもそも大きい者に敵うはずもありません。
少なければ多数に敵うはずがなく、弱ければ強いものに勝てるはずがありません。
いま世界には、千里の地方が九つあります。斉は、その一つを集めたにすぎません。一箇所で、残り八箇所を征服しようなどと、なんとも、鄒が楚を敵にするのと同じではありませんか。
基本に立ち返るのです。
今、王が政治を行い、仁を施せば、天下の仕官を求める者はみな王の朝廷に立ちたいと願うでしょう。
あるいは田畑を耕そうという者は、みな王の領地を耕したいと願うでしょう。
さらに、商人は、みな王の市場に品を置きたいと願うでしょう。
そして、旅人は、みな王の道を通りたいと願うでしょう。
ついには、天下で自分を虐げる君主を懲らしめようとする者は、みな王のもとに訴え出ればなんとかなると思うようになるでしょう。
ここまで行けば、人々が王のもとに集まることを、誰も止めることはできません。」
宣王は言った。
「私は愚か者で、そこまで進むことができそうにありません。
ですがどうか先生、私の志を助けて、はっきりと私を教え導いていただきたい。
私には、才能がありませんが、とにかく試してみようと思います。」
孟子は言った。
「安定した収入がなくても、心を安定できる。これは、選ばれた士だからこそできることです。
一方、民は、安定した収入がなければ心を安定させることができません。
そして、わずかでも心が不安定となれば、人間はやりたい放題にふるまい、横暴となり、何をしでかすかわからなくなります。
にも関わらず、民が罪を犯すと、次には罪に従って刑罰を与える、これでは民を罠に追い込むようなものです。
どうして仁の人が王位につきながら、民を罠に追い込むようなことをしなければならないのでしょうか。
ですから、古の明君は、民のために収入を確保することで、上は父母に仕えるようしてやり、下は妻子を養うようにしてやりました。
そして、豊作の年には人生に飽きるくらいに感じさせ、凶作の年には死ぬことがないようにしてやっていました。
そのうえで、民を駆り立てて善人になるように仕向けたのです。
だからこそ、民は、古の明君に簡単に従いました。
ところが、今の君主は、民の収入を確保してもたかが知れており、上は父母に仕えさせるには足らず、下は妻子を養わせるには足らず、豊作の年であっても人生苦しいと思わせ、凶作の年であっても死にゆくままにまかせています。
こんな状況では、民は、日がな死なずにすむようにと、あくせく働き、それでも明日の死に怯えることになるでしょう。
これでどうして、礼や義を学ぶ暇があると言うのでしょうか。
王よ仁の政治を行いたいと思うならば、基本に立ち返るのです。
民に五畝の宅地を与え、そこに桑の木を植えれば、五十歳の者は、絹の着物を着ることができます。
鶏、豚、犬、猪豚といった家畜も、繁殖と加工の時を間違わなければ、七十歳の者は、肉を食べることができるでしょう。
百畝の田畑を与え、その収穫の時期を奪わなければ、八人ほどの家族であれば、飢えることもないでしょう。
郷里の学校で教えをきちんと学び、これに加えて親孝行や年長者を敬う義を教えれば、白髪の老人が道路で重い荷物を背負うこともなくなるでしょう。
老人は絹を着て肉を食べ、庶民は飢えず凍えず。
ここまで行って、王者になれなかった者はおりません。」
*以上、『孟子』07―梁恵王上―孟子と斉の宣王の対話(1)牛を哀れむ〈5〉
◆全訳はこちら↓
【原文】
曰、「可得聞與。」曰、「鄒人與楚人戰、則王以為孰勝。」曰、「楚人勝。」曰、「然則小固不可以敵大、寡固不可以敵眾、弱固不可以敵彊。海內之地方千里者九、齊集有其一。以一服八、何以異於鄒敵楚哉。蓋亦反其本矣。今王發政施仁、使天下仕者皆欲立於王之朝、耕者皆欲耕於王之野、商賈皆欲藏於王之市、行旅皆欲出於王之塗、天下之欲疾其君者皆欲赴愬於王。其若是、孰能禦之。」王曰、「吾惛、不能進於是矣。願夫子輔吾志、明以教我。我雖不敏、請嘗試之。」曰、「無恆產而有恆心者、惟士為能。若民、則無恆產、因無恆心。苟無恆心、放辟、邪侈、無不為已。及陷於罪、然後從而刑之、是罔民也。焉有仁人在位、罔民而可為也。是故明君制民之產、必使仰足以事父母、俯足以畜妻子、樂歲終身飽、凶年免於死亡。然後驅而之善、故民之從之也輕。今也制民之產、仰不足以事父母、俯不足以畜妻子、樂歲終身苦、凶年不免於死亡。此惟救死而恐不贍、奚暇治禮義哉。王欲行之、則盍反其本矣。五畝之宅、樹之以桑、五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜、無失其時、七十者可以食肉矣。百畝之田、勿奪其時、八口之家可以無飢矣。謹庠序之教、申之以孝悌之義、頒白者不負戴於道路矣。老者衣帛食肉、黎民不飢不寒、然而不王者、未之有也。」
*ヘッダー画像:Wikipedia「孟子」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
