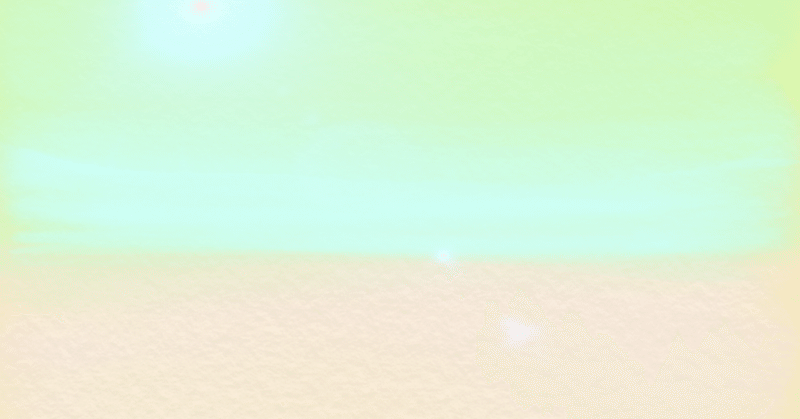
8月31日
隣に住んでいる住人の顔を2年近く住んでいるにも関わらず一週間前に初めてみた。普通の優しそうなお兄さん? いやおじさん? どっちともとれる顔や体躯はゲゲと声が出てしまうほどあたしのバッチリでグッとなるタイプだった。なぜ2年もの間知らなかったのかといえばお隣さんはなにせ朝ど早く出ていき帰ってくるのは次の日になってからでだから会うわけなどはない。多分土日休みだったろうと思うけれどあたしが土日休みではないためまずもって会うわけはない。
それが8月に入りいやにバタバタと部屋の中の音が夜中でもおかまいなしにガタガタと音をたててなにごと? かと思いつつもまあいっかとうやむやにしていた。
一週間前の土曜日にたまたまあたしは有給をとってうちにいた。そして腹が減り近所にあるドラックストアに行きパンかラーメンでも買いに行こうと決めいい加減なジャージ姿とキティちゃんのピンクのサンダルをつっかけ財布とスマホと鍵だけをポッケにしまいおもてに出た。そのとき隣の人が車にダンポールを積んでいるのが見え(それもどだくさん)なんとなく引っ越すのだろうという予感がした。だからここのところうるさかったんだなと納得もいく。この炎天下の中白いTシャツが反射して見える。汗だくでまるでどこかの引っ越し業者さんと見紛うほどに腕はたくましく育っていた。普通の人だけれどなぜか普通に見えずなぜかとてもその人のことが知りたくなる。知ってもしょうがないのに。どうしてそのような声が出たのか自分でもよくわからない。ただなんとなく。ただ理性に逆らえず。いやいやきっとただの興味だ。
「お手伝いしましょうか? あ、あたし103号に住んでいるものです。あやしくありませんのでぇ……」
目の前にいる隣人はぽかんと口をあけてあたしを大体見つめたあと、ははは、と大笑いをした。
「ははは、てゆうかさ、怪しいよね? 普通に」
え? あたしはまさかの返答に言葉に詰まる。
「だって普通さ、話しかけてこないっしょ? こんな暑い日に。手伝うなんて。それもそのスエットで。草履だし」
ジジジジー。とジージーセミが鳴いている。額から汗が垂れてくる。髪の毛が黒いのでもしかしてむかし虫眼鏡で光を集め火がついたことを思いだし、まさか燃えないだろうなぁとうだる暑さの中冷静なあたしがいる。
「す、すみませ」
「あ、じゃあまあ手伝ってよ」
同時に声が重なった。あたしは退散しようと決めていたのに。隣人はいとも簡単にあたしを怪しいものからお手伝いに昇格させた。
「あ、じゃあ。はい」
「頼むねぇ。助かるよー。てゆうか君さ、隣に住んでいたのに初めてあったし初めて喋ったね」
はははと隣人はまた笑う。ですねー。あたしもクスクスと笑った。
「かわいい子だったんだ。もっと早く知り合っておけばよかったな」
「え?」
あ、いいやと隣人はなんでもねーしと汗をTシャツの袖で拭う。急いで部屋に戻りタオルを持ってきて隣人に差し出した。わ、助かるわ。ありがとう。
あたしはどういたしましてというふうに首を横にふる。話しかけてよかったなとまずもって自分の行動力を褒めてやりたくなった。
だいたいの荷物を積み終えて車中が満タンになる。
「これ今から実家に運ぶんだよね」
「あ、そうなんですね」
どこまで行くのかとかもう戻ってはこないのだとか聞きたくても聞けなかった。もしかして奥さんのいる人かもしれないし。単身赴任の線もある。
「来週が最後の積み。来週でここ引き払うから。8月31日に」
隣人はそれだけいい車で去って行った。
夕方に出発する前に何かお礼がしたいからなにがいい? なぜあたしが月曜休みだと知っているのか偶然なのか知らないけれど隣人が急にきて玄関先に立っている。あれから一週間なにもご無沙汰でもう会えないと思っていたのに。時計を見ると午後3時だった。
「なぜあたしがいるのわかったの?」なんとなく気になり質問する形になる。
「だって車あるじゃない」目線はあたしの軽自動車に向いている。
ああなるほどねと納得をし、お礼かぁとつぶやく。
「まああとうちにおいでよ」
「あ、はい」
あたしは急いで薄化粧を施しシャワーをしてジャージはやめて黄色のマキシワンピに着替えお隣さんのうちに入った。
「え?」
その声があたしのものでもう布団しか残ってなかった。お礼をしたいってどこか行くのかなと思わせるなにもなさについプッと笑ってしまう。
「もう布団だけ。あとは随分運んだよ。往復8回くらいね」
「へえ」
引っ越し先は県内で高速を使えば1時間半くらいだという。
「奥さんが待ってるね」
ガランとした部屋にあたしの声が響き白い壁に吸い込まれてゆく。隣人ははっーと息を吐き、居ないよと首を横にふる。
「俺バツイチなんだよ。子供は2人いるけど。あっちが見てるし。もう結構あってないな。小学生と中学生」
へえ、そっかとまたへえといってしまう。
あたしはこの隣人にまつわることなどなにも知らないしあげく今日で最後なのだ。だからなにも知らなくていいしなにも怖くなどは毛頭になかった。
あたしはマキシスカートを脱ぎ下着もとって裸になった。冷房がワンルームなのかガンガンに効いていて寒さを感じ震えが止まらない。けれどその震えは緊張からくるものだと知ったとき隣人がそうっとなにも言葉もなくあたしを抱き寄せた。
カーテンを閉めやや暗ぼったい空間をつくりあげる。布団しかない部屋は妙に淫猥に感じた。最初からこのつもりだったのかなまさかなけれどまいっかもう会うことなどないし。あたしは必死で隣人に抱きつきそして抱かれた。もっと早く出会っていれば。今までこんなに素敵な人が隣に住んでいたのかと思うとひどく胸が痛んだ。もう決して会うことはないのだから。だからあたしはとんでもない格好やとんでもない退位を要求し舐めてもっとともうおかしくなるほど深く耽美に浸った。隣人も誠意一杯あたしを抱いた。もう、無理……。隣人の声が遠くなりあたしたちは裸のまま抱き合って深くて冷たい深海に落ちてゆく。
ねぇ、その声にはっとなる。とゆうか体が死体のように冷たくなっていた。それに喉がとてつもなく痛い。冷房にやられたようだ。
あ、また勃ったと隣人はあたしを横向きにさせまた入ってきた。あんあんとつい声をあげ腰を振るあたしも大した女だと自分でも呆れる。けれど猛烈な気持ちよさの中あたしと隣人は同時にイった。もう無理……。さっきもいったことをまた繰り返す。あたしはもう参ったよと隣人に抱きついた。
部屋がいきなり漆黒の闇に包まれていた。白い壁などはまるで見えずただ暗闇を彷徨うだけで目が追いつかない。スマホスマホと独り言をいい隣人が
「8時半だよ」
時間を告げる。朝の? とボケると、朝のじゃねーしと打てば響く速さで返ってきた。
「行かなきゃだよ。親父が待ってるんだ」
「うん」
灯りをつけて急いでお互いに洋服を身に着ける。何事もなかったかのような自然さがかえってもう会えないなんて信じられないという事実を突きつけた。
「じゃあね。道中気をつけてね」
「ああ、じゃあ」
うんとうなずきあたしは隣人宅から踵を返す。
夜気はほんのりだけれど秋の気配を纏っていた。星がピカピカとまだらに光っている。8月31日の夜。あたしは見事なまでの最高な恋をしそして8月31日の夜。同時に振られることになった。たった一度抱かれるだけでいいという胡散臭い台詞をよく小説などで見かけるけれど、なるほど。これはまんざら嘘じゃないかもということであたしも急いで自宅に戻りパソコンを開いで小説を書く。売れない小説家であるあたしにとって最高のセックスと最高のネタをくれた隣人に感謝。名前も知らない年齢も知らない。知っているのはその体にある体温とキスがうまいということだけ。これ以上なにを望む?
連絡先をお互いに聞かなかったのは意図的なのか故意的なのかは謎でけれど聞かないでよかったと思うとなんとなく気が楽になり冷蔵庫にあるハイボールを取りにいく。
題名 『8月31日の恋』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
