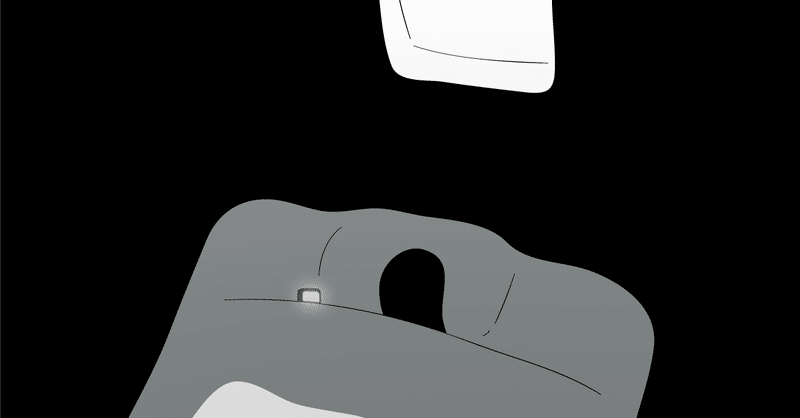
雨
雨が降っている。それもバケツをひっくり返したような大雨が。車、きれいになるかも。わたしはそうおもいながらわが愛車フィアットのハンドルをおそるおそる握りしめる。
【ブーブー】
助手席においてあるスマホが振動をし、信号に引っかかったとき、手に取る。
その名前をみて、はっとなる。と同時にそんな気もしていた。なぜならバケツをひっくり返したような雨だから。
修一さんからだった。
時間ある? というメールに あるよとこたえる。午前中、知り合いのところではじめたバナーつくりのバイトの帰り道だった。
ホームページに載せるバナー広告をつくる仕事があるからやらない? そう誘われ、先週から、好きな時間にいきいくつかつくってクラアント先に送り、修正をし、また送り、また修正をし、またまた送りを繰り返しやっと商品になる。ということをしている。
今日はたまたま仕事が早く終わった。もう帰ってもいいよ。と知り合いのデザイナーがいい、雨だしとつけ足した。雨だしって、わたしは笑いながらいい、なにそれとさらに笑った。
「ほら、前にいってたでしょ? 雨だと、頭が痛くなるって。気圧のせいとかなんとかさ」
「あーあー。いったわ。そんなこと」
よくおぼえてたね。といおうとしてやめる。このひとは知り合いだけれど、以前1度だけ体の関係を持ったことがある。もうないものになっているけれど。一線を超えてしまった。迂闊だった。そうとしかいいようがない。
『お前のうちの近くの公園で待ってる』
大雨のせいだろう。修一さんは気を利かせてのつもりかわたしのアパートのわきにある公園までくるという滅多にない台詞を打ってきた。
『わかった』
ひどく短い返事だった。雨はさらにはげしくなりうちに着く頃には道路が川のように水がダーダーと流れていた。
「きゃーすごい雨だよね」
助手席に乗ったせつな結構大きな声で修一さんに問いかける。けれど、修一さんの顔はみえなかった。運転席と助手席の間にサーフボードが挟まっていたからだ。邪魔。わたしはそのときばかりはサーフボードを憎んだ。物だけれど。
「すごいよな。現場で雨漏りがあってさ、朝いってきてさ。参ったよ」
「そっか。そっか。大変だ」
時計はまだ13時を示している。けれど、雨だからなのか薄暗い。夕方だといえばそうともみえるし、朝方だといえばそうかもしれないとさえおもう。雨はときに時間と季節、あるいは感情を狂わせる。
「どこにいくの?」
その声は雨の音に吸い込まれないものになってしまうが、どこにいくの? などと訊いてみたところでいく場所などわたしたちにはない。おもてで堂々と食事もできないのだし、抱き合うこと以外、なにもないのだから。そこには言葉すら介在しない。
いつもいくホテルは雨だからなのか、雨のせいなのか、大繁盛で部屋が残り2室だけだった。
狭い駐車場にカローラワゴンを入れ、無言でエレベーターに乗り、部屋のドアを開ける。
「はぁー、疲れたわ」
真っ赤なソファーに腰をおろした修一さんがソファーの中に埋もれていく。そのまま体中埋まってしまうのではないだろうか。とぼんやりと考える。
ちょっとだけ近況を語り合い、シャワーをお互いにしてベッドの上で上になったり下になったり、ときには声をあげ、悲鳴をあげ、獣になり、最後は枕を濡らしていつもの行為が終わった。肩で息をしている修一さんの吐息とおもてからわずかに聞こえてくる雨の音とわたしの咽び泣きだけが三重奏を奏でている。そして、修一さんの呼吸が落ちついてきたなとおもった途端、わたしはまるで崖から落っこちるような感覚になり、意識が遠のいた。修一さんの肩に頭を乗せたままで。
はっと目が覚めると修一さんはすやすやと深い眠りに入っていた。何時だろう。ホテルには窓がないしあげく時計がない。時計がないのは時間の感覚を無くすためだとホテルの清掃をしている友達から聞いた。嘘でしょ? ほんとうだって。男と女に時間なんている? 友達は意味のわからないことをあたりまえのようにいいはった。
最近、行為が終わってからこうやって眠るようになったなとおもう。以前はそんな余裕などなかったのに。余裕をみせるようになったのが嬉しいのもあるけれど、その余裕がなんだかかなしくもある。行為は決して手抜きなどはない。いつも泣いてしまうほどせつなくて苦しいけれど、満足しかない出来事だ。
薄目を開けた修一さんがわたしの方を一瞥し、あれ? という顔を向け、あちゃ、また寝てた俺? という。
「うん、寝てた。今、もう夜の8時」
「ええ!」
「なんて嘘。時間は不明です。雨は降ってるけど……」
ベッドから這い出てスマホをのあるテーブルにいき時間を確認する修一さんが
「5時だった」
特に焦ってもなくつぶやく。腹減ったなとつづける。
「なんか食う? 俺さ、昼飯食ってないし」
「あ、うん、なんかさ、休憩で入るとそのテーブルの上にある、ランチが無料みたいだよ」
冷やし中華だった。部屋に入ったとき、真っ先に目にとまり、あっ、夏の到来だなと夏を感じた。
「じゃあ、それな」
無料のわりにそこいらの中華料理屋に劣らずひどく美味しかった。美味いな。修一さんは3分ほどで食べ終えた。わたしはまだ食べている。酸味がちょっとだけきつい。
「あのさ、」
アイコスを吸い出そうとするその横顔に声をかける。
「何回もわたしとしてね、その……、飽きないの?」
いやいや違うくて。そんなことが聞きたかったわけではなかった。なにを口走っているのだろう。わたしは。
修一さんの方もいまさらなんで? そんな感じの顔をしつつ眉根をひそめる。
「……、あ、きる? いや、飽きないな。なんでだろう。わからない……」
おだやかな声でささやくよう吐き出した言葉はアイコスの煙と共に天井に吸い込まれていった。
「そっかぁ……」
辛子のせいだ。涙が頬を伝う。辛いからだ。うん、きっとそうだし、お腹が空きすぎているせいだ。
鼻水も垂れたまま泣きながら麺を啜る音が雨の音と共に部屋中に響き渡り、はぁとため息を吐いた修一さんのさっきまでわたしの胸に触れていた手のひらで今度は髪の毛をそっと撫ぜた。
バケツをひっくり返したような雨ではなくて涙がとまらずに困ったのはわたしではなくて、わたしの大好きな目の前にいるおとこのほうだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
