
口のない世界
口のない世界が長くなった。そして、当分口のない世界は続く。
あの人の、口角の端があがりっぱなしの朗らかな口元も、彼女の、夕方の水平線のように燃えあがる薄い唇の線も、あの子の、いつもぽっかり開いている口より垣間見える白い歯の煌めきも、あの方の、一度歪むとなかなか元の形に戻らないティースプーンのような口の形も、みんな遠い記憶となった。
朝の通勤電車に乗り、濡葉色の座席に腰かける。
力をふり絞る空調を鼻でわらうように、窓が大きく開いている。向かい側には7人の、形の違う14個の瞳が並ぶ。光の届かない洞穴のような、沈殿した澱みたいな、繭に覆われた蚕のような、瞳。その下に並ぶのは、白と青と格子柄とサーモンピンクと黒の旗で、吹き抜ける風に翻りもせず、その向こうにあるはずの7つの口を、慎重に包み隠している。
口紅を塗らなくなって半年経った。
暗黙の社会マナーに屈服して唇に滑らせていたベージュのルージュは、ポーチのなかでこの蒸し暑さに緩み、ポタージュのように蕩けているかもしれない。その様子を確かめるのはたぶん夏、もしかすると秋、だってそのまま捨ててしまったら私の心は咎めるだろうから、せめて冬になる前に。
通気性をうたいながら、黙って空気の入場制限をしているマスクの中は常に酸素が欠乏していて、職場に辿り着くころには、ここにある気が遠くなる。
外したい、とマスクの端にかける指は、塗り重ねられた除菌ジェルで粘りながら優柔不断を繰りかえし、決行できずに宙を掻く。私は空気が欲しいのです、ウイルスの含まれているかもしれない唾液は決してあなたに飛ばしませんから、と眉を吊り上げる誰かに向かい、言い訳をする夢を昨日見た。
口ほどに物を言うはずの目は沼のように沈鬱で、レジ係の彼は怒っているのかもしれないと思う。
「感染拡大を防ぐため最小限の会話にて対応させていただきます」と書かれた貼り紙を守護神とし、ささやき声で金額を告げると彼は、薄いビニール手袋に覆われた指で私の買い物籠を押し退ける。慌てて開いた財布の中の、5千円札と目くばせをしながら、漸く私はぬかるみの決意をコンクリートレベルに硬くする。あとでスイカにチャージをしよう。

打ち合わせで訪れる人に、マスク着用を依頼するタイミングは何度測っても難しい。
忘れました、という人に対しては渡せばよいので問題ないが、つけません、とはね除ける人への懐柔方法は浮かばない。密閉空間での対面相談でも、つけない理由は人の数ほどほあるはずだ。呼吸器脆弱、接触性アレルギー、痒みを伴う皮膚炎、外耳の怪我、マスク購入費用問題、口の回りを塞がれると起こるパニック発作、信じて止まない科学的根拠。ならばつけなくてはならない理由も星の数ほどあるのだろう。
マスクは要るのか、要らないのか。流行っていれば、いなければ。混んでいれば、いなければ。支障がなければ、苦しければ。人が見ていれば、見ていなければ。持ち合わせがあれば、手に入らなければ。マスクはするのか、しないのか。
要請されても、着脱は自由だ。あなたの選択は、きみに強要できない。だから (それでも) 私はつける、たとえそれがリスクを数%下げるだけでも、殆ど意味がないのだとしても。免疫疾患の娘のために。糖尿病の母を想って。
花粉症の娘には、春はマスクが必須だった。
赤い紐つきハローキティの布マスクを毎日つけて、保育園に通い、家路につく。深夜、洗濯したての小さな四角を四角い窓際に干しながら、朝にはすっかり乾くようにと祈る。
それを思い出したのは、1日使った使い捨てマスクをやっぱり捨てられなくて洗う夜更け、あのマスク姿が恋しくて開いた古いアルバムに、娘と揃いのマスクをしている愛らしい少女が立っている。ステロイドの副作用を想わせる満月状のフェイスラインに、14年遅れで気づいた私は、彼女と娘の明日の平穏を祈る。

感染症とのたたかいは少なくともあと1年は続くでしょう、と専門家なる人が胸を張れば、ガルシア・マルケスの『エレンディア』ばりの悲惨なシナリオを創り上げる自分が哀しい。ソーシャル・ディスタンスを取る隙間もない、袖振り合うも多生の縁の、午後5時半の中央線に、窓から射し込む夕方の光が私のマスクを茜に染める。
控え目に言っても20回は読んだアルフォンソ・リンギスの本を数冊持って来たのが運のつき、どうしても一章読みたい (息をつきたい) と心が騒いで降車する。
自分を許す、この3ヶ月の辛抱を讃えて。条件をつける、読み終わったらすぐに帰ること。お店にお金を落とすことは経済貢献、と迷える小心に説得すると、久方ぶりにコーヒーの香り漂う店の前に立つ。
誰もいない。
以前は10セットあったテーブルのうち、半数が辛うじて生き残り、40脚あった椅子は、15脚まで間引かれた挙げ句、閑古鳥が啼くその店では、2人の店員がドーナッツと油を売っている。マスクの上の4つの目が、私の2つの目と出会ってゆるむ。〈笑顔〉の代わりに〈笑眼〉という新種の言葉が私の内部で不意に芽吹く。
コーヒーとドーナッツをトレーに載せ、瓦礫と化したテーブル5個と25脚の椅子の山の麓を歩き、中央テーブルに席をとる。手を洗いながら世界を見渡す。
相変わらず誰もいない。
バッグを開き、マスクをしまう。コーヒーを飲み、ドーナッツを千切る。両手を拭き、マスクを眺める。遊び疲れた午後に眠る、白い仔猫のような無防備なかたち。このまましばらく眠らせてあげよう。
本を開く。
やっぱり誰もこない。
不意に、コロナ禍の世界の、極東日本の、東京西部の片隅で、リトアニア移民の子で、世界中を旅し、アメリカで哲学を叫ぶアルフォンソ・リンギスの本を開いている私の心が震えだす。
コロナ禍の世界の、極東日本の、東京西部の片隅で、無名だけれど名はちゃんとあるどうしようもなく悲観的な私が、リトアニア移民の子で、世界中を旅し、アメリカで哲学を叫ぶあなたの言葉を噛みしめる。
口のない世界で生きる私は、旅の翼も折られて久しい。ならばリンギスの慈愛に満ちた奔放な言葉にしがみつき、思いのままに旅をすればいい。言葉の飛行機を繰って世界の裏側へ、言葉の潜水艦に乗って心の奥ふかくへ。

“遠くまで旅をすると、われわれは自分がしあわせな幼児の世界に戻っていることに気づく”
アルフォンソ・リンギス
『リング』抜粋
本を閉じ、惰眠をむさぼる仔猫のかたちのマスクを、マスクのかたちに整えてから、身体を椅子から引き剥がす。カップとプレートを下げた手が、マスクをゴミ箱の奈落に落とす。
口のない世界に還るためのマスクを失くしてしまった愚かな私は、口を晒し、30℃近い蒸し暑い街中を薄氷を踏むようにして歩いていく。
人波を越えて進む、目が泳ぎ始める、そして両手で口を隠す、あたかもムンクの「叫び」のように。
口のない世界で生きるのは、ああやっぱり楽じゃない。
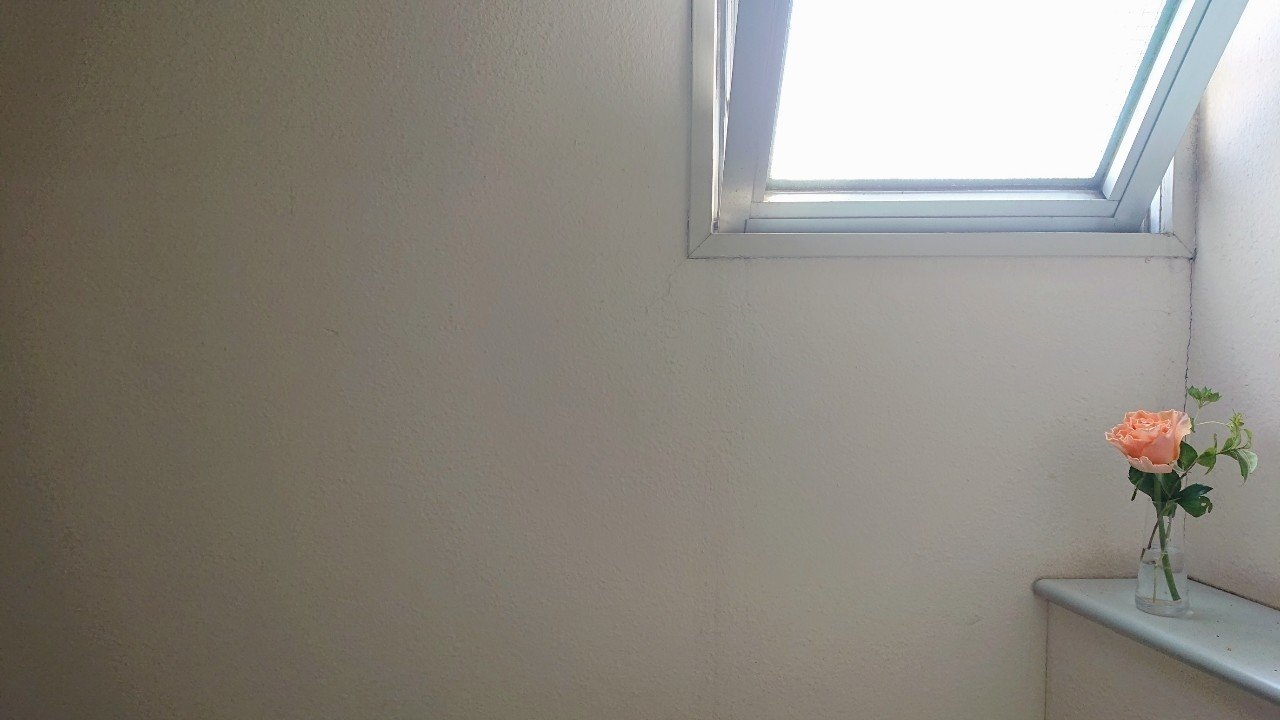
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
