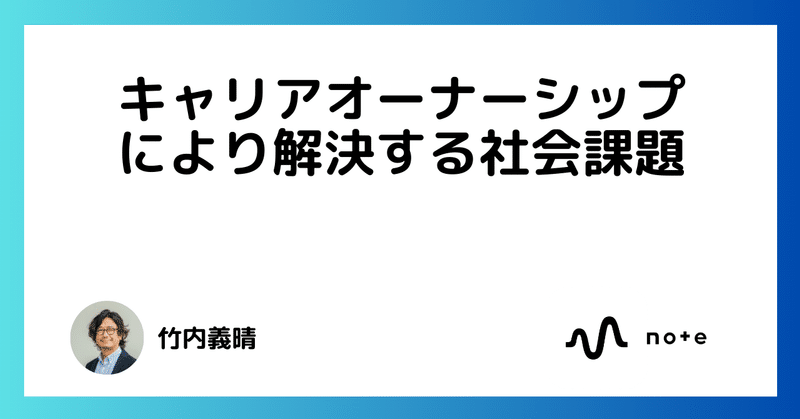
#217 キャリアオーナーシップにより解決する社会課題
竹内義晴の「これからの働き方」――この番組はこれからの働き方、組織づくり、地域づくりの実務家、竹内義晴が「楽しく働く」をテーマに、組織づくりやコミュニケーション、マーケティング、キャリアデザイン、複業、テレワーク、ワーケーションなどの視点で、これからの働き方や地域のあり方についてゆるゆるとお話をしていく番組です。この番組が面白かった、あるいは参考になったらフォロー・コメントなどいただけると嬉しいです。
今日はファシリテーションをしていました
というわけでございまして、今日はですね、細かく言うのは避けますが、都市部の企業の方々がですね、新潟県の上越、妙高エリアにおいでになっていました。
2日間、地域の中の、特に一次産業の実情を、実際に見たり感じたりしたことを1つのきっかけとして、「自分たちに何ができるのか」――そんなことを考える取り組みがあって、そのファシリテーターでお呼びいただいていました。
新たなことを始めるための企画って、できる人、できない人……っていう言い方は、あまり良くないかもしれないですけど、視点って大事だと思うんですよね。
ここでいう視点とは、新たなことをやっていこうとするときに「自分たち視点で考えるか、それとも、相手の視点で考えるか」の違いです。
たとえば、企業ではたらくみなさんの場合、地域の課題を解決するために「自分たちのソリューションを提供すれば解決できるんじゃないか」みたいに考えるケースって、よくあるんじゃないかなと思います。
一方で、地域側の課題って、「これを入れれば物事が解決します」というほど、そんなに簡単なものではありません。
重要なのは、いかに「相手視点になるか」っていうところだと僕は思っていて。
以前にも話したことがあるかもしれませんが、企画で重要なのは、自分たちの持っている何かを提供することの前に、「誰に、何と言ってほしいか」とか、「誰に、何と言わせたいか」っていう、相手視点が非常に重要じゃないかなって思っていて。
また、課題に対して「これが問題だから、これが解決ポイントです」みたいに、分析的に考えるのも重要なんですけど、ただ分析していっても、ありきたりな解決策しか出てこないケースも多々あります。
そこで、今回はフューチャーマッピングという、神田昌典さんが開発された、企画を立てるときの、イメージを使った思考モデルを使って企画ミーティングを行いました。
分析型で考える内容とはまったく違う感じの、いろんなアイディアとか企画案が出てきたような気がします。
キャリアの主体性についてお話しています
入り口の話が長くなってしまいましたが、いま、キャリアの主体性についてお話をしています。今日はですね、「はたらく未来コンソーシアム」というサイトにある、キャリアオーナーシップに関して、ちょっとお話をしてみたいなと思っています。
なぜ、キャリアオーナーシップの話をしてみたいかというと、はたらく未来コンソーシアムのサイトを拝見すると、結構「そうだよな」って思うことが多くあるからですね。
現状、僕は直接的に何か関係があるわけではないので、僕から見える感想を言うのはおこがましいような気もします。でも「そうだよな」って思うことが多いので、はたらく未来コンソーシアムの内容をネタに、お話してみたい……ということでございます。
キャリアオーナーシップとは?
はたらく未来コンソーシアムのサイトのトップページに「キャリアオーナーシップが社会を動かす」と書かれています。
キャリアオーナーシップとは、
個人が自分の「キャリア」に対して主体性を持って取り組む意識と行動のこと。
とあります。また、次のようにも書かれています。
激変する社会環境の中、企業と個人の持続的な成長を実現する「はたらく未来」を模索していくのが本コンソーシアムです。
次のページに飛んでみると、こんなことが書かれています。
人生100年時代の中、年功序列や一社終身雇用制度は崩れ始め、「はたらく」をとりまく社会環境は激変しています。これまでのような画一的な働き方ではなく、多様な個人に対応した、働き方や人材育成、雇用モデルといった変革は、もはや日本社会において待ったなしの必須課題となっています。
こうした状況の中で、一人一人の個人が、自律的に成長し続けるために不可欠なのが「キャリアオーナーシップ」。はたらく個人の力を最大化させ、社会の力にするために、企業はどう向き合い、新たな関係性をつくっていくべきなのか?まだ答えの問いに対し、先駆的に取り組む企業が自ら実践・実証し、企業と個人の持続的な成長を実現する「はたらく未来」を模索していくのが本コンソーシアムです。
激変する社会課題とは?
このページには「人生100年時代の中、年功序列や一社終身雇用制度は崩れ始め、「はたらく」をとりまく社会環境は激変しています」と書かれていますが、僕の見立てでは、これも1つの要素としてありますが、もう1つの、社会環境が激変している要素として、大きな課題として見ているのは、やっぱり人口減少ですよね。
いままでのように、1社の中で社員をずっと囲っているだけでは、一人ひとりの能力は、1社の中で限界を迎えてしまいます。会社の枠を超えることがありません。
しかし、人口減少社会のこれからは、人がどんどん減っていくわけだから、働く人たち一人ひとりが持つ能力を最大化していく必要がありますよね。それが、僕の見たで、課題認識です。
はたらく未来コンソーシアムのサイトに書かれているのは「本当そうだな」って思います。それに加えて、激変する社会環境というのは、僕の見立てでは、少子高齢化や人口減少というのが、今後、結構大きなウェイトになっていくだろうな……というふうに見ています。
無理に働かせるわけではない
「一人ひとりの個人の能力を最大化する」みたいな言い方をすると、なんとなく1社で働くだけでも大変なのに、さらに俺たちはこき使われるのか……みたいに思われる方も、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。
でも、そうではないな、と僕は思っていて。一人ひとりの能力をシェアすることで、仕事がより簡単になったり、やらなくてもよかったことを、より省力化していきながら、社会の課題を解決する。あるいは、省力化だけではなく、また、単にお金だけの関係性でもない、新たな関わり方というのがあると思っていて。
そういった関係性の中で、課題が解決していくと思っているので、その、新たな関係性とは何なのか? というのは、明日またお話ししてみたいと思います。では、今日の話はこれで終わりにします。じゃあね、バイバ~イ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
