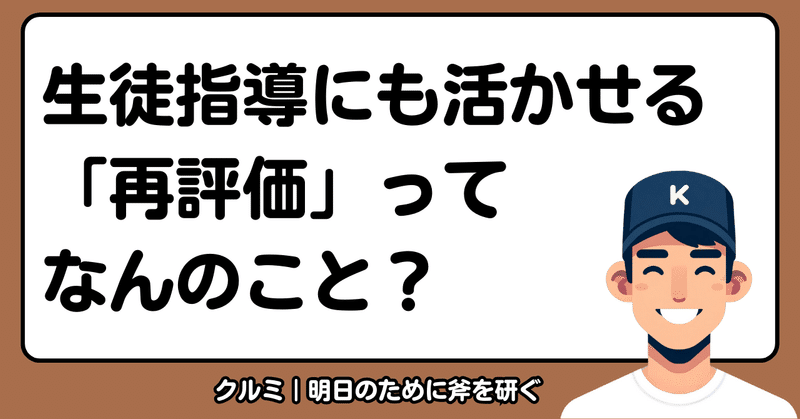
生徒指導にも活かせる「再評価」ってなんのこと?
みなさんこんにちは。
学校現場で働いていると、本当に様々な問題が起こりますよね。そして、その度に、生徒とじっくり話をしたり、時には叱ったりしますよね。いわゆる「生徒指導」です。
みなさんが学校で生徒指導をしていると、こんな悩みをもつことがあるのではないでしょうか。
生徒指導をしても・・・
この指導が正しいのかどうかわからない。
話はしたけれど、どこに着地させればよいかわからなくなった。
本人が納得できているかどうかわからない。
今回は、そんな悩みを解決する手立ての一つとして、私が実践している「再評価」についてまとめます。
なお、本日の内容は、内田舞さんが書かれた『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』を参考に、その内容を学校現場でどのように活用できるかを、私の実践を含めて解説します。
「感情」「考え」「行動」を「再評価」するとは
今回テーマとしている「再評価」とは、一体どんなものなのでしょうか。
以下は、本書からの引用です。
「再評価」とは、ネガティブな感情を感じた時に一旦立ち止まり、その感情を客観的に再度「本当に今このようなネガティブな感情を感じる必要があるのか」と評価して、状況、または感情をポジティブは方向に持っていく心理プロセスです。感情が「好ましくない状況である」と「評価」したときに、瞬時に行動に移す前に、一回立ち止まって再度「評価」し直すわけです。
引用部では、「行動に移す前に、一回立ち止まって再度評価し直す」とありますが、今回は生徒指導に関わって、「起きてしまったこと」について、改めて評価する方法を「再評価」とします。
実際、本書の中には、内田さんが息子さんと一緒に、息子さんの行動について後からじっくりと話し合い、再評価するエピソードが書かれています。
そのエピソードでは、認知行動療法で一般的な、「感情」「考え」「行動」の3つに分けて再評価する方法が用いられています。
わざと水をこぼした息子さんに対して、「感情」「考え」「行動」を確認し、1つ1つの答えを一緒に再評価しています。
そして、「感情」に関しては否定せず、「考え」に間違いがあることを指摘し、正しい「行動」に導いています、
実際に生徒指導で活用した話
このような「感情」「考え」「行動」を分けて指導することは、学校現場に置いても、非常に有効です。
私はこの方法を用いてから、生徒指導に関わって、話の着地点がわからなくなったり、生徒が納得できないまま帰宅したりすることがなくなりました。
ここでは、実際に起こった生徒指導事案に対して、私が「再評価」を活用して生徒と話をした例を紹介します。
起こった出来事
ある朝、教室内でトラブルが起こりました。生徒Aが生徒Bのペンを破壊してしまったというものです。
よくある指導であれば、生徒Aに対して「なんでそんなことをしたんだ?」「ペンを壊すことはよくないようね」「謝るべきなのではないか」という話をする流れになろうかと思います。
しかし、これでは、生徒Aの気持ちを理解することも、生徒A自身が考え直すこともできません。
ペンを壊してはいけないことくらい、本人もわかっているはずです。でも壊してしまったのです。その背景を考える必要があります。
ここで「再評価」の登場です。
今回は、話をわかりやすくするために、生徒Bに対するアプローチは省略します。
学校における「再評価」のステップ
1.事実の確認
まず初めに、事実を確認します。
・生徒Bがぶつかってきた。
・自分が、生徒Bのペンを壊した。
生徒Aは、自分の行動について嘘をつくことなく冷静に話をしてくれました。周りの生徒から聞いた話とも一致しました。
2.「感情」の確認
いよいよここからが「再評価」の出番です。
「感情」「考え」「行動」を3つに分けて、「再評価」していきます。
【私】ぶつかられた時、どんな気持ちになったの?
【生徒A】イラッとした。
ぶつかられてイラッとすることは、決して間違ったことではありません。
生徒が感じた「感情」に対しては、否定する必要がありません。
3.「考え」の確認
「感情」がわかったら、どう考えたのか、「考え」の確認です。
【私】イラッとして、どんなことを考えたの?
【生徒A】絶対わざとだと思った。許せないと思った。
どうやら、ここで「わざとだ」と決めつけてしまったようです。
しかし、ここではまだ指導はしません。じっくりと話を聞くことを続けます。
4.「行動」の確認
「考え」を確認したところで指導したくなるかも知れませんが、もう少し待ちましょう。
「行動」の確認です。
【私】そして、どんな行動をしたの?
【生徒A】生徒Bのペンを壊した
最初に確認した事実と同じになりました。
これで、生徒Aがどういったプロセスで、生徒Bのペンを破壊するに至ったのかがわかりました。
5.一緒に「再評価」
ここまでの確認を経て、ようやく「再評価」できます。
【私】ぶつかられて「イラっとした」気持ちはよくわかるし、間違っていない。
でも、「絶対わざとだ」って考えたことは、正しいのかな?
【生徒A】う〜ん・・・
もしかしたら、ぶつかってしまっただけかもしれない。
【私】そういうことも考えられるよね。
だったら、どんな「行動」をとるべきだったのかな?
【生徒A】ぶつかられて「イラッとした」ことを伝える。
【私】そうだね。そうやって「嫌だ」ということを伝える方法もあるよね。
ペンを壊す前に、言葉で伝えることで、Bさんもわかってくれるかもしれないよね。
大切なことは、どんな「行動」をするべきだったかを、生徒が自分の言葉で表現することです。
この「再評価」のプロセスを経れば、生徒が自分の行動に至るまでの「感情」や「考え」を振り返り、どんな「行動」をすべきだったのか、自分で考えることができます。
まとめ
今回は、内田舞さんの書かれた『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』を参考に、「再評価」の観点から考える生徒指導の方法について、内容をまとめました。
「感情」「考え」「行動」を3つに分けて再評価する。
分けて考えることで、生徒本人が正しい「行動」を考える。
当たり前ですが、生徒は「ペンを壊してはいけない」なんてことは知っています。
知っているけれど、やってしまうのです。
大切なことは、その行動を叱るのではなく、その行動に至るまでの「感情」や「考え」に焦点を当てて、冷静に、よりよい「行動」を一緒に考えていくことです。
生徒指導には正解がなく、常に迷いがあると思います。
そんな迷いがある中でも、今回紹介した「再評価」のような方法を活用することで、より効果的な生徒指導ができるようになるのではないでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
