
谷中を歩く
これも縁なのだろうか?
たまたま、仕事先に捨ててあった湯島天満宮の御守りを返しに行かなくてはとなり。
ついでに、上野公園内を散策。
なんやってーーーー!上野公園内にある建物は、鶯谷駅近くの東叡山寛永寺根本中堂まで行かないと意味がないのかーーーー!と、1週間後に。
そして、寛永寺だけでなく、近くを歩こうと辿り着いた先が猫の町・谷中であった。



まずは、上野駅から歩いて東叡山寛永寺に。
詳しくは、こちらに。

そして、寛永寺を出てすぐ目の前にある浄名院に行くわけだ。
ここからが、谷中散歩の始まり始まり~。
谷中霊園を横に歩いていくと、真言宗豊山派の多宝院が観えて来る。






多宝院は台東区谷中にある真言宗豊山派の寺院で、宝塔山龍門寺と号します。本尊は多宝如来。宥純法印が開山となり慶長16年(1611)神田北寺町に創建、慶安元年(1648)当地へ移転したといいます。
御府内八十八ヶ所霊場49番札所(寺の説明より)




多宝院の隣にあるのが天台宗・総持院だ。
天正18年(1590)徳川家康江戸入府のとき、旗本大久保七郎右衛門忠世(彦左衛門長兄)も大山不動尊と同木同作と言われている守護神の不動尊を奉持して、神田寺町に安置しました。慶長16年(1611)2月忠世の子忠隣の代に境内地400坪(1,320平方メートル)を賜り、栄松法印を開山として茲に創建いたしました。
これより37年後の慶安元年11月には、当所へ代地を賜り移転して、町名を総持院門前町と称し、明治2年に総持院町と改め、同12年4月に谷中町となります。通称谷中不動尊はこの町名に由来しております。芝崎町の東光院が本寺です。谷中町及び近辺の信者で講中を作り、大山詣りも盛んに行われ、毎月28日の縁日には屋台も出て賑わったと言われています。
家康の長子信康(1579自刃)と、その母築山(今川義元の養女。1579賜死)の母子共に生害されたのを忠隣の孫忠朝深く憐み、元禄11年(1698)120回の御忌辰には、御位牌を当院に安置されてご冥福を祈念されたと言うことです。正五九月には代参を遣わされています。
明治23年4月高村光雲は下谷西町から当院の宅地に転居しています。門構で平家建の家でした。光太郎7歳姉さくが14歳の頃です。光太郎は日暮里小学校に通っており、谷中墓地で友達と元気に遊んでいたと言うことです。
姉のさくは利発で絵が上手で、親思いであり、光雲の無事息災を祈って当院の不動尊に願をかけていました。明治25年9月9日さくは病没します。光雲は娘の死に力を落し、思い出の残る谷中を離れ、千駄木林町に移ります。
当院は関東大震災、戦災共に、幸いにも難を免れております。
(天台宗のページより)
小さなお寺であったが、なかなか歴史的にみると深い。
高村光雲・光太郎親子に縁あるお寺だという。
高村家のお墓は、巣鴨の染井霊園にあったもので、谷中と関係あるとは思わなかった。行ってみて知る。人生は勉強や。



谷中の中でも際立って大きな瑞臨時は、ここ谷中の地では重要になる。
詳しくは、こちらに。
しかし、谷中は見事に寺町だ。金沢市に行った時に、神仏分離を味わったのだが、それを感じる。お寺ばかりで神社が見当たらないのだ。






真言宗豊山派長久院瑠璃光山薬師寺だ。
長久院は、慶長16年(1611)2月宥意が神田北寺町に開山、慶安11年(1658)当地へ移転したといわれている。
写真に載せたが、感染を危惧してと、御朱印を頂くことが出来なかった。
他にも実に沢山の寺院で同じ事を言われたのだ。
ある寺院では、「個人の御朱印帳から感染するかもしれないから」と。
何故に、そのような事を言われるのか?
イヤイヤ、それは個人が悪いのではない。そのように国民に思い込ませてしまった尾身茂を始めとする偉い方のせいなのだ。


こちらは、日蓮宗の正行院だ。正行院は、正覚日順(寛永20年1643年寂)が開基となり創建したという。瑞輪寺の末寺だ。

こちらは、日蓮宗の浄延院だ。浄延院は、本照院日乗(寛永15年1633年寂)が開基となり創建したという。瑞輪寺の末寺だ。

こちらは、日蓮宗の躰仙院だ。躰仙院は、瑞輪寺6世日桂が開基となり創建したという。
鬼子母神の寺なのだが、立ち入ることも出来なかった。



日蓮宗の久成院だ。久成院は、尊慶院日順(元和元年1615年寂)が開基となり創建したという。


そして、本妙院に。
詳しくは、こちらに。


こちらは、有名な谷中のヒマラヤ杉だ。
目の前にある妙行寺さんには、何匹化の猫がおり、人に懐いている。




日蓮宗正栄山妙行寺。妙行寺は、顕性院日長(万冶3年遷化)が開山となり浅草寺附近に創建、元禄2年(1689)当地へ移転した。



お寺にいるミュウちゃん。人懐っこいのだ。

その隣にあるのが日蓮宗・延寿寺さんだ。

こちらは、健脚祈願で有名なお寺らしく。境内には沢山の祈願絵馬が奉納されていた。



対応してくださった住職夫人は、親切な方で、こちらの話を聴いてくださり、谷中の事も教えてくださった。

こちらのパンフレットも夫人がくださったのだ。
残念ながら、住職がおられないということで、御朱印はいただけず。
健脚はボケるまで願いがあるので、いつか行きたいと思う。

そして、寺に入らずとも観える弘法大師様の像!!
こちらは、新義真言宗 佛到山 西光寺だ。
詳しくは、こちらに。
さてさて、どこまで続く寺院群。
広さで言うと、金沢市の寺町よりも狭いが、寺の数は多いのではないだろうか。

こちらの樹だが、個人宅のものである。この家の男性が、「食べられる桜の樹」だと教えてくれた。
「ソメイヨシノじゃないよ、べらんめえ」
ということで、調べてみると、アメリカ桜のようだ。
この桜の樹を道を挟んだ向かいにあるのが、天台宗の大泉寺になる。


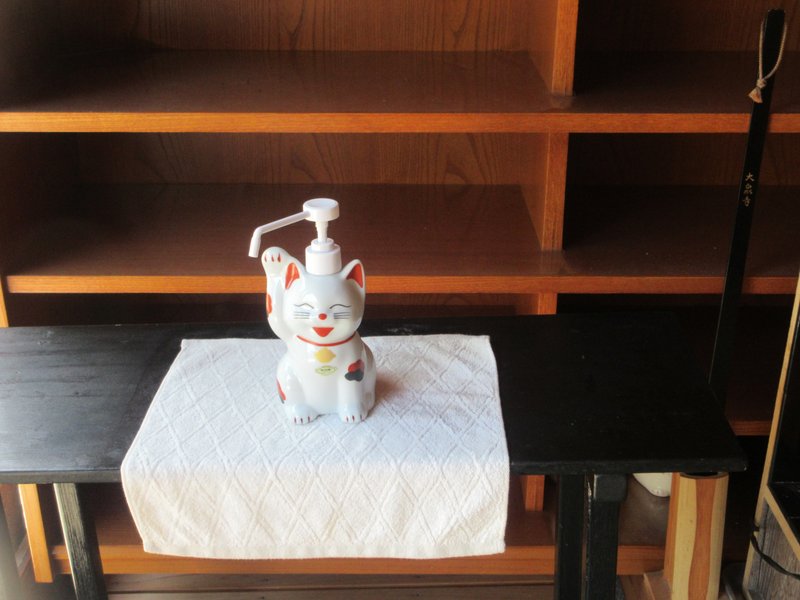
岡倉天心、高村光雲などの明治の美術家と深いゆかりのある寺らしい。
玄関にあった猫のアルコールスプレーは谷中銀座で売られていると若い住職が教えてくれた。



こちらは、新義真言宗寺院の自性院だ。
本覚山宝光寺という。自性院は、慶長16年(1611)道意上人が神田北寺町に開山、慶安年間当地へ移転したという。御府内八十八ヶ所霊場53番、御府内二十一ヶ所霊場10番札所、文豪川口松太郎の名作「愛染かつら」は、当院の愛染明王像と本堂前にあった桂の古木にヒントを得た作品だといわれている。
かなり歴史ある立派なお堂であった。
残念ながら、こちらでも御朱印は断られた。



こちらは、天台宗金嶺寺だ。倍増山宝城院と言う。金嶺寺は、慶長16年(1611)神田北寺町に寺地を拝領して創建、天海僧正が寛永17年(1640)開山。慶安元年(1648)当地へ移転。上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場31番とされている。
境内にいた犬が愛らしかった。



こちらは天台宗・法蔵院さんだ。光雲山元導寺と号する。法蔵院は、慶賢法印が慶長17年(1612)神田北寺町に創建、慶安元年(1648)当地へ移転したという。
天台宗のサイトより。
そして、谷中の寺院群から千駄木駅方面に歩いて行った。

瑞輪寺を曲がり、都道452号線沿いに坂を下りていき千駄木駅方面へ。



真言宗豊山派の観智院は幼稚園を兼ねていて、子どもたちの遊ぶ声でにぎわっていた。
鯉のぼりが舞い、子どもたちの遊ぶ姿は微笑ましかった。



こちらは、曹洞宗の永久寺だ。観智院の道路向かいにあったお寺がなかなか雰囲気が良かったから立ちよったのだ。
永久寺は、谷中玉林寺中興開山の風室興春和尚(慶安3年1650年遷化)が隠居寺として創建した。
猫塚があった。さすが!猫の町・谷中だ。



千駄木駅方面に坂を下りていくと、少し奥まった所に、真言宗豊山派・明王院がある。
明王院は、弁円法印が開山となり慶長16年(1611)神田北寺町に開山、慶安元年(1648)当地へ移転したという。
お地蔵様が素敵な所であった。





最後は、臨済宗国泰寺派の全生庵だ。
こちらは明治16年に創建ということなので新しいといえる。
山岡鉄舟と深い関わりを持つ寺だという。
歴史的にも見どころがあり素晴らしい寺であった。
Googleマップを観ていただくとわかるのだが、谷中は小さいものも入れると、余にも多数の寺があり、1日で廻り切れるものではなかった。
残念ながら、殆ど行っていないかもしれない。
それから私の勘違いなのであるが、鶯谷駅から千駄木駅の間が谷中銀座なるものと思っていたのだ。
日暮里駅近くが谷中銀座商店街だったようだ。

日暮里駅近くの谷中霊園に、私の尊敬する植物学者・牧野富太郎博士の墓があるのか。
次回は、日暮里駅まで電車で行こうと思うのだった。
そして、申し訳ないのだが、神仏分離もよいが、神社を全く見なかった日だったなと改めて感じたのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
