
島国日本の脳を鍛える~読書記録95~
2011年東日本大震災直後に書かれた、脳科学者・茂木健一郎先生の著書。
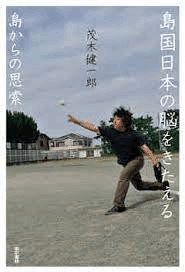
3/11に起きた東日本大震災、2010年に訪れた伊豆諸島・神津島での講演会を通じての思索。それが書かれている。
私は、茂木健一郎先生のように賢くないので難しい事はよくわからないのだが、脳を鍛える上での感覚。それの重要性が理解できた。
誰も読むことのない日記ではなく、多くの人が読むだろうブログやTwitterなど、他人が読む事を前提として書く。これは脳の活性化に役立つ。
確かにそうだなと思う。
出来れば、鍵付きアカウントではなく、全体公開の方がよいだろう。
鍵付きアカウントは大体の場合、凍結防止が殆どなのであるが、通報されるような事を書かなければ、通報されても問題ないなら鍵を付ける必要性もないだろう。
他者を批判・非難する場合の多くは、その根底に「嫉妬」の感情がある。何かに嫉妬している自分を認めたくないという無意識的な感情も働いて、なかなか本人も気づけない場合が多い。 なかには嫉妬を興味にすりかえ行動力に転換する場合もあるが、根底の嫉妬に気づくほうが成長出来る。 茂木健一郎先生
私は、舌を何度か手術しており滑舌が悪い。と同時に、他人が怖く、殆ど誰とも口をきかない。それもあったが、年々、衰えていく視力に記憶力。それらを克服すべく、ツイキャスで「朗読」を始めた。
ブログやキャスなどで収入など一切考えていない。自分の為のものだ。
それが、脳の活性化に良かったな、とこの本を読みながら思った。
黙読ではなく音読。全体公開なので、他人にもわかるように口を動かす。滑舌が悪いな、と時には絶望しながらも続けるうちに、なんとなく、「自殺願望」はなくなってしまった。Twitterと違い、特にイイネなどなくても構わない、マイペースなのもよかったのだろう。
島国日本ということで、日本人特有のガラパゴス化が書かれていた。2011年当時は、ガラケー時代で、mixiが流行っていたのだ。
けれども、ガラケーも終わり、mixiも廃れ。私的には良かったと思う。
mixiの持つ閉鎖性。なんとなく怖いものを今は感じる。
人に必要なのは「助け合い」。現在のインターネットも「助けあい」の精神がある。誰かが発信した情報を知る事が出来る。又、自分が出した情報で他人が助かることもある。
ただ、インターネットの情報が全て正しいとは思わない方が良いので、目を鍛えなくてはならないが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
