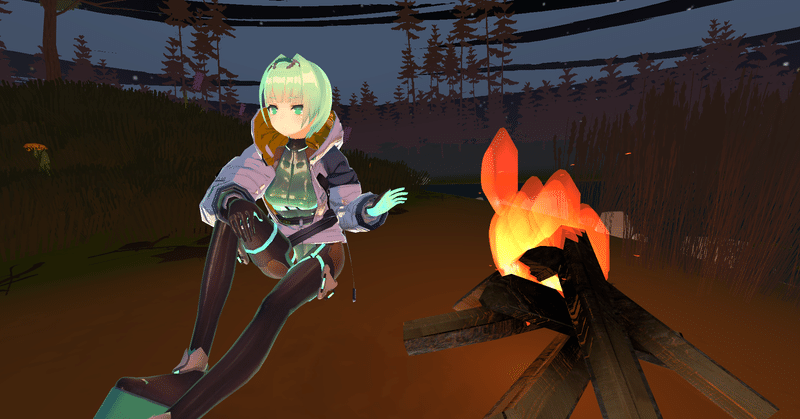
VR流れ藻(15):雑記/拒絶の言葉
ごく個人的な信条に関する話である。VRCが云々というよりも。
都市でぼんやりと人間社会に埋もれて暮らしたりしていると忘れがちなのだが、世の中には何だか奇妙な生物が無数にひしめいている。
例えば昆虫というのはその筆頭である。自室には体長1cmほどの小さなハエトリグモがどうやら同居していて(※1)、何気なく窓辺の鉢植を手に取ると、つうっと糸を垂らして離脱を図ったりする。空中でぶらぶら揺れているのを放っておくのも気の毒なので、指先で糸をたぐり寄せて他の鉢植に着地させてやる。たぶんその辺の羽虫でも食べているのだろうが、どうやって暮らしているのかいまひとつ判然としない。モニタからふと目を上げると、カーテンの上でぴこぴこと触肢を上げ下げしていたりする。あるいは壁をぴょいぴょい俊敏に跳ねていく。日常に溶け込んでいるのであまり皆気にしないが、これだってずいぶん奇妙なやつである。そもそも蜘蛛というのはどうやってあんなに糸を吐けるのかよくわからない。大方何かのタンパク質ではあるのだろうけれど。
あるいは雨後の晴天の日、植え込みから這い出たミミズが路上で干からびている。ミミズの種類の同定ってどうやるんだっけな、と思う。普通はあんまり思わないような気がする。これを書いているのはまあそういう種類の人間である。ミミズの種類がわかって一体何がうれしいのかと問われるとちょっと困る。これは世界認識の解像度の問題と結びついていて、なかなか説明が難しいのだけれど、ここでの本題ではないので放っておく。ともかくその辺に落ちているミミズの死体でも種類が判別できるとちょっとうれしい。しげしげと眺め、通り過ぎてしばらくした頃、背後で子供がミミズがどうだか言っているのが聞こえる。親が気持ち悪いねとか何とか言っている。
まあ路上で干からびたミミズの死体なんてあんまり気持ちのいいものではない。片付けが面倒なのはたしかである。しかしながらミミズという生物自体が気持ち悪いとかどうとかいうのはあくまで人間の価値観の問題であるといえる。昆虫と違ってちょっと内臓的で、ああいううにょうにょとした生き物はどうも本能的にヒトの嫌悪感を煽るところがあるのではないかという気もしないでもないけれど、さりとて気持ちの良し悪しは生物そのものの価値ではなく人間の勝手な判断である。一方では嫌悪ではなく興味を抱く人もいるもので、あのダーウィンだって自らミミズを研究していた。日本にも研究者はいるし一般書なども出ている。読むとたいへん面白い。
何でこんな話をしているのかというと、つい先日Twitterの生物界隈で、子が捕まえた虫に親が気持ち悪いとか否定的なことを述べるのはよろしくない、というような話が流れていたということがひとつの理由である。これについては、まあそれはその通りだね、という程度の感想しか持たない。一方でそもそもの話として、「気持ち悪い」という言葉そのものをあまり使わないほうがいいのではないか、という考えが随分前から心の内にあって、何となくそのことを書き留めておきたくなったのだった。
「気持ち悪い」という感情は、得体の知れない、理解の及ばないものに対するひとつの反応である。何であれ日常の中に溶け込むほどに見知っているものを今更気持ち悪いとは思わないはずで、いわば異物に対する警戒反応であるともいえる。
一方で「気持ち悪い」という言葉は非常に強い拒絶の言葉であって、それ以上関わり合いになりたくない、という意図を含む。「理解できない」なども場合によっては似た意味合いをもつ。関わりを強く拒絶すれば、対象についてそれ以上の理解が得られることはない。内心において対象を「気持ち悪い」ものであると分類した時点で、対象を深く理解することは困難になる。たとえミミズの形態に嫌悪感を覚えたとしても、あえて対象を理解しようとする意志があるのであれば、一定の距離で踏みとどまって再度対象と向き合う必要がある。もし対象を「気持ち悪い」の分類枠へと完全に投げ捨ててしまったらそんなことはできない。
言葉というのは強いもので、何かを「気持ち悪い」と言ったり書いたりした時点で自分の中での一次的な分類は完了してしまう。だからたぶん、広く何かを理解しようとする心を持とうとするのであれば、「気持ち悪い」という言葉は封じてしまったほうがよい。別にミミズを深く理解する必要は通常あまりないけれど、おそらくこれは幅広いものごとに当てはまる。奇妙な生物であれ、人間の感情であれ、複雑怪奇で手に負えないような概念や理論、創作物であれ。あえて言葉を飲み込んで、押し黙って考えることから始めなければならない。たとえ理解にまで至らなかったとしても、そういうものがあるとただ広く知り認めることは、未知による「気持ち悪さ」を軽減するだろう。
昆虫と子と親の云々がこの話のひとつの要因だと書いたが、実際には要因は他にもいくつかある。Twitter上で日々行われ続けており断片が流れてくる、相互の価値観の不理解による終わりなき泥仕合であるとか、あるいはVRChat内で込み入った性的嗜好についての話を耳にしたことであるとか。
どうにも人間というのは複雑なものを抱えてしまうことがあるけれど、まずはその複雑な何かに対する拒絶を捨てることから互いの理解が始まるのだろう。一応断っておくと、これは別に手の込んだスケベ行為を積極的に推進すべきという意味では決してない。
※1:不覚にも書き終えてから気付いたのだが、当然クモは昆虫ではない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
