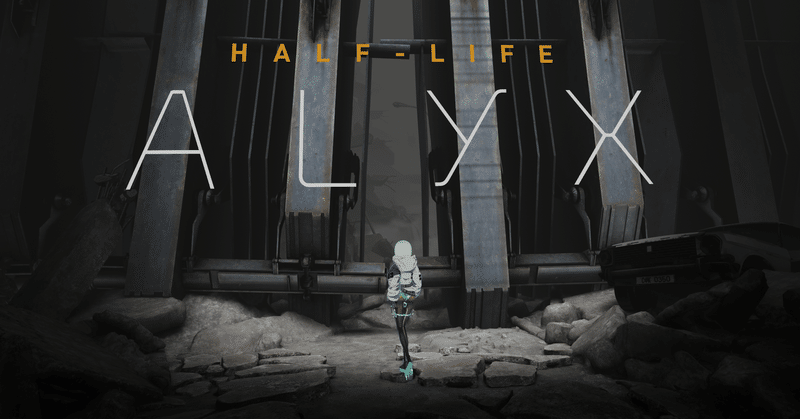
VR流れ藻(13):Half-Life: Alyx
『Half-Life: Alyx』をクリアした。
Half-Lifeシリーズはこれまで直接触れたことがなかった。せいぜい、かなり以前にいくつか発狂気味のプレイ動画を見た記憶があるくらいで、自分では関連作品である『Portal』の1・2をプレイしたに留まる。『Portal』はよく知られた名作だが、『Alyx』も実に素晴らしかった。VRChatの話ではないが多少関連する部分もあるため、『Half-Life: Alyx』の感想をここに書いておく。
徹底的に作りこまれたVRの世界がどのようなものであるのかを『Alyx』は示してくれた。開幕、光の中から現れた異質な都市の広がりに、きっと誰もが息を飲むだろう。灰色に霞む街並みの向こうにそびえる、あまりにも巨大な構造物の影。空を飛びまわり、あるいは建物をまたいで歩行する、見たこともない異形の乗り物の群れ。それらが放ち都市に反響する騒音、大気のうなり。かたわらを見れば雑多な日用品がいくつも置かれていて、それらはどれもが触れられる。つかみ取ってしげしげと眺めることもできるし、階下へと投げ捨てることもできる。ペンを手にすれば落書きだってできる。そこにはこの明らかに異質な世界に対して、まさに自分の「手」で作用できるのだという確かな手ごたえがある。
目の前に存在するすべての現象と存在が、有無を言わせぬ高密度の「現実」としてプレイヤーを殴りつける。その感覚は筆舌に尽くしがたい。おそらく、このプレイ開始数分に「VR環境で世界を描く」ということの精髄が凝縮されていて、それは世界を抽象化・簡略化する方向にある多くのVRゲームやVRCのワールドでは味わうことの難しいものだ。だからこそ、この冒頭だけでも触れてみる価値はある。
プレイヤーは主人公アリックスとなって、廃墟と化した都市の隔離区画を駆け抜けていく。放棄された駅や列車、年代物の住居やホテル、どことも知れない地下通路、工場跡など、いずれも荒廃した雰囲気が作りこまれている。個人的に素晴らしいと思ったのは動物園で、ガラスが散乱した展示室、朽ちた解説板やイラスト、誤って水槽にはまっているクリーチャーなど、雰囲気が丁寧に作りこまれている。最初ゲームのダウンロードサイズが49GBあってちょっと正気を疑ったのだが、この作り込みの前には納得せざるを得ない(※1)。
プレイヤーはこれらの廃墟を探索してアイテムや弾薬を集め、武器を強化し、仕掛けを解き、ゾンビや敵兵と銃撃戦を繰り広げながら先へ進んでいく。グロテスクな敵や死体の頻出するホラー風味の強いゲームなので、苦手な人はちょっと戸惑うかもしれない。射撃や弾倉交換といった細かな銃の扱いにも面食らうかもしれないが、やっているうちに慣れてくるし、薄気味悪いクリーチャーだって見慣れるとあまりどうということもなくなってくる。むしろ親しみすら湧いてくるかもしれない(※2)。その点、どこまでも厄介な相手は人間である。複数人で容赦なく銃撃を浴びせてくるコンバイン兵たちにはきっと何度も苦渋を舐めさせられるだろう。
さて、探索に効果を発揮するのがグラビティグローブである。これは、もののある方に手をかざすとそれが光って反応し、手繰るように手首をひねるとものがこっちに飛んでくる、という仕掛けである。操作感の気持ちよさ、自然さが優れていて、足元や少し遠くにあるものが扱いづらいというVR操作の問題を普段感じているとちょっと感動すること請け合いである。これも体験してみる価値のある要素である(※3)。
探索の対象となるマップは基本的には一本道になっており、随所でアリックスとサポート役のラッセルとの通信による掛け合いが入る。また道中では幾人かの人物(?)と出会うことになる。彼らの演技も見所なのだが、等身大のリアル調の人物が目の前で身振りを交えた演技をしてくれる体験というのはちょっと不思議なところがあり、これも面白い。
お話自体にはシリーズの内容を前提にしていてわかりづらい部分があるので、手早く理解するならここの記事の5と6を読んでおくとよい。
難易度ノーマルでしっかり探索する方針でプレイしたが、銃の扱いに不慣れなこともあり、後半は常に弾切れの恐怖がつきまとった。それはそれで緊迫感のあるプレイだったが、気楽に遊ぶなら最初はイージーにしておいたほうがいいかもしれない。完全に弾切れするとたぶん詰みだろう。攻略上のコツをひとつだけ書いておくと、限られた弾数を有効活用するためにも、銃強化は各銃のレーザーサイトの作成を最優先にするとよい。高コストもあってレーザーサイトを終盤まで作成しなかったが、実際使ってみると射撃制度が上がって格段に楽になった(※4)。
中盤以降は3種類の銃を使い分けたり、グレネードを投げたり(うまく投げられなかったり)しながら戦うのはかなりの緊張感を伴う。非常に面白いが、こまめに休憩しながらプレイすることをお薦めする。
全体として、価格分(約6000円程度)の価格の価値は十分にある。Indexを買って無料入手可能な人はとりあえず触れておいて損はない。いずれにせよ、プレイできるVR機器があって、どうしてもホラーは苦手という人でなければ強くお薦めする。
プレイし始めたのがたしか4月の中頃だったと思うが、ちょうどVRCではUdon製ワールドが続々と登場し始めたところだった。Alyxを終了してVRCを覗いたら、ちょうどフレンドがUdon製グラビティグローブのワールドで遊んでいたのだが、操作感がかなりの精度で再現されていて感心してしまった。やはりあれはアイデアによる「発明」であって、実装そのものはそれほど難解ではないのかもしれない(※5)。
また、Alyxのタイトル画面(タイトルマップ)のワールドがVRC内にある(ヘッダ画像)。説明文を読む限り公認のようだ。何か単独で遊べるような機能があるわけではないが、プレイ後に訪れると感慨深いかもしれない。
追記:
無事2週目を終えた(難易度はやはりノーマル)。見直すと物語のターニングポイントがはっきりと読み取れることや、ラストシーンの演出のVRであることによる感慨深さであるとか、やはりいろいろと興味深く感じた。合成樹脂はフル改造には34個不足で終わったが、フル改造可能な個数が隠されているのだろうか。そんなに見逃してたのかな、とちょっと首を傾げている。
――――――――――――――――――――――――――――――
※1:最近の非VRな第一級のゲームにあまり触れていないので、相対的な基準が適切ではないかもしれない。
※2:きっとクリアする頃にはヘッドクラブをかわいらしく思うことだろう。見たら即銃殺するが。
※3:本文側でリンクしている記事によると、あまりに優れているせいで即座に他ゲームで模倣されたらしい。
※4:逆にリフレックスサイトは必要性が低い。暗所の敵や弱点のハイライト機能があるが、暗所の敵が問題になる場面はかなり限られており、あとは天井の固定敵くらいなので適当に撃っても当たる。弱点については重武装の兵士はほぼヘッドショットしか通じない程度で、他に判断が難しい敵はあまりいない。
※5:Udon製グラビティグローブのワールドは複数あり、機能の再現精度も異なる。具体的なワールド名は忘れたが、対象物のハイライトなども再現されているところがあり、操作感覚の再現精度も高かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
